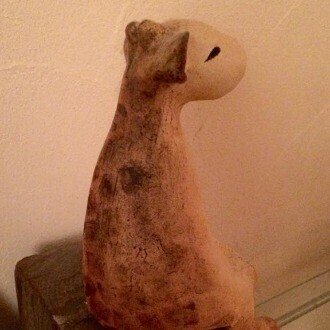記事一覧
倭国大乱を経て、時代は進みました
欠史八代 第十四話 第九代 開化天皇
開化天皇の皇妃と皇子
※(記)は『古事記』のみ記載
1
皇后: 伊香色謎命(物部氏)
─子: 御間城入彦五十瓊殖天皇(崇神天皇)
─※『古事記』では妹として御真津比売命が記されています。
2
妃: 丹波の竹野媛(丹波大県主由碁理の娘)
─子: 彦湯産隅命
3
妃: 姥津媛(和珥臣 『古事記』は意祁都比売命)
─子: 彦坐王
4
妃: 鸇比売
物部氏が独占! 大和政権で何があったのか?!
欠史八代 第十三話 第八代 孝元天皇
孝元天皇も事績が記録されていませんが、帝紀に記される皇妃や皇子に注目し、どのような時代だったかを考えたいと思います。
皇后と妃について
孝元天皇の皇后は鬱色謎命、妃は伊香色謎命と埴安媛です。埴安媛は第十代崇神天皇の時代に反乱を起こした武埴安彦の母です。
系図をつくってみました。埴安媛と孝元天皇皇女倭迹迹姫は省略しています。
できるだけわかりやす
吉備津彦の物語から製鉄の歴史を探る
欠史八代 第十一話 第七代 孝霊天皇 ③
今回は、吉備津彦の物語から「製鉄」を考えてみたいと思います。
あらすじ
阿曽の里人々が幸せに暮らしていたところ、百済の王子である温羅がやってきて、足守川流の新山に城を築き岩屋に住みついた。温羅は悪行の限りを尽くし、里人たちを苦しめた。そこで、里の人々は朝廷に陳情し、吉備津彦が派遣された。吉備津彦は吉備の中山に陣を据え、西に石の楯を築いた。そして温羅
奈良盆地と国家の始まり
欠史八代 第十話 第七代 孝霊天皇 ②
今回は少し違った角度から「欠史八代」を考えてみたいと思います。『古事記』と『日本書紀』本文に記される欠史八代天皇の皇后・妃、皇子、皇女の数を数えてみました。それぞれの皇子を見ると、一柱は次の天皇になられた方ですので、全26柱から8柱を引いて18柱。今回はその十八柱の皇子の封ぜられた地方、その皇子を祖とする氏族が本拠とする地域について考えてみたいと思います
唐古・鍵遺跡がカギ!
欠史八代 第九話 第七代 孝霊天皇 ①
黒田廬戸宮 六代までは伝承地が南部に集中していましたが、第七代 孝霊天皇はいよいよ奈良盆地の中央部に移ります。磯城郡田原本町黒田の法楽寺には孝霊天皇黒田廬戸宮伝承碑が立っています。また、法楽寺から南東へ500mほどのところには、孝霊(廬戸)神社があります。
唐古・鍵遺跡 黒田廬戸宮の近くには、奈良盆地最大の弥生遺跡である 唐古・鍵遺跡があります。皇紀を単
『ローマは一日にして成らず』です。
欠史八代 第八話 第六代 孝安天皇
孝安天皇
『日本書紀』に記される歴代天皇の中で、最も長い寿命と在位期間を持つ天皇として記されています。
和風諡号は「日本足彦押人天皇」です。父は第五代の孝昭天皇、母は尾張氏の世襲足媛です。
皇后は、姪にあたる押媛(『古事記』では忍鹿比売命)で、皇子は第七代 孝霊天皇お一人(日本書紀)。(『古事記』は兄に大吉備の諸進命を記します)。
宮は葛城之室秋津嶋宮
大和、新たな展開へ。
欠史八代 第七話 第五代 孝昭天皇
ヘッダー画像は、向かって右から孝昭天皇陵、大和葛城山、金剛山。
初代から第四代、神武、綏靖、安寧、懿徳天皇の御陵は畝傍山に築かれました。そして前々回の記事で、系譜をサザエさんに例えて、大和の 大地主神である大己貴神の血統を全て受け継いだことを書きました。
そしてこの第五代孝昭天皇から、新しいフェーズに入ったことを、『記紀』の記述から読み取ることが出来ると考
大和に祀られる出雲の神々
欠史八代 第六話 第四代 懿徳天皇
欠史八代の中でも、懿徳天皇は記事書くネタに困るだろうなと思って、『出雲国造神賀詞』を温存していました(笑)。
『出雲国造神賀詞』とは?
『延喜式』巻八の「祝詞」に収められている文書で、天穂日命に始まる出雲国造が新たに任命された際、朝廷で天皇の治世を祝して奏上した賀詞です。
この賀詞では、大己貴神の和魂を「大物主」という名で三輪山に祀り、御子神たち
安寧天皇をサザエさんで説明する
欠史八代 第五話 第三代安寧天皇 後編
「安寧」とは、穏やかで平和な状態を表します。安寧天皇の時代は、果たしてそのような平和な時代だったのでしょうか?この「漢風諡号」は、奈良時代後期に淡海三船により、神武天皇から持統天皇までの諡号(死後におくる名前。おくりな)を一括撰進したと考えられています。
便宜上、私も漢風諡号を使いますが、『古事記』や『日本書紀』が奏上された頃には、神武天皇の名はなく
淡路島。 御井の清水と五斗長垣内の鉄器工房
欠史八代 第四話 第三代 安寧天皇 前編
記事を書くのが難しい欠史八代シリーズ。第三代安寧天皇についても事績が残っていません。そこで何を書こうかと考え、『古事記』を読み返してみると、なんということでしょう! 何度も読んできたはずなのに、今まで完全に見逃していた記述がありました!
・・と言うのは冗談で、以前からその記述は知っていましたが、どう解釈すればいいのか答えが見つからず、自分の中で放置
綏靖天皇は、朝に夕に人を7人食らいなさったのか?
欠史八代 第2話 第二代 綏靖天皇 前編
タイトルの件は、南北朝時代に成立した安居院唱導教団の『神道集』「熊野権現の事」に記される内容です。文献のタイトルから古来の神道に関する内容かと思われがちですが、実際には神仏習合の本地垂迹思想、仏家による神道説話です。儒家神道や国学の勃興により、江戸時代には荒唐無稽とも言われましたが、以下当該部分の訳文を引用します。
中世には地方の村々を訪れ熊野