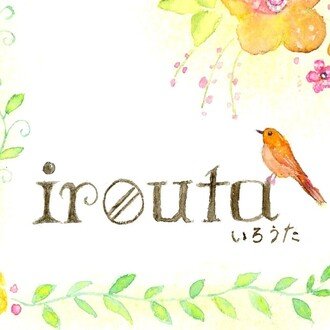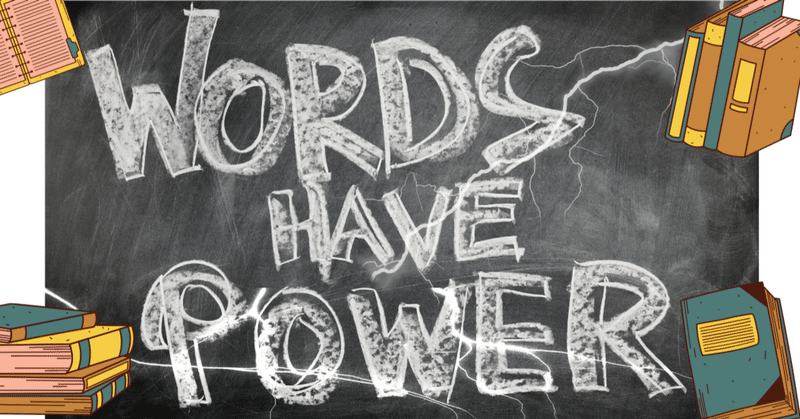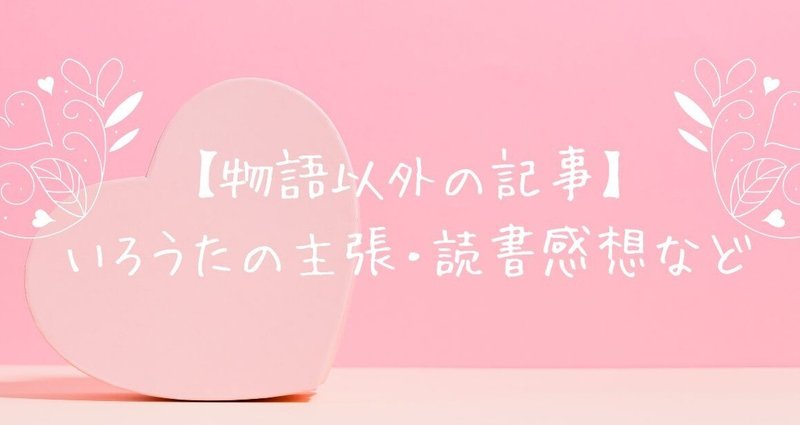
物語以外の記事の大半は、こちらにまとめています。哲学・人生論・内観・自己対話など、読書や実体験を通して感じたことを綴っています。
小説を通しで読むのはちょっと……の方は、こちら…
- 運営しているクリエイター
#言葉
改めて、「今ここを生きる」ことの大切さを思い出す
昨日(九月十三日)に、ペンキ画家のショーゲンさんとライフアーティストのサトケンさんのコラボ講演会に行ってきました!
「誰のために生きる?」と言う本の著者であるショーゲンさんのことは以前にご紹介しましたが、とても素敵なペンキアートを描かれるので、いつかその絵を手に取ってみてみたいなと思っていたところ、その夢が叶いました!!
ショーゲンさんのお話は、ほとんどが本に書かれていることだったのですが、知
日本語や|言靈《ことだま》について再考してみた ~よい影響を与える言葉を使う!~
先日ご紹介した本「今日、誰のために生きる?」をはじめ、最近では日本人の眠っている力を取り戻すことが鍵となる時代である、といわれています。
大學では國語學を学んでいたわたしとしては、とりわけ日本語の持つ力が取り上げれられることが素直に嬉しく、一層日頃使う言葉遣いに氣を付けようと思っているところです。
***
さて、お氣づきのかたもいらっしゃるかもしれませんが、この記事内で「靈」や「氣」といった
【読書まとめ&いろうたの考え】「言葉の品格」(イ・ギジュ著)を読んで、自分の使っている言葉を再考してみる
「何気なく口にしたひと言に品格が表れる。その人だけの体臭、その人が持つ固有の香りは、その人が使っている言葉から匂い立つものだ」
これは表題「言葉の品格」の冒頭に書かれている一文です。本書のすべてがこの言葉に集約されていると言っても過言ではありません。それくらい、日頃どのような発言をするか、心を込めた物言いをするかが重要だと著者のイ・ギジュ氏は述べています。
○どんな本?
本書は著者が過去に書