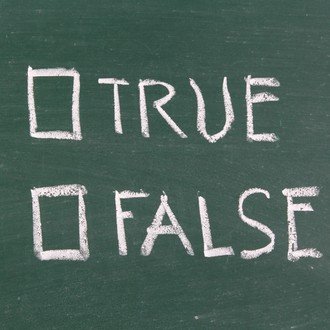#新聞
終戦記念日の新聞を読む2019(1)高知新聞「小社会」~特攻した子の親
▼ふと気がついた時、オンラインで読めるブロック紙、県紙のコラムにはなるべく目を通す。一年のうちに、何回かそういう日があって、8月15日付も、そのうちの一日だ。
この日は、どのコラムもだいたい力が入っている。今年の2019年8月15日付は、日本経済新聞と高知新聞が、全篇にわたって読ませる良質な内容だった。
▼日経は読む人も多いので、後回しにして、高知新聞の「小社会」を紹介しよう。
〈飛行機はい
「天気予報は平和の象徴」の件
▼「8月15日」前後は、新聞記事に「戦争の歴史」関連の話題が増える。
以下は、投稿から出来上がった記事なので、その流れとは別だと思うが、2019年7月24日付の東京新聞メトロポリタン(首都圏)面に、「天気予報と戦争」について考えさせられるいい記事が載っていた。
〈天気予報は平和の象徴/軍事機密化に心苦しさ/元気象庁職員 増田善信さん(95)/「爆弾低気圧に違和感」と投書〉
「天気予報と戦争」
『「いいね!」戦争』を読む(18) SNSが「グローバルな疫病」を生んだ件
▼『「いいね!」戦争』の第5章「マシンの「声」 真実の報道とバイラルの闘い」では、人間の脳がSNSに、いわばハイジャックされている現状と論理が事細かに紹介されている。
▼その最も有名な例であり、その後の原型になった出来事が、2016年のアメリカ大統領選挙だった。それは、何より「金儲け」になった。本書では
「偽情報経済」(216頁)
という術語が使われているが、フランスでも、ドイツでも、スペイ
『「いいね!」戦争』を読む(17)SNSは「承認」が最大の目的の件
▼前号では、「フェイクニュース」という言葉が広まっただけでなく、「フェイクニュース」の「定義」そのものが変えられてしまったきっかけが、アメリカ大統領選挙であり、なかんずくトランプ氏の行動だったことに触れた。
「フェイクニュース」は、もともとの「真実でないことが検証可能なニュース」という意味から、「気に入らない情報を侮蔑(ぶべつ)する言葉」、つまり、「客観的」な言葉から、とても「主観的」な言葉に変
ヘイトとウソと外国と(2)
▼前号では、フェイクニュースを広める人々は、あたかも「市場調査」のように、まずちょっと「ネット上に出す」、次に「自分たちのブログに載せる」、そして「動画配信サイトや地上波のテレビで拡散」という道筋を使うことに触れた。
その続き。
▼前号の内容は、フェイク拡散グループの「タテ」の動きだが、今号はその拡散がどう広がるのか、つまり「ヨコ」の動きに関する分析の一つだ。
▼アメリカの現代思想に造詣が深
ヘイトとウソと外国と(1)
▼フェイクニュースについてのニュースがとても多くなってきた。そのなかの一つ。2019年4月23日付の朝日新聞夕刊から。
〈現場へ! フェイクニュース 2/ヘイトと結びつくウソ〉(松本一弥)
ハーバード大学のショレンスタインセンターで、〈テクノロジーと社会変化について調査するプロブラムのディレクターをしている〉ジョーン・ドノバン氏の研究。
彼が調べているのは〈SNSや動画配信サイトを駆使しつつ
羽生善治氏と羽田圭介氏が「新聞」をオススメする理由
▼新聞がインターネット、特にSNS経由のニュースに押されるようになって数年が経つが、新聞の価値は減っていないことを、2019年6月15日付の産経新聞で、将棋棋士の羽生善治氏が語っていた。
その記事を読んでいて、ずいぶん前に読んだ羽田圭介氏の文章も思い出したので、あわせて紹介しよう。
▼まず、羽生氏の談話から。
〈最近はニュースそのものがあふれていますね。そのニュースは本当なのか、フェイク(偽
「ギャンブル依存」が簡単にわかる4つの質問
▼「依存」は「否認の病」ということを何度も書いてきたが、これからも機会があれば何度も書こうと思う。
▼2019年6月5日付の日本経済新聞夕刊に、ギャンブル依存が簡単にわかる4つの質問が載っていた。金子冴月記者。
■Limitless
ギャンブルをするときには予算や時間の制限を決めない、決めても守れない
■Once again
ギャンブルに勝ったときに「次のギャンブルに使おう」と考える
「平成31年」雑感17 松本サリン事件からマスメディアは変わっていない件
▼オウム真理教の幹部13人が処刑された件で、松本サリン事件について、「今」の話をメモしておきたい。
松本サリン事件の概要については、先にメモしておいた。
▼「創」2018年9月号に、かつて松本サリン事件の際、凄絶(せいぜつ)な報道被害をこうむった河野義行氏のコメント。2018年7月6日、オウム死刑囚13人のうち、7人が処刑された日の災難について語った。適宜改行。
〈6日の執行のニュースが流れ
「平成31年」雑感05 オウム一斉処刑で忘れ去られたもの
■松本サリン事件▼すっかり忘れ去られた問題があって、2018年7月7日付で、その幾つかが新聞記事になっていた。そのうち3つをメモしておく。
1)松本サリン事件
2)地下鉄サリン事件の全体像
3)警察庁長官狙撃事件の顛末(てんまつ)
▼それぞれ、指摘されているのは長野県警とマスメディアの問題、警察庁の問題、警視庁の問題である。
▼オウム真理教は、長野地裁の松本支部の裁判官を殺そうとする。2
「平成31年」雑感04 オウム一斉処刑から見える法律の現実
■オウム一斉処刑に対する弁護士の抗議▼2018年7月7日付の新聞記事を振り返っている。前の2回分は、
「平成31年」雑感02 オウム真理教の死刑囚一斉処刑
「平成31年」雑感03 オウム一斉処刑で日本が失ったもの
▼きょうは、
1)オウム一斉処刑に対する弁護士の抗議(東京)
2)松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚の精神状態(朝日)
3)刑事訴訟法の現実(東京)
の3点を簡単にメモしておく。
アニメの「キャラ」が「現実」を反映している件
▼アニメは、こどもの現実を必死に追いかけ、「いま」を映し出そうとする。
2019年3月30日付の東京新聞夕刊1面トップは、
〈キャラ みんな違って、いい〉
〈褐色肌プリキュア・セサミに自閉症少女/子どもの多様性育む〉
という見出しが目を引いた。今川綾音記者。
▼これは、以前メモした〈「男の子だってお姫様になれる!」ーー東京新聞の特集に子ども文化を学ぶ〉と同じ系列のニュースだ。
▼今回の