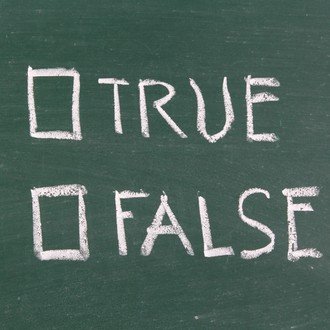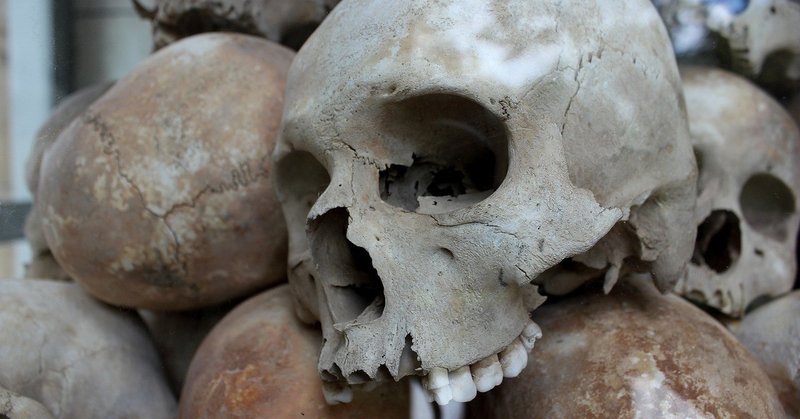2019年4月の記事一覧
「平成31年」雑感20 須賀敦子「古いハスのタネ」の続き
▼前回のつづき。
▼須賀敦子のエッセイ「古いハスのタネ」にあった、
散文は論理を離れるわけにはいかないから、
人々はそのことに疲れはて、
祈りの代用品として呪文を捜すことがあるかもしれない。
という一文は、「近代化」された社会の運命を物語っている。
現代の特徴の一つは、人類の歴史のなかで「文書」がこれほど強い権威を持つようになった時代はない。
▼「古いハスのタネ」は1995年の日本で
「平成31年」雑感19 須賀敦子「古いハスのタネ」を読む
▼オウム真理教による地下鉄サリン事件が起きたのは1995年。作家の須賀敦子が「新潮」1996年1月号に書いた「古いハスのタネ」という短いエッセイがある。
いまは河出文庫の『須賀敦子全集 第3巻』で読める。いい全集である。
〈1995年は、宗教という言葉がどっと街にあふれ、人びとの目に触れ、口にのぼるという、忘れられない年であった。なにもこれに限ったことではないけれど、正確な意味がただされないま
「平成31年」雑感18 死刑制度は「存在してはならない生」を想定している件
▼まったく流行(はや)らない議論だが、知っているのと知らないのとでは結果が異なる場合がある話を紹介する。
▼死刑制度の是非について、憲法学者の木村草太氏が「世界」2018年9月号に書いた論文が読みごたえがあった。
〈死刑違憲論を考えるーー「存在してはならない生」の概念〉
▼木村氏はまず、「形式論」の次元で死刑制度を憲法違反だと指摘する。
それは単純な話だ。
日本国憲法の36条は、「残虐な
「平成31年」雑感17 松本サリン事件からマスメディアは変わっていない件
▼オウム真理教の幹部13人が処刑された件で、松本サリン事件について、「今」の話をメモしておきたい。
松本サリン事件の概要については、先にメモしておいた。
▼「創」2018年9月号に、かつて松本サリン事件の際、凄絶(せいぜつ)な報道被害をこうむった河野義行氏のコメント。2018年7月6日、オウム死刑囚13人のうち、7人が処刑された日の災難について語った。適宜改行。
〈6日の執行のニュースが流れ
東京ではGWに深作欣二映画の名作が520円で見られる件
▼ゴールデンウィークに入ったので、おすすめの映画の企画を紹介する。
とはいえ、暴力描写が苦手な人にはオススメしない。
▼しばらく休館していた国立映画アーカイブで、4月23日から5月26日まで、「映画監督 深作欣二」を上映している。住所は東京都中央区京橋3-7-6。
▼じつは今日27日が、最大のお目当てだった「軍旗はためく下に」(1972年、96分)を上映していた。有名な「バトル・ロワイアル」
「平成31年」雑感16 集団処刑への批判がほとんどなかった件
▼きのうのつづき。
▼きのう書き忘れたことが一つあった。1911年に大逆事件があったということを書いたが、二・二六事件と東京裁判のこともメモしておく。
大逆事件で12人が処刑されたのは1911年。ちなみに24人が死刑判決を受け、半数が明治天皇の「仁慈」を受けて減刑されている。
二・二六事件で、軍法会議で処刑されたのは15人。1936年のことだ。
東京裁判では、A級戦犯7人が処刑された。19
「平成31年」雑感15 日本はオウム真理教の「大臣」から順番に殺した件
▼きのうは死刑執行の手続きについてメモした。
▼きょうはオウム真理教の死刑囚13人の、「誰から殺すか」の順番の理由がよくわかる記事があったので、メモしておく。
2018年7月7日付の東京新聞がわかりやすかった。
〈(7人に)共通するのは、元代表の麻原死刑囚をはじめ、7人とも教団内で高い立場にあった点だ。(中略)全員が「大臣」クラス以上だった。〉
▼具体的には、麻原彰晃(松本智津夫)死刑囚を
「平成31年」雑感14 「死刑執行」の決裁には二つの道がある件
▼2018年7月7日付の各紙報道のなかに、「どうやって死刑は執行されるのか」についての少し詳しい記事があった。毎日新聞から。適宜改行。
〈死刑を決める手続きはどう進んだのか。
毎日新聞が過去に情報公開請求で入手した文書や同省関係者らの話を総合すると、死刑執行は刑事局総務課が起案する。〉
▼へー、総務課なんだ、と思った。
〈その後の決裁は二つの道筋がある。
1)「死刑事件審査結果(執行相
「平成31年」雑感13 「無差別大量殺人」を忘れ去る国
▼きのうのつづき。
▼『教育激変』のなかで池上彰氏は、いくつかの大学で教えていて体験した、面白い話をしていた。
〈死刑執行後、講義を担当しているいくつかの大学で、オウム真理教について話をしたんですね。「選挙に候補者を立て、負けると自分たちの王国を建設しようとして過激な活動に走っていった」なんてことを言うと、学生たちは唖然(あぜん)、茫然(ぼうぜん)。要するに、なんにも知らないのです。〉
〈愛
「平成31年」雑感12 「無差別大量殺人」を正当化する伝統
▼先日のメモで紹介した、池上彰・佐藤優両氏の対談が、新刊本になっていた。先日紹介したのは、まともな調査をせずに、オウム事件を幕引きにしてしまった日本国家の失敗についての指摘だった。
▼両氏の本は、中公新書ラクレの『教育激変 2020年、大学入試と学習指導要領大改革のゆくえ』。薄くて手軽に読める。おすすめ。
▼この本のなかで、佐藤優氏がルターの話をしていた。これは、彼がオウム真理教に言及するとき
「平成31年」雑感11 「無差別大量殺人による救済」の行きつく先
▼前号では、オウム真理教が起こした数々の事件の底を流れるのは、「宗教的動機」であり、具体的には「無差別大量殺人による救済」だったことをメモした。
▼今号では、この論理の行きついた先は何だったのかを確かめる。
▼オウム真理教の危険に気づいていた数少ない人の中に、弁護士の滝本太郎氏がいる。滝本氏は「文藝春秋」2018年9月号で次のように書いている。
〈教団が明らかに変質してきたのが1993~94
「平成31年」雑感10 「無差別大量殺人による救済」の論理
▼オウム真理教が用いた「論理」を確かめる、前回のつづき。
▼フォトジャーナリストの藤田庄市氏の論考をもとに考える。「世界」2018年9月号から。適宜改行。
前回、「殺人が救済になる」という論理を紹介した。麻原彰晃が坂本弁護士一家3人を殺すよう命じた時も、同じ論理だった。
1989年、つまり「平成元年」のことである。
〈麻原は殺害命令に際して、「(坂本に)これ以上、悪業を積ませてはならない」
「平成31年」雑感09 オウムにとって「殺人」が「救済」になる件
▼月刊誌「世界」の2018年9月号に、フォトジャーナリストの藤田庄市氏の論考が載っていた。〈死刑大量執行の異常 宗教的動機を解明せぬまま〉というタイトル。適宜改行。
▼オウム真理教は、その犯行が世俗的な動機だと考えると、理解できない行動をとっている。
〈1995年の地下鉄サリン事件と教団への強制捜査の状況を、彼らは「戦争」と認識した。それ故に強制捜査に対して都庁爆弾事件などを起こし、対抗したの
「平成31年」雑感08 オウム報道から欠落した「宗教的動機」
▼刑事司法は、世に言う「真実」を求めるものではない。あくまでも「刑事責任」をはっきりさせるためのものである。
オウム裁判において、刑事司法は己の領分で最善を尽くしたと思う。
法廷は宗教的動機の解明を避けたが、それは日本の刑事司法が不完全だということではない。それは、そもそも、そういうものなのだ。
▼ここのところの機微をわかりやすい言葉で説明している文献を、二つメモしておく。一つは、「中央公論