
本格ミステリとは何か : 「やさしい共犯」の深層心理
鏡は横にひび割れぬ
「ああ、呪いが我が身に」と、
シャルロット姫は叫べり。
一一テニスン「レイディ・オブ・シャルロット」より
本年(2022年)8月24日に亡くなった、旧友と呼んで良いだろう、ミステリ作家・光原百合についての「作家論」を、私はその死の直後といってよい時期に書いた。
これは私なりの、旧友への、「追悼文」であると言うよりは、むしろ「惜別の辞」であろう。私が彼女を、どう評価し、どう思っていたかを語ることで、思い残すことなく、彼女を葬送しようとしたのである。
私はこの論文の中で、私が光原百合という作家に対して負わねばならなくなった「責任」の発端として、彼女の本格デビュー前の習作たる、短編ミステリ「やさしい共犯」について、次のように書いた。
(少々長い引用とはなるが、彼女に対して負っていた私の「責任」ということの意味をご理解いただくためなので、どうかご容赦願いたい)
『こうしたつきあいの中で、光原さんに関して、最初に思い出すのは、光原さんの応募作品「やさしい共犯」が『本格推理6』に採用されたことから、「SRの会」で開催された、同作の合評会である。
忌憚なく言えば、私はこの「やさしい共犯」を、まったく評価できなかった。と言うよりも、これは「間違った作品だ」という、積極的な否定評価を下した。一一だからこそ、この合評会に参加するのは、正直、気が重かったのだが、私はその場に参加して、光原さんを目の前にし、正直にその評価を語ることから逃げるわけにはいかなかった。
すでに、当時の私は「批評家」としての自意識を持っており、身内であろうと何であろうと「作品は作品として、差別なく評価する」ということを自らに課していた。
だから、合評会において私がどのような評価を語ることになるかは、事前にハッキリしていたため、私が願ったのは「せめて、否定評価を下すのが、私だけではなければいいのだが」ということだった。
「やさしい共犯」の内容を紹介しよう(※ ネタバラシもする)。
手元に『本格推理6』がないので、もっぱら記憶に頼っての記述となるが、記憶違いについてはご容赦願いたい。
この作品も、『遠い約束』などの「浪速大学ミステリ研究会もの(なんだいミステリ研もの)」に属する「学生もの」だったと記憶する。
この作品では、ある男子学生が、何らかの被害(凶悪犯罪ではなく盗難などの、比較的小さな犯罪被害)に遭う。そして主人公がこの謎を解いたところ、犯人は、この男子学生に心を寄せていたものの告白することができなかった女子生徒の「親友の女生徒」であった。
で、どうしてこんなことをしたのかと言うと、この男子生徒が、女心にまったく鈍感であり、その結果として、想いを寄せる女生徒を、深く傷つけていたため、「すこし懲らしめてやれ」と犯行に及んだ、ということである。だからこそ「やさしい共犯」ということになるのだ。
前述のとおり、この要約も部分的に間違っている蓋然性が低くないが、要は、私が「否定的評価」を下したのは、そうした「ミステリとしての作り(設定やストーリーなど)」の部分ではなく、作者自身が気づいていない「犯行動機の不備」であった。
この作品の狙いは、言うなれば「鈍感男を懲らしめる、友情物語(いい話)」だと言えるだろう。そう考えたからこそ、作者はこの作品に「やさしい共犯」というタイトルを付けたのだ。
だが、これはあまりにも「女生徒の側」の偏した、一方的な非難による犯行ではないだろうか。
たしかに、その「鈍感」ゆえに他人を傷つけることはあるし、鈍感であるよりは「繊細敏感」であり「察しが良い」に越したことはないだろう。まさに「名探偵」のようにだ。
だが、「鈍感」であるということは「罰せられるに値する罪」なのだろうか。言い換えれば、「繊細敏感」であり「察しが良い」人間でなければ、罰せられるのが当然なのだろうか。
一一だが、これはきつい言い方をすれば「繊細人間のエリート主義」であり「選民意識」であり「優生学的な思想」である、とも言えよう。
女子生徒の気持ちに気づかなかった男子生徒は、何も「わざと気づかないふりをしていた」のではない。故意に「イジワル」をしていたわけではないのだ。純粋に、単純に、ただ「気づかなかっただけ」なのである。だから、彼は、自分がそうした被害に遭う理由に、まったく思い当たらなかったのだ。
無論、彼に想いを寄せて「片思い」に苦しんでいる女子生徒の「親友の女子生徒」にすれば、「なんたる鈍感男! 彼女をこんなに傷つけて、絶対に許せん!」という「気持ち」になるというのは、わからない話ではない。しかし、だからといって、何の悪意もない彼を「罰する」行為が「正義の行い」として行われたのだとしたら、それはまごうことなき「独善」ではないだろうか。
そして、本作の問題点は、そうした「独善」を持っているのが、作中の「片思いの女生徒の、親友の女子生徒」ではなく、作者自身である、という点なのだ。
作者が、作中の「可哀想な女子生徒と、その優しい友人」に一体化してしまって、状況を客観的に見ることができなくなっており、この「独善的行為」を「思いやりある優しい行為」として描いてしまっている点なのである。
私は、こうした評価を、光原百合の目の前で語らなければならない立場に立たされた。だから、「せめて、否定評価を下すのが、私だけではなければいいのだが」と思い、できればそうした評価を「誰かが私より先に語ってほしい」と願ったのだ。
だが、現実は、そう甘くはなかった。
現実には、私より先に評価を語ったすべての人が、「やさしい共犯」を「心優しい物語」として「光原さんらしい」などと褒めそやした。
そして私は「この無能どもめが!」と、目の前が真っ暗になる思いがしたのだが、自分の番が回ってくれば、私は私の使命を果たすしかなく、淡々と私の評価を語り、説明した。当然、その場が凍りついたのは、言うまでもないことだろう。』
ここでの「やさしい共犯」の内容紹介には、記憶違いによる間違いがあった。この作品で描かれたのは、「学生」間の「事件」ではなく、大学時代に仲の良かった仲間内での、卒業後の再会時に発生した「事件」であった。
ただし、中身的に大した違いはない。要は「ある女性から片思いされていることに、完全に鈍感であった男性が、ほかの友達から懲らしめられる」というお話だったのである。
だから、私がこの物語に感じた「間違った作品だ」という評価の根拠も、上の引用文に書いているとおりである。
要は、この「ささやかな代理復讐」は、一方的で独りよがりな「正義」の暴力でしかなく、作者がそれにまったく気づいていない点に最大の問題があった、ということだ。
私はこの合評会において、光原の友人として、彼女のこの習作に「お世辞」を述べるのではなく、その根本的な「錯誤」を正さなければならなかった。
言うなれば、彼女に対し「その正義の犯罪とやらは、倒錯した復讐でしかない」という真相を告げることで、彼女の「やさしさ=正義」という無難な「うぬぼれ鏡」に「ひび」を入れ、その結果として、彼女に『凍りついたような表情』させねばならなかったのだ。(※ 『凍りついたような表情』というのは、「やさしい共犯」作中の描写)
さて、私は上の論文「弱かった人:光原百合『遠い約束』ほか」を書いた際、残念ながら、「やさしい共犯」の掲載された公募作アンソロジー本『本格推理6』(鮎川哲也編)が手元になかったため、「やさしい共犯」の内容紹介が不正確なものとなり、かつ、本稿の冒頭に掲げたテニスンの詩については、完全に失念していた。
このテニスンの詩は、アガサ・クリスティの『鏡は横にひび割れて』からの孫引きとして「やさしい共犯」の冒頭にも掲げられており、これらの作品の象徴するものとなっている。本稿冒頭での引用は、その形式を踏まえたものだ。

ともあれ、私としては、光原百合に対する「責任」を果たすためには、やはりこの「やさしい共犯」を再読して、かつての私の評価が適切なものであったのかどうか、それを確認したかった。
しかし、無論、自身の評価が正しかったであろうとほぼ確信していたから、前記の論文「弱かった人」を、光原の逝去後の早い時期に書いたのだが、しかし、それでも確認する義務はあると思っていたので、今回、やっと同アンソロジーを入手して再読し、このように改めて論じることになった。
だがまた、それだけのことであれば、物語については記憶違いはあったものの、作品の肝の部分とその問題点理解に間違いはなかったと、それだけ書けば、用は済んだ。
しかし、それで終わらせることができないと今回考えたのは、光原百合に憑いていた「呪い」とは、「本格ミステリ」というものの本質に由来するものだったのではないか、ということに気づいたからである。
したがって、そこを論じずに済ませるわけにはいかないと考えたのだ。
「本格ミステリ」というものが、その本質において、どのような性質を持っているのか。そして、それが光原百合に憑りつき、要は「本格ミステリという呪い」がかかったために、彼女は「やさしい共犯」という作品を書いてしまったということだったのではないか。
一一私が以下に論じるのは、そのような「本格ミステリ」についての本質論であり、その精神史である。
○ ○ ○
「やさしい共犯」における作中の「事件」とは、大学時代に仲良しグループだった、男2人女2人の4人組が、社会人となってひさしぶりに再開した喫茶店での、たわいない雑談中に発生する。
たまたま、この喫茶店に、『遠い約束』の主人公で語り手の「吉野桜子」を含む「浪速大学ミステリ研究会(なんだいミス研)」の4人が居合わせて、その「事件」の謎解きをするというお話だ。
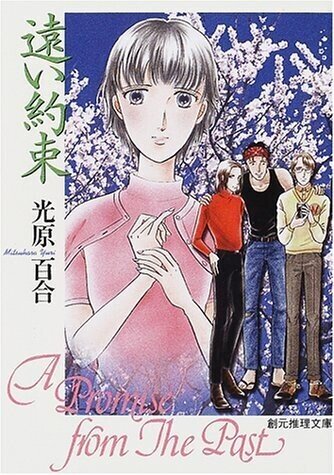
要は、その「社会人4人組」の雑談の中で、ある一瞬、その中の一方の女性が『凍りついたような表情』を見せたのだが、それは何故だったのかというのが、この作品の肝である。
すでに紹介したとおり、この女性は、学生時代から、その「4人組」の中の2人の男性の片方に、ひそかに思いを寄せていた。つまり、片思いをしていた。
そんな彼女は、「思い人」との、ひさしぶりの再会ということで、おめかしをして出かけたのだが、雑談の中で、彼が「結婚した」ことを知らされ、「片思いという呪い」が解けて(希望が失われ)「鏡が横にひび割れ」て(傷つき)『凍りついたような表情』を見せた、という次第である(ちなみに、彼女の「片思い」を「呪い」と考えるか、この「失恋」を「呪い」と考えるかで、その意味するところが真逆になる点に注意)。
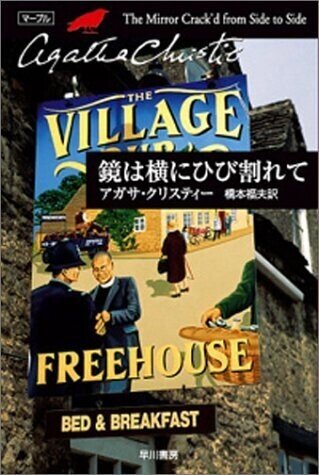
彼女(仮に「シャルロット」嬢と呼ぼう)のこの『凍りついたような表情』の原因については、彼女に片思いされていた「鈍感男」氏以外の2人の男女は気づいていた。かねてより、彼女の「片思い」を知っていたからである。
そんな(「鈍感男」氏以外には)気まずい会話の後、4人が店を出ようとしてところで、一歩先に店外に出たシャルロット嬢の身に発生したのが、軽微な「あて逃げ」容疑事件だ。
角から飛び出てきた車に驚いたシャルロット嬢が転倒して、頭を打って気を失う。その状況を見ていたのは、同じく先に店を出ていた「鈍感男」氏だけであった。
シャルロット嬢は、そのまま救急車で病院搬送され、残りの友人3人と、なぜか「なんだいミス研の4人」は、シャルロット嬢が搬送された病院へと向かう。
そして、その病院の待合室において、事故を目撃したのは「鈍感男」氏のみという状況を利用し、残り友人2人(男女)と、一連の事情を察した「なんだいミス研の4人」が(暗黙のうちに)協力し、「鈍感男」氏を「あて逃げ偽装事件の犯人」とする「冤罪」をイタヅラ的にでっち上げて「告発」し、精神的に「懲らしめる」。一一これは、そんな奇妙なお話なのだ。
このお話が、お門違いの「正義の名における暴力」でしかないというのは、すでに説明済みであるから、本稿で問題とするのは「なぜ、作者・光原百合は、こんな独り善がりな作品を書いてしまったのか?」という点について、ということになる。
そして、結論から言えば、「真面目な正義漢」でありながら、しかし「この世の理不尽さ」と真正面から対峙することのできない「弱い人」であった光原は、「フィクション」の中で「この世の理不尽さ」に対して鉄槌を下す「代償行為」によって、自身の「弱さ」というやましさから「観念的自己回復」を果たそうとした、ということになろう。
言うまでもなく、この現実世界は「理不尽」である。
例えば、「正義は勝つ」とは限らないし、「努力は報われる」とは限らない。同様に、どんなに切実かつ誠実な「愛」であっても、それに見合う「見返り」がある保証などない。
この世は、あまりにも「不公正(アンフェア)」であり、その意味で「理不尽」なものなのだ。
私たちの多くは、幼い頃に「正義は勝つ」とか「努力は報われる」といった「理想」を、あたかも「現実」そのものであるかのように教え込まれる。だが、人生経験を積むうちに、それは「理想」でしかなく、「現実」そのものではないということを、嫌々ながらも学んでいき、徐々に、この世の「現実」との「折り合い」をつけていく。
ところが、そういう「折り合い」のつけられない人がいる。そうした「折り合い」を、むしろ「敗北主義的な妥協」であるかのように感じ、それを「受け入れられない」と感じる「真面目な人」がいるのだ。
しかし、そういう「真面目な人」も、現実社会で生きていく中では、不本意ながらも「現実との妥協」を強いられ、それを受け入れざるを得ない経験を重ねることになるだろう。その結果、その人の中には、「不本意さ」だけではなく、「罪悪感」や「後ろめたさ」が、澱のように積み重なっていく。
そして時に、「論理(意味)のユートピア」である「本格ミステリ」は、そんな「屈折を抱えた真面目な人」に対し、一時的なものではあれ、「カタルシス(浄化作用)」をもたらす。
現実のこの世では「悪が蔓延り」「謎は解かれないまま」になることが多く、その意味で「理不尽(道理が尽くされない)」である。しかし、「本格ミステリ」の中でだけは、そうした現実の澱を残さず、問題をスッキリと解決してくれるのだ。
だから、現実に対して不満を持ってはいても、それと正面切って闘うだけの強い意志を持たない人は、そうした「論理のユートピア」に「逃避」してしまう。一一つまり、そんな「本格ミステリ」ファンの一人が、光原百合だったのだ。
○ ○ ○
笠井潔の「大戦間ミステリ論」とは、「謎と論理のユートピア」である「本格ミステリ」が、欧米において、二度の大戦に挟まれた時期に、その「黄金期」を迎え得たのは、第一次世界大戦における「大量死」の経験によるものだ、とする議論である。

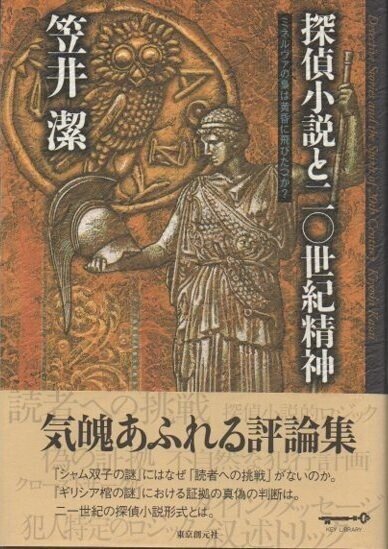
それまでの戦争では、「兵士=戦士」としての尊厳が、曲がりなりにも生きていた。戦士たちは、「やあやあ、我こそは」と「名乗り」をあげ、自身の尊厳とプライドを賭けて戦い死んでいった、そんな「騎士」たちの末裔であった。
ところが、第一次世界大戦では、機関銃、毒ガス、飛行機、戦車といった「大量殺戮兵器」が導入されることにより、「兵士」たちは、敵の顔も見ないまま、「名もない死骸」へと変えられていき、その「尊厳」を決定的に奪われたのである。
第一次世界大戦がもたらした「大量死」は、個人を「死骸の山の一部」であったり、「無惨な挽き肉=生ゴミ」に還元して、人間の尊厳を決定的に毀損してしまったのだ。
だからこそ、そうした「無意味な死」に堪え難さを感じる「知的」な人たちは、「人間の死」に「意味を回復する」物語としての「ミステリ」を愛好し、その形式を発展させた。
殊に、「ミステリ」の中でも「論理的解決」を重視する「本格ミステリ」の形式が、この世の「無意味」や「理不尽」に傷ついた人々の「無力感」や「虚無感」を癒すものとして、ほとんど無自覚的にではあれ、歓迎されたのである。

「本格ミステリ」において、作品の冒頭に登場する「殺人被害者の死体」は、「大量死の戦場における、尊厳なき無名の死体」の対極にある、「特権的な存在」だ。
その死体は、名探偵や警察官などによって「特別扱い」にされる。
「彼は、何者なのか?」「彼は、なぜ、殺されたのか(死ななければならなかったのか)?」「彼は、どのような方法で殺されたのか?」と、寄ってたかって「注目」され、その「死の意味」が、当然のごとく探求される。一一それが「本格ミステリ」という小説なのだ。
笠井潔は、こうした「本格ミステリ」における「死体」の扱いを、「二重の光輪で飾られる」と表現した。
それは、物語冒頭に登場する「死体」は、彼を殺した犯人によって「偽装(偽の意味)」が施され、物語の最後では名探偵によって、その「偽装」が解体されて、本来の意味が回復される、ということを意味する。
つまり、大量死の戦場における死体は、その場に置き去りにされなかったとしても、個別認証も十分になし得ないまま、ひとまとめに穴の中に放り込まれ、そのまま埋葬されたりする。
それに比べてば、「本格ミステリ」における死体は、個別的に、言うなれば懇切丁寧に、二度も、その死に「意味が与えられる」のだ。
そして、これは、現代の日本においても同じだった。
戦争における「大量死」の無意味性に堪えられない精神が、「本格ミステリ」という文学形式を発展させたのだとしたら、バブル経済末期の豊かな現代日本において、なぜ「新本格ミステリ」ブームが起こったのだろうか、という疑問は、当然のごとく提起された。
この疑問に対し、「大量死理論」の提唱者である笠井潔は、「大量生」という言葉で応じた。
戦争における「大量死」が「個人の尊厳」としての「意味」を見失わせたのだとしたら、バブル経済期末期の「大量生」の「豊かな時代」においては、「大量死」とは逆さまのかたちで、ブロイラーのごとき「大量生産的な生」を生かされる若者たちもまた、その「生きる意味」を見失っていたから、意味回復の物語としての「本格ミステリ」が求められたのであろう、という議論だ。
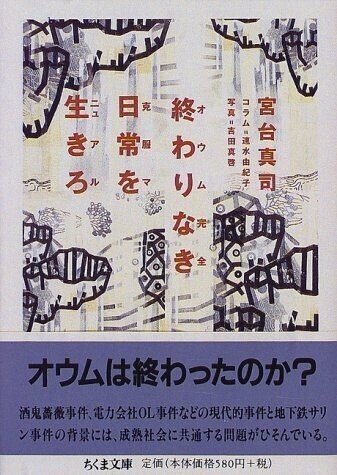
実際、「バブル期」の頃、人々は必ずしも「生の充実」を感じていたわけではなく、むしろ「浮かれ騒ぐ生活の中で、どうしようもない虚しさ」を感じていた。ただ快楽を求めて刹那に生きるだけの生活に、疑いを感じていた。もっと「意味のある生き方」があるのではないかと「生きがい」を求め、「自分らしい生き方」とは何かと問うて、「自分探し」の旅に出たりしたのである。
こうした「豊かさの中の虚しさ」、言い換えれば「群衆の中での孤独」的な「意味喪失」において、日本の若者たちは「意味回復の物語」を希求した。それが「新本格ミステリ」ブームだったのだ。一一というのが、笠井潔の「大量生」理論である。
じっさい、「本格ミステリ」とは、その本質において「逆説的」なものである、と言ってもいいだろう。
つまり、「合理的・論理的な思想や思考」が優勢なご時世だからこそ、「合理的・論理的な作品」が求められる、というわけではない。
そうではなく、むしろ真逆に、この世の中が「非合理的・非論理的」つまり「理不 尽」であるからこそ、「合理的・論理的な作品」が求められる。
「大量死」の経験における「意味喪失」によって「本格ミステリ」が求められたというのは、わかりやすい話だが、その逆である「大量生」の経験における「意味喪失」の方も、決して難解な話ではないだろう。
「大量生」においては、「個人」の価値は相対的に下がって、「私が私であることの特権的な意味(「世界に一つだけの花」としての存在価値)」が見失われるからである。
こうした「逆説」性は、例えば『ブラウン神父の童心』などで知られる「逆説のミステリ作家」であった、G・K・チェスタトンなどにも、象徴的に見られる。「ブラウン神父シリーズ」に見られる面白さは、その「逆説的論理」にあると言って良いだろう。
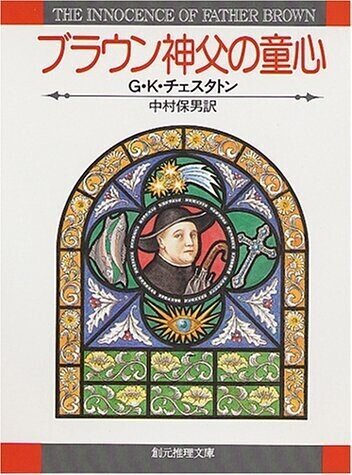
例えば「彼は、気が狂っているから、殺人を犯した」という説明は「順接の論理」だから、面白くない。要は「当たり前」だから面白くないのだ。
だが、「彼は、誰よりも心優しく、人の命を大切にした人だからこそ、殺人を犯した」という説明は、「逆説の論理」だからこそ、人の想像力を刺激し、より「深い意味」が感じられ、その点で「面白い」のだ。
で、このように、「順接の論理」は当然として、「逆説の論理」まで見事に駆使してみせる「アクロバチックな論理家」であるチェスタトンが、人としても「合理主義者」であったかというと、必ずしもそうではなかった。
英国人である彼は、プロテスタント(新教)の一つである「英国国教会」から、わざわざ「カトリック(旧教)」に「改宗(帰正)」した、カトリックの「伝統」の重要性を強調する「護教家」であり、「保守思想家」であった。
彼は、カトリックの教えである「マリアの処女懐胎」や「イエスの、死後の復活と、さらに5日後の肉体を持った昇天」といったことを「奇跡」の教義を、「心から(文字どおりに)信じる」と「信仰告白」した、「非科学的で非合理主義的な信仰者」なのである。

どうして、こんなことになってしまうのかと言えば、それは彼もまた、「近代」のおける「意味の喪失」に堪え得なかった「弱い人」の一人だったからだ。
「神は死んだ」「近代的合理主義と科学の発展によって、宗教は過去の遺物と化した」という趨勢において、彼らは「不安」を覚えた。
すべての事物の「存在の意味」を根底で保証するのは「創造神たる神」であって、それが無くなってしまえば、私たちは「意味の宙吊り」の不安定状態に生きなければならない。だが、そんな「無意味」になど、とうてい堪えられない、という意識が、彼らにはぬぐい難くあった。
ところが、「神」を殺した「近代的理性」は、決して「神」の代わりにはならなかった。その証拠が「第一次世界大戦」における「大量死」の惨禍だ。
「理性を信じ、科学を信じれば、きっと人類は、より良い世界を作れる」と言っていたのに「このザマはなんだ?!」というのが、大戦間における「反動」の心理的根拠であり、チェスタトンの「カトリックへの改宗=伝統回帰」も、そうした文脈でなされたものだったのである。
つまり、過剰に「合理的・論理的」であるというのは、じつは「この世の現実としての、不合理・理不尽」に堪えられないということであり、その意味での「現実逃避の一種」だということだ。
チェスタトンが、典型的な「本格ミステリ作家」であると同時に、頑迷な「保守主義者」であり「護教家」であったというのは、決して矛盾したことではなかったのである。
チェスタトンには、『正統とは何か』と題する、カトリックのための有名な護教書があるけれども、ここで言う「正統」とは、言うなれば「本格ミステリ」における「本格」と同じような「権威主義的なもの」だと見ていいだろう。
「これこそが、根本であり、揺るぎない真理なのだ」と信じたい「現実逃避」的な弱い心の引き寄せた、それは、いかにも「強そうで偉そうな言葉=頼れそうな言葉」だったのである。

また、日本の「新本格ミステリ」が、それまでの主流だった「社会派ミステリ」を駆逐したという「歴史」も、同様の心理によるものであろう。
「社会派ミステリ」とはどのようなものだったかというと、要は「社会的な矛盾」としての「社会悪」を敵としてテーマ化した、謎解き形式を採り入れた小説だと言えるだろう。
つまり、「社会派ミステリ」においては、社会的な「不合理」や「不条理」あるいは「理不尽」というのは、自明な事実(現実)として、その存在を認められている。
だが、それをそのまま容認するわけにはいかないから、それを、この現実社会における「正義の論理」において告発し、裁くことで、少しでも正し減らしていこうとする、言うなれば「現実改善主義的な小説」だったと言えるだろう。

(松本清張)
だが、「社会派ミステリ」は、本質的な矛盾としての「弱点」を抱えていた。
それは、この現実世界は「不合理」で「不条理」で「理不尽」なものだということを認めながら、それを「合理性」において解決しようとした点、つまり、「正義は勝つ」という不合理な信念への、無根拠な信仰である。
「合理性」によって、現実の「不合理」や「不条理」や「理不尽」なものを解体するという行為は、論理的な矛盾をはらんでおり、おのずと限界があるのだ。
だからこそ、この世の中には「不合理」なものや「不条理」なもの「理不尽」なものが、のさばっているのであり、「社会派ミステリ」の中で「現実的な悪」が懲らしめられはしても、それは多くの場合「フィクション」の中だからこそ可能なものでしかなく、どこかで「大人のファンタジー」性を帯びたものとならざるを得ない。
したがって、「厳しい現実」に直面している人からすれば、「最後に正義が勝つ、社会派ミステリ」こそ「現実逃避の娯楽」でしかないということにもなろうし、逆に「最後に正義が破れる、リアルな社会派ミステリ」は「娯楽にもならない、不愉快な小説」といったことになってしまうのだ。
だから、どうせ「現実」に対抗する力が無いのであれば、いっそ「ファンタジー」に徹したほうが、文学形式として純化されていて「美しい」、ということにもなってしまう。
「小説中における純粋論理」では扱いきれない「リアルな矛盾」など、無理に扱うからこそ「社会派ミステリ」は「中途半端なもの」になってしまうのだから、いっそ「ミステリ」は、「社会性」など捨てて、「謎と論理のファンタジー」に徹したほうが「気持ちがいい」だろう。一一というのが、「本格ミステリ」の「精神」だと考えてもいい。
「僕らはもう、どうにもならない社会悪になど向き合いたくない。そんな面倒なイデオロギーなどとは関わりたくない」というのが、「新本格ミステリの精神」だと言っても、決して間違いではないのである。
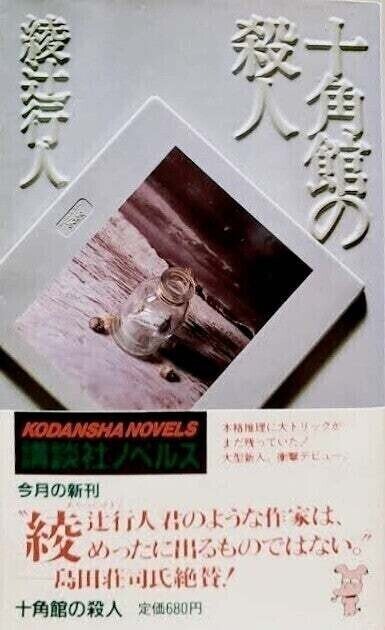
さらに忌憚なく言えば、彼らは、「社会における政治ゲーム」ではなく「子供部屋の論理ゲーム」に耽溺したかったのだと、そうも言えよう。
だが、そんな「ユートピア」を成立させるための「新本格ミステリ」文壇にも、政治ゲームが発生したのは、必然的なものではあれ、皮肉な現実であった。
○ ○ ○
以上のように、「本格ミステリ」というものは、「合理性・論理性の重視」、あるいは、そうした「こだわり」において、「現実逃避」的なものであり「宗教的」なものであった、と言っても良いだろう。
少なくとも、「その虚構世界」の内部に止まっているかぎり、世界の「意味」を保障する「神=論理性」は揺るぎなく存在し、そこに身を委ねているかぎり、「意味の宙吊り」としての「非合理性」「非論理性」あるいは「理不尽」に脅かされることはないからである。
そんなわけで、「意味の宙吊り」としての「非合理性」「非論理性」あるいは「理不尽」に脅かされて、「スピリチュアル」でさえあった光原百合が、「本格ミステリ」の「論理的な世界」に「救い」を見出したというのは、それこそ論理的な帰結であって、決して「矛盾」したことではなかった。
光原もまた、「非合理性」「非論理性」あるいは「理不尽」な世界に傷つけられた結果として、「本格ミステリ」の虚構世界に逃避した者の一人であり、それはチェスタトンをはじめとした、多くの「本格ミステリ作家」と同じことだったのだ。
そして、拙稿「弱かった人:光原百合『遠い約束』ほか」でも指摘したとおり、光原が「アンチ・ミステリ」的なものを無意識に嫌ったのは、それが「謎と論理のユートピアたる本格ミステリ」を、もう一回、論理的にひっくり返して、「現実世界への通路」を開くものだったからである。
「アンチ・ミステリ」とは、「非合理」的で「非論理」的、あるいは「理不尽」な現実世界への、回帰をうながす性格を隠し持っていた、「合理的な非合理小説」だったのである。
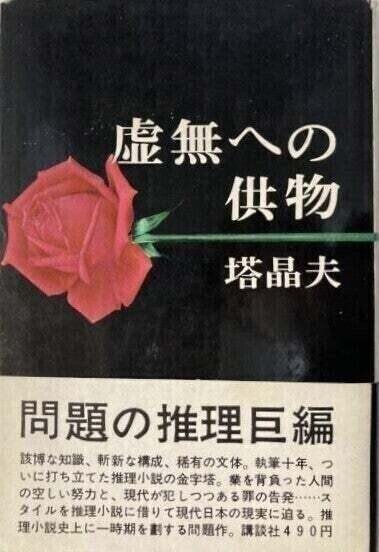
昨今、ミステリの世界では、「多重解決ミステリ」や「特殊設定ミステリ」といったものが流行っており、その意味では「正統派の本格ミステリ」が相対化され、弱まっているようにも見えるが、これはどういうことだろう?
例えば「多重解決ミステリ」とは、「本格ミステリ」の「ファンタジー」性を暴くことにより「現実回帰」を促す、「アンチ・ミステリ」的な性格を持ったものなのだろうか?
そうではない。
たしかに、かつての「多重解決ミステリ」には、「本格ミステリ」的な「特権的解決(解釈)」を相対化して、その「欺瞞(虚構性)」を暴く、といった性格を持たされた作品もあっただろう。
だが、昨今の「多重解決ミステリ」における「多重解決」とは、読者を「現実世界」へと導くものではなく、むしろそれとは真逆に、自ら構築した「合理性の迷宮」に自らを封じ込める、という意図によるものだと見ていい。
「たしかに、本格ミステリにおける特権的な解決などといったものは、本格ミステリという形式が生み出した、一種のファンタジーでしかない。それは認めよう。しかし、それなら、どこか他所に、正しい解釈としての真理などというものが存在するのかと言えば、そんなものもまた、ありはしない。つまり、私たちができることと言えば、多様な解釈の迷宮のなかで、比較的もっともらしい解釈を求めて、非決定的に、さまよい歩くことだけなのだ」といった、「ニヒリズム」である。
「非合理的」で「非論理的」で「理不尽」なこの現実世界に対して、「合理性・論理性の徹底」において抵抗する、といった「キレイゴトの建前」の失効は、もはや明らかであるからこそ、もう「非合理的」で「非論理的」で「理不尽」なこの現実世界への抵抗なんていう偽善的なタテマエは「放棄します」というのが、昨今の「多重解決ミステリ」の精神性だと言えるだろう。
であれば、「特殊設定ミステリ」の精神性が、いかなるものかもまた、もはや明白であろう。
それは「どうせ、この現実世界との闘いが、敗北を運命づけられたものなのであれば、この世界にこだわる必要などどこにもない。つまり、ユニークな合理性に遊ぶのならば、不自由なこの世界への執着を捨てて、ユニークな合理性の成立する、ユニークな世界をでっちあげれば、その方が首尾一貫していて美しいものになり得るというのは、理の当然だ」といった「開き直り」に発するものなのだ。
○ ○ ○
このように「本格ミステリ」というものには、その根底において「非合理的」で「非論理的」で「理不尽」なこの現実世界に対する「ニヒリズム」が存在する。
どうしたって、この世界との闘いでは、敗北が運命づけられているのだから、そこからの逃避が、どうしていけないのか。自分たちが勝利しているかのような「虚構世界」をでっち上げ、そこで遊んでいてはいけない、などというご託宣を口にする権利が、誰にあるというのか。一一そうした思いが「本格ミステリ」における「論理のユートピア」性を支えている。
たしかに、この世界には、「唯一の真理」だとか「不動の現実」などといったものはないだろう。
何かが「実在」すると仮定したとしても、私たちは「それそのもの」に接することはできない。私たちに可能なのは、ただ、「解釈」だけなのである。
そして、そんな「解釈」を持って、私たちはそれを、「真理」だとか「現実」だとか「事実」だなどと錯覚しがちなのだが、そこに「解釈深度の優劣」はあるにしろ、いずれにしても「解釈」とは「人の数だけ存在する」ものであり、その意味で、それは「唯一の真理」だとか「不動の現実」などといったものではあり得ない。一一私たちは、そんな「不安定」で「何の保証もない世界」に住んでいるのである。
こうした、絶対的に「不安定」で「何の保証もない世界」において、心理的に相対的優位に立つことで安心を得ようというのが「ニヒリズム」である。「真理など無いなんてことはわかっているが、私はそんなことなど気にはしない」という「強がり」である。
その典型的なものといえば、例えば、かつて柄谷行人との対談で、笠井潔が口にした「理屈など、どうとでもつけられる」という「開き直り」であろう。

たしかそのとおりだ。仮に「真理はひとつ」であっても、その「解釈は無限」であるとすれば、頭の良い人間は、次から次へと「その場かぎりの解釈(一人多重解釈)」を繰り出しては、現実の難局を乗り切っていくだろう。
それが、「不条理」で「何の保証もない」この世の中においては、むしろ「賢い生き方だ」と賞賛されることだって少なくない、というのも事実である。
しかし、こうした生き方には「私は、常にぺてん師である」という「やましさ」が、ついて回ることになるだろう。かりに格好良く、この不条理な世界をそのままに「すべて良し」と認めて見せたところで、自分自身の「やましさ」からは、決して逃れられないはずだ。
ご立派な理屈も、所詮は「自己正当化」のためのものであれば、その理屈は、少なくともその当人にとっては、完全な欺瞞効力を持ち得ないからである。
○ ○ ○
いずれにしろ、この世界には、完璧な救いなどない。完璧な意味としての「特権的な意味」が存在しないのだから、それは当然のことだ。
だから、私たちはしばしば、特権的な「真相」を保証するかのような物語(フィクション)に、すがりつく。その代表的なものが、「宗教」であり「イデオロギー」であり「本格ミステリ」だ。
だが、同時に、それらの保証する「真相」や「真理」が、作りごとの嘘っぱちであるという思いも、私たちのどこかに、ぬぐいきれずに残っている。だから、そうした「見たくない現実としての理不尽」を、私たちは憎む。
しかも、圧倒的な「悪」としての「理不尽」には、「社会派ミステリ」のように正面切っての闘いを挑む自信など無いけれど、「小さな理不尽」に対してなら、何とか勝てそうだし、それが「小さい悪」だからこそ、余計に目障りで、勘に触る、といったこともあるのではないだろうか。
例えば、悪徳政治家や暴力団の存在については、もはや気にならないが、マスクをしていない人、くわえタバコで歩いているような人は「絶対に許せない」というような、事の軽重判断の転倒した、歪んだ感性である。
しかし、これこそが、光原百合の「やさしい共犯」に描かれた、処罰されなければならない「小さな悪」の正体だったのである。
「この程度の小さい悪に対してなら、私たちが力を合わせて、リンチにすることも可能だ。報復の恐れもないだろう」と、無意識ながらも、そう考えて実行された、その「ささやかな犯罪」において、作者は「主犯」であり、作中人物である「吉野桜子となんだいミステリ研のメンバー」たちは、「やさしい共犯」であった。
「私たちの小さなユートピア」の中に、「無神経」という「小さな悪」を持ち込んでくる存在は、許さない。
みんなが、お世辞にも「良い作品ですね」という作品に対して、「空気」も読まずに「これはダメでしょう。こんな作品を褒めるなんて、どうかしている」などといった本音をぶちまけるような「無神経」な輩は、裁かれ罰せられてしかるべきである。一一このようにして、学校や職場における「イジメの論理」も正当化される。
「やさしい共犯」という「意味回復の物語」の深層に秘められていたのは、「小さな楽園での幸福」に「ひび」を入れようとする、そんな「情け容赦のない現実」の声への、物語の中という自分だけのフィールドでの、「復讐心」であったと言えるだろう。
そして、さらにその根底にあるのは、「非合理的」で「非論理的」で「理不尽」なこの現実世界への、「ルサンチマン(恨みつらみ)」という「黒い感情」であり、その解消としての「やつあたり」であった。
端的に言ってしまえば、光原百合の「やさしい共犯」という作品に私が見た「許すまじきもの」とは、ニーチェが何よりも憎んだ、「弱き者たち=畜群」のための「癒しの物語」という性格であったのだ。

光原百合が、その自覚のなさにおいて、その後もそのままの姿勢で「本格ミステリ」を書くことがあってはならないと思ったからこそ、私は友人として、彼女の「本格ミステリ」という「うぬぼれ鏡」を叩き割り、彼女やその周囲の「本格ミステリマニア」たちに『凍りついたような表情』をさせないではいられなかった。そのことで、「呪い」を解こうとしたのである。

(2022年10月23日)
○ ○ ○
○ ○ ○
