
谷崎潤一郎 『陰翳礼讃・ 文章読本』 : 美しい国の「美しい文章」へ
書評:谷崎潤一郎『陰翳礼讃・文章読本』(新潮文庫)
今回、本書を読んだのは、前々から「陰翳礼讃」が気になっていたからだ。
谷崎潤一郎の「陰翳礼讃」を褒めたり引用したりする日本人の99パーセントは、「日本人には昔から、暗闇の魅力を知る繊細さがあった。西欧人のように、すべてを光に下に明らかにしてしまうような、無粋で無神経な態度は、繊細な日本人には不可能なことであった」といったような、「受け売りの自慢話」をしたがる阿呆で、それが我慢ならなかったからである。
谷崎がこうしたことを書いているからと、頭の悪い読者は、その権威に乗っかることで、まるで自分までもが、西欧の「近代的理性主義」をのり超えたつもりになる。まったく、うんざりさせられる阿呆どもだ。
その実例を見たければ、本書の「Amazonカスタマーレビュー」を確認するといい。
「近代理性主義」の何たるかも知らなければ、自分でそれと対決したこともないような凡百の徒が、谷崎の尻馬に乗って「日本人はこれでいいんだ。もともと、ある意味では日本人の方が優れていたんだ」と、まるで自分が「優れた日本人」ででもあるかのような、いかにも頭の悪いことを書いている。しかし、そんな愚物こそが、まぎれもない「日本人」の典型なのである。
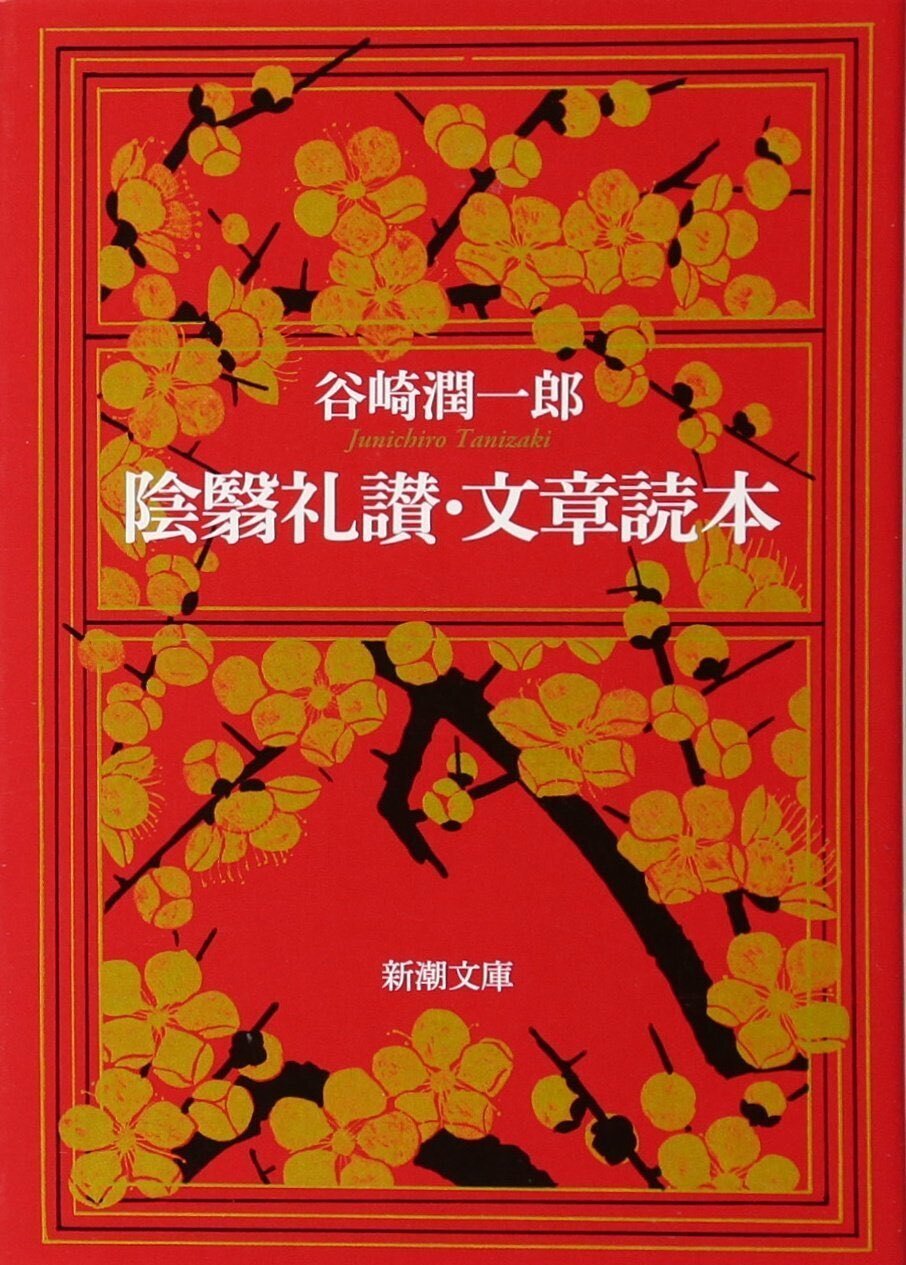
そもそも、日本人がそんな「繊細」なら、馬鹿みたいに「日本人は繊細だ」などという「自慢話」を、大っぴらに書くわけがない。書ける道理がない。
同様に、日本人が「奥ゆかしく、我を張らない」という美意識を持っているのであれば、「日本人は、西欧人なんかより、繊細である」などといった、臆面もない「自慢話」などしないだろう。
むしろ、日本人の「弱さ」や「愚かさ」の方を問題にして、西欧に「学ばせていただきます」と謙って、自分に無いものを学ぼうとするはずではないか。
ところが、そうした「謙虚さ」とは真逆に、谷崎の「陰翳礼讃」をうれしがって言挙げするような、「ネトウヨ」並みに無教養な日本人は、「日本人はこんなにスゴイ!」「世界に冠たる日本文化!」とか、あるいは、殺された元首相のように「美しい国」などと、いかにも裏付けに乏しい「自画自賛」を垂れ流して、恥じるところを知らない。
「あんた、それは自慢話ですよ」と、西洋人のごとく、身も蓋もなく指摘してやらないことには、その程度のことにも自ら気づくことはなく、人前での「マスターベーション」を恥じもしないのだ。
まさしく、そんな輩は「日本の恥」だから、とっととこの国から出て行け。一一とさえ言いたくなるのが、西欧人的に「事実は事実として指摘」する私なのである。
○ ○ ○
近年ほとんど興味のなかった谷崎を読んだ、もう一つの理由は、先年、芥川龍之介の『侏儒の言葉 文芸的な、余りに文芸的な』(岩波文庫)を読んだからでもある。
「侏儒の言葉」は、いわゆる「箴言集」、「アフォリズム」集であり、ニーチェなどが好んで書いた「寸鉄人を刺す」といった短文を集めたもの。
「論文」的に理路整然と「説明」するのではなく、物事の本質を、短い言葉でズバリと突くような文章。いかにも、志賀直哉に憧れ、短編を得意とした芥川らしい「批評形式」だと言えるだろう。
一方「文芸的な、余りに文芸的な」の方は、文学に関する連載エッセイで、その時々いろんなことを書いているとはいえ、しかし、この時期、芥川は、谷崎潤一郎と「筋のある小説」論争をやっていた。その一部が、ここに含まれているのだ。
『『文芸的な、余りに文芸的な』(ぶんげいてきな、あまりにぶんげいてきな)は、芥川龍之介が雑誌『改造』1927年(昭和2年)4月号から8月号(7月号は休載)に連載した文学評論。同時代の文豪谷崎潤一郎との「小説の筋の芸術性」をめぐる論争が特に注目される。
この芥川対谷崎論争のそもそもの発端は、1927年(昭和2年)2月に催された『新潮』座談会における芥川の発言である。この座談会で、芥川は谷崎の作品「日本に於けるクリップン事件」その他を批評して「話の筋というものが芸術的なものかどうか、非常に疑問だ」、「筋の面白さが作品そのものの芸術的価値を強めるということはない」などの発言をする。するとこれを読んだ谷崎が反論、当時『改造』誌上に連載していた「饒舌録」の第二回(3月号)に「筋の面白さを除外するのは、小説という形式がもつ特権を捨ててしまふことである」と斬り返した。これを受け、芥川は同じ『改造』4月号に(同誌の記者の薦めもあったと思われる)「文芸的な、余りに文芸的な——併せて谷崎潤一郎君に答ふ」の題で谷崎への再反論を掲げるとともに、自身の文学・芸術論を展開した。
以後さらに連載は続き、谷崎の再々反論、芥川の再々々反論があったが、同年七月芥川の自殺によって、「改造」誌を舞台に昭和初頭の文壇の注目を集めた両大家の侃々諤々の論争は幕切れとなった。』
(Wikipedia「文芸的な、余りに文芸的な」)
決して難しい話ではない。
結局のところ、要は「美意識の違い」でしかないのだ。

今でこそ、小説が「エンタメ=大衆文学」であることは「当たり前」になっているから、芥川の「話の筋というものが芸術的なものかどうか、非常に疑問だ」、「筋の面白さが作品そのものの芸術的価値を強めるということはない」という発言を、「理解不能」だと感じる人も多いことだろう。だが、この時、芥川の念頭にあったのは、多分、志賀直哉の文学である。
志賀が、小林多喜二の、いわゆる「プロレタリア文学」作品について、「主人持ちの文学」といって批判したのは、今時だと知らない人も多いだろうが、文学史的にはあまりに有名な話で、文学史なんぞ学んだことのない私でも、それなりに本を読んでいれば、勝手に耳に入ってくる程度のことでしかない。
ともあれ、ここで志賀が言ったのは、要は「政治的目的実現のために、その道具として小説を書くのは、いかにも不純である。プロレタリア文学とは、要は、思想の下僕となった、エセ文学でしかない」というようなことだ。「芸術は、あるいは芸術としての文学は、芸術として純粋であるべきで、下心を持って書くのは下品であり、二流であり、偽物だ」と、まあそんなことを言いたかったのである。
で、この考え方に賛同する人は、今でも少なくないだろう。
「文学は、人間をありのままに描くものであるべきなのに、イデオロギーに従属したようなものは、為にする小説であり、偽物だ」というような感じだ。
だが、問題は、こうした「純粋指向の芸術主義」というのは、当然のことながら「筋の面白さで読ませるなんて、結局は、美を解さず娯楽を求めるだけの大衆への迎合でしかなく、文学としては不純だろう。それは大衆読者のための〝主人持ちの文学〟だと言ってもいいわけで、文学の本来のあり方には反する。文学とは、何かのため、に書くのではなく、あくまでも書くことにおいて、自己目的的に極められるべきものだ」と、このような考え方にもなりうるわけで、芥川の発言の趣旨も、そうしたところにあったのであろう。
ところが「筋のある小説」こそ「面白い」と思って書き続けてきた谷崎潤一郎には、この言い方がカチンと来た。じゃあ、俺の文学は「不純な文学」「大衆迎合の文学」だと言うのか、ということで反論したのである。
で、この論争は、当然のことながら、谷崎の「現実主義」に、芥川の「理想主義的観念論」が圧倒されることになる。芥川としては、あくまでも「理念的な話」をしたかったのに、谷崎は「現実問題」で反論してきたから、どうしたって分が悪いのは芥川の方だ。
私が谷崎の立場だったら「そういう君の小説だって、筋があるじゃないか。主人持ちはよろしくないというのは、原則としてはわかるけれども、そんな子供にものを言うような抽象議論を振り回されても迷惑だ。人間には色々なタイプがあり、そのタイプに従って、いろんな小説を書くだろう。その中には、筋で読ませる小説を書く作家も当然いるわけだが、それは自分の本性に忠実に、誠実に小説を書いているだけであって、主人持ちというわけじゃないんだよ。だから、そういった、現実を見ない抽象議論は、はた迷惑なだけだね」とでもやり返すだろう。
谷崎が、どんなことを言ったかは知らないが、この程度の反論なら容易だということだ。
だが、しかし、こうした「現実主義」的な反論、というのもまた、芥川の言わんとしたところを「曲解」したものでしかない。
芥川は、自分でも、書きたくても書けない「理想としての文学」を問題にし、作家が「通俗」に流されずに「文学」するための「理想」的な「心がけ」として、それを語ったというのは明白だ。
だから、それに対して「現実」を持ち出すのは、いくらカチンときたとは言っても、基本的に「お門違い」なのである。

しかし、このように「観念的な理想主義」を抱えた芥川龍之介と、「図太いリアリスト」である谷崎が議論になれば、議論の内容ではなく、「押しの強さ」において谷崎が優勢になるのは、それこそ「現実」問題として明らかだ。現実の論争とは、単に「論理」だけで行われるような「抽象的なもの」ではなく、論者の「気迫」で、その様相がコロリと変わったりするようなもの。「これ、言ってもいいのかな?」なんてビビる奴は、論争には勝てないのである。
で、前述のレビューにおいては、芥川に注文をつけた私だけれども、しかし、基本的には、私は「真面目で線の細い」芥川が、可哀想に思えた。
谷崎みたいな、自分勝手なほどに自身の欲望に忠実な男に、真面目な芥川が敵うわけがない。
そもそも、谷崎なんていう「倫理観の欠落した男」など、真面目な議論に値するような相手ではない。
「うるせえ、馬鹿野郎! 変態で人非人のお前が、売れっ子だからといって、芸術家ヅラするな!」と、そう言ってやればよかったのだが、真面目な芥川は、日本人的な慎みに欠ける谷崎の迫力に押されて、「議論にならないな」と黙り込むしかなかったというのは、容易に想像できるところであった。
要は、私は、谷崎潤一郎が嫌いだったのだ。
佐藤春夫との「細君譲渡事件」なんてことを平気でやるような男に、「日本人の繊細さ」を語って欲しくない。
また、そんな男のいう「日本人の美徳」とやらを真に受けるやつは、無知で馬鹿な「権威乞食」でしかないと、私は斯様に考えるわけなのだが、しかし、谷崎については大昔に、初期短編集などを何冊か面白く読んで以来、長らくご無沙汰だったので、やっぱりここは、小説ではなく評論なりエッセイなりを読んでおくべきだろう。それで、見込みどおりなら、遠慮なくぶっ叩けるし、誤解なら訂正すればいいやと、おおむねそんなふうに考え、やっと今になって本書『陰翳礼讃・文章読本』を読むことができたという次第である。
もっとも、実際には、それを待ちきれずに、文芸評論家・井口時男の『悪文の初志』を読んだ際に、すでに谷崎を罵倒してしまってはいたのだが。
『伝統的な日本の美文は、それがすべてではないにしろ、谷崎が思うには「ブスを美人に見せかける高等テクニック」を主眼としたものであり、「ブスは暗闇の中で、袖で顔を隠してオホホと笑っておれば、おお、美人だ!と思ってくれるのが、日本の男の美意識だ」ということであり、ついでに言うと「大の男が、おむつをつけて、母親役の女性の膝で、バブバブ、おっぱいおっぱい! と強請るのが、大谷崎の美学」だということである。
そりゃあ、そういう変態プレイも、好きな人にはたまらんものなのだろうが、そんなもの「とうてい、見ておれん」というのが、「幸せなマザコン変態さん」に対し、わざわざ「そんな恥ずかしいプレイをするくらいなら、私は鞭でしばかれる方が、まだしもマシだ」と言っちゃうのが、言うなれば「悪文の初志」なのである。
端的に言って、谷崎潤一郎は「自分の美的世界に見合う、自分の文体を作ってきただけ」であり、それがたまたま通俗的にも受けたから「俺の文章は、本来の日本語の美しさを体現しているのだ」などという、頭の悪い「勘違い」をした、というだけの話なのである。
(またもや)言うなれば、今どきの人気ラノベ作家が「私の、この読みやすくて、みんなから支持されている文体こそ、日本語本来の美文なのだ!」とか言い出すようなものである。
つまり、端的に言って、谷崎潤一郎は「頭は悪かった(視野が狭かった)」ということなのだ。そもそも「流行りの文体」というのはあっても、「本来の日本語」なんてものは、存在しないのだから。』
こんな具合である。
今回、本書『陰翳礼讃・文章読本』を読んでみて、上の私の「読み」が、大筋において間違ってはいなかったことが確認でき、意を強くした。
「陰翳礼讃」など、基本的には「薄っぺらい西欧近代主義理解」に基づいて、「なるほど毛唐は、実用に優れたものをたくさん生み出しただろう。それを否定するつもりはないが、しかし、彼らには理解できない美が日本にはあるのだ」なんていった、薄っぺらな「独り決め」を語っているにすぎない。
「西欧近代主義」が、どれほどの「陰」を持っているのか、そんなことを谷崎がまともに知らないというのは、このエッセイを読めば明白だ。
暖房設備などの便利の部分(実用的先進技術)は、しれっと取り込んでおいて、しかし、そこ以外で日本には「こんな美があるぞ」などと言っても意味がない。
否応なく取り入れざるを得なかった「便利なもの」を生み出せなかった、「日本の消極主義」「長い物に巻かれて平気な負け犬根性」という「陰」があってこその、日本の「陰影」なのに、そうした日本の「負の面」はあっさりとスルーし、負の面における「犠牲者」の存在まで無視して、「でも、日本には」などと自慢ばかりするというのは、結局のところ、谷崎が「勝ち組」であり「他人を踏みつけにして平気な人間」であり「虐げられた人たちに対する思いやり(や想像力)」などカケラも持たない、徹頭徹尾「自己中心的な人間」だからに他ならない。
「勝ち組」であり、その現状に満足しているからこそ、すべてを「白日のもとに晒す」ような「西欧理性主義」を、谷崎は好まない。
谷崎は、美しい日本語を書くためのポイントとしての「饒舌を慎むこと」という項目において、次のような項目を挙げている。(P200〜201)
イ あまりはっきりさせぬこと
ロ 意味のつながりに間隙を置くこと
要は、身も蓋もなくはっきりさせないのが日本人の美徳だということだが、これによって「誰が得をするのか」を考えてみればいい。
これは「なし崩し的な現状追認」を期待する、「勝ち組」の理屈でしかないのは明白だ。
また、そんな谷崎だからこそ、英語などの「階級・性別による区別のない言語」と比較して、日本の「敬語」を称揚し、臆面もなくこんなふうに書く。
『この際特に声を大きくして申し上げたいのは、せめて女子だけでもそう云う(※ 謙譲的な)心がけで(※ 文章を)書いたらどうか。』(P318)
要は「女は女らしく、謙って愛嬌のある文章を書け」ということである。
こんな男だからこそ、友人に「いらなくなった嫁さん」を譲渡するなんてことができたのだ。
そして、こんな男が、日本人の「謙遜」や、ものをはっきりとは言わない「奥ゆかしさ」を称揚してみせたのだが、これこそが、「陰翳礼讃」や「文章読本」の、本質なのである。
そもそも、たいした頭もないくせに、大作家から「日本人は、西欧風に明晰なばかりの文章なんか書かないほうがいいんだよ。それが日本人の、日本語の美徳なんだ」などとおだてられて、すぐにその気になるような馬鹿が多いからこそ、日本は、愚かな戦争へと突き進み、無残な敗戦を経験することにもなったのだ。
「ただの人」を喜ばせるような、調子のいいことを言う奴なんて、絶対に信用するな。
一一これは、大谷崎であろうと、電話の向こうの親切めかした詐欺師であろうと、まったく同様なのである。
(2023年2月2日)
○ ○ ○
