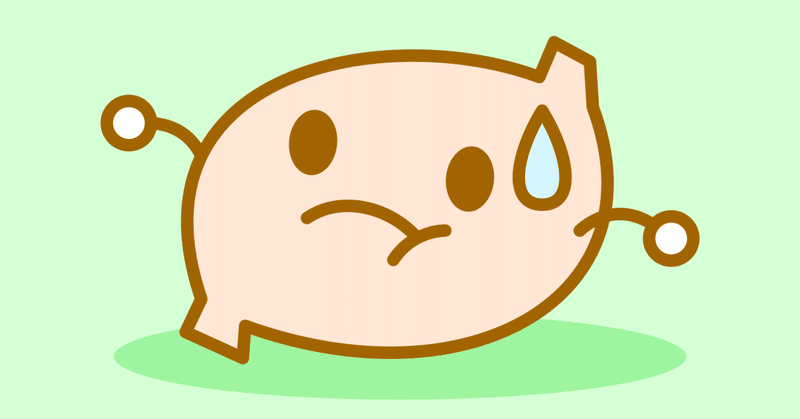#私の仕事
「リフレクション」の効果に関する考察
ここ数年、授業の後に「リフレクション」(=振り返り)を生徒に書いてもらっている。
授業のプリントに本時の到達目標などを設定し、それに対して言語化する作業をGoogle formで入力する形式をとっていました。
それに関してのこの2年で得た知見をまとめたいと思います。
授業の流れと書かせるタイミング私の授業では、原則として15~20分程度の範囲学習解説をはじめに行います。
基本的な内容や教科
「ギフテッド」対応の学校が民業圧迫で誰も得しない未来を生む
特別な才能を持つ子供、「ギフテッド」に対して公教育がどう対応するか、ということが話題になっています。
文科省は何らかの対応を表面上は行うようです。
こうした特別な生徒に対しての対応に関しては、これまで前向きな施策はほとんどなかったと思います。
そういった意味では今回の取り組みを行おうとする姿勢は評価できます。
「ギフテッド」へのこれまでの対応これまで「ギフテッド」に関して無策を貫いていた公
判定困難な「教員の適性」からの「でもしか先生」歓迎論
「でもしか先生」という言葉を聞いたことがある人も多いと思います。
主にやる気がない教員に対して使われる表現で、最初に流行ったのは1950年代というなかなか伝統ある表現のようです。
教員人気と生徒数減少その後は人材確保法(学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教職員の人材確保に関する特別措置法)や給特法の成立で、教員志望者数が一定数確保できるようになりました。
また、1990年代をピ
リアル授業の価値の低下が教員に「教科学力」を要求する
ICT普及に伴い、リアル授業の価値が低下しています。
オンライン授業で教員側が配信するというケースもコロナ禍の初めにはありましたが、現在ではオンデマンド配信を利用するケースが増えているようです。
小学校ではNHK for School、中高でのスタディサプリや学びエイドなど多くの授業動画がそろっています。
またYouTubeにも無料で利用のものが多数存在し、学校でリアル授業を受ける価値は相対
「始めに過去問ありき」
教員は授業を行うだけが仕事でありません。
具体的には教科担当だけでなく担任として、生徒の大学受験に向けての学習をマネジメントを行っています。
(事務仕事などももちろんありますが)
大学受験を目指す生徒(特に高3に上がってすぐの生徒や、難関大学に向けて受験勉強を始めた生徒)との面談やホームルームでの声掛けで常に口にするのが
「始めに過去問ありき」
という言葉です。
どのぐらいの知識を要求さ
本当は教えている「○○を学校教育で教えるべき」こと
社会に出ると学生時代には知らなかった、見えていなかったことに出会うという機会が増えます。
あるいは、人生のステージを登って結婚や子育ての場面でも知らなかったことは少なくありません。
そうした知らなかったが、現実社会に必要なことに出会ったときに悔し紛れに「○○を学校教育で教えるべき」という言葉を吐く人がいます。
その気持ちは十分理解できるのですが、では義務教育で習ったことであれば社会全体に定着
職務上の過失で個人に賠償責任を負わせるという悪しき前例
毎日暑い日が続いています、我が家でもビニールプールが活躍する時期となっています。
さて、この時期学校のプールの水を止めていなかった、という話題が目に付くようになります。
プールの管理に関する「過失」こうしたミスは過去にも、そして全国的に頻繁に起こっているようです。
Googleで検索をかけるだけでも相当な数の事例が上がります。
Yahooコメントなどでは「蛇口をひねることもできないのが教師
ICT教具論者はICT導入に学力向上の夢を見る
前回からの緩い続きになります。
ICT導入反対論者の論拠に多いのが、「教育効果が低い」、「教育効果が向上するエビデンスが得られていない」といったものがあります。
今回はこれについて考えていきます。
ICTによる教育効果とは文字通り、ICT機器を用いた授業や学習によって得られる学力の伸びのことです。
ICTを導入することで、生徒の興味をひいたり、授業の効率化が図れるとする教員の意識調査にも表
「ICTを使えない」という言い訳を許さない強い意志を持とう
ICT環境がこの数年で教育現場にも整備されました。
他業種と比べて遅すぎた感もありますが、GIGAスクール構想などの前倒しの効果は絶大で、日本中の学校でICT機器を導入できたことは社会全体の環境改善として大きな一歩と言えます。
私は勤務校でICT推進に携わっており、授業での活用だけでなく日常利用に関しての実験を行うなどICT教育の普及に取り組んでおり、校内においての利用も大きく進んでいます。