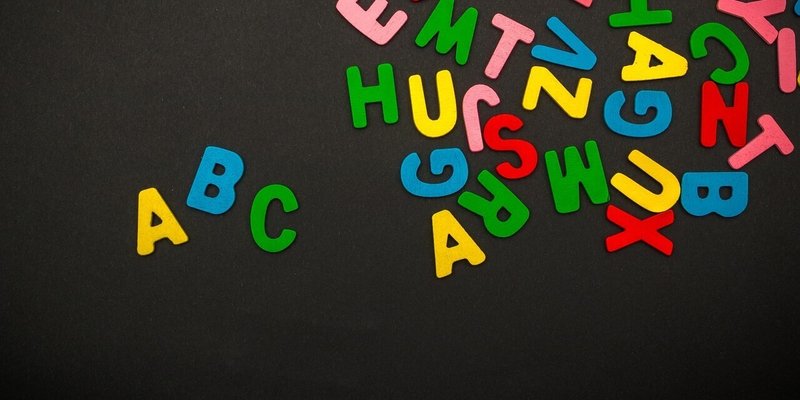記事一覧
【日本語】ネイティブの謎
ネイティブって不思議な言葉だ。
英語の native は「出生地の」とか「土着の」という意味だが、「《侮蔑》(通例白人から見て)(未開の)原住[土着]民の」という意味すらある(ジーニアス英和辞典)。
でも普通日本語で「ネイティブ」といえば、「英語が母国語の人」という意味だ。
すなわち、日本人の英語学習の文脈で使われる場合がほとんどだろう。
goo辞書では「4『ネイティブスピーカー』に同じ」
江戸っ子AIパート2(アイザック・アシモフ『銀河帝国の興亡 1』)
巨匠アイザック・アシモフによる宇宙SFの古典より。
物語冒頭、主人公ガアルが惑星トランターに降り立つ場面である。おそらくネイティブなら何も引っかからない、何でもない文章だろう。
私が引っかかたのは2点だ。
まずは minor。荷物が minor とはどういう意味なのか。小さいのか、少ないのか。
次に taken apart and put together とは何が起きているのか。荷物が何
匠の技(J.R.R.トールキン『ホビットの冒険』)
ファンタジーの名作より。目的地であるドラゴンの住む山をみはるかす場所にたどり着いた場面。
問題は Lonely Mountain をどう訳すかだ。「孤独山」だと味気ないし、「寂寥山」とかだと中華ファンタジーみたいだ。
「おさみし山」とか「ぼっち山」では語感がもう一つだ。他には思いつかないな……
ネットで答え合わせをしてみたら「はなれ山」(瀬田貞二訳)だった。
負けた…(勝つ気だったのか?)
ネイティブ、ヤバい。(J. R. R. トールキン『ホビットの冒険』)
ファンタジーの名作より。魔法使いガンダルフと、森に住む大男 Beorn が出会った場面である。
いや〜すばらしい。ここで heard of "him" を使うネイティブの言語感覚がすばらしい。
私ならたぶん the name か your name にしただろう。「そんな名前は聞いたことがないな」か「お前さんの名前なぞ知らんな」にしただろう。
しけしネイティブはここで「そいつのことは聞いたこ
マルティン・ルター・キングJr
『サピエンス全史』の著者が、人間と社会の未来を予測する本。ここでは、宗教とスピリチュアリティとの違いについて述べている。
読み上げを聴いていて驚いた。いま「マーティン・ルーサー」って言ったよね?
つまりマルティン・ルターは英語読みするとマーティン・ルーサーだったのである。
マーティン・ルーサー・キングJrは、マルティン・ルターだったのである。
知ってた?わしゃ知らんかったよ。
ヘボンとヘ
下半身は上半身の乗り物なのか【フレーズ】as fast as one's legs would carry one(J・R・R・トールキン『ホビットの冒険』)
ファンタジーの名作より。主人公ビルボが一つの指輪を盗んで、ゴラムとオークの群れから逃がれようとしている場面。
この his legs carry him (彼の足が彼を運ぶ)という言い回し、実に英語らしいフレーズだ(注1)。
英文を読んでいると、今でも時々 they が指すものを勘違いしていて、意味が取れないことがある。よく読み直してみると、それが語り手の両手だったり両目だったりする。
日本
イールズ・アス(ウィリアム・ギブスン『ニューロマンサー』)
サイバーパンク小説の金字塔より。
今回の書影はドイツ語版を選んでみた。舞台が日本というより香港みたいだし、絵柄も士郎正宗みたい、というか、80年代のパソコンゲームのジャケットみたいで味わい深い。
まだ3割も読んでいないし、造語やスラングが多く、要約や解説サイトを見てもいないので、物語の輪郭がおぼろげにしかわかっていないが、ともあれ主人公 Case と相棒の Molly が construct
ホモ・サピエンスは死よりも孤独を恐れる
フェイスブックで「ニュースフィード」というフィーチャーが初めて投入され、プライバシーを侵害されたと考えた人々が憤慨し、物議を醸す。炎上の中、やがてザッカーバーグは自分の考えが間違っていなかったことを確信する。
20年ほど昔、携帯を持たない上司がいて、「つかまりたくないから」と言っていたのを思い出した。当時でもめずらしかったと思うが、それでも日常生活にそれほど支障はなかったのだ。いま携帯を持たない
文学の特権(ウィリアム・ギブスン『ニューロマンサー』)
おもしろい比喩だ。
海外小説での人物描写は、目の色や髪の毛の色にこだわったものが多く(日本の小説ではみんなどちらも黒だから取り立てて言うことがないわけだが)、唇も性的なアピールとして描かれることはあるだろうが、「子供が描いた飛ぶ鳥の絵」に例えるというのはめずらしい。
女性の唇の性的な要素を子供っぽく抽象的なもので中和して、無機的な世界を演出しているということだろうか。
女性との思い出をノスタ
新しい大衆小説と神経漫遊者(ウィリアム・ギブスン『ニューロマンサー』)
読み始めてしばらくして、ふと「ニューロマンサーってネクロマンサー(死人使い、降霊術)のもじりだったのか!」と気づいた。
調べてみると、半分当たっていた。
ウィキペディアによると、あとの半分は New Romance (新しいロマンス)をもじったもの、ということらしい。この場合の「ロマンス」とは、恋愛小説というより、大衆小説のことだろう。
次に、「ニューロン(神経)」はわかるけど、「マンサー」