
神 ではなく 〈人〉としての、 エラリー・クイーン : 飯城勇三 『エラリー・クイーン 完全ガイド』
書評:飯城勇三『エラリー・クイーン完全ガイド』(星海社新書)
本格ミステリーを代表する作家の筆頭に挙げられるのが、エラリー・クイーンである。
少なくとも、日本においてはそうであり、その日本における不動の地位の礎を築いた一人が、本書著者の飯城勇三であるというのは、業界筋においては異論の出るところではないはずだ。
事実、今日の日本におけるエラリー・クイーンの特権的な地位を、一般認識の場で確定したと言えるであろう「新本格ミステリ」の作家たち、その中でもエラリー・クイーンの影響を隠さない、新本格第一世代の作家の中には、作家になる以前に、飯城勇三の主催する「エラリー・クイーン・ファンクラブ(EQFC)」の会員であった者もいる。
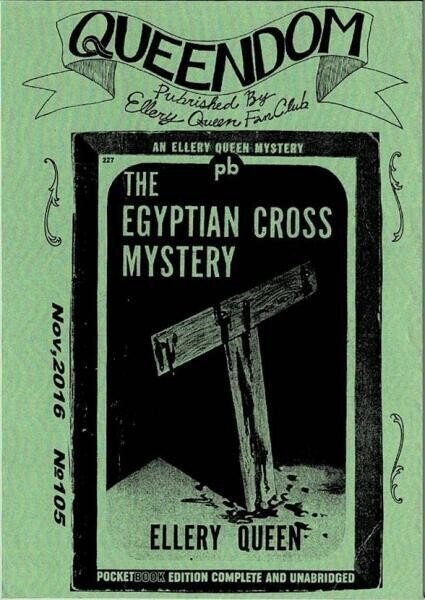
(EQFCの会誌『QUEENDAM』)
また、新本格第一世代前後のミステリマニアの場合、本格ミステリの二大巨頭として、エラリー・クイーンと並べて、ジョン・ディクスン・カーの名をあげる者も少なくなかった(例えば、二階堂黎人)が、今日、エラリー・クイーンの一人勝ちに近い印象があるのは、新本格第一世代の作家たちの働きというよりも、ファンダムにおける飯城勇三の「理論的活動」の影響だと言っても、決して過言ではないだろう。
クイーンを論ずる人は多いのに、カーを論ずる人が少ないのは、カーが論じにくい作家であったと言うよりも、クイーンの場合、飯城勇三の過去の仕事によって、理論的な議論の下地ができていたからなのである。

(ジョン・ディクスン・カー)
このように、皮肉でもなんでもなく、ほとんど「日本におけるエラリー・クイーン教の教祖」と呼んでいいほど、クイーンの紹介に長年取り組んできた飯城勇三が、いまだに本書のような入門書を書くというその情熱は、まったく持って尋常一様なものではない。
これだけの長きにわたり、クイーンについて書いていれば、嫌でもパターン化が起きてしまって、書くものに情熱が感じられないといったことになるのは、ほとんど避け難いところだろう。だが、飯城勇三の場合、エラリー・クイーンを語る筆に込めた熱量が、四半世紀を軽く超えても下がらないというのだから、まさに怪物だと言ってもいいくらいである。
したがって私は、飯城の書いたものの、内容や出来不出来を議論する以前に、この枯渇しない熱量に敬服しないではいられないのだ。
今日、エラリー・クイーンファンの多くは、エラリー・クイーンという、すでに完成した「権威」を担いで回っているだけだが、飯城勇三の場合は、一人の「本格ミステリ作家」であったエラリー・クイーンを、その豪腕で「本格ミステリの神」という「権威」にまで担ぎ上げたのだから、同じ「ファン」とは言え、両者の大きな違いは、正しく認識されなければならないのではないだろうか。
○ ○ ○
さて、本書だが、私の場合、本書のようなガイドブックは、滅多に読まない。というのも、作品を読む前にそういうものを読んでしまうと、読みがそちらに引っ張られてしまう蓋然性が高いので、なるべく真っ新な目で作品を読めるよう、ガイドブックの類は意識して避けているのである。

そんなわけで、若い頃なら、このような本は読まなかった。エラリー・クイーンを読みたいのなら、作品の内容にまで踏み込んだガイドブックなど読まなくても、読むべき代表作くらい、ちょっと調べれば簡単にわかることだからだ。
しかし、自分の年齢と読書における守備範囲の広さを勘案し、自分にとっての「本格ミステリ」あるいは「エラリー・クイーン」の重要度を考えれば、すでにその代表作の多くは読んでいるので、いまさら残りの作品にまで手をのばす蓋然性は低い。
クイーンに限らず、本格ミステリ作家のめぼしい作品は「全部読みたい」という気持ちはあっても、すでにそれが不可能であることを、嫌でも意識しなければならない年齢になってきた。だから「もう、残りの作品については、このガイドブックで、最低限に知識を得るに止めよう」と考え、本書を手に取ったのである。
だが、本書を読んだ結果として、やはり、新たに興味の開かれるところがあった。それは、作者エラリー・クイーンの「宗教(信仰)問題」である。
かつても「後期クイーン的問題」には興味を持ち、そこから柄谷行人を読んだり、不完全性定理に関する入門書を読んだりしたし、この問題の背景として無視できない「宗教問題」にも興味は持った。
しかし、当時の私は、「宗教問題」自体に、それほど突っ込んだ興味を持っていたわけではなかったし、ましてや「宗教」を研究していたわけでもなかったから、「操りの問題は、神と人間の関係に絡んでくるんだろうな」というくらいの認識はあっても、それ以上に突っ込んで考察することはしなかったのである。
しかし、素人なりに「宗教」問題に取り組み、特に「キリスト教」を研究して、神父や牧師と議論できるくらいの知識と経験を持った今なら、エラリー・クイーンの「宗教問題」について、飯城勇三や新本格ミステリ作家のように「本格ミステリ」の側からではなく、「宗教」の側から、より深いアプローチができるのではないか、と考えた。
昨年(2021年)読んだ、飯城勇三の長編評論『数学者と哲学者の密室 天城一と笠井潔、そして探偵と密室と社会』のレビューで、私は、飯城勇三に関する思い出話として、次のように書いた。
『飯城の評論文については、SRの会の会誌「SRマンスリー」に載ったものや、その後だいぶ経ってからの単発同人誌『天城一研究』などで、いくつかは読んでいるが、当時の私の興味を惹くことはあまりなかった。
当時も、飯城の評論は「アナロジー」を駆使したユニークなもので、たしか、これもご一緒した同人誌『新世紀エヴァンゲリオン研究』だったかに「エラリー・クイーン作品と『新世紀エヴァンゲリオン』の類似性」を論じた文章を投じているのを見て「本当に器用な人だな」と感心したり呆れたりした記憶がある。
つまり、私にとっての飯城勇三という評論家は、「ユニークかつ有能な評論家」ではあるけれど、当時すでに私の方向性となっていた「人間の内面」の問題を扱う「文芸批評」や「社会批評」「思想哲学」といったところには踏み込まない、「オタク評論家」だとして、あまり興味を持たず、目にしても読まないことが多かったのだ。』
このとおり、本書『エラリー・クイーン完全ガイド』を読むまで、私は、飯城勇三が「エヴァンゲリオンとエラリー・クイーンを結びつけたのは、少々強引なアナロジー思考によるもの」だと思っていた。

ところが、本書にはこのあたりの事情を紹介する、「エヴァンゲリオン」と題した次のようなミニコラムがあった。
『 今年完結したアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の最初のTVシリーズ(1995〜96年)を観た時、私は『十日間の不思議』との類似点が多いので驚きました。シリーズはその後も続き、変わった点もありますが、面白い指摘だと思うので、TVシリーズとの類似点を記しておきましょう。
何と言っても、登場人物の設定と配置がそっくりです。精神を病み、父の支配から逃れられないハワードは碇シンジ。ハワードの母親にして恋人のサリーは綾波レイ。すべての計画者ディートリッヒは碇ゲンドウ。その脇にいつもいるが目立たないウルファートは冬月。ハワードの保護者であり、何者かに操られている感じを抱くエラリーはミサト。
さらに『エヴァ』は「使徒(聖書から採っている)を一体ずつ倒していく」というプロットも『十日間』とよく似ています。『エヴァ』のファンの方は、ぜひ『十日間』を読んでみてください。
また、シンジがエヴァのパイロットやめようとして加持に諭されるシーンは、『九尾の猫』のラストシーンと同じ。TVシリーズ最終回は、クイーンの『孤独の島』のラスト(人類の一員に加わったことを感じている主人公のまわりに町中の人々が集まって祝福し、さらに作者も祝福して終わる)とよく似ています。こちらも比較して、時空を超えたシンクロを味わってみませんか?』(P125)
つまり、飯城勇三のよる「エラリー・クイーン作品と『新世紀エヴァンゲリオン』の類似性」を論じた文章は、それほど突飛でもなければ牽強付会なものでもなく、クイーン作品を細部まで記憶しておればこそ可能だった、ユニークな「類似性」の発見だったわけである。
ともあれ、飯城勇三が「エラリー・クイーンから宗教問題を扱った」のだとすれば、私は「宗教問題からエラリー・クイーン」を扱うことも可能なのではないだろうか。
エヴァマニアによって詳しく分析された、『新世紀エヴァンゲリオン』と「ユダヤ神秘主義」との関連の方は、それをさらに犀利に分析した大瀧啓裕(H・P・ラヴクラフト、フィリップ・K・ディック、コリン・ウィルソンなどの翻訳などで知られる翻訳家で、神秘学に詳しい)の『エヴァンゲリオンの夢 使徒進化論の幻影』などには及ばずとも、「ユダヤ・キリスト教とエラリー・クイーン」の方なら、付け加えることのできる部分が、まだ私にも残されているのではないかと思うのだ。
それに、日本の方が、本場アメリカよりも、エラリー・クイーンの研究が進んでいるのだとすれば、作家エラリー・クイーンの「宗教」の問題は、アメリカでもさほど進んではいないはずだと思えば、やりがいもある。
ユダヤ系アメリカ人である、エラリー・クイーンが「ユダヤ教とキリスト教の間」で、アイデンティティの問題に直面せざるを得なかったというのは、容易に推察できるところで、だとすれば、エラリー・クイーンが「本格ミステリ」という極めて「自己完結性が強く、帰属性の高い文学」形式を選んだという事実は、そのまま「宗教」の問題と考えることだって可能なのである。
本書を読むことで、私は「宗教」という側面から、「人間エラリー・クイーン」に興味を持つことができた。
したがって今後、未読作品を穴埋め的に読むようなことはしないけれど、昔とは違った観点から、エラリー・クイーンの作品を再読することならあるだろう。ひとまず、近いうちに『十日間の不思議』を、新訳で読んでみるつもりである。

本書によって、私にとってのエラリー・クイーンは、「本格ミステリの神様」ではなく、「人間」として、初めて立ち上がってきたのである。
(2022年1月22日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
