
G・ガルシア=マルケス 『百年の孤独』 : まったく〈趣味〉に合わなかった物語
書評:ガブリエル・ガルシア=マルケス『百年の孤独』(新潮社)
タイトルのとおりである。私にはまったく合わず、とても退屈なのを我慢して読みきった。
無論、この「ラテンアメリカ文学の帝王」のごとき名作を、私ごときが「不出来な作品だ」などと、不遜なことを言いたいのではない。
面白くなかったというのは、あくまでも、私個人が、面白がれた人とは違ったタイプの人間だった、というすぎない。あくまでも、私向き(趣味)の作品ではなかったということだ。一一この言い方からして「不遜だ」と言われても困るのだが…。

が、何はともあれ、どのあたりで「私向きではなかったのか」、それはハッキリしている。
要は、この作品は「描き込み(稠密な描写)とエピソードの積み重ね」で作られている小説なのだが、私の好みは「内面(心理の機微や内省)」であり「思想や論理」性といったことだから、こういう落ち着きのないタイプとは、「好み」がまるで真逆なのだ。
例えば、(もちろん例外はあれ)イメージとして言えば、私が好きなのは、「寒い地方」で紡がれた物語。つまり、外は寒いし暗いし、仕方がないから、家の中であれこれ考え、色々と妄想するしかない、というような環境から生まれた小説。
一方、この『百年の孤独』は「暑い地方」の物語。外は自然がいっぱいで、植物が緑濃く激しく繁茂し、艶やか鳥たちが賑やかにさえずり、動物たちも元気に駆け回っていて、人間もそれに負けないほど、大勢がにぎやかにうろついては大声で喋っている、といった具合だから、それを書くだけでもう十分だ、みたいな「風土」から生まれた小説なのだ。
事実、1972年の初訳版の「訳者あとがき」で、翻訳者の鼓直は、本作の魅力を次のように語っている。
『 気難しい批評家たちのあいだで好評を博しているだけではなく、これまで読書とはおよそ縁のなかった人びとにも熱狂的に迎えられているという、『百年の孤独』の驚くべき人気の秘密のひとつが、そのもっとも伝統的な小説形式にあることは間違いない。
人気のいまひとつの秘密は、「最初のものは樹につながれ、最後の者は蟻のむさぼるところとなる」ブエンディア家のいずれも孤独な面々の運命に、ラテンアメリカの読者が自分の、あるいは親しい者たちのそれをまざまざと読み取りうるということだろう。早くも十七歳のころにこのような物語を書くことを思いついたガルシア=マルケスだが、その言によれば、そこに書かれていることで幼時の経験、見聞でないものは何ひとつないということである。生地はかつてバナナ農場の栄えた土地であり、祖父はわずか一度ながら実際に反乱に加わった経験の持主である。祖母は幼い彼に、さまざまな奇怪な昔話を語ってくれた。そして……自然的な要素を探ることが目的ではないからここまででやめるが、要するに『百年の孤独』を手にしたラテンアメリカの人びとは、凹凸だらけの鏡面に映された己れの姿をそこに見て、その歪みを無邪気によろこび、あるいは自虐的に楽しんでいるのにちがいないのだ。人物の風貌や能力や行動がことごとく、作者の奔放自在な想像力によって誇張され、戯画化されているのは見たとおりで、ラテンアメリカの人ならぬ読者といえども、微笑、苦笑、哄笑、あらゆる種類の笑いを誘われざるをえない。しかし、ここで注目しなければならないのは、そのような戯画化やデフォルメを可能にして笑いを巻き起こす、作品中の現実的な要素と非現実的・空想的な要素とのかかわり方である。結論を先に言えば、前者と後者は何らの違和もなく共存しているのだ。その鍵は文体にある。例えば、謎の自殺を遂げたホセ・アルカディオの血が通りを越えてウルスラの部屋に達するという場面や、教会建立の資金集めにニカノル・レイナ神父が思いついたチョコレート飲用による空中浮遊の場面などに見られるが、ある種のヌーヴォー・ロマンのパロディーではないかと思われるような細緻な視覚的描写や正確な数学的記述がそれである。ありうべからざる異常な事件が、微細なディテールの執拗きわまる積み重ねによって、現実的・日常的な要素よりもはるかにリアルで、自明なものにすり替って、ふたつの要素のあいだには何らの違和もない。最初、幾つかのその種の出来事に立ち会っているうちに、やがて読者は、本来現実的なものにたいしてむしろ胡散臭さを感じるという仕儀にさえ立ち至るのだ。』
(1999年「全面改訳 新装版」P434〜436)
そもそも私は、人と群れるのが嫌いだし、お祭り騒ぎもバカ笑いも嫌い。親戚づきあいも面倒くさいし、友達は5人もいれば十分だと公言してきたような、ひきこもりの「書斎派」人間なので、「何代にもわたる一族の物語」と言われただけで、もう「えーっ、面倒くさそう…」とか思ってしまう。
よく「登場人物の名前が覚えられない」などと悪口を叩かれるドストエフスキーの長編なら面白く読めるのに、『百年の孤独』の登場人物の名前は、まったく頭に入らず、憶えようという気にもならなかった。
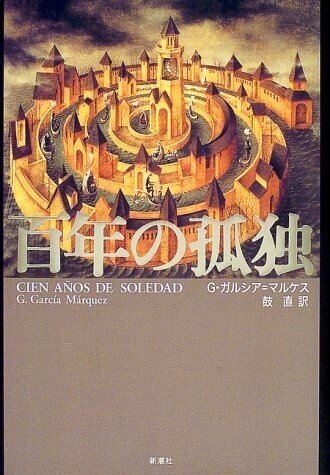
それに、筒井康隆が大騒ぎしていた当時ならまだしも、いまどき「魔術的リアリズム(マジック・リアリズム)」とか言われても、本気でありがたがるには遅すぎる。もっと早くに読んでいたら良かったのだろうが、今となっては、あとの祭りだ。
だが、じつのところ、私は20年前に、すでにマルケスを読んでいた。ところがそれを、すっかり失念していたのだ。
今回『百年の孤独』を読みながら「合わないタイプの小説だなあ」と嘆息していたら「あれっ? 前に読んだことがあるんじゃないか?」と気づき、漠然とながら記憶が蘇ってきた。そこで、昔の読書ノートを確認してみると、果たせるかな、短編集『ママ・グランデの葬儀』を2003年に読んでいたのだ。
だが、案の定その時の(主観的)評価点数は辛く、楽しめなかったからこそ、記憶にも残らなかったようだ。

では今頃になって、どうして『百年の孤独』を読んだのかと言えば、やはりマルケスと言えば、日本酒の銘柄にもなるくらいで、少なくともわが国では、断然『百年の孤独』が代表長編なんだから、いくら短編集が合わなかったとは言え、この作品を読まずして、マルケスに見切りをつけるわけにはいかなかったのだ(ちょうど、最近読んだ、野間宏の『青年の環』みたいなものだ。読んでおかないと、決着がつけられないのである)。
『ママ・グランデの葬儀』を2003年に読んだのは、短編集だし文庫本だったから、マルケスの小手調べには丁度良かったということなのであろう。一方、私が今回読んだ『百年の孤独』は、1999年の改訳新版の初刷の美本だが、古本価格の鉛筆書きが残っているので、いつ買ったのか正確なところはわからない。だが、いずれにしろ『ママ・グランデの葬儀』を読んだ前後数年の間で、それを長らく積ん読の山に埋もれさせていたのだ。言うなれば、「二十年の沈黙」を強いてきたのである。
今回はたまたまこの本を、土砂(積本)崩れのあとから発見したので、この機会にと読むことができ、これで思い残すことなく、マルケスともお別れできそうだ。
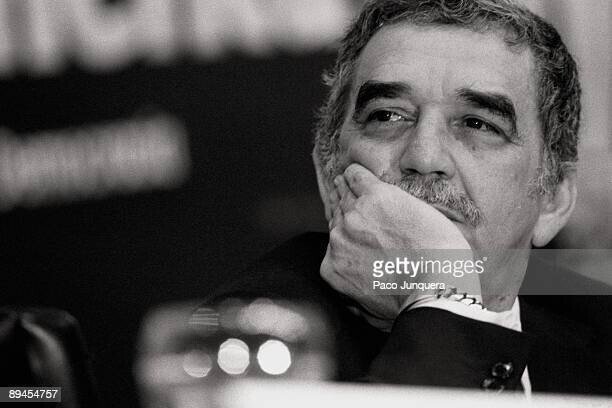
マルケスファンや『百年の孤独』ファンには申し訳ないような、無理解な読者による感想となってしまったが、まあ、解説やあとがきを引き写したような、ありきたりな紹介文よりは、マルケスが合わない読者には役に立つものになったのではないかと、勝手に納得したいと思う。
そもそも、『百年の孤独』は、小難しい「読み」を必要とするようなタイプの作品ではなく、あくまでも、南米庶民の伝統的な物語形式を、現代文学として洗練した作品として、楽しく読めるか否かが問題なのだ。
だから、楽しめなかったのなら、それはそれで仕方なく、それで何か支障のあるような内容ではない。ただただ、楽しめなかったのは「残念だ」、ということなのだ。
そんなわけで、お愛想なしだが、マルケスよ、さらばである。
(2022年7月18日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
● ● ●
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
