
ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア 『愛はさだめ、さだめは死』 : 「二重性」の悲劇
書評:ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア『愛はさだめ、さだめは死』(ハヤカワ文庫)
ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア『愛はさだめ、さだめは死』は、先日読んだ『たったひとつの冴えたやりかた』に続く、私にとっては2冊目となる同著者の著作なのだが、本書を読んで、前冊に感じた「違和感」の正体が、ほぼ判明したように思う。
それは、原題がどうであれ、『たったひとつの冴えたやりかた』とか『愛はさだめ、さだめは死』とかいったタイトルは、いずれにせよ、娯楽小説らしく表面をとり繕った「偽善的な綺麗事」にすぎない、ということである。
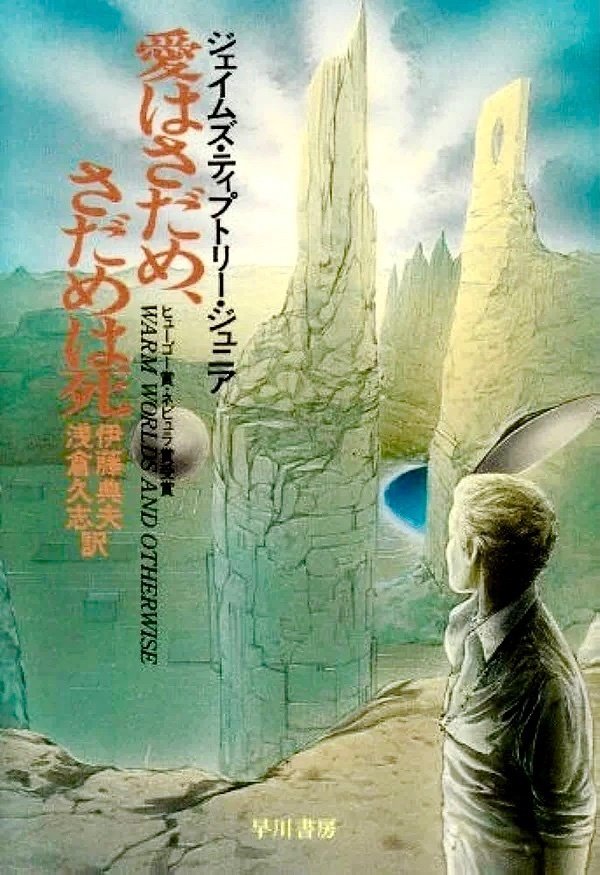
本書の冒頭には、先輩SF作家であるロバート・シルヴァーバーグによる「ティプトリーとはだれ? はたまた何者?」と題する序文が収録されている。
内容は、ジェイムズ・ティプトリー・ジュニアが、まだ「覆面作家」だった頃に書かれた、シルヴァーバーグの「ティプトリーとは、こんな人物ではないか」という人物推理エッセイに、ティプトリーの正体が明かされた後の感想を追記したものである。
つまり、3年前のSF業界内では、ティプトリーという「謎の存在」について、様々な揣摩臆測が飛び交い、中には「男性名を使っているが、実は女性なんじゃないか」と推理する者もいたけれど、シルヴァーバーグとしては、作品の内容や文体などからして「男性としか考えられない」とする立場だった。
ところが、ティプトリーの正体が女性だと明らかになったので、シルヴァーバーグは、自分の中にあった思い込みや偏見を再検討しなければならなくなったと、そういう趣旨のことをユーモアを交えて追記したのが、この序文である。
このシルヴァーバーグのエッセイで、私が面白いと感じたのは、次の二箇所である。
(1)『ティプトリーは一一たぶん、抜け目のない宣伝感覚からか、それとも彼の気質の中にある隠遁的な性向からか一一自分のペルソナを謎に包む道をえらんだ。SF界は、作家たちが自然におたがいをひきよせあう分野であり、作家の親友の大部分がおなじSF関係者であることが多い。しかし、その友愛組織めいたSF界で、ティプトリーに会ったという人間はおろか、彼がどんな顔をしているか、本職はなんであるかを知っている人間にさえ、わたしはお目にかかったことがない。作家ティプトリーの名声が高まるとともに一ーしかも、一九七一、一九七二、一九七三年と、その作品にますます磨きがかかるにつれて、名声は高まるいっぽうなのだがそれらの作品の背後にいる男への好奇心も、しだいにつのってきた。群居性の点では悪名高いSF界の中で、彼ができるだけプライバシーをたもとうとしていることが明らかになって以来、みんなの好奇心はよけいに刺激された。』(P10〜11)
(2)『追記一一三年後。
一九七六年のクリスマス直前に、あのなじみ深い青のリボンで打った一通の手紙が届いた。その手紙には、"ティプトリー"がアリス・B・シェルドン博士の筆名であることがためらいがちに告白してあり、あなたが〝ティプトリー〟男性説をのっぴきならないほど強力に主張したことを、どうかあまり気にしないでほしいと書いてあった。たいへんなびっくり箱だ。まずいことに、こっちは〝ティプトリー〟の動かしがたい男性的特徴うんぬんを、堂々と活字で力説したものである。よろしい一一恥の上塗りはしないでおこう。わたしも、ほかのみんなも、みごとに彼女にかつがれただけでなく、小説の中のなにが"男性的”であるか、または"女性的”であるかという観念ぜんたいに疑問を投げかけられたのだ。わたしはいまもその問題と格闘している。このことからわたしがまなんだのは、伝統的に男性中心の話題を、たいていの男よりも博識に書ける女性がいるということ、そして、本当に優れた芸術家は、題材にふさわしいいかなるトーンをも採用して、ちゃんとそれを成功させるということだ。そして、わたしは一一またまた一一もうひとつのことをまなんだ。まったく、なんべん教えられたらわかるのだろう一一〝物事が外観どおりであることはめったにない〟のだ。アリス・シェルドンよ、これらの面でわたしを教育してくれたあなたに、ここで感謝をささげたい。そしてそのほかのもっとたくさんのことにも。
(一九七八年二月)』
まず、(1)について興味深いのは、かねてから指摘されてきたとおりで、SF界は、よく言えば身内で寄り合う『友愛組織』、悪く言えば『群居性の点では悪名高い』ということを、当事者であるシルヴァーバーグ自身が認めている点である。
同じことは、日本のSF界にも言えるし、私はそのことを、かねてから日本SF界の「たこ壷」性として批判的に指摘してきた。
なぜなら、こうした「たこ壷性」は、周知の事実であるにもかかわらず、日本のSF界の場合は、そのことをシルヴァーバーグのように公然と正直に認めることはせず、あろうことか真逆にも、さもSF作家は、世界的な視野と未来を透視する視力を持っていると言わんばかりの、なれあいの身内褒めしかしないからである。
(2)の「追記」部分で注目すべきは、「SF作家も、世間並みの偏見にとらわれているものである」という当たり前の事実と同時に、シルヴァーバーグは、ここでそのことを「反省」しているのだけれど、日本のSF関係者は、その『群居性の点では悪名高い』という自身の弱点を公然と認めることをしたがらず、率直に反省することもしていないから、しばしば、おかしな「誤魔化し」や「隠蔽」に手を染めているのではないか、という点である。
そしてこれは、本稿の冒頭に書いた、
『先日読んだ『たったひとつの冴えたやりかた』に続く2冊目となるのだが、本書を読んで、前冊に感じた「違和感」の正体が判明した。』
という部分とも関連してくる。
『たったひとつの冴えたやりかた』に収められた中編「たったひとつの冴えたやりかた」を読んで、私はこの名作を単純に「感動作」だとするだけではなく、この作品の持つ意味とは「自決への自己鼓舞」だったのではないかと指摘した。
『作品の出来不出来とは別の部分で、語っておかなければならないことがある。それは、「作家論」の部分で、注目すべき点である。
本作品集所収の3本の「共通点」とは、「勇気ある潔い決断(の美)」ということであろう。
詳しく書くと「ネタを割ってしまう」ことになるから書かないが、いずれの作品も、主人公たちのそうした「ヒーロー性」が、読者に感動を与えるものとなっているのだ。
(中略)
つまり、平たく言ってしまえば、ジェイムズ・ティプトリー・ジュニアは、夫ともども「どのようにすれば、最も美しく幸福な死に方ができるのか」という問題を、リアルなものとして考えていたのであり、そうした思索が本作品集にも、おのずと反映しているということだ。
そして、ここで肝心なことは、「潔く死ぬこと」が「美しい」と感じていたとしても、いざ、それを実行しようと考えれば、人間誰しも躊躇せざるを得ない、ということである。
そしてまたそれは、単に「自殺が怖い」ということだけではなく、「理由はどうあれ、愛する夫を我が手にかけるのは、果たして真の愛と言えるのか?」といった「疑問」が、当然のごとくあっただろうということだ。
つまり、彼女だって、自然にボケて、夫婦がお互いを認識できないようになったり、病気で身動きが取れなくなったりした果てに死ぬ、ということも、あながち「間違い」だとは言えない、ということくらいは、理解していたのである。
言い換えれば、自分一個の意志で、すべてを裁断してしまう「理性主義」というものには、どこか「不自然さ」と「傲慢」の匂いがつき纏っている、といったくらいのことは、彼女だって当然意識していたはずなのだ。
だから、「決断主義的に美しく死ぬ」か、それとも「自然の成り行きのままにゴミになることを受け入れる」か、については、彼女なりに悩んだはずなのだ。
一一そして、そうした悩みを抱える中で、彼女が書いたのは「かくありたい自分」の物語であり、こうした作品を書きながら、彼女はたぶん「私は、こういう自分でありたいと願ってしまう人間なのだ。だから、その死に様は、選択の余地のないものだ」と、そう考え、作中人物たちに励まされるようにして、その決意を固めていったのではないだろうか。』
つまり、ジェイムズ・ティプトリー・ジュニアは、『たったひとつの冴えたやりかた』に収められた作品を書くことによって、自分自身をコントロールしようとしたのではないか、ということである。

そして、そのことを私に確信させてくれたのが、本短編集『愛はさだめ、さだめは死』に収められた、サイバーパンクSFの先駆作品として名高い「接続された女」である。
この作品は、身も蓋もなく言ってしまえば、醜女が、培養された美少女の肉体(※ 要は、Vtuber用アバターのリアル版)にジャック・インして夢を叶えるのだが、やがてその「もともと魂を持たない、培養された体(美少女)」の方で恋をしてしまい、その結果として行き着いた「悲劇」を描いた作品だと言えるだろう。
だが、この作品で興味深いのは、この物語には「第三者としての語り手」がいて、その人物は、主人公の醜女には少しも同情的ではなく、「こうなることは最初からわかっていたのに、愚かな女だ」というスタンスを、最後まで崩さない点だ。
そして、そこに私が見たのは、ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア(以下「ティプトリー」と記す)という作家の、「二重性」である。
つまり、「ロマンティストとして、醜女に同情するティプトリー」と「醜女の愚かさを冷徹に評価するティプトリー」である。
これは、どちらかが一方がティプトリーの本質だというのではなく、たぶん、この「二重性」こそが、彼女の本質なのであろう。
そして、こうした「二重性」は、彼女の人生に、死ぬまでつきまとうことになる。
だから私はここで、単にティプトリーが「覆面作家」として「男性」を装ったという事実だけを指して「二重性」と言っているのではない。
最も肝心なのは、彼女が、自身の「死の選択」にあたっても、やはりこの「二重性」を利用した、という事実である。
先に指摘したとおり、彼女が自らの「死の選択」にあたって採用した、自作を利用した「自己鼓舞」という手法とは、言うなれば「自分をコントロールしようとした自分がいた」ということなのだ。
そして、衝撃的で悲壮な死を遂げたティプトリーとは、実のところ、冷徹にその演技をつけ、そのように演出した陰のティプトリーの操った、世間向けの「人形」であり、死ぬまで被り続けた「仮面」だったのではないか、ということだ。例えば、割腹死した三島由紀夫のそれと同様の。
ここで、念のために、ジェイムズ・ティプトリー・ジュニアの死の状況を確認しておこう。
『 ちょうど本書の翻訳が終わりにさしかかっていたある日(正確には一九八七年の五月二十一日)の朝、寝耳に水のニュースがとびこみました。原作者のジェイムズ・ティプトリー・ジュニア(本名アリス・シェルドン夫人)が亡くなったという知らせです。しかも、その死にかたがただごとではありません。弁護士に電話をかけて後事を託したのちに、病気で寝たきりだった最愛の夫ハンティントン・シェルドンを射殺、おなじベッドの上でみずからの頭を撃ちぬいた。夫は失明の上にアルツハイマー病の疑いもあり、彼女の心臓疾患も悪化していた。彼女は七十一歳、夫は八十四歳。取調べに当たった警察の発表によると、どうやらふたりのあいだには、かねてから自殺の取り決めがあったらしい……。』
(『たったひとつの冴えたやりかた』P373、浅倉久志「訳者あとがき」より)
この、ある意味では、見事なまでの「覚悟の自殺(心中)」、言い換えれば「最愛の夫を自分の手にかけて安楽死させ、自分も自殺する」という「最後のミッション」は、心理的には決して簡単なものではなかった。
だからこそ「もうひとりのティプトリー」は、『たったひとつの冴えたやりかた』に収められた作品を彼女に書かせて、「君なら、ここに語られた主人公たちと同様に、見事な死を選ぶことができるはずだ」と、そう「鼓舞」したのではないか、言い換えれば「コントロール」したのではないかということだ。
そしてさらに言えば、私たちの目に触れた「見事な心中を果たしたティプトリー」の「美しさ」とは、「接続された女」と同様に「コントロールされて動いていただけの、魂のない美少女」と同種のものでしかなかったのではないか、ということである。
ジェイムズ・ティプトリー・ジュニアという作家を考える場合、この「二重性」と、それに基づく「コントロール指向」というものを無視できない。
浅倉久志は、前記の「訳者あとがき」で、ティプトリーの幼少時代を、次のように描いている。
『 いま、ぼくの前には、やっと最近手にはいった『ジャングルの国のアリス』Alice in Jungle Land(一九二七)という本があります(編集部註・訳は未知谷より明行されています)。 これはティプトリーの母、作家で探険家でもあったメアリー・ヘイスティングズ・ブラッドリーが、家族ででかけた最初のアフリカ旅行の経験を、娘のアリスの目を通したかたちで書きつづったものです。たくさんのさし絵を描いているのはその幼いアリス・ヘイスティングズ・ブラッドリー、つまり、のちのティプトリーその人で、女子大在学中から画家としてひとりだちしていたという才能をすでにうかがわせて、幼い子供の絵とは思えないほど達者なスケッチです。
かねてからアフリカにあこがれていたティプトリーの父母は、したしくつきあっていた有名な探検家カール・エイクリーがウガンダ地方のマウンテン・ゴリラ狩りをもくろんでいるのを知って、出資と交換条件に自分たちも同行させてくれないかと持ちかけ、話がまとまりました。幼いアリスを含めた一行六人は、一九二二年の夏シカゴを出発、イギリスを経由して船でケープタウンに着き、鉄道でヴィクトリア瀑布へ、さらにルアラバ川の上流へと向かいます。めざすのは、タンガニーカ湖からキブ湖を経てウガンダにはいり、ナイロビにいたるコース。もちろん、トラックもなにもなかった時代のこと。鉄道の終点から先は、小舟と二本の足で進むしかありません。長期間のサファリをつづけるためには、二百人のポーターが必要でした。一行は野生動物の生態を映画におさめながら、お目当てのゴリラに出会います。アリスたちは野生のゴリラを実際に見た最初の白人女性になったのです。このときにエイクリーとアリスの父がしとめたゴリラの製は、いまもニューヨークのアメリカ自然史博物館に展示されているとか。ついでながら、アリスの母は、とつぜんライオンにおそいかかられたときも、冷静に銃で相手の心臓を撃ちぬいたほどの気丈な女性でした。
活発でおませな少女だったアリスにとって、このはじめてのアフリカ旅行は、毎日思いがけないことが起こり、三度の食事がいつも野外のピクニックになる、たのしいおとぎの国の旅でした。挿入された何枚かの写真には、フランス人形のようにかわいい彼女が、子象の背に乗ったり、チンパンジーと仲よくすわったり、丸木舟に乗ったり、現地の子供たちからふしぎそうに見つめられたり、キクユ族のダンスに仲間いりしたりしているところが記録されています。印象的なのは、帰国が決まったあと、ふたたびアフリカを訪れる日を夢見ながら、ヘルメットをかぶって川べりに腰掛けている、ちょっぴり寂しそうなアリスの姿でした。』(P374〜376)
一方、本書『愛はさだめ、さだめは死』の解説者である大野万紀は、ティプトリーの幼少時代とともに、その後の人生についても、次のように紹介している。
『 彼女の名前はアリス。高名な探険家の父と作家である母に連れられて、十歳になるまでに世の中のありとあらゆる現実を見てしまった銀色の髪の美少女。幼いころから世界中を巡って、飛行機や銃によって荒らされる以前のアフリカ、月の山と呼ばれるルベンゾリを眺め、カルカッタの町では飢えた人々の間を歩き、まだ平和だったベトナムの森を小馬に乗って駆けた彼女。五歳のころ、彼女を女神のように崇拝する三十人の原住民の見守る前で平然と髪にブラシをかけていたという彼女は、しかし誰よりも鋭い感受性の持ち主であり、様々な異文化、宗教、タブー、その他との接触によって〝同年代の普通の子供たちとの生活に深い疎外感を覚え、文化の相対性に悩まされる〟早熟で孤独な少女となった。
アリスの思春期は強大な両親(特に美しく、知的でエレガントな、その一方でライフルを肩にアフリカの大地を踏破し、巨象を狩るとてつもなくタフな母親)の影響力から自立しようとする激しい苦闘の日々だった。十二歳で自殺を試み、十代の終わりごろ、母親が彼女をニューヨーク社交界にデビューさせるための盛大なパーティと世界一周旅行(英国王室に招かれて国王陛下に拝調するのがそのクライマックス)を計画しているのを知るや、それをぶち壊すためだけに三日前に知りあったばかりのハンサムな男の子と駈け落ちし、結婚する(すぐに離婚したが)。
二十代前半の彼女は、グラフィック・アーティストとして著名な雑誌に寄稿したり、個展を開いたり、美術評論を書いたりして暮らしていた。また左翼運動に没頭し、みずからをアナーキストと規定していた彼女だが、ヨーロッパの戦争が激しさを増した一九四二年、陸軍に入隊。女性として初めて空軍情報学校を卒業し、写真解析士官としてペンタゴンの中枢で働きはじめる。
四五年、彼女はドイツに渡り、ドイツ科学の成果と科学者たちをできるだけたくさん合衆国へ連れ帰るプロジェクトに参加。アメリカのアポロ計画も、もともとは彼女たちの活躍がなければ実現しなかったかも知れない。このプロジェクトの立案者で指揮官だったハンティントン・D・シェルドン大佐とアリスは結婚する。二人はその後軍を離れ、ささやかな生活をしていたが、五二年、CIAの発足とともにその設立に力を貸すよう政府から要請される。ハンティントン氏はトップレベルで、アリスは写真解析部門の技術レベルでCIAの組織づくりに力を注ぐことになる。五〇年代の東西対立の中で、夫妻はCIAの活動に深く巻きこまれるが、このころのことはあまり知られていない。フルシチョフ首相の健康状態を調べるためにその尿を入手する作戦など、いろいろ面白そうな話はあるのだが、詳しくはわからない。
五五年、政治・軍事の秘密をさぐるよりも自然の秘密を知りたいという思いがつのり、辞職願いを書いて姿をくらます。CIAで学んだテクニックを駆使して別人になりすましたが、結局は夫のもと、戻る(この自分を別人にするテクニックというのは、後にティプトリーとしてSF界に袋を現わす時も役にたったものだろう)。彼女は基礎科学を学びたいと思い、もう四十代の後半になっていたが、大学に入り直して実験心理学に挑戦した。アリスはここでもすばらしい才能をあらわし、大学を最優秀の成績で卒業、優等で博士号を取得する。その後心理学の講師となり、大教室で学生たちを教えるが、ついに体をこわして、講師生活を続けることができなくなった。
大学を辞める前に、アリスは"正気ではできない"ことをやってのけた。SFを書いてしまったのである。もともと彼女はSFが大好きな少女だった(それもまた、母親が決してやらないことの一つだったから)。九歳のころからSF雑誌を読みふけっていたという。彼女はSFを発表するにあたって、ちょっぴり茶目っ気を発揮した。渋い中年の男性を創作し、彼をその作者としたのである。彼の名はジェイムズ・ティプトリー・ジュニア。本書の作者である。
一九六八年、ティプトリーはSF界にデビューした。彼はたちまちSF界の話題をさらう。』(P383〜385)
要するに、典型的な金持ちのお嬢さんであったティプトリー=アリスは、幼い頃から「野蛮な後進国」への旅行を経験して「野生動物」や「原住民の土人」たちに直接触れる機会を得て『様々な異文化、宗教、タブー、その他との接触によって〝同年代の普通の子供たちとの生活に深い疎外感を覚え、文化の相対性に悩まされる〟早熟で孤独な少女となった』のだが、『強大な両親(特に美しく、知的でエレガントな、その一方でライフルを肩にアフリカの大地を踏破し、巨象を狩るとてつもなくタフな母親)の影響力から自立しようとする激しい苦闘の日々だった。』とあるとおりで、「先進国の富裕層の価値観」に強く惹かれる部分も、当然のことながらあったのである。
つまり、彼女は、この頃すでに「支配者と被支配者」の両面性という「二重性」に引き裂かれた人間だったのだ。
だから、「金持ち結婚式」からは逃げ出して、自由なアーティスト生活をし、政治的には「左翼」であるアナーキストになったつもりだったのだが、戦争となれば、左翼として戦争に反対するのではなく、あっさり転向して陸軍に入り、「愛国女性」に転身する。
そしてそれからは、原子爆弾の開発プロジェクトたる「マンハッタン計画」にも浅からず関わったであろう陸軍情報部の軍人である夫と結婚し、戦後はおのずと『CIAの発足とともにその設立に力を貸すよう』にもなるのである。
もちろん、彼女の「生まれ」がこうした人生を否応なく強いたという側面はあるだろう。だが、いつまでも子供ではないのだから、大人になってからの彼女の人生選択の責任は、彼女自身が負うべきであろう。
つまり彼女は、幼いころの豊かな経験や、それに由来する「この世の差別的現実」、言い換えれば「二重性の現実」に対する認識を、突き詰めることができず、結局は「金持ち」らしい生き方を選んで、「金と力で、被支配者たちの抵抗をねじ伏せる」という「支配者の立場」を選んだ、ということなのである。
本書収録作の「男たちの知らない女」には、次のような描写がある。
『「どちらの官庁にお勤めですか?」
彼女は優雅に打ち明ける。「あら、ただのGSA(総務庁)記録部よ。司書をやってます」そうか。それで納得がいく。記録部の、経理局の、調査課の、人事室、行政室のすべてのミセス・パースンズたち。あ、七三年度の対外事業契約の概括がほしいんだがね、パースンズさんに頼んでくれ。とすると、ユカタンには観光で来たのか?かわいそうに……使い古したジョークをいってみる。「すると死体をみんなどこに埋めてあるかもご存じのわけだ」(GSAが各官庁の資産の管理を行うところから、その記録部へ行けば、政府の関わった秘密の事件で、死体を埋めた場所が場所までわかるというジョークである)
彼女は恨めしそうな笑みをうかべ、立ちあがる。「日の暮れるのが早いこと。そう思いません?」』(P248〜249)
つまり、ここに登場するミセス・パーソンズとは、ティプトリー自身の似姿なのである。
ティプトリーは『空軍情報学校を卒業し、写真解析士官としてペンタゴンの中枢で働き』、軍の偉い人と結婚し、その後は夫と共に『CIAの発足とともにその設立に力を貸』したような、言うなれば「CIAの母(の一人)」であり、現場には出なくとも「諜報謀略活動のプロ」の一人だということである。
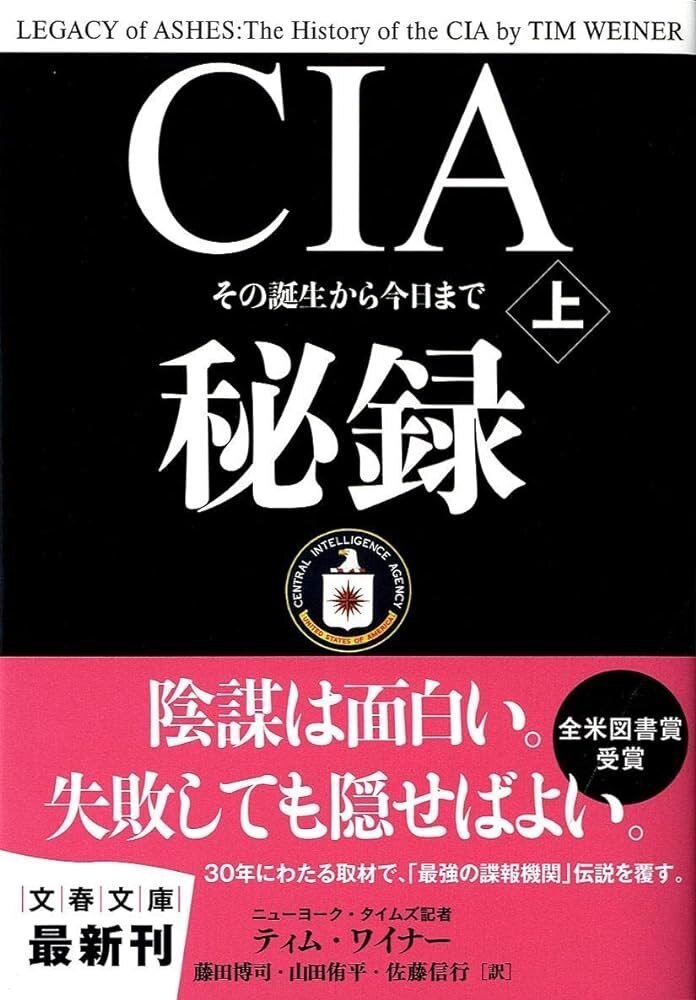
当然のことながら、CIAが世界各国で行った謀略活動、具体的に言えば「暗殺」だの「左派政権転覆の謀略(クーデターの画策支援)」などということも、書面上ではあれ、確実に知っていたはずし、決済手続きくらいになら関わっていただろう。言うなれば、彼女の手は、間接的にならば確実に「他国の人々の、血に塗れていた」ということである(戦中の活躍からすれば、当然、ヒロシマ・ナガサキとも無関係ではあり得ない)。
だからこそ、「男たちの知らない女」の母娘は、地球を捨てて「異星人」の世界へ旅立とうとするのだ。地球人世界の、あまりにも醜悪な現実に絶望して。
また、同じ心理は、本書所収の別の作品「最後の午後に」にも見出すことができる。
ある惑星に不時着し、そこで運良く生き延びることができた人類の一団のリーダーは、その地に自分たちが確保した生活圏が、原住生物によって脅かされつつある現実を前にして、強力な能力でこれまで彼を何度か救ってくれた別の異星生物に対して「もう一度だけ、われわれを助けてくれ」と訴える。
だが、その異星生物は、その求めに乗り気ではないのか、なかなか反応してくれないのだが、彼の繰り返しの嘆願に対して、ついに「それが君の本当の望みなのか? もうこのようなことはやめて、すべての生命が共存できる場所へ行きたいとは思わないか」と尋ねてくる。しかし、その「救い」は、彼個人に限られたものであり、彼が救われるということは、家族や仲間を見捨てていくということを意味するのだ。
それで彼は、やはり仲間たちの方を選ぶのだが、この物語を「アメリカ人・アリス・シャルドン=ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア」のこととして考えれば、ここで考えられているのは、「ベトナム」だの「アメリカの裏庭(中南米)」だの「イラク」だの「アフガニスタン」だのといった国で、アメリカ人が現に行った「愛国」的行為と同じことである、というのが容易に理解できるはずだ。
「そりゃあ私だって、すべての国々の人たちと仲良く暮らせるものなら、そうしたいよ。しかし、現にわが祖国の国益がかかっており、同胞の命運がかかっているからには、私は、我が国に抵抗する原住民たちを抹殺することの方を選ぶ」と、そういうことなのであり、そういう話なのだ。

つまり、ジェイムズ・ティプトリー・ジュニアという人は、そういう人生を生きてきたからこそ身元を隠そうとしたと、そう考える方が自然なのだ。
自らの手が血みどろであり、それを知ったら嫌悪を覚える人もきっといるだろうし、自分の書いた小説を「深読み」する者も、きっと出てくるだろう。一一それはいかにも不都合だから、あくまでも「無色透明な人間」を装おうとしたのである。かつて「諜報活動」に関わってきた時のように、あるいは、ミセス・パーソンズにように。
○ ○ ○
したがって、そんな彼女の経歴を知りながら、
『 大学を辞める前に、アリスは"正気ではできない"ことをやってのけた。SFを書いてしまったのである。もともと彼女はSFが大好きな少女だった(それもまた、母親が決してやらないことの一つだったから)。九歳のころからSF雑誌を読みふけっていたという。彼女はSFを発表するにあたって、ちょっぴり茶目っ気を発揮した。渋い中年の男性を創作し、彼をその作者としたのである。彼の名はジェイムズ・ティプトリー・ジュニア。本書の作者である。』
などと書いた大野万紀は、何も考えていない「SFオタク」か、そうでなければ「偽善者」であると断じても良いだろう。
ティプトリーが手を染めてきた『"正気ではできない"』ことというのは「SF小説を書きました」とか「男性と偽って、SF作家デビューしました」などというような能天気な話ではなく、『茶目っ気』で許されるような話ではないことくらい、「常識」があるならば、容易にわかる話だ。
したがってこれは、お茶目ぶって、いかにも「良い話」ふうに書き換えて良いことではないし、そんなことくらいわかっていたはずなのだが、「たこ壷社会」で無難に生きているような輩は、ユダヤ人の虐殺を黙認したかつてのドイツ国民や、朝鮮人虐殺を黙認して口をつぐんだ日本人みたいなことを、今も平気でやるのである。
ティプトリーがやったことは、結局のところ彼女の母親が、「ハンター」として象を撃ち殺した(支配的な高等生物が、下等生物の生殺与奪を自由にした)のと同じことに過ぎない。
幼い彼女は、人間と他の動物、先進国の人間と後進国の人間、支配者層と被支配者層といったこの世界における「二重性」の現実に疑問を感じ、そこから逃れようという気持ちも、確かに持ってはいたのだけれど、結局のところ、恵まれた「力の正義」の側から離脱できるほどには、強い人間ではなかったのである。
しかしまた、そんな自らの意志を貫くことのできなかった生涯だったからこそ、人生の最後においては、自らのその「二重性」において、自らをコントロールして、自らの「意志を貫いた人間」という自作自演の猿芝居を、その木偶人形に演じさせることになったのではないか。
アリス・シェルドンの死亡現場にあった遺体とは、ジェイムズ・ティプトリー・ジュニアが接続してコントロールした、「抜け殻の美少女」も同然だったと、そうも理解し得よう。
そう。〝物事が外観どおりであることはめったにない〟のだ。
(2024年3月15日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
