
荻原浩 『押入れのちよ』 : 忘却という〈救済〉
書評:荻原浩『押入れのちよ』(新潮文庫)
個人的には、直木賞作家・荻原浩は、長らく興味のない存在だった。
もともと私はミステリファンだったのだが、ミステリと言っても、広義の「ミステリー」小説ではなく、好きなのはもっぱら「本格ミステリ」つまり「謎と論理とトリック(仕掛け)」が売り物の「パズル小説」である。
したがって、荻原浩が最初に私の視野に入ってきたのも、ミステリー小説の年間ベストランキングなどで評判の良かった、『ハードボイルド・エッグ』(1999年)、『噂』(2001年)、『誘拐ラプソティー』(2001年)、『コールドゲーム』(2002年)などの初期のミステリー作品によってであった。
だが、それらは、タイトルや評判からして、どうやら「ハードボイルド」や「犯罪小説」のようだったので、私の興味を惹かず、そのままスルーした。
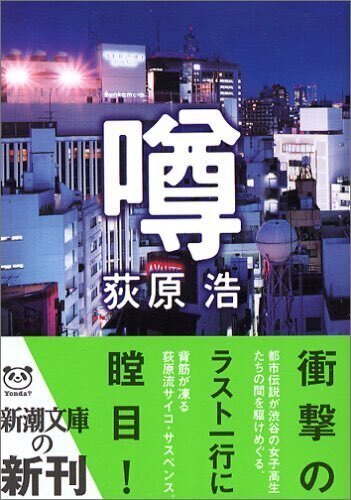
次に私の視野に入ってきたのは、山本周五郎賞を受賞した『明日の記憶』(2004年)。「若年性アルツハイマー症」を扱った感動作で、映画にもなった話題作だが、もうそれだけで、お話が透けて見えるようなので、興味は持ったが、読むには至らなかった。

その次が、いよいよ本書『押入れのちよ』(2006年)の表題作「押入れのちよ」。
私は、中井英夫と澁澤龍彦のファンだったので、両者にゆかりの深い『幻想文学』誌(1982〜2003)をずっと買っていた(購読していた、とは言い難い)のだが、同誌の編集発行人だったのが、本書『押入れのちよ』の文庫解説者である東雅夫。そんなわけで、本書の単行本刊行当時に、東がどこかで本書を褒めているのを目にしたのだろうと思う。
しかし、同文庫の「解説」で『私の専門分野であるホラーや怪談のジャンル』とする東とは違い、私は、ホラーや怪談にはさほど興味がなかったので、短編1本のために、それまで興味のなかった作家の本を、まる1冊読もうとは思わず、結局はこの時もスルーしてしまった。
そして、それからずいぶん経って、ひさしぶりに荻原浩の名が私の目に惹いたのは、こう言ってはなんだが、当時の感覚で言うと「今ごろになって、直木賞を受賞した」時である。受賞作は、連作短編集『海の見える理髪店』(2016年)。
しかしながら、直木賞を受賞したからといって、私の評価が上がるというわけではない。私の「直木賞」観とは「読ませる娯楽小説を書く程度の力量を持つ、若手または中堅作家の、比較的よく書けた作品に与えられる賞」というもので、「直木賞」受賞作は、一定の質の保証はあるけれども、「傑作」とまで言える作品だとは限らないし、まして、たいがいの場合「遺る作品」ではない、からである。
直木賞受賞作が売れるのは、受賞からせいぜい5年ほど。直木賞作家が受賞時ほどの売れっ子作家でいられる期間も、10年を超える人はほとんどいないのではないだろうか。
そんなわけで、荻原浩の直木賞受賞を見て「おお、やっと今ごろ直木賞を取ったか。この人は、比較的当たり外れの少ない、安定した力量の持ち主なんだろうな」と思ったのだが、言い換えれば「尖ってところがない」ということにもなるので、「普通ではない作品」が好きな私は、やはり、この受賞作も読むには至らなかった。

ところが先日、そんな荻原浩が、マンガの単行本を刊行しているという新聞書評が、私の目にとまった。その書評は、同書が「文庫」化された際のものだから、単行本は数年前に刊行されていたのだが、興味がないので、全然知らなかったのである。
だが、20年以上のキャリアを持ち、それなりに評価され売れてもいるだろう小説家が、今頃になって、わざわざまるまる1冊のマンガ本を描くというのは、やはり生半可な気持ちでできることではない。また、ネット検索してみると、その『人生がそんなにも美しいのなら 荻原浩漫画作品集』(2020年)の表紙画や中身の絵は、決して小説家の手すさびではなく、へたなマンガ家よりもよほどうまかったので、元漫画部員の私としては、これは読まなくてはと、早速購読した。
そして、下のレビューを書いたのである。
『荻原の描く世界は、「この世とあの世」がシームレスにつながる「民俗社会的な世界」だと言えるだろう。
そこでは、「生者と死者」に大きな区別はなく、「この世とあの世」、あるいは「現実世界と異界」があっさりとつながっていて、そこに「差別」はない。両者は完全に「同等」なのだ。
そして、この「同等性」であり「非差別性」とは、荻原の本質的な「肯定性」に由来するものであり、そこに発する「おおらかな優しさ」が、作品全体を覆っていると評してもいいだろう。
本作品集の中には、地球の滅亡を描いたような作品もあるけれども、それは決して恐ろしいような作品ではない。むしろそれは、ユーモラスな作品であり、そうした点で、他の「心優しい作品」と矛盾するものでは、まったくないのだ。
つまり、荻原浩の作家的個性とは、結局のところ、この「肯定性」にある言えるだろう。
何がどうなろうと、それはそれで、決して悲観すべきことでも不幸なことでもない。私たちがこうして生きられたことこそが、あるいはまた、死んでしまえることすら、その大前提として、幸福なのである。一一そんな、悠々とした肯定性を、この作家は持っている。
だから、こうした他を持って代えがたい「荻原ワールド」に魅せられる固定的なファンが、かなりいるのだろうというのも容易に察せられる。
私個人は、こういうものより、不幸を不幸として直視するという方向に惹かれるリアリストではあるのだが、思いのほか、荻原浩の「肯定性」の強度は、侮りがたいものだと、本書によって知らされたのだ。』
『荻原浩の「肯定性」の強度は、侮りがたい』と、そう思ったからこそ、本業である小説の方を読んで、そのあたりを確認しなくてはならない。
ならば、荻原浩の一面しか見られない恐れのある長編よりも、短編集のほうが良いだろうと考えて、本書『押入れのちよ』を読むことにしたのである。
○ ○ ○
本書の収録作は、以下の9篇。
それぞれにつながりはないが、広い意味での「ホラー」作品集だとは言えるだろう。
(1)「お母さまのロシアのスープ」
(2)「コール」
(3)「押入れのちよ」
(4)「老猫」
(5)「殺意のレシピ」
(6)「介護の鬼」
(7)「予期せぬ訪問者」
(8)「木下闇」
(9)「しんちゃんの自転車」

本作品の中で、やはり一番「魅力的な作品」は、表題作の「押入れのちよ」であろう。
この短編を「荻原浩の代表作」と呼ぶファンもいるようだが、その気持ちがよくわかる、とても愛着のわく作品だ。
作品集としては、「ちよ」のような幽霊に代表される「怪異(お化け等)」が登場するものもあれば、しないものもある。つまり、生きた人間の恐ろしさを描いた「サイコホラー」系の作品もあるので、作品集としては「広義のホラー」を扱っていると言えるだろう。
ただ、一般的にいって「感じの良い作品」は、「押入れのちよ」と「コール」くらい。それに、せいぜい「しんちゃんの自転車」を加えてもいいかなという程度で、あとの作品は、どちらかというと「人間のいやらしさ」を描いたホラー作品で、お世辞にも「感じの良い作品」だとは言えない。解説者の東雅夫もそうした作品を「ウラ荻原」と読んでいる。要は「黒荻原」ということだ。
したがって、「押入れのちよ」(や、たぶん「コール」)は文句なしに評判がいいのだが、短編集全体として見た場合は、必ずしも評判が良いというわけではない。頭から3作、「押入れのちよ」までを順に読んだ読者の多くが、その流れで同系統の作品を期待するのだろうが、その期待は、おおむね裏切られると思っていただいて良い。
そんなわけで、まずは、間違いなく本集の代表作である表題作「押入れのちよ」について書いてから、そのほかの作品については、簡単に触れようと思う。
「ちよ」は、主人公の恵太が入居したオンボロアパートの押入れに住んでいた「幽霊」である。妙に家賃が安いと思ったら、案の定「曰く付きの物件」だったのだ。
「ちよ」は、かむろ髪に振袖を着た、昔のお人形さんのような少女(の幽霊)だ。年齢は、10歳ほどに見えるが、本人の曰くは「14歳」で、実年齢より幼く見える。また生まれたのは「明治三十九年」だという。
「ちよ」が、そんな身なりをしているのは、そんな時代の子供だからなのだろうが…。
恵太も、はじめは、夜中に押入れの中から登場した幽霊「ちよ」にビビったのだけれども、そのうち「ちよ」に馴れてしまった。なにしろ「ちよ」のやること言えば、夜中に押入れから出てきて、買っておいた食料を盗み食いするだけなのである。しかも、食われても、いつの間にか元に戻っており、実質的被害を被るわけでもない。
そのうち、恵太は「ちよ」のために、彼女が気に入ったらしい「ビーフジャーキーとカルピスウオーター」を買っておいてやり、それを美味しそうに食べながらテレビを視たりしている「ちよ」の身の上話を、尋ねるともなく訊くようになる。
ところが、彼女の記憶は、あるところから先は、すでに消えてしまっているようだ。もしかすると、幽霊にとっての「生前の記憶」というのは、徐々に消えていくものなのかもしれない。
とは言え、「ちよ」の話を聞いていくうちに恵太は、「ちよ」自身はすでに忘れてしまっている、「ちよ」の悲しい「その後の人生」に気づき、振袖を着ている意味まで理解して、目の前の無邪気な「ちよ」を、いっそう愛おしく思うようになっていくのである。

一一つまり、「ちよ」という幽霊は、何の害もないのは無論、まるでハムスターのように可愛いらしい存在であり、さらには、その無邪気な姿の奥に「悲しい過去」を持っていたのだ。
だから、「ちよ」という存在には、ただ「可愛い」だけではない、深みのある魅力があって、本作は一読忘れがたい印象を残すのである。
版元「新潮社」の、本書紹介ページには、惹句的な見出しとして、デカデカと、
『発表! とり憑かれたいお化けNo.1。ままならない世の中を必死で生きる人間(と幽霊)の可笑しみと哀しみを見事に描いた、傑作短編集。』
とある。
そういうアンケートを何処かでしたのかもしれないが、「まあ、そうだろうな」とは思う。
そもそも「とり憑かれたいお化け」なんてものは、そう多くはないはずだし、そんな中で「可愛いさ・無害さ・愛おしさ」を兼ね備えた「ちよ」のような「お化け」は、他にいないからだ。
もちろん、私も「ちよ」のような幽霊とならお近づきになっていいとは思う。しかし、同居したいとまでは思わない。
なぜなら、彼女と向き合って生活するということは、彼女自身は忘れていても、こちらは彼女の「悲しい過去」と向き合い続けなければならないだろうからだ。
そして、生前の彼女と同じような苦しみや悲しみの中に生きている子供たちが、現に今も、世界中に大勢いるのだということ意識せずにはいられないからである。
「そうした子供たちの存在を知りながら、ただ、ちよと向き合って、のほほんを彼女を愛でていれば、それでいいのか? ちよを、可愛い可愛いと言って、ペットのように可愛がっていれば、それでいいのか? しかしそれでは、〈奴ら〉のしていることと、大差ないのではないか?」一一そう思わずにはいられなくなるだろうからである。
だから、また嫌なことを言うようだが、「ちよ」に「とり憑かれたい」などと呑気なことを言っている読者や、「押入れのちよ」や「コール」などの作品だけを評価して、他の「嫌な作品」の意味を考えないで済ませられるような読者は、所詮「ちよ」たちを食い物にする存在でしかないのではないかと思う。
一一この批判の意味は、このレビューを読んだ読者が本作品集を読むなら、嫌でも、はっきり理解できるはずだ。
残りの作品に、簡単に触れておこう。
(1)の「お母さまのロシアのスープ」は、「日本推理作家協会賞(短編部門)」の候補作になった作品であり、その意味で「仕掛け」のある作品なのだが、私は最初の1ページでそのネタに勘づいてしまった。つまり、本格ミステリを読み馴れた読者には、いささか初歩的な作品で、受賞に至らなかったのも故なきことではないと思う。
(2)「コール」も、同種の作品だが、それを悟らせない点で、(1)より数段良くできていた。よくある「懐古的青春恋愛小説」かと思わせておいて、それには終わらない作品で、しかも仕掛けと内容がうまく噛み合っており、抒情的な余韻を残す作品となっている。
(3)「押入れのちよ」は、前述のとおり。
(4)「老猫」は、「老猫の呪い」を書いた、いや〜な作品。
(5)「殺意のレシピ」は、筒井康隆にありそうな、悪意のドタバタ喜劇。
(6)「介護の鬼」は、「老人介護」をめぐるドロドロした感情を、ホラー仕立てにした作品。
(7)「予期せぬ訪問者」は、殺人の隠蔽をめぐる、舞台演劇的なドタバタコメディー。
(8)「木下闇」は、行方不明となったまま戻ることのなかった妹をめぐる「怪異」譚で、まずまずの出来である。
(9)「しんちゃんの自転車」は、『人生がそんなにも美しいのなら 荻原浩漫画作品集』に収録されていたいくつかの作品に近い『「この世とあの世」がシームレスにつながる「民俗社会的な世界」』を描いた作品だが、ふんわりとした絵柄で描かれたマンガに比べると、こちらは、けっこうグロテスクな印象も否めない。
それを、良いと感じるか、気持ち悪いと感じるかは、人それぞれだろう。
以上のようなわけで、本作品集を読んでみて分かったのは、「押入れのちよ」がそうであるように、作者の荻原浩は「記憶を失う」ことを、必ずしも否定的には捉えていないということだ。だから、私は未読の、「若年性アルツハイマー症」を扱った『明日の記憶』も、「感動作」たり得たのではないだろうか。

そして、そんな荻原にとっては、「記憶」とは、すなわち「この世の記憶」なのである。一一それならば、いっそ忘れてしまっても、それはそれで良いのではないか。忘れてしまうというのは「ひきずらない」「清算する」ということであり、その意味で、「あの世」へ行くのは、必ずしも不幸なことではなく「別の世界に生まれ変わり、新たにそこで生きる」という程の意味でしかなく、自明に悲劇的なこととは、少なくとも荻原には、認識されていないのではないだろうか。
そして、このことを裏返すならば、ほんわかとした作風の目につく荻原だが、しかし、彼の中には「この世への嫌悪」があるのではないだろうか。
だから彼は「あの世」を、むしろ好ましいものとして希求し、その世界を身近に感じているからこそ、彼の描く世界は、どこか「浮世離れ」していて、そこが「救い」とも感じられるのではないだろうか。
だとすれば、荻原浩の作品における「救い」とは、「この世」という「現実」に対する諦めを根底に持ったものだとも言えるのだが、私はそれを、あえて責める気にはなれない。なぜなら、実際のところ、「この世」の現実とは、その程度のものだと、私自身もそう感じているからだ。
荻原浩の「肯定性」とは、「死後含めて」のそれ、だったのかもしれない。
そう考えれば、漫画作品集である『人生がそんなにも美しいのなら』というタイトルの反語的な意味も、今にして理解できるのである。一一私も、表紙画の「明るさ」に騙されて、その「苦さ」を見落としていたのかもしれない。

(2023年11月15日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
