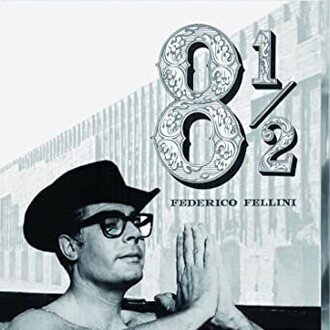#創作大賞2024
シン・現代詩レッスン41
西脇順三郎
『百人一詩』は今日は休みで『詩人たちの世紀―西脇順三郎とエズラ・パウンド』から。西脇順三郎は確かに重要性があるなと思った。また西脇順三郎の詩はパロディとか諧謔性でわたしも詩にイメージするのはそういう部分だった。それは所詮言葉は借り物で何かを言いたいときも言葉を借りてこなければならない。その中で近似値を探るのだが、まったく同じというわけでもなく少しズレている。その部分がパロディとか諧謔
シン・現代詩レッスン37
今日も阿部公彦『詩的思考のめざめ: 心と言葉にほんとうは起きていること』からいよいよ萩原朔太郎の登場である。萩原朔太郎が重要なのは、口語詩を確立したというよりも「内面」の言葉を詩にした詩人だからなのか。それは誰もがやる方法ではあったけど朔太郎ほど意識的に魅力的にやった詩人はいなかったのである。それが「青猫」の登場する象徴詩であり、その声の音楽性であった。
その境地に達するのが「月に吠える」で描か
シン・現代詩レッスン33
今日も川本皓嗣『アメリカの詩を読む 』から「第4講 花ひらくモダニズム」からカミングス『時まさに』をやりたいと思ったのは、「シン・俳句レッスン」のほうで俳句から影響を受けたパウンドとカミングスとを比較して批評したのだが、カミングスの詩を書いているうちにカミングスの魅力をカミングアウトするぐらいに好きなってしまった。カミングスの魅力は一言で言えば高柳重彦並の多行分け現代詩なのだが、一言では言えない魅
もっとみるシン・現代詩レッスン28
テキストはエーリヒ・ケストナー『人生処方箋詩集』。そもそも詩が作者の意図通りに読まれるということがあるだろうか?例えばここにまとめられた詩は、ナチス・ドイツによって禁書とされ、ドイツ人の学生たちの焚書のターゲットとなった詩なのである。それ以前の詩は、ドイツの若者たちを熱狂させた詩であると言われている。それはケストナーが意図してベストセラーを狙ったり焚書の憂き目に合わせるために書かれた詩でもなかった
もっとみるシン・現代詩レッスン27
テキストは寺山修司『戦後詩』,第五章「書斎でクジラを釣るたまの考察」から。最終章はベスト7選出なのであった。ベスト5でもなくベスト10でもなくラッキー7が寺山修司らしさなのだろうか?あまり数は問題ではなく、寺山修司がどんな詩人を選ぶかだった。詩ということだけれども、俳句と短歌も入れている。それは桑原武夫「第二芸術論」を踏まえてのことだ。つまり俳句でも短歌でもそれが十分文学として成り立つとした上であ
もっとみるシン・現代詩レッスン23
テキストは『教科書の中の世界文学: 消えた作品・残った作品25選』から尹東柱「たやすく書かれた詩」。90年代は学校教科書に尹東柱の詩も載せていたのだ。韓流ブームだったからか?直接の契機は茨木のり子が紹介した本『ハングルへの旅』がヒットしたからとあった。他にも李正子(在日歌人)の短歌が掲載されていたりいた。1989年の芥川賞が李良枝(在日作家)だった影響もあるようだ。
ただし同じ頃に高史明のエッセ
シン・現代詩レッスン17
テキストは寺山修司『戦後詩―ユリシーズの不在』。長編詩、12p.以上あった。声を出して読むように指示があったのだ、途中で疲れてやめてしまった。詩が御経のように、言霊として、目前に存在する。長谷川龍生『恐山』。
日本現代詩人会の元会長だから現代詩の世界では有名なんだろうな。残念ながら初めて知った作家だったが。詩の世界ってそのぐらいなのかなと思う。寺山修司をテキストにしているぐらいだから、現代詩のこ
シン・現代詩レッスン15
テキストは寺山修司『戦後詩―ユリシーズの不在』は前回と同じ。前回作った「空回りするモルモット」(仮題)は安永稔和の詩「鳥」に似ているな。めちゃくちゃ否定されていた。彼は書くことによって、鳥になったつもりだがその飛行行為は、ことごとく「飛びそこねた詩人」であると言われてる。人生に意味があると思っているからいけないのだろうか?別の世界(想像世界)が見えているとも言っている。そこまで辿り着ければいいのか
もっとみるシン・現代詩レッスン10
今日も『春と修羅』から「小岩井農場(パート九)」。
「小岩井農場」は賢治の地元にある酪農農場。
『春と修羅』の中に「小岩井農場」と題の詩は「パート1」から「パート9」まであるのだが、5,6,8が欠落している。賢治が小岩井駅から小岩井農場までを歩いた歩行詩であり、その中に回想や心象スケッチが含まれる。例えば5.6は欠落しているのだが、後の別の形で「第五綴」「第六綴」と題されて宮沢賢治の学校(教師