
新たな謎があなたの骨の中で歌う
ミシェル・フーコー『L'archeologie du savoir, L'ordre du discours』(原題)『The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language』(英題)

知の考古学と言語の Discourse …… 談話・言説・演説・論文 …… 彼の言うところの Discourse とは、何なのか。
彼の言葉を引用して、イントロとする。
これを解説するような内容にするつもりだ。私はマンガやアニメをあわせて書くスタイルをよくとる。今回は『亜人』でいく。


あなたはまたもや豹変し、投げかけられた質問に応じてポジションをシフトし、その反論はあなたが話している場所に向けられたものではないと言うつもりか。
またもや、自分は非難されるような人間ではないと宣言するつもりか。
次の本でも、どこか別の場所にとび出し「いやいや、君が私を待ちぶせしている場所に私はいない。こちらから君を笑っているのだ」と宣言できるように、すでに逃げ道を用意しているのか。
私がふるえる手で、冒険し自分の Discourse を進められる迷宮を用意していなかったら。ライティングにこれほど苦労し・これほど喜びを感じ、これほどねばり強く自分の仕事を続けていると思うか。
その中で私は自分を見失い、最後には、二度と出会うことのない瞳に姿を現すことができるのだ。
顔をもたないために書いているのは、間違いなく私だけではない。
私が何者であるかを問うてきたり、私に以前と同じままでいてほしいと望んできたり、しないでほしい。
私たちの書類がきちんとそろっているかどうかの確認は、官僚や警察に任せておけばいい。少なくとも、私たちが文章を書く時、彼らの道徳観念は必要ない。
ミシェル・フーコー

Discourse という概念は、ミシェル・フーコーの作品の中心的要素の1つである。
フランス語でも英語でも(スペルもほぼ同じで)、物事や考えを言葉で表すことを意味するが。フーコー的には、単なる言語による表現ではなかった。
無意識のうちに制度や権力と結びつき、現実を反映するとともに現実を創造する。制度的権力のネットワーク。そんなニュアンスで、フーコーは Discourse という用語を使っていた。
制度的権力は、抑圧・排除・差別などと関連していて。多くの人間による言表の集合であり・個々人を反映していない Discourse は、そのような力と関係しているのだと。

サルトルについて書いた過去回。

サルトル「道徳的な選択は芸術作品を構築するようなものだと言えよう」
フーコー「全ての人の人生が芸術作品になることはできないだろうか?」
サルトルとフーコーの作品には共通点がある。ブルジョア社会に対する反感と、疎外されたグループに対する共感だ。疎外されたグループとは、「狂人」や同性愛者や囚人のことだった。
2人が一緒にうつっている写真もいくつかある。



しかし、結局、フーコーはサルトルを拒否した。
サルトルが全ての分析の出発点として個人主体を優先していると感じ、それを拒否した。個人の自由の不可侵性などの普遍的な道徳原理にうったえて、社会を判断しているとサルトルを認識し、それを拒否した。
サルトルは、1940年代から1960年代にかけて、フランスの知的シーンに深く浸透していた。公的領域における影響力も著しかった。(物質主義的な資本主義社会で、哲学者がそのような地位に。偉業だ)
次世代のフランス思想家たちの中で、各人が望むと望まざるとにかかわらず、サルトルは生き続けた。フーコーの中にだけではない。ドゥルーズ、デリダ、ボードリヤール……の中にもだ。たとえ、著作に直接的にその名が出てこなくとも。

フーコーは、自身を思想史家と見なしていた。サルトルは、自身を哲学者・随筆家・革命家と見なしていた。フーコーは、権力と権威に焦点をあてていた。サルトルは、個性と自由に焦点をあてていた。

私の言いたいことが伝わるといいのだけれど……。
ヨハン・ハインリヒ・フュースリーは、「自然は集合的な概念であり、その本質は種のそれぞれの個体の中に存在するが、その完全性は単一の物体の中に宿ることはできない」と述べていた。

ウィリアム・ブレイクは、「ある人を感動させ涙を流させる木は、他の人の目には邪魔な緑の物体にすぎない」と述べていた。


誰もが独自の視点をもち、他の人たちとは違った見方をする。誰もが語るべき独自の物語を、誰もが自分だけの小さな世界をもっている。
同じ目的に対して異なる手段を用いる者たちは、わざわざサヨナラしがち。
力みすぎなんだよ……。

全文・全段に「フーコーによると」と書きそえていくと、読みづらいだろう。そうはしないが。フーコーによると、だ。
社会秩序内の権力は、特定の規則やカテゴリーを定める。これらの規則やカテゴリーは、演繹的なものである。

権力が発生させた Discourse は、理論が「集合的に理解されること」と「社会的事実として受容されること」を通じて、社会的関係を(最終的にはグローバルな関係をも)構造化する。
具体的には。発言やテキストが社会で繰り返されることを通じて、その生産の根底にある政治的合理性などに資するように、人々の中で「意味」が固定されていく。
そして、Discourse は Discourse にその能力があることを隠している。つまり、意味を固定する力があることだけでなく、政治的意図があることも隠している。
Discourse は、普遍的かつ科学的・客観的かつ安定的なものであるとして、自らを偽装することもできる。


フーコーを知っている人は、すぐに Discourse じゃんと思い。フーコーから教わらずとも気づく人は、違和感を感じ。それ以外の人たちは、おいおいい実感していく。
自分の首がしまる社会を率先してつくりあげておきながら、自分が被害者側になった時にはじめて、成り行きを理解する者もいる。こんなはずではなかったと。

洗脳のこと?近いとは思う。
だが。「洗脳」という言葉は、1951年に米国のジャーナリストが、中国政府の心理戦について語る文脈の中ではじめて導入したものだ。(そのジャーナリストは、それを脳の戦争とも呼んでいた)
それぞれに、着眼すべき大事なことがあるように思う。せっかくフーコー(など)が考えてくれ伝えてくれたのだから、雑にひとまとめにはしたくない。
特定の存在条件をともなう一連のアイディアは、多かれ少なかれ、制度化され実践されている。それらに含まれる個々の人々は、部分的にしか理解されない可能性がある。

「敵」キャラの佐藤も人気だよね。
当時、フーコーが同性愛者としてフランス社会で生きるのは難しいと感じていたことは、周知の事実である。
フーコーの研究方法は特徴的だった。精神医学などからアプローチするのでなく、歴史の観点からそれを行った。「狂人」や同性愛に対する(当時のフランスの)一般的な見解は、歴史の産物であり。歴史が違う道をたどっていたならば、あるいはーーと考えた。
サルトルの個人主体を受け入れていたら。気持ちがふさぎこんでいる時などに、「全て自己責任」的な感情になりかねなかったのかもね。何か、自分以外のところに、理由がほしかったのかもしれないね。
フーコーは1984年にエイズで亡くなった。
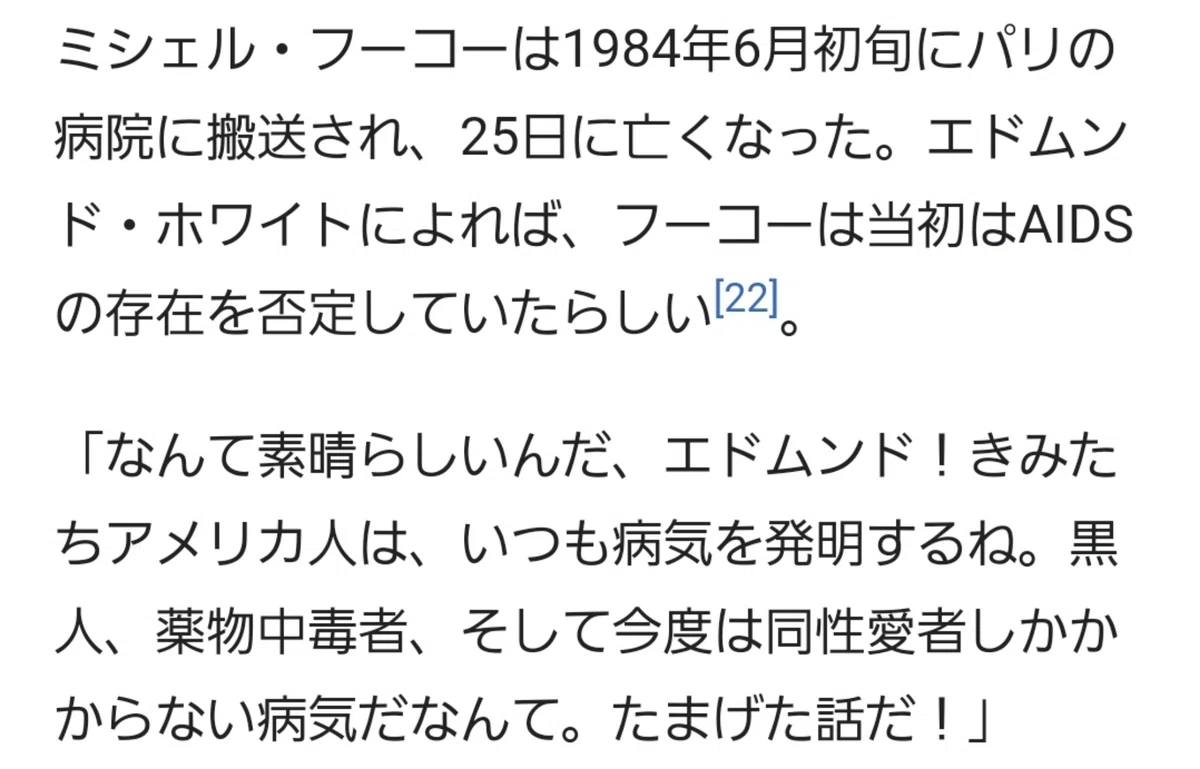
まだ、この病気の理解が進んでいなかった頃だ。仕方あるまい。このような発言は彼の思考と一貫性がある。
思い悩み自殺をはかったこともあるとのことで、軽くあつかってはならないが。逆に、重くとらえすぎるのも違うのかもしれない。
フーコーの伝記を書いた人物も、苦悩に満ちた男 → リラックスした陽気な男 と、彼の印象は変わったと記していたし。
冒頭のフーコーの引用をもう一度。「私が何者であるかを問うてきたり、私に以前と同じままでいてほしいと望んできたり、しないでほしい」
ドラッグでハイになったり、いわゆるハッテン場でエキセントリックになったり。彼に楽しい日常生活がなかったと、勝手に決めつけるのはいけないかなと。

ゴヤもすごくあたまがいい。
Discourse の話に戻る。
Discourse の特定の意味や力を固定するために、他の意味や解釈は排除される。
たとえば。Discourse で表明された「真実」に従わない者を社交の外側に配置すれば、テキストの偶然性(他の意味や解釈)を減らすことができる。

『亜人』を貼りながら解説したため、『亜人』のキャラクター内で言うと。彼は彼で、人々の中で意味を固定させようと目論んで、discourse(演説)をしている。


このキャラクターの本懐は別のところにある。
フェイク・ニュースの方が真実の報道よりも、6倍速く・1.7倍多く拡散される。
カラクリはいたって単純。
真実はより地味な内容、フェイクはより過激な内容の確率が高い。後者は何者かの創作である可能性も高く、話がほどよく盛れるため。人間は、不安や怒りをかき立てられた情報を(そうでない情報に比べよっぽど)拡散する。

誰が語っているのか。どのような立場や視点から語っているのか。

語られた内容によって生み出される、「権力」の影響を分析しなければならない。支配的な Discourse がどのように行使されているのか、検証しなければならない。
少なくとも。同等に有効な(別の)主張を構成する者たちを排除し疎外し抑圧する、そんな方法が存在するということには、意識的でいなければならない。

フーコーは、受けたインタビューにこう述べたことがある。「今になって考えてみると。私が語っていたのは権力以外の何かだったのか、と自問する」

こういうフーコーに好感をもつ人たちがいる一方で、最後までやりきれよ的な苦言を呈する人たちもいるようだ。
私たちが考えたっていいではないか。そうした未完の課題のいくつかを自分たちで試みてみることを、禁じられているわけではないのだから。
ドゥルーズは、彼の死後、彼に関する本を書いた。
フーコーが懸念していたのはこういうことなんじゃないかと、「管理社会」という概念を提示したり。あーね。監視カメラとか個人情報とかね。メリットもデメリットもある感じね。

ドゥルーズは、政治的な「ビオトープ」の成長を追うことを信じていた。言いたいこと(革命的になろう・脱領土化しようなど)に、木や根や枝というワードを使った。


ドゥルーズとガタリの『Anti-Oedipus』は、ジラールの考え方に似ているが。また植物をあわせてくるものだから、自己と他者と欲望の話もリゾームになる。


ボードリヤールは『Forget Foucault』という本を出版した。フーコーは怒ったそうだ。

フーコーを忘れよう!にフーコーが怒ったという当たり前すぎる展開が、おもろすぎて無理。今だったら、インフルエンサーどおしのケンカを想像してほしい。YouTubeで互いにお気持ち動画を出しあったりするアレ。(ああいうものにはヤラセもあるのかもしれないが)
ブレない男(笑)ボードリヤールに言わせれば。フーコーの「権力」も、ドゥルーズとガタリの「欲望」も、シミュラークルとシミュレーションだ。何もかもがシミュラークルとシミュレーションだ。

ボードリヤールによると。「第3段階」である現代社会は二進法的な関係にあり。もはや対立の関係でさえない。では、なんなのか。シミュラークルだ😂
リセットする。まじめに書く。部分的に笑えるだけで大事な話だからな。
決闘的な行為も失われており、挑戦者も出てこないと。

「ファイト・クラブ」が「プロジェクト・メイヘム」になってしまい、「プロジェクト・メイヘム」が腕力を失いネットでしかイキれなくなってしまい、今にいたる。そんな感じだ。
現代社会は閉ざされた記号体系で。一面鏡ばりの部屋でヒトとモノが永遠に反射していると。
みんな意見が違っておもしろい。
ルネ・シャールの「新たな謎があなたの骨の中で鳴り響く」だ。私はこれが楽しくて一生勉強が好きだ。

佐藤は身勝手だ。それでも人気がある。

これまでにあまりにも嫌気がさすと、破壊者寄りでも救世主寄りに見えてしまう。物事は比較だからね。
カントは言っていた。自分自身で悟った者だけが影を恐れないと。

これは私もよくわかる。人生を悟ったーーなんて壮大な意味ではなく。生きていく中である、無数のそんな機会の話だ。実体験を書きたいのは山々だが、長くなりすぎてしまう。みんなそれぞれに体験談があると思う。
哲学は典型的に、常識を疑問視することをともなってきたが。カントは、哲学を知識批判としてとらえるという現代的な考え方を発展させた。

カントの言う「批判」にネガティブな意味あいはない。彼にとっての批判とは、純粋に吟味することだ。『純粋理性批判』私は何を知り得るか。『実践理性批判』私は何を成し得るか。『判断力批判』私は何を望み得るか。
神は存在するのか・人間は自由なのかといった形而上学的な疑問について議論する、多くの哲学者たちを見て。カントは思った。個々の経験からくる全く独立した世界を知ることは、そもそも可能なのか?と。そして、1つの考えにいたった。
世界のどんな事柄であれ。経験から完全に独立してあるがままに認識することはできない。
人は自分の見たいようにしか世界を見ないーー的な話で終わらせない。カントはポジティブだ。
カントの偉大な認識論的革新は、我々の認識力の限界を明らかにしたのと同じ批判が、その認識力を発揮するための必要条件も明らかにできると主張したことだ。

カント「啓蒙とは、人間が自らまねいた保護からの解放である。保護とは、他人からの指示なしには自分の理解を活用できないことだ。この保護が自らまねいたものとなるのは、その原因が理性の欠如ではなく、他人からの指示なしにそれを活用する決意と勇気の欠如にある場合だ。Sapere aude!これが啓蒙のモットーである」
フーコーはと言うと。このカントの動きを逆転させる必要があると示唆した。
一見偶然的なものの中で、実際に必要なものは何かを問うのではなく。一見必然的なものの中で、何が偶然的であるかを問うことを提案した。
こういうところに、だり〜・逆張り合戦かよと思う人がいるかもしれない。わかる。けれども。進化したものが退化しただとか、そういうことではない。それが、誰が絶対的にあっている/誰が絶対的に間違っているのではない・白/黒ではないということだ。
多様性ーー言うは易し行うは難し。
しばらく、話のつながりが見えづらいと思うが。聞いてほしい。
『亜人』のキャラクターに、交通事故で首が切断されるという死に方をして、自分が亜人だと知った青年がいる。頭部の損傷や半壊だったのならば、修復がなされたのだろうが。断頭であったため、体から新しい頭部が生える形で復活にいたった。
それでも、記憶が受け継がれるらしい。

「スワンプマン」(沼男)という思考実験のことだ。

『変身』は、脳移植によって主人公の人格が変わっていく物語だが。

仮に。脳移植というものが技術的に(理論上より現実的にと言うか)可能、かつ、他の臓器移植のように行われるものになったとして。
それは、Aさんの脳をBさんの体へ移植する、Bさん主体の脳移植でなく。Bさんの体をAさんの “脳に” 移植する、Aさん主体の体移植ということになる気がする。
現実に存在するのは、心臓移植後に人格特性が人から人へ移行する現象の報告だ。半世紀近く前から報告されている。
大前提、この現象はまだじゅうぶんに理解されていないが。ドナーとレシピエントの間で、何らかの形の記憶転送が発生していなければ、性格の変化は起こっていない。
ドナーの人生における記憶が提供された心臓の細胞に保存されていて、移植手術後にドナーによって「思い出される」とでも言うのだろうか。
これをあきらめても二項対立にはならないが。一笑に付して終わってしまえば、この先はない。
エピジェネティック記憶・DNA記憶・RNA記憶・タンパク質記憶など、記憶を保存する可能性のあるメカニズムについて、さまざまな研究と議論がなされている。

もちろん、科学的に解明されることが全てではないが。
ちなみに。Cardiac memory 心臓の記憶 という言葉があるが。それは循環器学の用語であり、前述したような話とは関係ない。
必要があり電気刺激で脈を補助された心臓が、通常の脈に戻った後も、一時与えられたパターンを忘れない。そのようなふるまいを見せる時があることだ。

これまでの報告から。心臓移植後の性格の変化は、嗜好の変化・感情や気質の変化・個人のアイデンティティーの修正・ドナーの人生に関する記憶の、4つのカテゴリーに分類されている。
1988年に心臓と肺の移植手術を受けた後に、自分の性格・嗜好・行動に変化があったと報告した女性。彼女は、それまで嫌いだったピーマンとチキンナゲットが好きになった。退院してすぐに買いに行ったほど。それはドナーの好物だったことが判明した。
5才の子に3才の子の心臓が移植された。「小さな子。弟みたい。パワー・レンジャーが好きだったけど今は好きじゃない」彼のドナーは、窓枠に落ちたパワー・レンジャーのおもちゃに手を伸ばそうとして、転落死していたことが判明した。
ある大学教授に、顔面を撃たれて亡くなった警察官の心臓が移植された。「移植後、同じ夢を何度も見るようになった。閃光が見え顔が熱くなる夢だ」そういう決まりごとになっているため当然だが(前述の2名もそうだが)、彼はドナーの死亡理由を知らなかった。
勘違いやバイアスもなくはないだろうが。全例が「ハッタリ」とは思い難い。そもそも、ハナから全てを疑ってかかるなんて、体験談を伝えてくれた方々に失礼だしな。
フーコーの観点からすると。科学的知識への「崇拝」は、それが権力と切り離せないことを見えなくさせてしまう/忘れさせてしまうのかもしれないが。
私は人間の信仰心や芸術がとても好きで、科学の恩恵を受けている日々にも大変感謝してい る。AIを万能だとは思わないが、今日聞いたAI生成ミュージックを気に入った。
同じようにフーコーにも、あなたの考えを伝えてくれてありがとうと言いたい。みんな、すごくおもしろい。
【お知らせ】去年まで毎週月曜更新でしたが、今年から毎週火曜更新になります。よろしくね。いつもありがとう。
