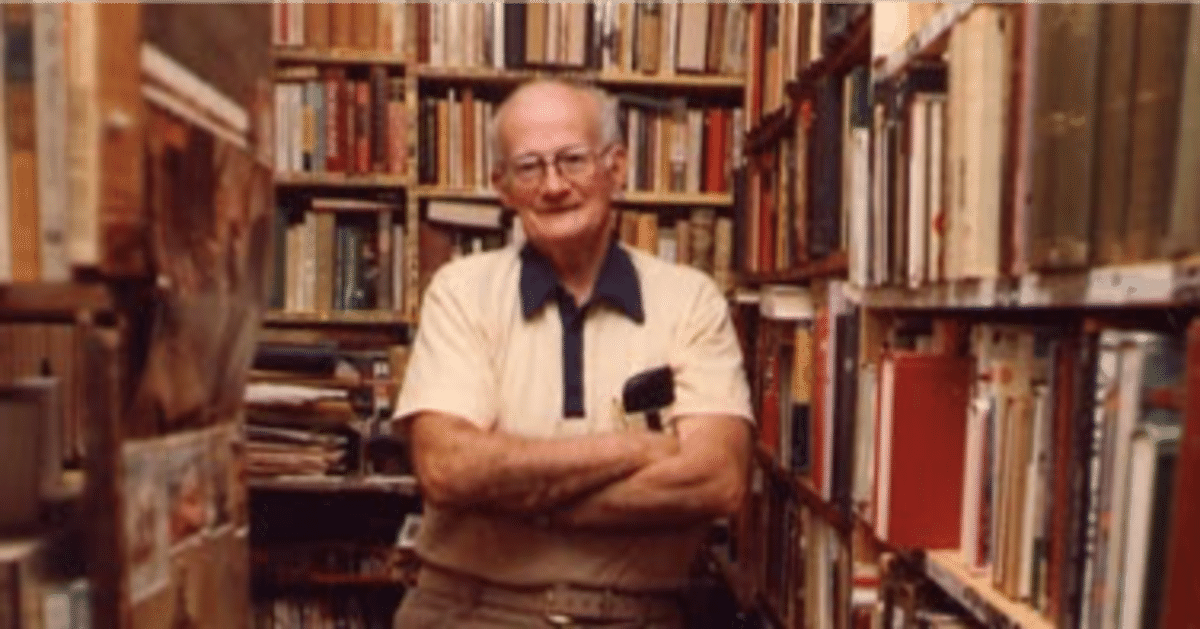
牧眞司編 「ラファティ・ベスト・コレクション」 : 愛嬌のある〈ホラ吹き怪獣〉 R・A・ラファティについて
書評:R・A・ラファティ著、牧眞司編「ラファティ・ベスト・コレクション」全2巻:第1巻『町かどの穴』、第2巻『ファニー・フィンガーズ』(ハヤカワ文庫SF)
初めてラファティを読んだ。もともと、小説はミステリを中心に読んでいたから、読みたいという思いはあっても、SFはあまり読んでいない。内外ともに、個人的な好みに合致するSF作家については集中的に読んでもいるが、SF史的に「当然読んでおくべき作家」の多くについては、まだまだ読めていないのだ。
いくつか読んだ上で「この人は、まったく合わない」とわかって読まないのはいいのだが、試しに読んでみたいと思いながら、その試しがなかなか読めないというのは、「宿題」を抱えているようで、どうにもスッキリしない。
だから、定年の近づいた年齢になって、いろんなジャンルの読み残し作家を読んでいるわけだが、昔ほどではないにしろ、新人の新作だって気にはなるので、なかなか昔の作家の昔の作品は、思うほどには読めないのが実情である。
さて、今回ラファティを読めたのは、ひとえにこの「ベスト・コレクション」のおかげと言えよう。
飛び抜けた代表作がある場合は別にして、まったく読んだことのない作家については、どの本から読み始めるかが重要かつ難しいところだからなのだが、「ベスト・コレクション」なら「ひとまず、これを読んでおけば安心だ」と考えたのである。
ちなみに、なぜこれまでラファティを読まなかったのかと言えば、それは、以前にハヤカワ文庫刊行されていた『九百人のお祖母さん』などの表紙画が、マンガっぽいタッチのものであり、いかにも「ユーモアもの」だという印象を与えたからである。

別に、ユーモアものが悪いわけではないし、気難しい小難しい小説が偉いと思っているわけでないのだが、私の好みは「硬派」な「男性的」作品ということになるので、どうしても「ユーモアもの」は敬遠していたのだ。無限に時間があるのならばともかく、読みたい本の方が無限にあるのだから、原則として、軽いノリのものや女性作家のものは、どうしても後回しにせざるを得なかったのである。
ちなみに、ミステリを読んでいた頃もそうで、私は女性作家のものをほとんど読んでいなかったのだが、例外的に、ほとんど唯一好きになった女性作家は、デビュー当時、その重厚な作風で男性作家と間違えられることの多かった、高村薫だった。
ともあれ、ラファティの場合は、日本語版著書の表紙画から推して、作風が「軽いのではないか」と思えたから、これまでは後回しにしてきたのだが、そのラファティを、なぜ今頃になって読むのかと言えば、それは30年も前、古本友達だった、今はミステリやSFなんかの評論を書いている友人がまだアマチュアだった時代に、ラファティを熱心に読んでいたという記憶があったからだ。
「何を読んでるの?」「ラファティです」「それ面白い?」「ラファティはすごい作家ですよ」といった程度の会話だったが、彼はとにかくたくさん小説を読んでいて、一家言ある人だったから、私も「読まずに、ラファティを軽んじてはいけないな」と、ずっと気になっていたのである。
○ ○ ○
さて、今回刊行された「ベスト・コレクション」2冊に収められた短編39作を読んでの感想だが、牧眞司による解説に、あえて付け加えるほどの、独創的な見解は示せそうにない。まったく「あ〜あ、やんなっちゃった」という感じだが、私の感じたところを率直に書いておこう。

まず、ラファティは、いわゆる普通の「SF作家」ではない。SF的な舞台設定やアイデアが使われる作品が多いとは言え、「科学的」というわけでもなければ、「思弁的」というわけでもない。
いわゆる、物事を「哲学的」に考えるタイプでもなければ、ましてや「リアリスト」などでもなく、「神話的」な世界に魅せられていて、それを表現することのできる「変な」作家であり、言ってしまえば、「この世界」よりは「あちら側の世界」に惹かれ、その間にあって「あちら側の世界」を引っ張ってくる「霊媒」的な作家、とでも言えるかもしれない。
その表現は、深刻さを避けて、あえて陽気な「ホラ吹きぶり」を見せる点で、「ユーモア」作家という印象を読者に与えるのだが、しかし彼は、本当に「陽気な作家」なのだろうか?
私は「違う」と思う。
彼の「陽気さ」には、本来自分のいるべき故郷から流刑にあった人の「寂しさ」が、にじんでいるように思う。彼の小説における、にぎやかさやユーモアの陰には、「こちら側の世界」に順応しきれない者が、酒で酔っ払って、ことさらにぎやかに騒いで見せているような感じが、どことなくするのだ。
もしかすると、彼は「あちら側の世界」に帰りたいのではないだろうか。
だが、帰れないことを知っているからこそ、せめて陽気に騒いで「この世の憂さ」を晴らそうとするし、「ホラ話」めかして「あちら側の世界」って語って見せるのではないだろうか。
だからこそ、彼の作品には、牧眞司も指摘するように、「二重性」があり「可愛らしさ」があり、この二つが重なるところでの「悲劇性」もある。
○ ○ ○
ちょっと、突拍子もない喩えになるだろうが、ラファティの作風とは、特撮ドラマ『ウルトラマン』(初代)の第35話「怪獣墓場」(監督:実相寺昭雄、脚本:佐々木守)に登場した、亡霊怪獣シーボーズみたいなところがある。

この回を視たことがある方ならご承知のとおり、シーボーズは「亡霊怪獣」と言われるだけあって、骸骨がむき出しになった、「グロテスク」と評してよい外見を持つ怪獣だ。
しかし、シーボーズは決して、人類に仇なすために地上に現れたのではない。人類が宇宙に向けて発射したロケットが、「怪獣墓場」に漂っていたシーボーズを、誤って連れ帰っただけなのだ。
この「怪獣墓場」の回では、どこへ行っても嫌われ者でしかない怪獣たちの、最後の「安息の場所」が怪獣墓場ではなかったかと語られ、事実、シーボーズも怪獣墓場に帰りたいのだろう、空を見上げては、悲しげに吠えるのである。
このように、シーボーズは外見こそグロテスクなものの、その行動所作は、作中でも語られているとおりで「宇宙の孤児」とも呼ぶべき、寄る辺なく哀れな、まるで「迷子」のような怪獣で、シーボーズが寂しそうにうなだれて歩く姿や、石ころ(?)を蹴ろうとして空振りをし、ひっくり返るというその様子は、明らかに「子供」を意識した「カワイイ」ものだった。
だから、シーボーズが、「怪獣墓場」から心ならずも「地上」につれ来られた「グロテスクだけれども、カワイイ怪獣」であるのと同じように、ラファティの描くキャラクター(のいくつか)も、そしてラファティその人も、「あちら側の世界から、こちら側の世界に、心ならずもつれ来られて怪獣」だと言えるのではないだろうか。
無論、ラファティは「大人」の外見を持っており、だから「酔っ払いのホラ吹きオヤジ」という、あまり一般には歓迎されない外見(イメージ)をまとってはいるが、彼の中にいるのは「一匹のシーボーズ」なのかもしれないと、私はそんな風に感じたのである。
○ ○ ○
(2021年12月20日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
○ ○ ○
