
山上たつひこ 『光る風』 : 通過できない〈未来〉
本作は、1970年4月から11月にかけて「週刊少年マガジン」に連載された、「近未来ポリティカルフィクション」である。
1970年と言えば、「大阪万博」の開催された年だが、前年には「東大安田講堂事件」があって、『1959年(昭和34年)から1960年(昭和35年)、1970年(昭和45年)の2度にわたり日本で行われた日米新安全保障条約(安保改定)締結に反対する国会議員、労働者や学生、市民及び批准そのものに反対する左翼や新左翼の運動家が参加した反政府、反米運動とそれに伴う大規模デモ運動である。』安保闘争が、まだ現に闘われていた、いわゆる「70年代安保闘争」時期である(Wikipedia「安保闘争」)。
本作は、そんな時代に、「X年後の日本」の政治状況を描いた、言うなれば「ディストピア」漫画だ。
『軍事国家化が進む架空の近未来日本を舞台とする。「愛国心」という名の狂気へと突き進む政府、狡猾に操る巨大権力、簡単に洗脳され人間性を失って行く国民。抗おうとする若者たちは容赦なく踏みにじられていく。』
(Wikipedia「光る風」より)

本作をいま読むと「いかにもな感じだなあ」という印象は否めないが、決して読むに苦痛な、「ハズした」作品などでは決してない。
作中で「戦争から30年経った今」というようなセリフがあるので、年号は明記されていないものの、想定されているのは「1975年前後」と見ていい。
つまり、「このまま日米安保体制」に巻き込まれていけば、日本は、そのくらいのペースで、アメリカの属国的な立場に置かれたまま、遠からず「軍事国家化」していくのではないか、一一という「危機感」を持って、この作品は描かれたということであり、その「危惧」は、半分はハズれたものの、半分は当たった。その意味で本作は、決して「ハズした」作品などではないのである。

言い換えれば、本作に描かれた問題は、今も決して、古びてはいない。
だからこそ、今でも「読める」作品になってはいるのだが、問題は、「読者」の方が、「現在の日本」についての適切な「現状認識」を持っていないと、本作の問題意識を共有する(読み取る)ことができない、ということの方なのだ。
この当時、作者の頭には、反政府運動をした多くの人たちと同様の「このままでは、日本はアメリカ帝国主義の片棒を担ぐ国になってしまい、平和国家の理想が潰えてしまう」という危機感があった。
しかし、そのおよそ半世紀ののち、本作をに読むことになる「日本人読者」の多くは、すでに作者らの危惧した「洗脳」が完了しており、「平和国家・日本」というのは、「日本の中が、平和であること」であって、「日本が、世界の平和に貢献する国家であること」など、すでに意味してはいない。
要は「自分たちさえ幸せであれば、他国を踏みつけにしても、気にしない」というのが、「洗脳」の終わった日本人の姿なのである。

今の日本人の多くにとっては、「日米安保体制」は「自国防衛」のための「自明の前提」となっている。「アメリカに守ってもらうためには、アメリカとの軍事協力が必要だ」という、完全な「依存体質」が確立されていて、「独立自衛」という発想は無いに等しい。
もう、「アメリカの子分(属国)」であることは自明の前提であり、「ジャイアンにくっ付いているスネ夫」であることを「恥ずかしい」と思う「独立自尊」の精神など失ってひさしいのだが、これが戦勝国であり、日本の占領国であったアメリカからすれば、「洗脳」でなくして何であろうか。
「日本は決して逆らわない、アメリカの下僕」であり、そのことを忘れた「民主党政権」は、「アメリカ政府の意向を受けた自民党」と「奴隷根性の染みついた国民」によって、早々に葬られてしまった。
「属国」が、領主に向かって「一人前の口」をきいたのだから、ただでは済まされなかった、というわけだが、それを「悔しい」とも思わないのが、「洗脳」によって「奴隷根性」を刷り込まれた、今の日本人なのである。
その点で、「戦力としての自衛隊」を認めるか否かなどという問題は、本来なら「自分たちで決めるべき、二の次の問題」でなければならない。
つまり、まずは「独立国」として、アメリカの「支配」から自由になった上で、「自衛」をどうするのかを、「自分たちで」決めなければならない。
「軍事力」を自前で持って「自衛」するのか、それとも「軍事力」は持たないで「理想主義的平和国家」であろうとするのかを決め、その上で、アメリカを含む他国との関係を、自国防衛を含む自国利益と世界平和の観点から、自己決定で進めていく、というのが、本来の「独立国家」としての、当たり前の姿なのである。
しかし、これが「当たり前」ではないのが、「アメリカの属国」たる「現在の日本」なのだ。
日本国民の多くは「選択肢など無い」と思っている。「基本的に、アメリカの子分」という立場しかなく、その中で「アメリカの一の子分」として、せいぜい「世界的にも認められたい」というのが「今の日本の政治方針」だが、そんな立場さえ、経済的な失政によって、すでに失われているだろう。
だがまた、そんな「情けない現状」すら見えないというのもまた、「アメリカ政府の意を受けた、自民党政府」の「洗脳」のせいなのである。
したがって、本書を読んで、「予想がハズれた」とか「古い」といった感想しか持てない日本国民が多いというのも、その「被洗脳」のゆえに、致し方のないことだろう。

たしかに、今の日本は、本作が描いたような、露骨な「軍事国家」にはなっていない。表面的には「平和国家」の体裁を維持していて、その意味では、本作が描いた「近未来の日本」にはならなかった。
しかし、その一方、日本が、「平和国家」たらんとした理想は、完全に放棄されて、「一国平和主義」になってしまっているのは事実であり、外から見れば「アメリカ軍の補完戦力」になっているというのも否定できない事実なのだから、本作の「危惧」は、半分は当たって、すでに「現実化している」と言えるだろう。
一一なのに、その「半分は当たった、不吉な予言」の側面について、まったく意識できない読者とは、どういう精神構造をしているのか。
それは「目の前の(自分の)平和さえ、ひとまず確保されていれば、そこ以外にはすべて目を瞑る」というのが習慣化した「奴隷根性」である。
だからこそ、「当たってしまった、不吉な予言」からは目をそらして、それをなかったことのように思い込もうとするその一方で、ハズれた部分を、ことさらに強調したがる。
しかし、少し考えてみればわかるとおり、本作は「予言書」ではなく、「警告書(預言書)」である。
「未来を言い当てるため」に書かれたものではなく、「こうならないように注意せよ」という警告を発して「こうならないようにするため」の作品なのだ。つまり、一種の「抑止力としての作品」なのだから「作品に描かれたまんま」にならないというのは、いわば「当然のこと」なのだ。
だが、「洗脳」されているがために、そのことを理解できない読者が、本作について「予想が外れた」とか「古い(古くなった)」などという、的外れな評価をして、安心しようとするのである。
ここまで書いても、「洗脳されている読者」には、理解不能だろうから、たとえ話で、子供にでもわかるように説明しよう。
ある人が、いまどき珍しい「ヘビースモーカー」だったとして、その友人が彼に対し「そのままじゃ、君は肺はまっ黒になったあげく、肺がんになって、大変な苦しみの末に死ぬことになるぜ。まあ、君自身はそれで構わないのかもしれないが、君が死んだら、残された奥さんや子供さんはどうなる? 当然、奥さんたちは大変な苦労をすることになるし、君の喫煙の副流煙のために、子供さんまでガンになったら、君に責任が取れるか? 取れないよな、すでに死んでいるんだから」と言って、禁煙を奨めたとする。それで彼も、少しは考えて、禁煙はできないまでも、タバコの本数を減らし、喫煙はベランダでするようになった。
そんな彼が、10年後、彼に禁煙を奨めた友人に対し「おまえは、あんなことを言って俺を脅したけど、今でもタバコを吸っている俺は、肺がんになってもいなければ、無論、死んでもいないぜ。つまり、おまえの予言はハズれた。おまえは心配しすぎなんだよ」と勝ち誇ったとしたら、どうだろう。
無論、そんなことを言うようなら、彼は完全にバカである。
なぜなら、彼は、未だガンを発症していないのは、タバコの本数を減らしたせいかもしれないし、言い換えれば、まもなく発症するかもしれない。それに、本数を減らしても、彼の肺が、非喫煙者のそれとは違って、ずいぶん汚れてきているというのは、否定できない事実だろう。
それなのに、「まだ発症していない」という「現時点における、表面的事実」だけを見て、友人の「警告」が「ハズれた」などと言うのは、明らかな浅見でしかなく、そうした物言いの裏側にあるのは「今後もガンを発症したりはしない(と信じたい)」という「願望」に他ならないのである。
したがって、日本が、本作が描いたような軌跡を「そのまま」だとったわけではないとしても、本作の「未来予測」が「ハズれた」ということにはならない。
そこに描かれた「来るべき近未来」とは、「70年当時の日本の流れ」に対し、「何も対処せずに、そのまま流されたならば」という「条件付き」のものとして、「こうなってしまう恐れもあるぞ」という警告として発せられたものなのだ。本書は、「70年当時の日本の流れ」への、「対処」の一つに他ならなかった。
当時の流れに「抵抗した人々」や、本作のような「抵抗としての作品」があったからこそ、多くの国民は、「警戒」し「思考」し「自制」したのである。
本作がなぜ「伝説的な傑作マンガ」と呼ばれるのか。
それは、本作が当時として「衝撃的な作品」であったばかりではなく、半世紀を経た「今の日本」に対してさえ、有効な「警告」を発し続けているからである。

「どんなことがあろうと、日本は、こんなことにはならない」と、そんな呑気なことが、果たして言えるだろうか?
例えば、敗戦時に焼け野原となっていた日本が、奇跡的な経済復興を果たすとは、当時の日本人の「誰も想像しなかった」し、経済復興を果たして「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と呼ばれていた頃の日本人、自分たちを「一億総中流」だと認識していた日本人は、誰も、
『厚生労働省の「2018年 国民生活基礎調査」による相対的貧困の基準は世帯年収127万円とされ、相対的貧困率は15.7%に達しています。 つまり日本人口の6人に1人、約2,000万人が貧困ライン以下での生活を余儀なくされているのです。』
(『GRAMEEN NIPPON』・「日本における貧困の実態」より)
なんて酷いことになるとは、想像だにしなかった。
だが、これはすべて「現実」であり、このとおり「現実」とは「予想どおりにはいかないもの」なのである。
だから、「なってほしくない未来」を、自らの手でたぐり寄せるようなことにならないためにも、私たちは、「不幸の芽」を小さいうちに摘まなければならない。
それが「大きく育って」しまってからでは遅いのだ。あとで「あんなに心配するほどのことではなかったのかな?」と思うくらいに「心配」しておいて、ちょうどいいのである。
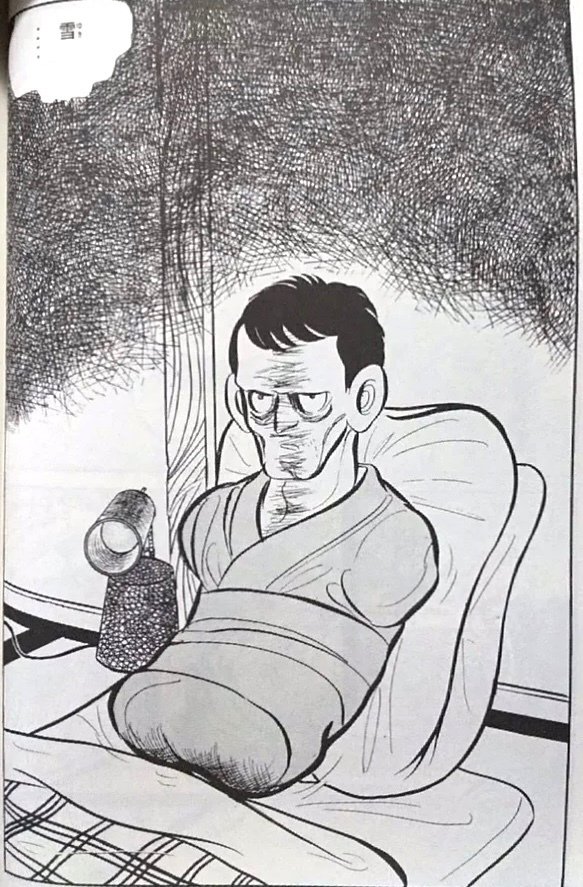
「洗脳」とは、自分では気づけないもの。だからこそ、私たちは「最悪の事態」を想定して、それに備えなければならない。一一まさに本作のように。あるいは「原発事故」のように。あるいは「敗戦」のように。
本作に対し、「予想が外れた」とか「古い」などと思う人は、自分が何から目をそらしており、それは、どのような「洗脳」によるものなのかと、そう自身に問うべきであろう。
そうした意味で、本作は今でも「日本人の試金石」たり得る作品なのである。
(2023年4月15日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
