
飛浩隆 『ポリフォニック・イリュージョン 飛浩隆 初期作品集』 : 〈見えているもの〉としての世界
書評:飛浩隆『ポリフォニック・イリュージョン 飛浩隆初期作品集』(河出文庫)
『 本書は、二〇一八年刊の『ポリフォニック・イリュージョン 初期作品+批評集成』の前半部分(小説と作者解題)に最近発表した小品を新たに加えて文庫化したものである。』(P225、「文庫版のためのノート」より)
親本を買っているはずなのだが、積読の山に埋もれさせてしまったため、正確なところはわからないのだが、たぶん親本から「評論」や「書評」の部分を削り、自身の「創作」に関するものだけに絞って文庫化した、ということなのであろう。
飛浩隆が、私好みの「メタ・フィクション的な性格の強い作品」を書く作家だと知って以降、その著作はすべて贖っているはずだが、私の場合は、昔はミステリの方を専門的に読んでいたので、SFは買ってはあるけれど読んでいない、というのが少なくない。
その後、ミステリ界における使命としての「笠井潔葬送」を果たしたせいか、急速にミステリから興味が薄れたのだが、ミステリの次には、宗教学や社会学などの方に興味が移って、やはりSFを読むことができなかった。読みたいという気持ちは常にあったのだけれども、小説というのは、いま読まなければならないというものでもないので、どうしても後回しにしてしまったのである。
ところが、そろそろ定年も近い年齢になって、人生における「片づけ」を考えるようになってきた。人生90年の時代に、少し気が早いだろうと言われそうだが、気分はすっかり「老後」なのである。
それで、これまで読みたいと思いながら、読み落としていた小説家を読み始めた。ここ数年は、日本近現代文学史的に「絶対読み落とせない純文学作家」で、しかも1冊も読んでいなかったような作家の代表作を、穴埋めでもするように読んだりしていたのだが、今年に入った頃から新旧のSF作品を読み始めた。
と言っても、飛浩隆の作品については、積読の山に埋もれさせて発掘できない初期作品を読んだわけではなく、近年の作品を刊行時に読んでいるだけである。しかも、寡作な作家だから、読んだのは『零號琴』『自生の夢』の2冊だけで、今回の『ポリフォニック・イリュージョン 飛浩隆初期作品集』が、やっと3冊目。この調子で(?)『象られた力』『グラン・ヴァカンス 廃園の天使I』『ラギッド・ガール 廃園の天使II』も(古本で再度贖って)読んでしまいたいところだが、さて、どうなることか…。
○ ○ ○
親本について、Amazonの方でレビュアー「amazou@karakuchi」氏が『初期作品には、後年の諸作に通じる要素が全て秘められていた』と題したレビューを書かれているが、全くそのとおりである。
そして、その上で、私が「メタ・フィクション」たる飛浩隆作品に感じ続けてきた「違和感」については、本書に収められた「著者による解題」により、その正体をほぼ了解することができた。
(1)『 後年の諸作に通じる要素はこの(※ 表題短編)「ポリフォニック・イリュージョン」が出発点となる。
手法に自覚的であること。一人称の多用。現実崩壊を見せ場として使うところや、五感を重視するところなどなど枚挙にいとまがない。
当時自分ではこの現実崩壊感覚はディックにつながるものと考えていたが、だんだんそうではないことが判明していくのであった。』(P193)
(2)『 (※ 短編「地球の裔」は)小さなスケッチみたいな小品だが、飛の根源的な作家的関心のありか、すなわち「もの」と「かたち」と「ちから」の相克、の萌芽が提示されている。』(P196)
(3)『これらの女性のイメージは作中で非常に不安定な形で受肉している。その不安定性の上に、先ほど書いた飛の根源的モチーフ、すなわち「もの」と「かたち」と「ちから」の相克が投影され、大きく揺れ動く。この揺動と作品のカタストロフを一致させるというのが、テーマ的にもストーリー構築的にも飛作品の基本構造なのである』(P201)
(4)『 これ(※ 短編「象られた力」)を書いていたころ高山宏の著作を何冊か読んでいて、そのうち『目の中の劇場』の影響が強烈に出ています。この本は十八世紀以降のヨーロッパ文化の中でいかに「ヴィジュアルな快楽の追求」がおこなわれたか、それが世界を表層としてコレクションする趣向に転じ「世界を収集」しようとする思考を生み出していったかをあぶり出していくものです』(P209)
(5)『 で何が言いたいかというと、こうした視覚面での革新を、文芸作品の文章はどこまで追っかけていけるかということなのです。このごろのエンタテインメント小説が長くなっているのは、あきらかに他メディアの情報量に対抗し、食感や満腹感を競おうという、進化圧(笑)の結果でしょう。しかし映像系エンタテインメントがどのように変化していくかを見つめ、ある程度予想し、それへの対抗措置を準備しておかなければ、小説はますます売れなくなるっていくだろうなと思うのですが……まぁ飛は別にそれでもかまわないけど。
どこまでやれるか、新作でも試みています。』(P224)
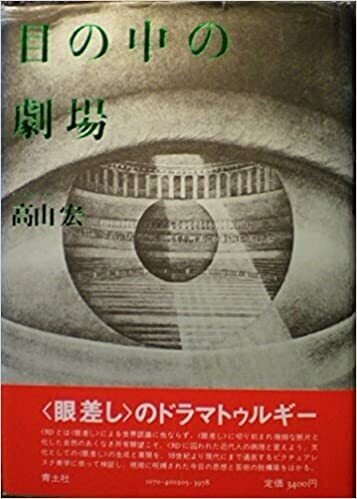
たしかに飛浩隆の作品は「メタ・フィクション」であり、私の大好きなパターンである。しかし、にもかかわらず、作品を読み終えた後、一抹の物足りなさとしての「何か違う」という感覚がつきまとったのだが、その正体が、ここで著者自身によって語られていた。そのキーワードは、「表層」である。
どういうことか。
「メタ・フィクション」作品というのは、一般に「入れ子構造」を持っており、小説の場合だと「枠物語」の形式を採る場合が多い。「作品世界という小世界」の中に、さらに「(「フェッセンデンの宇宙」のごとき)小世界」が存在するのだ。そして、しばしばそれは「作品の中の作品の中の作品の中の…」といった眩惑感をもたらす、ボルヘス的な「無限構造」を(本質的に)有している。
つまり、一般の小説作品のように「作者や読者がいる、この世界(現実)」と「小説内世界(虚構)」という非対称的で二分階層的関係ではなく、「メタ・フィクション」の場合は「小説内世界(虚構)」の中にさらに「世界内世界(虚構内虚構)」を設定ことによって、「虚構世界」が無限展開するだけではなく、翻って「小説内世界(虚構)」の外、つまり「作者や読者がいる、この世界(現実)」もまた、実は特権的な「外部」ではなく、さらに「外部」を持つ「世界内世界(小宇宙)」なのではないかという疑いを発生させて、私たちの現実感を揺るがすのである。
この「メタ・フィクション」における「自己相対化」は、きわめて「批評的」なものだと言えるだろう。「私の世界だけは疑いなく磐石である」と信じていたところに、「はたしてそうなのか?」という「疑い=懐疑」を発生させ、その「盲信」を検討に付すからである(世界信仰の自己検討)。
言い換えれば、「小説が小説では終わらない」ところが「メタ・フィクション」の面白さなのだ。
ところが、飛浩隆の「メタ・フィクション」には、こうした「リアル」な「現実崩壊感覚」が薄い。そこが、フィリップ・K・ディックのそれとは、違うところなのではないだろうか。
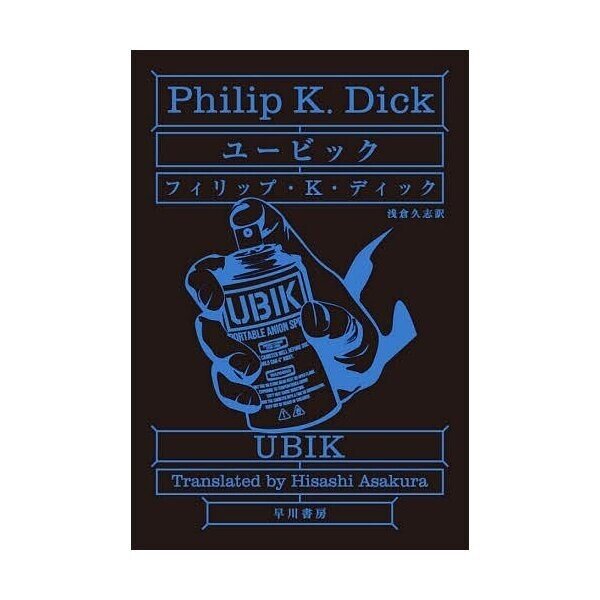
しかし、私はここで何も、飛浩隆に特有の「現実崩壊感覚」を否定的に評価したいのではない。そうではなく、その「質の違い」を指摘したいのだ。
どういうことかというと、一般に「メタ・フィクション」作品の対象とは、「世界」そのものである。ところが、飛浩隆の「メタ・フィクション」が描くのは、「世界」そのものではなく、「世界の表層」なのだ。ここが違う。
一般に「メタ・フィクション」作品では、「世界」は「世界」としての「奥行き」を持っている。ところが、飛浩隆の場合は、優れて「視覚的」であるために、「奥行き」は問題とされない。「奥行き」とされるものは、「視覚的」には、しばしば「(遠近法的な)錯覚」でしかないのだ。
無論、飛浩隆のこうした「視覚的表層主義」というのは「理念」的なものではなく、「嗜好」的なものだと思う。飛は、物事を「見えるとおり見る」人間であり、あまり「見えない意味を問う」タイプではないのだろう。だから、飛作品には「世界の多相性」が描かれても、「私たちの現実世界」の「特権性」を問うようなことはしない。
「世界」は見えているとおりのものであり、それ以上の「奥行き(意味)」というのは、実体的ではないと感じられているから、飛は「奥行き(意味)」を問うことに魅力を感じず、常に「見えているもの」の「表層」に魅せられ、それゆえに、その「崩壊」にも魅せられるのではないか。
こうした「嗜好」は、ハッキリって、私の趣味ではない。私は「奥行き(意味)」を問うことにこそ魅力を感じる人間であり、その意味では「現実崩壊感覚」そのものではなく、重要なのは「現実崩壊した後に立ち現れる、真の現実」という位相なのだ。
だから、その方向へは進まず、「現実崩壊」の中で宙吊りになることに、怯えと同じくらいに喜びを感じているらしい飛浩隆の「メタ・フィクション」作品に、私は、一抹の物足りなさと「何か違う」という感覚を持ち続けたのだと、やっと了解することができたのだった。
思えば、かつての私も、高山宏には惹かれた。『アリス狩り』に始まる高山宏の(装幀が美しい)初期著作は、ほとんど所蔵している。にもかかわらず、ほとんど読んでいないのは、いくつか読んだ文章において「何か違う」という物足りなさを感じたからであったと思うのだが、その正体が、今回、飛の文章によって明らかになった。
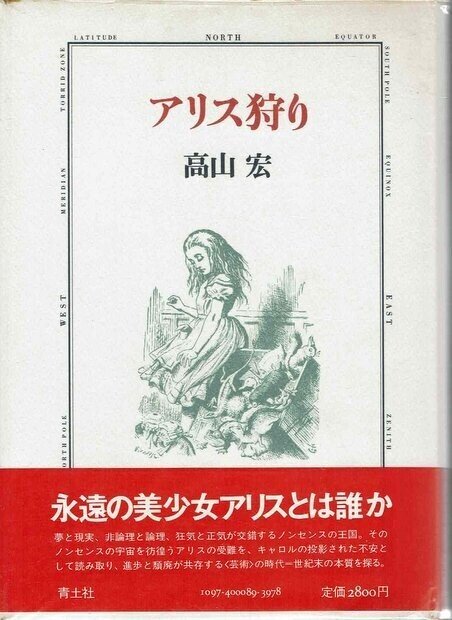
私も、高山と同じで「図象」が好きだし「収集=コレクション」も好きだ。したがって「世界をコレクションする」という観念には、とても惹かれるのだが、ただ、私の「コレクション」の仕方は、「視覚的」なものではなく、「観念的」なものであり、要は「理解」なのである。言うなればそれは、南方熊楠的な「一切智の夢」であり、そこでは「図象=表層」は、「窓」であって「世界」そのものではない。私が所有したいのは「窓の向こうの世界」なのだ。
この違いが、ディックを含む私のような(オーソドックスな)タイプと、飛浩隆や高山宏のような(表層執着的な)タイプ(たぶん、海野弘や荒俣宏などの博物趣味人たちもそうなのではないか。偶然にも、3人とも「ひろし」なのだが)を分けたのであろう。
とは言え、なぜ飛や高山が「表層」に執着するのか、「世界」をあえて「表層」としてとらえるのか。そのあたりが私には、まだよくわからない。
だから、今後、飛浩隆を読む場合に注目するのは、そうした「世界を表層として見る目」の由来である。飛浩隆はなぜ、世界の「奥行き(意味)」を見ようとしないのか。なぜ、「奥行き(意味)」に魅せられないのか。あるいは、それを信じないのか。
そのあたりの「独特な世界観」の「意味」を探りながら、私は飛浩隆を読み続けることになるのだろう。

---------------------------------------------------
【補記】
飛浩隆の言う『手法に自覚的である』というのは、すなわち飛は「マニエリスムの作家」だということなのだろう。
当然、連想させられるのは、高山宏もそうであった「澁澤龍彦サークル」のメンバーである種村季弘と矢川澄子の翻訳した、グスタフ・ルネ・ホッケの『迷宮としての世界 ――マニエリスム美術』(あるいは、種村季弘訳『文学におけるマニエリスム』)であろう。
飛は私の二つ上だが、こうしたところの同世代感が、なかなか半端ではない(笑)。
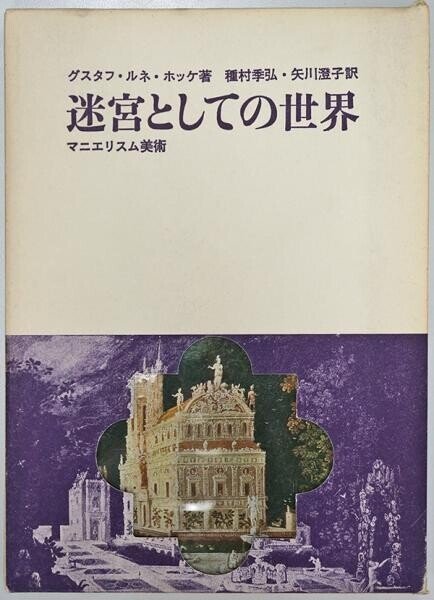
(2021年10月27日)
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
