
〈変格ミステリ〉は、ジャンルとして成立可能か? : 竹本健治編 『変格ミステリ傑作選 【戦前篇】』
書評:竹本健治編『変格ミステリ傑作選【戦前篇】』(行舟文庫)
「行舟文庫」という聞きなれないレーベルから刊行された、「変格ミステリ」というこれまた聞いたことがありそうでないようなミステリジャンルの傑作選である。
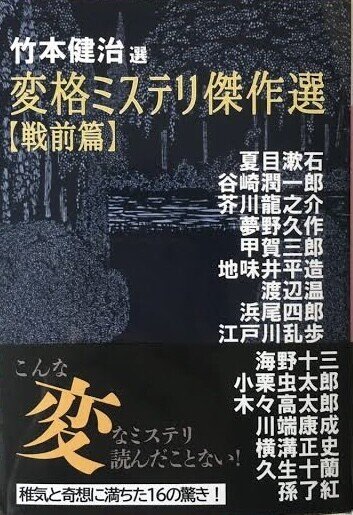
どうして、聞いたことがありそうでないのかというと、「変格」というのは従来「変格探偵小説」という言葉で使われてきたものであり、「変格ミステリ」とは、あまり言われなかったからで、これは「史的用語論」的な問題だと言えるだろう。だが、難しい話ではない。
○ ○ ○
しごく大雑把に言うと「事件が起こり、その謎を解いて、事件を解決する物語(大衆小説)」が、明治日本に輸入されて以降、そうした小説を古い順に「探偵小説」「推理小説」「ミステリー」「ミステリ」などと呼んできた。
そして、戦前の「探偵小説」は、大雑把に言えば、「事件が起こり、その謎を(論理的)解いて、事件を解決する物語」を「本格探偵小説」と呼び、この基本形から逸脱したものを、全部ひっくるめて「変格探偵小説」と呼んだ。
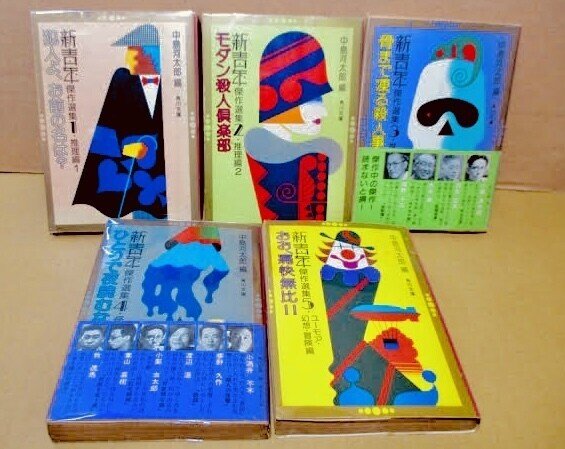
(※ 中島河太郎編 角川文庫版『新青年傑作選集』。1・2巻が「本格推理」、3・4巻が「怪奇」、5巻が「ユーモア・幻想・冒険」という構成)
つまり、「本格探偵小説」とは、今で言う「本格ミステリ」「謎解き小説」「パズラー」「謎解きミステリー」「本格ミステリー」などであり、一方「変格探偵小説」には「事件が起こり、その謎が解かれて、事件を解決する」けれども、謎の解き方が「論理的ではないもの」、例えば「直観」「超能力」「運」「なりゆき」で謎が解かれて事件が解決してしまうようなものや、事件と言っても、警察や名探偵が扱うようなものではなく、そうした人たちも登場しない、今で言う「SF」「怪獣もの」「ホラー」「冒険小説」「スパイもの」「ファンタジー」「奇妙な味の小説」などなどまでが、ぜんぶ「変格探偵小説」に含まれていた。
それが、戦後になってからは、「当用漢字」の問題で、「探偵小説」が「推理小説」と呼ばれるようになるのだが、「推理小説」というのは、その名のとおり「推理をする小説」なので、基本的には「本格探偵小説」を意識した名称であり、「変格探偵小説」は本来含まない。
そこで、便宜的に「本格探偵小説」と「変格探偵小説」をひっくるめて「ミステリー」と呼ばれるようになったのの、今度はそこから「SF」「怪獣もの」「ホラー」「ファンタジー」などが独立して行き、「冒険小説」や「スパイもの」は「ミステリー」の中に残ることになる。
しかし、「論理性」を重視し「知的読み物」を自負する「本格推理小説」と、「頭でっかち」ではない「冒険小説」や「スパイもの」とは、それぞれの作家同士、趣味的にあまり折り合い良くないし、世間的には「ミステリー」に「オカルト」や「超能力」や「UFO」や「ネス湖のネッシー」まで含まれてしまったので、「本格推理小説」側は「ミステリー」という締まりのない名称を嫌って「本格ミステリ」を使うようになる。

(※ フジテレビの番組タイトル・「ミステリ」ではない)
「ミステリー」も「ミステリ」も英語では同じだが、発音が原語に近いということで、マニア的に「ちょっと違うぜ」という感じで、「ミステリー」という「何でもあり」的な名称から、距離を置いたのである。
これは、本格ミステリ作家エラリー・クイーンについて、日本では、作家名は「エラリー・クイーン」と表記し、作中の同名探偵は「エラリィ・クイーン」と表記して区別するのと同じような、エリート趣味のマニアックさに発するものと見て、まず間違いないだろう。
「本格」側が「本格ミステリ」を名乗り、線引きを強化すると、当然、「冒険もの」や「スパイもの」の方も「冒険小説」「スパイ小説」を名乗るが、日本では作品の絶対数が少ないため、どうしても「推理小説」や「ミステリー」のサブジャンルという印象が否めなかった。
一時期、「冒険小説」がブームになった頃には「日本冒険小説協会」も出来て、ジャンルとして独立した感もあったが、このブームも過ぎて同協会も解散すると、やはり「推理小説」や「ミステリー」のサブジャンルという印象に逆戻りしてしまった感じである。
さらに、ここまでは言及してこなかった「私立探偵もの(あるいは、ハードボイルド)」や「警察小説」などは、そもそも主人公の「職業設定」による名称で、内容的には「本格推理もの」と「冒険もの」(後は「人情悲劇」など)の中間的なジャンルであり、作家の作風によって、どちら「寄り」にもなるので、やはり独立したジャンルにはならず、その時々に人気のある方のサブジャンルに位置付けられることが多いようだ。
「本格推理もの」は、「冒険小説ブーム」の後に巻き起こった「新本格ミステリブーム」によって、「本格ミステリ」という名称を、ほぼ確立したと言って良いだろう。永遠にこの名称が使われる保証はないが、あと20年や30年は使われるだろうと考えられる。
○ ○ ○
さて、ここで問題となるのが、「本格ミステリ」に対応するものとして、今回竹本健治が提唱した「変格ミステリ」という名称である。
完全にオリジナルな言葉とは言えないが、これまでこの言葉を、一定のジャンル名称として自覚的に提唱した者はいないはずだ。

竹本健治は、本書の「あとがき」で、この「変格ミステリ」という呼称を、自身の個性と絡めて次のように説明している。
『 そもそもの発端はツイッター上で「変格ミステリー作家クラブ」なるものを立ちあげたことだった。
一九八七年に起こった「新本格」ムーブメントからこちら、わが国は世界的にも稀有な本格ミステリの降盛期を迎え、ミレニアムの二〇〇〇年には本格ミステリ作家クラブも設立されて、現在はまさに百花繚乱の爛熟期といえるだろうか。その影響が折り返し、西欧へ逆輸出されようというまでの状況だ。
そんななかで僕はというと、作家デビュー以来四十余年、ミステリを中心に創作を続けてきたものの、常にミステリのメインストリームから大きくはずれたところを歩いてきたと自己評価しているし、多分客観的にもそうだろう。あえて区分けするなら、僕は変格作家という呼称がいちばん似合っているんじゃないか。そんな想いがずっと頭の片隅から離れなかったし、近年ますますふくれあがるばかりだった。
そうしたところに、倉野憲比古さんが一人でも変格探偵作家クラブを名乗ろうかとツイートしているのを見つけ、すかさず、では二人で立ちあげませんか、ついては本格のほうに名称も揃えて、「変格ミステリ作家クラブ」でどうでしょうと提案し、晴れて発足したのが二〇二〇年の八月十三日(なお、このユニットに会長は存在せず、僕は単なる世話係に過ぎない)。以降、ぽつぽつとまわりにお誘いをかけたり、自主的な参加希望もあったりで、あれよあれよとメンバー数がふくれあがり、一年足らずの二〇二一年七月二十二日現在で百八十名に達したのは、必ずしも会費が無料でノルマがゼロ、変なものが好きな物書きさんなら資格ありという極限に近い敷居の低さばかりでなく、そもそも「変格」という響きに仄かな郷愁やシンパシーを感じていた物書きが少なくなかったことにことを示しているのではないだろうか。』(P693〜694)
『 考証的にはどうあれ、今この現在、僕は「変格」にあまり厳密な定義は必要ないと思っている。ユニットの名称に「変格探偵小説」ではなく「変格ミステリ」を使ったのもその意味あいをこめてだった。
「何だかとても変テコなミステリ」
「ミステリのふりをした異形のもの」
「こんなミステリを書くの、変態だな」
そんな主観的な判定でおおむね間違いないだろう。そしてこれだけ「本格」が隆盛を誇っている今だからこそ、「変格」にもますます新たな存在意義が高まっているのではないだろうか。まして、「本格」をぎりぎり突き詰め、濃縮していくと、「変格」としかいえない領域に踏みこんでいくというベクトルもあることだし。
一一少なくとも僕にはそう思えてならないのだ。』(P696〜697)
竹本健治がここで言わんとしていることは、とてもよくわかる。要は、戦前の「変格探偵小説」のように「型にとらわれない、ヘンテコな小説」が、もっとあって良いはずだ、ということだろう。まったく賛成である。
ただし、それが倉野が最初に考えていた、戦前と同じ「変格探偵小説」ではなく、「本格ミステリ」に揃え、あえて「変格ミステリ」としたのは、これからもっともっと書かれてしかるべき「型にとらわれない、ヘンテコな小説」が、戦前の「変格探偵小説」への懐古趣味や模倣に終わってはつまらない、と考えたからではないだろうか。
つまり、竹本も含め、多くのミステリファンが「もちろん本格ミステリも面白いけど、昔の変格探偵小説みたいなものも読みたいなあ」と思ってはいるものの、しかし、現実に「新作」として書かれるからには「戦前の変格探偵小説のパスティーシュ(やパロディー)」に終わってしまっては、ジャンルとして成立したとは到底言えない。そこで、なんとか戦前の「変格探偵小説」の味わいを残しつつ、しかし「現代の新作小説」として書かれねばと考えたため、現代風に「変格ミステリ」としたのではないか。一一そうであるなら、私はこの考え方にも、まったく賛成である。
しかし、問題は「戦前の変格探偵小説のような、しかし現代小説」を、「新たな文芸ジャンル」を形成するほど(の量)書くことは、果たして可能なのか、という問題である。
というのも、戦前と現在では、「変格」のおかれた状況が、決定的に違っているからである。
先に長々と「名称変遷史」で説明したとおり、戦前の「変格探偵小説」は、言うなれば「本格以外の新娯楽小説」と呼んでも良いほどの「ゆるい縛り」しか持たない「融通無碍な文芸ジャンル」だった(※「新娯楽小説」としたのは、江戸時代からある古い娯楽読み物の末裔である「時代小説」「歴史小説」「人情小説」といったものは、「探偵小説」に含まれないからだ)。
ところが、現代においては、この「変格探偵小説」から、「SF」「怪獣もの」「ホラー」「冒険小説」「スパイもの」「ファンタジー」「奇妙な味の小説」などなどが、実質的に独立しており、それらは今や、ほぼ全ての読者に「変格もの」とは思われていない。
つまり、戦前では「変格探偵小説」に分類されたものが、現代では「SF」「怪獣もの」「ホラー」「冒険小説」「スパイもの」「ファンタジー」あるいは、ジャンル越境的な新ジャンルとしての「ラノベ」と認知されてしまい、結果として「現代小説としての変格ミステリ」というのは、実質的には、ほとんど成立の余地が残されていないのではないか、ということだ。

(※ 涼宮ハルヒシリーズの、ミステリ色が強い番外編作品集)
もちろん、竹本健治のように「ジャンル越境的な作風の作家」の書く「ジャンル越境的な小説」を、「変格ミステリ」と呼ぶことはできるだろう。しかし、そうした「生来の個性」ではなく、「いろんなものを書く(書ける)」作家が、意識的に「変格ミステリ」小説を書いた場合、それは果たして世間から「変格ミステリ」として認知されるのだろうか。
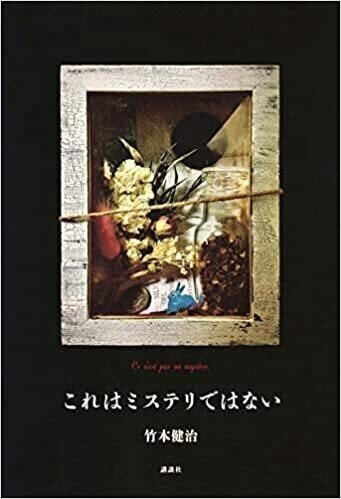
(※ 竹本作品の中でも屈指の「変格ミステリ」)
もちろん、自ら「これは、SFでもホラーでもなく、変格ミステリです」と宣言して、その名称を読者に強いることは可能だろう。
しかし、そのようにして、言わば、すでに他ジャンルの一部として取り込まれ認知されているものを、半ば強引に「変格ミステリ」と呼ぶようなやり方には、やはり無理があるのではないだろうか。
実際、竹本健治が「変格ミステリ」と考えるような作品は、現在「SF」や「ホラー」の中にこそ、見いだすことができる。それくらい、「SF」や「ホラー」は、幅のあるジャンル概念となっており、それで何の不都合もなく流通しているのである。
(※ 竹本が「変格ミステリ」と呼ぶ作品の多くは、現在、井上雅彦編の書き下ろし短編アンソロジー「異形コレクション」に寄せられているようなものなのであろうが、「異形コレクション」というのは、ジャンル名ではなく、いわば、メタ・ジャンル名称だから、無理なく通用していると言えよう。また、だからこそ、この「異形コレクション」シリーズに寄せられた作品は、のちに作家別の個人短編集としてまとめられる際には、SF短編集、ホラー短編集、幻想小説集、などというジャンル名称が添えられ、それぞれのレーベルから刊行されることにもなる)
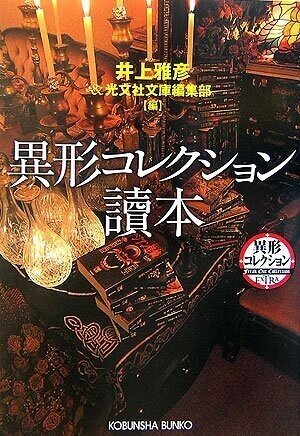
たぶん、竹本の場合にも、「変格ミステリ作家クラブ」に集った作家たちの頭にも、「変格ミステリ」とは実質的に「戦前の変格探偵小説」がイメージされているのであろう。
もちろん、イメージするだけなら、何も不都合はないのだが、それを「現代小説」の「新作」として書くとなると、否応なくそれは「戦前の変格探偵小説」から離れざるを得ず、かと言って、すでに「SF」や「ホラー」のうちに含まれている小説を書いて、無理やり「変格ミステリ」を名乗るというのも、やはり無理があるのではないだろうか。
「変格ミステリ」という名称の提唱者である竹本健治としては「形式に縛られない自由」ということに重点をおいたはずなのだが、しかし、竹本のようにもともと「変格」作家である人以外には、「SF」や「ホラー」に分類されることなく、自分たちの提唱する名称を、読者に押し付けることもせず、自然に「変格ミステリ」と認知してもらえるような作品を書くのは、至難の業なのではないかと、私にはそう思えてならない。
そして、そうだとすれば、今の日本において「変格ミステリ」というジャンルを成立させるというのは、ほとんど不可能なように思えるのだが、さていかがであろうか。
------------------------------------------------------------------
【補記】 現代にも通じる「天一坊殺し」の問題
上の本文では、当アンソロジー収録作品について、具体的に触れることはしなかったので、ここで補足的に触れておきた。
私は、「変格探偵小説」が好きなミステリマニアの一人として、
・「日本探偵小説全集」(東京創元社)
・「新青年傑作選集」(中島河太郎編)
・「怪奇探偵小説集 幻の傑作ミステリー」(鮎川哲也編)
・「大ロマンの復活」シリーズ(桃源社)
・「異色作家傑作選」(現代教養文庫)
などを読んでいるので、当アンソロジー収録作品のすべてを読んでいるわけではないにしろ、特に目新しく感じる作品はなかった。

ただ、再読して、特に感心したのは、私の「幻想」好みとはまた別の好みである「批評性」のある作品で、例えば、夏目漱石の「趣味の遺伝」は、「遺伝」の非理性的ロマンティシズムよりも、漱石の世間を突き放して見る、周囲に流されない目の方に、再読か三読ながら、あらためて共感した。
しかしながら、一番感心した作品は、再読となる浜尾四郎の「殺された天一坊」で、そこに描き出された大岡越前の人間的変貌ぶりが、「組織の論理」や「公の論理」に取り込まれていく人間心理をリアルに描いて、実に見事であり感心させられた。
そしてさらに言えば、これは「変格ミステリ作家クラブ」といった「括り」を作ってしまった人たちにも付きまとう問題であろう。自分一人なら望まなかったことまで、「みんなのため」に望んでしまい、それまでの自制が失われて、「身内」以外の他者に犠牲を強いてしまうというようなことは、今もそちこちで起こっていることだからだ。
平たく言えば、読者を置き去りにした「身内褒め」がその典型的なものだが、この誘惑に抗って、一個の作家的倫理を守ることの困難性を、「組織人」は十分に自覚しなければならない。
(2021年11月25日)
○ ○ ○
○ ○ ○
