
藤田直哉をめぐる〈トゥルース〉 : 藤田直哉 『娯楽としての炎上 ポスト・トゥルースの時代のミステリ』
書評:藤田直哉『娯楽としての炎上 ポスト・トゥルースの時代のミステリ』(南雲堂)
ここまで酷いとは思わなかった。2018年刊行の本だが、私が今年(2020年)読んだ200冊弱の本の中では、最低である。こんな本を読むのは、まったくの時間の無駄で、途中で何度投げ出そうかと思ったことか。
しかし、それでも我慢して最後まで読んだのは、本書自体に興味があったからではなく、本書を「笠井潔がどう読むのか」に興味があったからに他ならない。
藤田直哉の著作は、初めて読んだ。雑誌などで短文を読んだり、ツイートを目にしたりしたことくらいはあると思うが、それも何年も前の話だから、ほとんど印象に残ってはいない。だから、今頃になって藤田の本を読んだのも、ひとえに「笠井潔の新刊を読むため」であった。
先ごろ、笠井潔が、ひさしぶりに評論書を刊行した。作家デビュー以来、それなりにコンスタントに(ミステリ、純文学、社会などをテーマとして)評論書を刊行してきた笠井だが、『容疑者X』論争(2005〜2006年)で、実質的に総スカンを食らい、少数の子分を引き連れてミステリ界を去って以降は、徐々に評論書が出なくなった。近年では、出しても、人気のある著述家などとの対談本で、半ば以上は、相方の人気に依存して刊行し得たような本であったと言えよう。

もともと評論書というのは、商業出版としては厳しいジャンルなので、業界的な人脈があってこそ刊行できるという部分が大きいため、当時はまだメジャージャンルであったミステリ(推理小説)の業界から離れるということは、プロの著述家としては、かなり痛手であり、不利な選択だったと言えよう。
実際、笠井潔は小説家でもあり、雑誌連載を終えていた長編ミステリ作品がいくつもあったのに、その多くが今でも単行本になっておらず、完全な塩漬けになっているのも、ミステリ業界との関係悪化が、ミステリ本を刊行している版元との関係を弱めてしまったからであろう。もはや「義理」だけで、さほど売れないであろう小説を単行本化するほど、出版社も楽ではないのである。
ともあれ、そんな笠井潔がひさしぶりに単著の評論書を刊行した。それが『限界状態の道化師 一一ポスト3・11文化論』(南雲堂・2020/11/13)である。
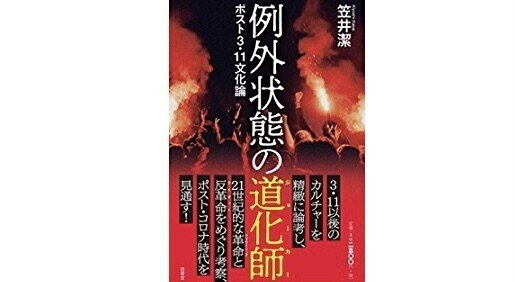
かつて「笠井潔葬送派」を名乗っていた私としては、笠井の死後出版とも呼ぶべき同書の刊行は、言葉は悪いが「舌なめずり」をする思いであった。だから、同書に収録されている9本の書評の対象となった本について、いずれも未読だった私は、それらを読み、私なりの評価をAmazonレビューとしてアップしておいてから、おもむろに笠井の評価を読んで検討しようと考えたのである。こんな手間のかかることをするのは、いまどき笠井の読者でも、私だけだという自負を持っているが、さていかがであろう。
一一ともあれ、この9冊のうちの1冊が、本書『娯楽としての炎上 ポスト・トゥルースの時代のミステリ』であったのだ。
本書の酷さについては、先行のレビュアーである「Amazonのお客様」氏が『数多くの作品が取り上げられているので、作品リストとしては有用だと思いますが、評論としては、読者に新たな視点を与えてくれるものではありませんでした。』等と評価しているとおりなので、屋上屋根を架すような贅言を連ねるつもりはない。
私の興味は、笠井潔にあるのであって、その子分である藤田直哉にはない。「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」という了見もない。「見下している」部分はあるにしてもだ。
そもそも、私が笠井潔を厳しく批判するようになったのは、私が笠井の熱心なファンだったからに他ならず、それほど笠井を高く評価していたし、その力量については今も高く評価しているからなのだ。
その点「高校生の作文か」と言いたくなるような藤田直哉とは、笠井潔は「格」が違うし、その意味で、藤田の方は論じるにも値しない存在なのである。
ちなみに、私が厳しく指弾した「笠井潔の問題点」とは、昔、柄谷行人との対談で、笠井が「(全共闘セクトの理論家だった時代に、仲間の前で)理屈なら、どうとでもつけられると言ったので、仲間から顰蹙を買った」と自慢げに語っていたことにも明らかなとおり、その「有能かつ不誠実な、三百代言」性にあった。

したがって、著述家として拙い(笠井のような「悪しき有能さ」を持たない)藤田は、「笠井潔の子分」という以外には、語るにも値しないのである。
そこで、藤田直哉について簡単に紹介しておくと、彼は『2008年2月、スティーヴン・キング『ダーク・タワー』を論じた「消失点、暗黒の塔――『暗黒の塔』第5部、6部、7部を検討する」で第3回日本SF評論賞選考委員特別賞を受賞しデビュー。』(Wikipedia)した後、『2008年3月から2009年8月にかけて行われた、『東浩紀のゼロアカ道場』に参加。』(前同)し、そこを離れた後は、笠井潔が実質的なリーダーである「限界小説研究会(現・限界研)」に参加して、評論活動を続けている評論家だ。

つまり、「有力な評論家」の傘下に入って、その庇護の下に評論活動をしている人物であり、おのずとその論調も「党派性」を帯びている。簡単に言えば、笠井潔と問題意識を共有するだけではなく、笠井やその周辺の評論家を褒めるばかりで、決して批判はすることはない、提灯持ち評論家なのだ。
さらにわかりやすい話をすれば、本書は藤田直哉の著作としては4冊目で、それまでの3冊のうち、最初の2冊は「作品社」から刊行されているが、この出版社は、まだ無名に等しかった笠井潔が評論書デビュー作である『テロルの現象学』を刊行し、その後も初期の評論書を刊行してくれた、奇特な出版社である。
要は、笠井は、作品社に「全共闘時代のコネ」があったということであり、藤田は、その笠井にコネでデビュー評論書を刊行できた評論家なのである。
ちなみに、本書を刊行している「南雲堂」も、笠井潔のコネである。
南雲堂は、もともと教科書出版の会社だったのだが、「新本格ミステリ」ブームの際に、若社長が島田荘司のファンだったことから、島田本を刊行し始め、その縁で、当時、島田に近かった二階堂黎人と繋がり、二階堂黎人とスキー仲間でもあった笠井潔が繋がった(のちに、二階堂と笠井は『容疑者X』否定派として、当初は共闘する)。さらには、翻訳ミステリ叢書の刊行企画で二階堂黎人と繋がりのあった「原書房」が、実質的に笠井潔が組織した「探偵小説研究会」が編者となる「年間ベストミステリ本」の『本格ミステリ・ベスト10』(つまり『このミステリーがすごい!』の後追いムック)の版元となった出版社だ。
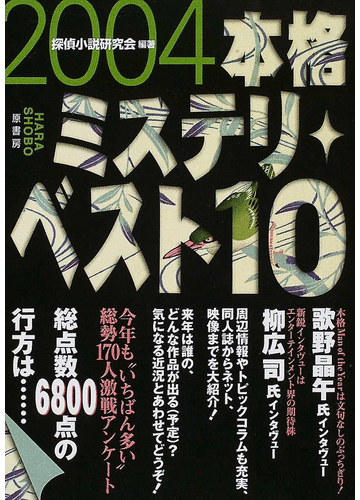
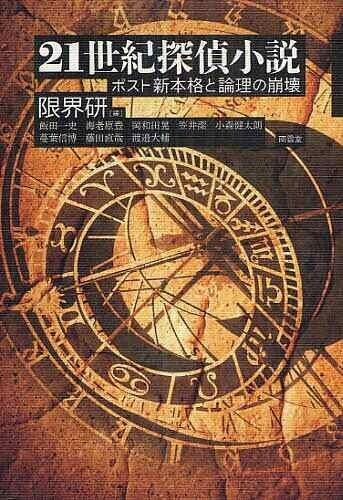
その後、前述した『容疑者X』論争で、笠井潔と「探偵小説研究会」の多くのメンバーが対立し、笠井と小森健太朗などの数名が同研究会を割って出て、その後に笠井が新たに組織したのが、藤田直哉の参加した「限界小説研究会」というわけである。
「探偵小説研究会」と「限界小説研究会」。この名称の相似性は、決して偶然ではなく、端的に「笠井潔の趣味」だったのだ。
これが、評論業界の、ひとつの現実である。
評論書などというものは、もともと部数の捌けるものではないから、特別な力量の持ち主でもないかぎり、人気があるか(業界的に)力のある作家や出版社にコネでもないかぎり、そう簡単に刊行できるものではない。したがって、藤田直哉が本書を刊行できたのも、ひとえに彼が「笠井潔の子分」であったからに他ならないのだ。
まあ、物書きになりたいという若者が、人気評論家の下に馳せ参じて、実質的な「弟子入り」をし、仕事をもらったり便宜をはかってもらったりするというのも、「著述業界の伝統的現実」としては避けられないものなのかもしれないが、そんな自分自身の現実から目をそむけておいて、世間が「現実を見ていない」などとご高説を垂れるのだから、もはや「何をか言わんや」なのである。
本書著者の「ミステリは、時代を見通していた、特別なジャンルである」などという寝言も、こうした「業界的な背景」のあることを知れば、多くの人に「なるほどね」と了解してもらえるものと確信する。
残念ながら、これが藤田直哉をめぐる「トゥルース」なのである。

初出:2020年12月29日「Amazonレビュー」
(2021年10月15日、管理者により削除)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
