
平山瑞穂 『エンタメ小説家の失敗学 ~「売れなければ終わり」の 修羅の道』 : 業としての美意識
書評:平山瑞穂『エンタメ小説家の失敗学 ~「売れなければ終わり」の修羅の道』(光文社新書)
平山瑞穂は、私の「偏愛する小説家」だ。
彼の魅力は、私の好きな「現実から異世界への遷移」を、リアルに描写できる点にある。
無論、お話として「異世界転移もの」というのは、掃いて捨てるほど存在するが、私が言いたいのは、「その遷移をリアルに描写できる」ということであって、「俺はその時、思いもよらないヘンテコな世界に落ち込んでいた。」などと、説明的に「書く」ことではない。
まず、この「リアルな世界」を描くだけの「筆力」があり、そこから「異世界」へ遷移する際の「世界変容」をリアルに描写できるだけの「筆力と文体」が無ければ、「状況を説明した」だけのものなど、「文学」と呼ぶに値しない(「お話」とでも呼んでおくべき程度のものだ)からである。
そして、平山瑞穂という作家は、それが書ける、まことに「稀有な作家」なのだが、しかし、残念なことに、そうした彼の力量は、「駄菓子のごときエンタメ小説」しか口に合わない「イマドキの読者大衆」の、よく玩味しうるところではない。
ドストエススキー作品を「面白くない」「退屈」「冗漫」あるいは「共感できない」「理解不能」「不愉快」などと宣った挙句、「失敗作」「駄作」などと言いかねないのが、甘やかされて、自身の「無能力」を反省することも知らなくなった(「反省」の意味も知らない)「イマドキの読者大衆」なのである。
(もっとも、彼らは、本物の自信を持たない臆病者でもあるから、押しも押されもせぬ大家の作品だと知っていれば、理解できなくても「すごい!」だの「さすが!」だのと、無内容な賛辞を口にして恥じない、無節操な手合いなのではあるが)
平山瑞穂は、その力量に反して「不遇な作家」だ。
喩えて言うなら、主君に恵まれなかった孔子みたいなもの、かもしれない。
だから私は、いちファンとして可能なかぎり、平山の新刊を購読するようにしている。
無論、焼け石に水なのは重々承知しているが、これも「お布施」の一種だし、こうしてレビューを書くのも同様のことなのだ。
しかしながら、平山瑞穂の作品ならぜんぶ面白いのかというと、決してそうではない。
数少ない「平山瑞穂ファン」の多くが高く評価する、デビュー作で日本ファンタジー大賞受賞作である『ラス・マンチャス通信』の「変」さを、私は楽しむことができなかった(私が一番好きなのは、短編集『全世界のデボラ』で、中でも「十月二十一日の海」は奇跡的な傑作)。

だが、その作家が「個性的」であればあるほど、作家の全作品が「好き」だなどということはあり得ない話なので、私自身は、『ラス・マンチェス街道』の魅力がわからないことを恥じてはいない。
言うまでもなく、私も「万能ではない」のだから、個性的な作家の作品の中に、わからないものもあるというのは、むしろ当然。見栄でわかったふりをするような、そこいらの「三流の読者」とは、訳が違うのだ。
さて、本書である。
本書は、言うなれば、平山瑞穂版『しくじり先生』(テレビ番組)とでも言えよう。
自身が、プロの作家として、どのような「しくじり」をしたために、作家的成功をみすみす逃してきたのか、それを検証しつつ、「後進のために」語った本である。
同種のものとして、私はすでに、ラノベ作家・吉田親司の『作家で億は稼げません』を読んでいるし、そこまで「小説家のおかれた厳しい現状」に興味があるわけではないから、本書が平山瑞穂の著作でなければ、購読することはなかったろう。
さらに言えば、本書の8割がたは、版元である光文社のウェブサイトでの連載時に読んでいるので、本書は、実質的には再読に近かった。実のところ、それを読んでいたからこそ、前記の吉田書にも興味を持った、という順序だったのだ。
そんなわけで、本書の具体的な内容は、目次を見るだけで、わかる(人には大筋でわかるし、わからない人には本書を読んでもらうしかない)のだが、ひとまず、本書カバー袖の「紹介文」と「目次」を紹介しておくことにする。
『いつの時代もあとを絶たない小説家志望者。実際にデビューまで至る才人のなかでも、「食っていける」のはごく一握りだ。とりわけエンタメ文芸の道は険しい。ひとたび「売れない」との烙印を捺されたら最後、もう筆を執ることすら許されない――。
そんな修羅の世界に足を踏み入れてしまった作家は、どのような道を辿るのか。華々しいデビュー、相次ぐ映画化オファー、10万部超えのスマッシュヒット――。栄光の日々すら塗りつぶす数々の失敗談と、文芸出版の闇、商業出版の崖っぷちから届けられた、あまりにも赤裸々な告白の書がここに。「書く」前に「読む」べし。』
『第1章 入り口をまちがえてはならない
第2章 巧を焦ってはならない
第3章 作品の設計を怠ってはならない
第4章 編集者に過度に迎合してはならない
第5章 「編集者受け」を盲信してはならない
第6章 オチのない物語にしてはならない
第7章 〝共感〟というクセモノを侮ってはならない 』
著者が、こうした「教訓」を学ぶに至った経緯を、具体的な「失敗談」を交えながら紹介したのだが、本書である。以上。

一一というわけにはいかない。
私がここから記すのは、「Amazonカスタマーレビュー」でも読めるような、「内容紹介」や「感想文」の類いではなく、本書のような著作からですら読み取ることのできた、平山瑞穂の「稀有な個性」であり、私がそれに惹かれた理由、といったことになろう。
ここからは、一種の「作家論」であり「芸術家論」であり、「人間論」である。
○ ○ ○
まずは、私が平山瑞穂に惹かれた、その「個性」を端的に示す部分を、本書から紹介しておこう。
第7著作『桃の向こう』について、書かれている部分である(※ 途中に入る「見出し文」は省略)。
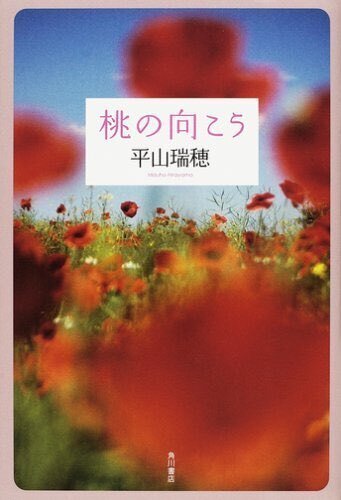
『 それを通じて僕は、何を描きたかったのか一一それは、煌子の思い出を栗栖に語る多々良が放つ、以下の台詞に集約されている。
「なんというか、彼女はどこか、遠くへ行ってしまったんだって気がする。こちら側ではない、〝向こう側〟のどこかへ。俺たちが手を伸ばしても決して届かない、〝向こう側〟へ」
(※ 中略)
「桃の向こう」とは、手が届かず、関与することもできない彼岸のような場所・立場を暗示している。「向こう側」に行ってしまった煌子は、もはや関わることの許されない存在なのであり、そういう存在について、なにかをより詳しく知ることはできない。煌子がそういう不可視の、そして不可触の存在になってしまったということ自体が、本作のテーマのひとつでもあるのだ。それでいてどうして、(※ 読者の求めがあったとしても)これ以上彼女についてくだくだしく語ることができるだろうか。
もちろん、僕はこの物語の作者として、いわゆる「神の視点」を持ちうる位置にいるわけだから、煌子がなぜ、いかにしてそのような状態になったのか、あえて説明しようと思えばできなくはない。しかしもしそれをすれば、僕が醸成しようとしてきた煌子の「彼岸性」一一どうなってしまったのかを具体的に知りようがないという不可知性は台なしになってしまう。それでは、興ざめもいいところではないか。
僕はおおよそそのような信念(「美学」と言い換えてもいい)のもとに、この作品をこのような形に仕上げ、自分としてはそれで何ひとつ疑問を抱いていなかったのだが、おおかたの一般読者の反応は、僕自身の狙いとは乖離したところにあった。
「煌子は結局、どうなったのか」「煌子のその後が気になる」「結局、何が言いたいのか」一一ネット上には、そうした感想が目立った。「そうした感想がメインだった」と言ったほうが正確かもしれないほどだ。
「こうであった」という確定的事実を明示するよりも、「こうだったかもしれない」「ああだったかもしれない」という想像の余地を残すほうが、物語として美しく、表現としても適切だと思えることが、僕にはしばしばある。物語には、一意的には定められない多義性が必要だと思うからだ。しかしそういう流儀は、(※ 純文学の読者には通用しても)エンタメ文芸の一般読者には通用しないことが多い。』(P195〜197)
引用していて、本当にうんざりさせられてしまう。もちろん、『一般読者』のレベルの低さにだ。
ここで平山が書いているのと同じことを、私自身、これまで何度書いてきたことか。
例えば、『ドグラ・マグラ』『黒死館殺人事件』『虚無への供物』、いわゆる「三大奇書」に続く「第四の奇書」と呼ばれることさえある、竹本健治の歴史的名作ミステリ『匣の中の失楽』をつかまえて、「結末がついていない」「これはミステリではない」「なにが描きたかったのかわからない」とかいった感想を口にした、レベルの低い読者が、ミステリマニアの中でさえ、どれだけいたことであろう。
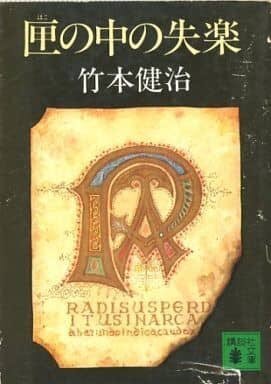
例えば、私が、今は亡き「創元推理ファンクラブ」に所属していた頃、会報を担当していた編集者が、会報に「『匣の中の失楽』は、すごいすごいと言われているけれど、みんな、本当にわかって言っているのだろうか? みんながそう言ってるから、迎合しているだけではないのか? 自分には、何が良いのか、ちっともわからなかった」という趣旨のことを書いていたので、私は早速「あなたがわからないからといって、他の人もわからないだろうなんて考えるのは、あなたの思い上がりだ」と、手厳しく批判してやったこともある。
ミステリを得意とする東京創元社の編集者になったくらいだから、たぶん彼は、ミステリには詳しいという自負を持つ「ミステリマニア上がり」の編集者だったのではないか。「その自分がわからないんだから、他のやつにわかるわけがない」と思い、つい、そんな本音を漏らしてしまったのだろうが、その頃すでに「鬼の論争家」として鳴らしていた私は、きっちりと噛みついて、身の程を知らせてやったのである。
ま、それはともかく、イマドキの読者というのは、「ぜんぶ説明してもらわないとダメ」という、オムツが必要な幼児のごときオツムの持ち主が大半で、そのために文学のレベルがどんどん下がっているというのは、間違いのない事実だ。歯ごたえのある作品など、書いても刊行できないのだから当然の結果である。
書評家の豊崎由美が「TikTokerけんご」の薄っぺらい「小説紹介」に噛みついた結果、「それ(※ TikTokによる、中身の薄い紹介)で本が売れるのなら、別に何でもいいじゃないか」という業界的な俗情に押されて袋叩き状態になっていた時、私が、横合いから割り込んでいって、全部ひっくるめて殴り倒すようなことを書いたのも、同じ理由だ。
とにかく、今の読者はレベルが低すぎるのだが、出版業界は、その「レベルの低い読者大衆」に媚びることしかできなくなっており、書評ライターなどは、完全に「太鼓持ち」を生業とするに至っているし、自分の価値観で作品を論じる「批評家」と呼べるような人は、完全に淘汰されてしまった。
そんな業界事情だからこそ、もともと「純文学」志向だった平山瑞穂のような「書ける=書かないではいられない=ぜんぶ説明するような野暮ができない」作家は、おのずと「理解されない」ことにもなる。
だが、私の場合はむしろ、平山のそうした「説明するのではなく、感じさせる(感性に訴える)」小説の「文学性」にこそ惹かれたのであり、中でも、ここで語られているような、平山の描く『こちら側ではない、〝向こう側〟のどこかへ。俺たちが手を伸ばしても決して届かない、向こう側〟』への「憧憬」とでも呼ぶべきものにこそ、惹かれた。
そんなものに、こだわる作家など、滅多にいないからこそ、平山瑞穂は、私のとって、またと得がたい「偏愛作家」となったのだ。
一一ところが、世間は、そんな平山の美質を理解できず、忌々しいことに、彼の美質を抑圧するばかりである。
『 読者としての僕が、小説に求めているもの、小説を読む際に重きを置いているものは何か。その問いに、ひとことで答えるのはむずかしい。
心にズシリと響いてくるものがあるかどうか。物語として、僕にとって美しいと思えるたたずまいを備えているかどうか。テーマとその描き方に、説得力があるかどうか。一読しただけで、忘れがたい印象残す場面になり叙述なりがあるかどうか。登場人物が、体温の感じられるリアルな造形によって描かれているかどうか。世界のよい面と悪い面の両方に、公平に目配りしたものになっているかどうか一一。
読む作品のタイプにもよりけりなので、一概には言えない。もちろん「その気持ち、わかる、わかる!」と共感できる部分があるかどうかを問う場合もある。しかし「共感できるかどうか」は、実のところ、僕にとってそれほど重要なファクターではない。たとえ登場人物の誰にも共感できなかったとしても、その他の面で十分な説得力なり美点なりのある物語であれば、「読み応えがあっておもしろかった」と満足するケースも往々にしてある。
そして、小説に対する僕のこうした嗜好は、そっくりそのまま、小説家としての自分の姿勢につながってくる。僕は何よりも、自分の読みたい小説、自分が読んで満足できる小説を書きたいという思いのもとに、自分の作品を執筆してきたのだ。能力がそこに及ばなかったり、その他の外因的事情(多くは、版元からの要望など)によって思いを果たせなかったりすることも多々あるが、僕が自分の小説を書く際に、先に列挙したような要件を可能なかぎり多く満たすものを書こうと常に心がけていることはまちがいない。
逆にいえば、読者として「共感」を重要視していない僕は、小説の書き手としても、そこにあまり比重を置いていない。そもそも、読者から共感を得ようなどとはこれっぽっちも思っていない場合さえある。そのとき僕が目指しているのは、なにかそれとはまったく別のことなのだ。
ところが、どうやら一般読者の大半は、最初から「わかる、わかる!」という共感を求めて小説を手に取っているようなのだ。そして、作中で共感できるポイントを見出せなかった場合、その作品は「共感できなかった」のひとことで切り捨ててしまう。彼らにとって「共感できない」とは、「つまらない」と同義なのだ。
驚くべきことかもしれないが、プロの小説家になってからもなおしばらくは、僕はそのことに気づいていなかった。たぶん、それまでに僕が発表した小説には、(僕自身が執筆時にそれを意識していたかどうかは別にして)たまたま一般読者の共感を呼びうるなんらかのフックが備わっていたため、ネットでレビューなどを見ていても、「共感できなかった」という声にそれほど多く触れずに済んでいたのだろう。』(P212〜214)
平山瑞穂の「小説観」あるいは「文学観」は、ごく真っ当なものである。
ただし、今の「エンタメ小説界」は、読者は無論、出版社・編集者でさえ、「小説」に「文学」を求めていない。
「エンタメ小説」とは、基本的に「暇つぶしの消費財」でしかないし、読者の方も「接待されること」しか望んでいないから、「作家と読者が切磋琢磨する」ような「文学」の存在など、理解の外なのだ。
この引用部分でも、特に、
『そもそも、読者から共感を得ようなどとはこれっぽっちも思っていない場合さえある。そのとき僕が目指しているのは、なにかそれとはまったく別のことなのだ。』
というのは、私が批評文を書くときの姿勢「そのまま」だといっても過言ではない。
はっきり言えば、私の文章は(難しい言葉を使ってなくても)「頭の悪い読者」には、その意図するところが理解できないし、読み通せない。なにが書かれているのか、さっぱりわからないなら、読むのが苦痛になるのも当然なのだから、私はそんな読者にまで理解されようとは思っておらず、むしろそんな読者に向けて、しばしば「読めない読者」という言葉を使い、ハッキリと挑発すること(ショック療法)で、その「気づき」をうながそうとさえしている。無論、無駄は承知の上でだ。
だからこそ、「一般読者」とは、「共感」し「感動」し「泣ける」ことが、小説の魅力だなどとしか考えられない「原始的な頭脳の持ち主」でしかないという事実に、平山が長らく気づかなかったというのは、この人の「頭の固い理想主義者」的な「弱点」であると考える。
私自身は、「読者の立場」から、もうずいぶん以前より、そんなことは「分かりきった」ことと認識していたし、そう認識しながらも、苛立ちを抑えられずに来た。
例えば前記のとおりで、「なぜ『匣の中の失楽』の魅力がわからない」「なぜ『匣の中の失楽』のような作品に、解決(オチ)を求める」「『匣の中の失楽』という作品が、そういう作品ではないということくらい、どうしてわからないのか」といった具合で、『匣の中の失楽』に限らず、小説にすら限らず、読者・鑑賞者の「頭の悪さ」に苛立たされ続けてきたのだ(ちなみに、『匣の中の失楽』の著者・竹本健治も、平山瑞穂と同様、ジャンル分けのしにくい、ぬえ的な作家である)。
ともあれ、「アニメファンなんて、バカばっかり」「特撮マニアなんて、バカばっかり」「ミステリマニアなんて、バカばっかり」「SFマニアなんて、バカばっかり」「映画マニアなんて、バカばっかり」といった経験を、切れ目なく、ずうーっと重ねてきた結果、私のたどり着いた「世界理解」が、シオドア・スタージョンの言う、次の言葉だったのである。
『SFの90パーセントはクズである。一一ただし、あらゆるものの90パーセントはクズである。』
いくらかでも私の文章を読んできてくれた人なら、私がこの言葉をたびたび引用するのを、よくご存知だろう。
ともあれ、そんな私からすれば、平山はあまりにも「世間知らず」だった。
「世間知らず」のまま小説家になんぞなってしまったから、大変な苦労をし、こんな本を書かなくてはならないことにもなったのだ。
その点、私は幸運にも、高校卒業時に応募した「アニメーション制作スタジオ」の書類審査(自分の描いた絵を送っての審査)に落っこちたので、その後の人生を、パッとしないアニメーターとして、陽も当たらなければ稼ぎも乏しい社会人として送らずに済ませることができた。平たく言えば、「才能が無かった」からこそ、その後に、無難に公務員にもなれたのである。
ところが、平山瑞穂には、なまじ「文学的才能があった」ために、日本ファンタジー大賞を受賞して作家デビューしてしまい、なまじ「文学的才能があった」ために、レベルの低い「通俗小説」を書くことができなかった。
書こうと思っても、自分の「目」が「手」が、それを邪魔したからこそ、彼には決して、完全な「駄菓子小説」など書けなかったのである。
今、このレビューを書いている最中に、「note」をチャックしたところ、旧稿「〈文体〉とは、オタク以前以後だけに非ず。」に「いいね」をくれた人がいたので、「どんなことを書いたんだっけ?」と読み返してみたら、ここに書いていることと、まさに同様のことを書いていた。一一曰く、
『この記事は、私のような「文学趣味」の人間にとっても「面白い」。
ただし、「面白い」といっても、その意味するところは、「オタク」の人たちとは少し違うはずだ。
この記事には、「これがオタク構文」「それを早口で言っちゃうよね」「語彙力高まってる」といった反響ツイートがたくさん寄せられたそうだが、これらは、この記事への「共感」を示した言葉だと言えよう。つまり「そうそう、そのとおり!」「私も、そんなこと感じていた」というような「感情」を表明した言葉だ。
たしかに、私にも「そうだな。面白い指摘だ」(なんていう、シャア)みたいな感想はある。
しかし、「文学趣味」の人間は、単なる「共感」に、満足はできない。「共感」でお終いなのは「エンタメ」であって、「文学」的には、もう一段「深い」ところに踏み込んだものでないと、物足りないのだ。
「共感的消費」ではなく、「文学」には、そこから「新たな何か」を生み出す、クリエイティブさが求められるのである。』
つまり「共感できたから、面白い」というだけでは、少なくとも「文学」ではないし、感性としての「文学趣味」を持つ者を感心させることはできない、ということである。

『 この作品(※ 第16著作『僕の心の埋まらない空洞』)の読者レビューで代表的なものは、おおよそ以下のような論調だった。
「不倫を正当化している男たちの身勝手な言い訳を延々と読まされてうんざりした」「不倫以外のなにものでもないものに意味づけをして美化しようとしているのが見苦しい」「男二人の自己正当化の言い訳が不愉快」。中には、「浮気はよくない。ストーカーも良くない」だけで完結している感想もあった。
浮気やストーカーがいけないなどというのはあたりまえで、わざわざ言及するまでもないことだ。当然のことながら、僕はこの作品を通じて、不倫やストーカー行為を肯定していたわけでもないし、弁護していたわけでもない。そうした倫理的反感や批判の先にあるもの一一非難される行為であることがわかっていながら、人はなぜ不倫やストーカー行為に走ってしまうのか、その根源を突きつめたかったのだ。
読者を不愉快にさせることも、織り込み済みだった。むしろ不愉快にさせることによって、問題の核心に目を向けさせたかった。だが、読者の多くは、「不愉快だった」という感想で終わりにしてしまった。その理由は、「共感」という語をキーとした一連の感想を目を通していれば、おのずと見えてくる。
「身勝手な男の話で、共感できなかった」「女性の共感は得られないだろう」「これは男性のほうが共感できる内容なのでは?」などなど、こんな感想もある。「既婚者が共感すると帯に書いてあったが、実際にはどうなのか訊いてみたい」一一これは、単行本のオビに書かれていた以下のコピーのことを指しているのと思われる。
「これって俺の話!?」と震え上がる既婚男性、続出!
これは担当のTさんが考えたコピーだが、いずれにせよ、「身に覚えがある」、あるいは「思い当たる節がある」という理由で脅かされることは、「共感」とは違うと僕は思う。「既婚者が共感する」とは、オビにはひとことも書いていない。にもかかわらずこのレビュアーは、それを「共感」と解釈したのだ。それはとりもなおさず、「小説を読めば、なんらかの共感が得られるはず」ということが当然の前提になっていることを示唆しているような気がする。
だからこそ、「共感できない小説」は、「つまらない、読んでも意味のない、不愉快なだけの小説」とジャッジされてしまうのである。』(P228〜229)
つまり、今の「一般読者」とは、「共感乞食」なのだ。
そして、この「共感」を、「感動」とか「泣ける」とかに言い換えれば、私が最近、映画レビューなどで書いていること、そのままだと言えるだろう。
今の日本人は、知性や感性を働かせることを知らない、「一億総感動乞食」になってしまったのである(残りの例外2500万人の9割は、作品の意味が取れない幼児か、認知症の老人である)。
ともあれ、私と同様、平山もまた、「単純に、喜ばせたり、楽しませたりする」のが「文学」ではない、というくらいの「文学的な常識」は持っている。
しかし、こうした「文学における常識」は、今や死滅状態と言ってもよく、「読者」の多くは、「お客様あつかい」を当然のこととして、指一本動かそうとはしないのだから、脳が退化するのも当然なのだ。
なぜ、私が、このように「不愉快なこと」ばかり書くのかというと、その意図が理解できる「頭のいい読者の共感」を得たいためではない。
そうではなく、私の意図するところを理解できない「頭の悪い読者」を、少々痛めつけてでも、彼らの知性に刺激を与えて、多少なりことも覚醒を促したいと、そう考えるからだ。つまり私は、「悲しい憎まれ役」をわざわざ買って出て、無駄と承知しつつも「希望」を捨てられないでいる、実に哀れまれるべき人間なのである。
そして、それは、基本的には、平山瑞穂だって同じなのだが、彼はそれを、私のような「アマチュアという自由な身分」において行うのではなく、「プロという不自由な身分」において行う、「ドンキホーテ」なのだと言えるだろう。
だから、私は、彼を支援しないわけにはいかないし、少しでも彼が書きたいものを自由に書けるよう、執筆環境の整うことを望まないではいられない。それは、誰よりも、私自身のためであるからだ。
しかし、現実はどうか?
例えば、本書の「Amazonカスタマーレビュー」を覗いてみると、次のようなレビューが、すぐに目に入ってくる。
『 potcharin 「この作家は中途半端」・(5つ星のうち3.0)
2023年3月12日
・自分のやりたいことがあるのならやれば良いのに、なぜか編集者と戦わない
・共感を求めて作品を書いていないのに、★1レビューに心傷つき、他レビュワーの「言いたいこと分かるわぁ」に感動している。
共感を否定する作家が、読者の分かるわぁのコメントに共感してどうするんだ。
・良かれと思って編集達がアドバイスしてくれてるのに、自分こだわりで突っぱねる。でも最後までこだわらず妥協する
・後悔している。でもまた妥協する
バタフライという小説を刊行する際に、映画の『バタフライ・エフェクト』は知らない。
なんというか、世の中のエンタメに興味がないのでは? と感じる。
エンタメ小説は勉強したが、エンタメそのものは勉強していないまま来ている印象があった。映画や漫画やアニメといった、大衆が興味ありそうなものに興味ないまま来ているのでは。
その上、人の心を勉強しているはずなのに、作品に活かそうと考えていない
売りたいのか売りたく無いのか分からない。それが本作家の魅力なのだろうか。
本書ではエンタメ小説家としての過ちが勉強できた。
たぶん、本書がこの人の本の中で一番面白いと思う。』
本書を読んで、この程度しか理解できない(まったく理解できていない)のに、これで自分は、著者の平山よりも『映画や漫画やアニメといった、大衆が興味ありそうなもの』を理解しているつもり、『大衆』よりも「賢い」つもりなのだから、なんともおめでたい話だが、この「頭の悪さ」こそが、「一般大衆(読者)」の「一般大衆(読者)たるところ」である。
しかも、自分が、そんな『大衆』のひとりに過ぎないという「劣等感」を密かに抱えたまま、(皮肉でも利かせたつもりで)作家をこき下ろすことで、刹那にも「上に立てた」と思い込もうとする、そんな愚鈍な「大衆的ルサンチマン」を抱えた、これは「選ばれようもなかった人間(その他大勢)」の醜い姿だ。
これこそが「自分がバカ丸出しであることに気づく能力もないバカ」の「見苦しい姿」なのだが、しかしまた、これが「一般大衆(読者)」大方の姿なのである。
こうした読者には、「美を理解する目を持つがゆえの苦しみ」など、とうてい理解できない。
「繊細な味覚や聴覚を持つがゆえの苦しみ」ということが理解できない。
「微細な美的価値」に反応してしまう「鋭い感性」のゆえに、「大衆向けの大味な粗悪品」に、どうしても妥協できない「選ばれた者の苦しみ」が理解できない。
大衆が、「資本主義リアリズム」に染め上げられた世界の「裸の王様」でしかないことを見抜き、その平民権力に妥協した方が「利口」な立ち回りだとわかってはいても、しかし、その「鋭い美意識」が邪魔をして、「でも、王様は裸ですよ」と言ってしまうような、それで損をしてしまうような、そんな「選ばれた人間」の苦しみがわからない。
このようにして、この世界からは、どんどんと「美」が失われていくのだろう。
ちょうどそれは、『桃の向こう』の「煌子」と同様、いずれ完全に失われて、「不可視・不可触」な「彼岸」の存在と化してしまうのだろう。
だが、その「美」の記憶を持っている者は、その失われたものの方へ、つい手を伸ばさずにはいられないものなのである。
(2023年3月24日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
