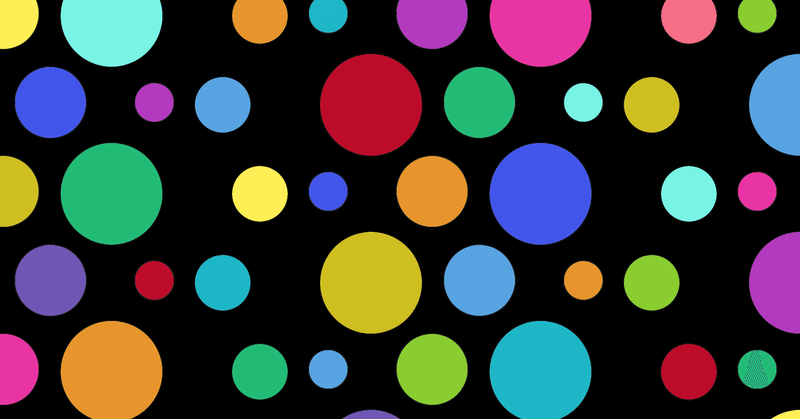#書評
#読書感想文 スーザン・ネイピア(2019)『ミヤザキワールド 宮崎駿の闇と光』
スーザン・ネイピアの『ミヤザキワールド 宮崎駿の闇と光』を読んだ。
翻訳は仲達志さん、2019年に早川書房から出版された本である。
スーザン・ネイピアさんは、アメリカのタフツ大学の日本文学の研究者で、宮崎アニメのゼミの授業を行っている大学教授だ。
この本は、宮崎作品と宮崎駿自身の人生や家族、東映の会社員時代、スタジオジブリのエピソードが一緒に語られており、はじめて知ることも多かった。
『と
中島美鈴(2016)『悩み・不安・怒りを小さくするレッスン~「認知行動療法」入門~』の読書感想文
中島美鈴の『悩み・不安・怒りを小さくするレッスン~「認知行動療法」入門~』を読んだ。2016年に光文社新書から出された一冊だ。
認知行動療法とは
日本では、2010年4月から保険診療適用となった。これはつまり、かなり多くの人に対して効果が認められた診療方法ということになる。もちろん、合わなかった人、効果がなかった人もいると思うが、希望を感じる。
わたしは、フロイトのソファに寝転がって、自分の
篠田桃紅(2015)『一〇三歳になってわかったこと 人生は一人でも面白い』の読書感想文
篠田桃紅の『一〇三歳になってわかったこと 人生は一人でも面白い』を読んだ。2015年に幻冬舎新書から出された一冊だ。
篠田桃紅(しのだ とうこう)は美術家で、1913年3月28日に生まれ、2021年3月1日に亡くなった。108歳まで生きた人だ。
ある種の箴言集として読める。忘れたくない箇所を引用しておきたいと思う。
著者を何度かテレビで見かけ、100歳を過ぎて、これだけ明晰に話せるものなのか
安部公房(1991)『カンガルー・ノート』の読書感想文
大学時代、安部公房の『壁』と『砂の女』を読んで、うわさどおり、予想どおり「ああ、天才だな」と生意気にも思った記憶がある。
その勢いで、ほかの作品もどんどん読んでいけばいいのに、その当時の私は「天才であることはわかった。放っておこう!」と安部公房から離れてしまった。なぜ、そう考えたのかは、はっきりとは覚えていないのだが、心残りではあった。安部公房の天才ぶりを確かめずに、死ぬのはよくない。
という
川上弘美(2003)『ニシノユキヒコの恋と冒険』の感想
川上弘美の『ニシノユキヒコの恋と冒険』を新潮文庫で読んだ。単行本が2003年に出版され、2006年に文庫化されている。
読了して、まず思ったことは、なぜわたしの人生にニシノユキヒコは現れないのだろう、ということであった。
ニシノくんは、色男である。川上弘美は、現代の光源氏として、『源氏物語』の翻案として、『ニシノユキヒコの恋と冒険』を創造したのだと思われる。
十人の女性の目を通して、読者はニ