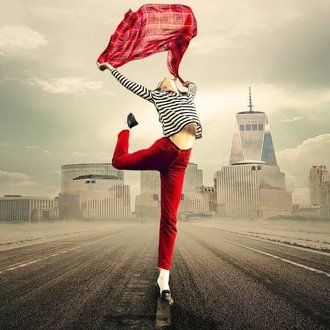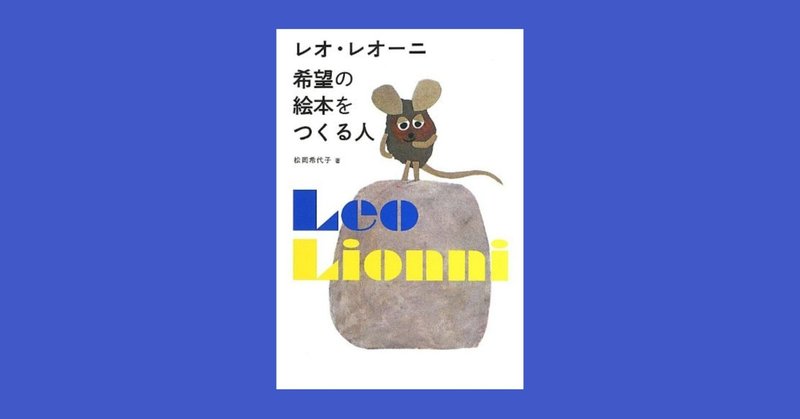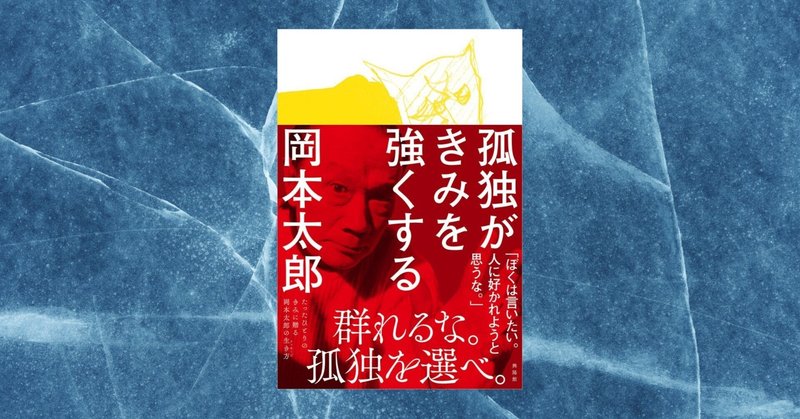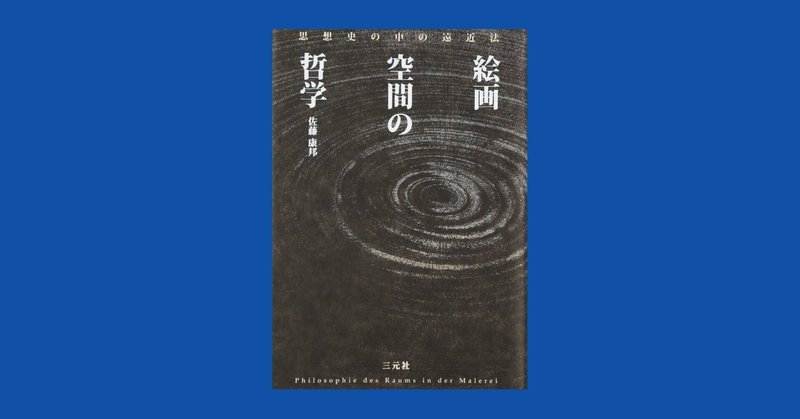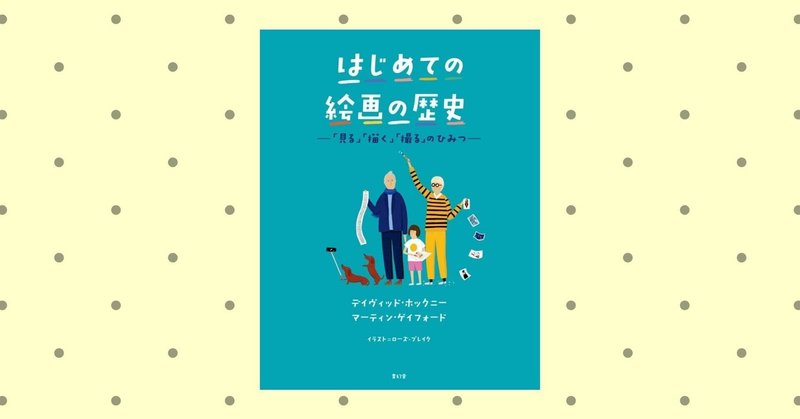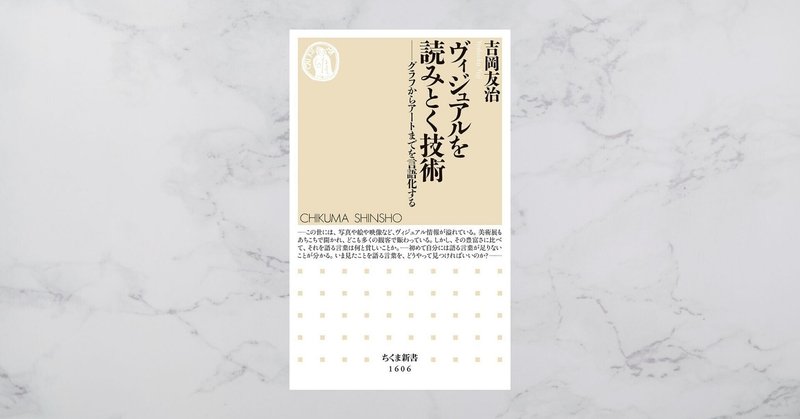#本
『レオ・レオーニ 希望の絵本をつくる人』松岡希代子著
美術館学芸員として、デザイナーや絵本作家として活躍したレオ・レオーニの展覧会を企画した著者がつづる、レオ・レオーニとの関わりや、その作品、魅力についての本。
レオ・レオーニの絵本としては、『あおくんときいろちゃん』『スイミー』『フレデリック』などがよく知られている。
『自分の中に毒を持て』岡本太郎著
本気で生きよう、というような話。うなずけることも多い。タイトルは過激だが、ごくまっとうな生き方だと思う。
『孤独がきみを強くする』岡本太郎著
芸術家、岡本太郎の言葉を集めた格言集のような本。
人に流されず、自分のままの自分で、挑戦し続けよう、という内容。
ほとんどどの言葉もいたってまともで、岡本太郎はむしろ謙虚な人間という印象を受けた。
「男は~、女は~」という記述には、時代の限界を感じるところもある。
『未来のアートと倫理のために』山田創平 編著:なぜ今の世界で私は芸術に関わろうとするのか
京都精華大学のプロジェクト「芸術実践と人権――マイノリティ、公平性、合意について」で行われた2年間のレクチャーやゼミなどの公開プログラムと、新たな原稿を収録した本。
多彩なアーティストや芸術関係者が登場し、どの話もとても興味深い。
最も感銘を受けたのは、山田創平「芸術が、私と世界を架橋する」。一般的に言われていることなのかもしれないが、人間は世界を直接つかむことはできず、芸術があることで世界と
『はじめての絵画の歴史』芸術家ホックニーと評論家によるやさしい美術案内
ディヴィッド・ホックニー、マーティン・ゲイフォード著。 イラスト:ローズ・ブレイク。
「『絵画の歴史 洞窟壁画からiPadまで』のエッセンスを凝縮した、大人から子どもまで楽しめる書き下ろし版」。
ハードカバーの大型本で、絵画などの作品の美しい画像や、イラストが楽しい。ホックニー自身の作品も掲載されている(最近はiPadなどでも絵を描いているらしい)。
読んでいるとわくわくしてきて、絵や写真、
『絵を見る技術 名画の構造を読み解く』秋田麻早子著:美術の造形的な見方を解説する本
題名の「名画」が示唆するように、主に西洋美術のいわゆる「オールドマスター」(ある定義では1300~1800年のアーティストを指す)と19世紀の絵画を取り上げている(ほかの時代の絵やイラスト、日本画なども少しあり)。
その時代の絵画は、時代ごとの主流に基づいた描き方をすることが多いため(原題では「伝統的」とされるような描き方)、同じ「見方」で構図などを分析できる、ということで、主に絵画の構図や構造
『ヴィジュアルを読みとく技術―グラフからアートまでを言語化する』吉岡友治著
著者は比較文学・演劇理論を専攻して、アメリカ大学院の修士課程を修了し、塾講師を経て、小論文のインターネット講座を主宰。ロースクールやMBA志望者、企業を対象にライティングを教えている。
前半の「I 基礎編」は、グラフや入試問題、アート作品を題材に、ヴィジュアルの言語化の方法や例文を提示。ちょっとつまらないと思った。
後半「II 応用編」では、各章で1つのアート作品を取り上げて、1つのテーマを切