
千葉雅也『勉強の哲学 来るべきバカのために 増補版』 : 君たちは荒野を行け!一一私は行かないが。
書評:千葉雅也『勉強の哲学 来るべきバカのために 増補版』(文春文庫)
とても興味深い本だった。オススメである。
本書には「共感できる言葉」が山ほどあり、その一方「これはどうだろう?」といった部分も少なからずあったのだが、それらについて、逐語的に語っていたのでは長大なレビューになってしまうので、本稿では、第3章までの理論編について、その基本的な考え方に賛同しつつ、その上で、著者のスタンスに対する疑義を呈しておきたい。
(1)『 人は、「深くは」勉強しなくても生きていけます。
深くは勉強しないというのは、周りに合わせて動く生き方です。
状況にうまく「乗れる」、つまり、ノリのいい生き方です。
それは、周りに対して共感的な生き方であるとも言える。
逆に、「深く」勉強することは、流れのなかで立ち止まることであり、それは言ってみれば、「ノリが悪くなる」ことなのです。
深く勉強するというのは、ノリが悪くなることである。
いまの自分のノリを邪魔されたくない、という人は、この本のことは忘れてください。それは、ひとつの楽園にいるということです。そこから無理に出る必要はありません。
勉強は、誰彼かまわず勧めればいいというものじゃありません。
もし、何か生活に変化を求めていて、しかも、これまでのようにはノれなくなる方法にそれでも興味があるならば、ぜひこの先を読んでみてください。
これから説明するのは、いままでに比べてノリが悪くなってしまう段階を通って「新しいのノリ」に変身するという、時間がかかる「深い」勉強の方法です。』
(P14〜15、太字強調は原文)
ここで、言われているのは、簡単に言えば「勉強とは、ぬるま湯をぬるま湯と自覚するための努力である」ということだ。
「ぬるま湯」は『ひとつの楽園』で、「熱い風呂」が好きというのは、マニアックな趣味だと言えるかもしれない。
もちろん、好きで「熱い風呂」に入るのならばともかく、本人にその気もなければ覚悟もないのに、無理に「熱い風呂」に入れて、倒れられでもしたら面倒なので、『誰彼かまわず勧めればいいというものではありません。』ということになる。要は、同語反復ながら「ヌルいやつは、ヌルくしか生きられないのだ」ということだ。
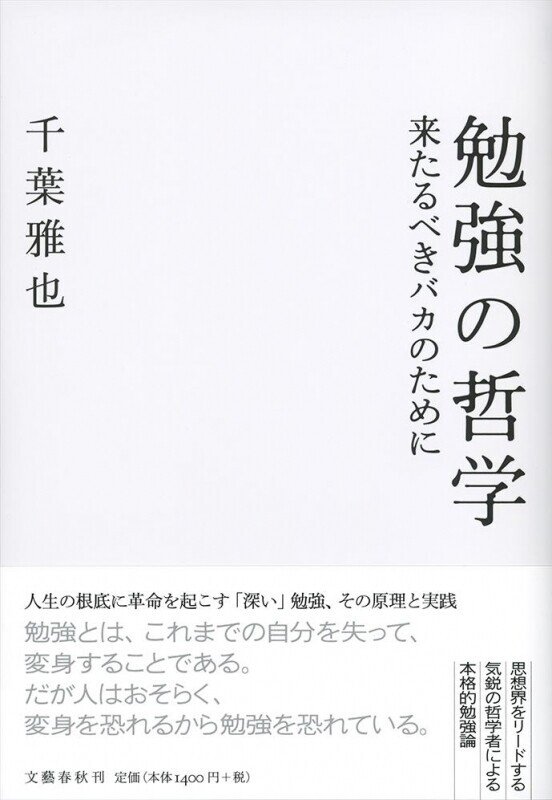
(上の画像は、初版単行本)
ところで、著者がここで『「深い」勉強』と、特に「深い」を強調しているのは、「普通の勉強」つまり「深くない勉強」とは、要は「ヌルい勉強」に過ぎず、それでは「ぬるま湯」からは出られない、つまり「変われない」ということを意味している。
ぬるま湯から出たければ、「キツい勉強」をしなくてはならない。そして「キツい勉強」とは、単に「難しい勉強」ということではなく、「周囲の評価を求めない(バカになる)勉強」ということなのだ。だから「キツい」。
(2)『 勉強の目的とは、これまでとは違うバカになることなのです。』
(P15)
「深い勉強=キツい勉強」を極めると、当然のことながら「周囲の理解」が得られなくなるので、「あいつは、何をわけわかんないことを言っているんだ?」ということになる。つまり、周囲からすれば、その人は『バカ』になった、ということだ。
(3)『 勉強とは、自己破壊である。
では、何のために勉強するのか?
何のために、自己破壊としての勉強などという恐ろしげなことをするのか?
それは、「自由になる」ためです。
どういう自由か? これまでの「ノリ」から自由になるのです。
私たちは、基本的に、周りのノリに合わせて生きている。会社や学校のノリ、地元の友人のノリ、家族のノリ……そうした「環境」のノリにチューニングし、そこで「浮かない」ようにしている。日本社会は「同調圧力」が強いとよく言われますね。「みんなと同じようにしなさい」一一それは、つまり「ノリが悪いこと」の排除です。「出る杭は打たれる」のです。
しかし、勉強は、深くやるならば、これまでのノリから外れる方向へ行くことになる。
ただの勉強じゃありません。深い勉強なんです。それを本書では、「ラディカル・ラーニング」と呼ぶことにしたい。ラディカルというのは「根本的」ということ。自分の根っこのところに作用する勉強、それを、僕にできる限りで原理的に考えてみたいのです。
私たちは、同調圧力によって、できることの範囲を狭められていた。不自由だった。その限界を破って、人生の新しい「可能性」を開くために、深く勉強するのです。
けれども、後ろ髪を引かれるでしょう一一私たちは、なじみの環境において、「その環境ならではのことをノってやれていた」からです。ところが、この勉強論は、あろうことか、それをできなくさせようとしている一一勉強によってむしろ、能力の損失が起こる。
一般にもの知りになると、大胆なことがやりにくくなる。
「昔はバカやったよな!」という遊びが、できなくなってしまう。かつては、仲間内の「ただのノリ」でバカをやるのは素朴に楽しかった。その後、成熟して、可能性をさまざまに考えられるようになると、「狭い世界にいたんだな……」と気づいてしまう。しかし、狭い世界だったからこそ、エネルギーを圧縮して爆発させるようなバカができたのかもしれない。
あるいは、お笑いの技術を勉強してネタの自由度が広がると、十分おもしろかったはずのネタがありがちなパターンにすぎないとわかってしまい、笑えなくなる。
自己流で歌っていたときの荒削りだからこその迫力が、一念発起してまじめにボーカルレッスンを受け始めたら、だんだん失われてしまった。
こんなふうに、勉強はむしろ損をすることだと思ってほしい。
勉強とは、かつてノっていた自分をわざと破壊する、自己破壊である。
言い換えれば、勉強とは、わざと「ノリが悪い」人になることである。
そんなことに踏み出したいと思ってもらえるでしょうか?』(P18〜20)
『そんなことに踏み出したいと思ってもらえるでしょうか?』一一もちろん、普通は、そんなことを思ってはもらえない。
そんなことを「面白そう」だと考えるのは、端的に言って「変態」である。
わざわざ「熱い風呂」に入ってみたり、わざわざ「ぬるま湯をぬるま湯だと指摘して、周囲の顰蹙を買ったりする」のは、どう考えたって「変態」に決まっている。要は、わざわざ「嫌がらせめいたことをして嫌われる」のを「喜んでいる」のだから。
しかしながら、こういう人がたまにはいないと、社会は「自己相対化」ということができなくなる。
「みんな」と違う視点に立つからこそ、「みんな」の社会の、良いところも問題点も見えてくる。だから、こういう人も必要なのだが、わざわざ「みんな」と同じ「ぬるま湯」から出て、「寒風」に吹きさらされたり、逆に「熱い風呂」に入ってウンウン唸ったりしたがる者など、普通はいない。
しかし、にも関わらず、現実には、そういう人がたまに現れるのだ。頼まれもしないのに、そういうことをやりたがる人が現にいる。ならば、その人は、もう「好きでやっている」としか考えられないし、事実そうなのだろう。自分としてはやりたくはないし、人が求めもしたくないものを、あえてやる人というのは、社会的な貢献だけを望んで「他人のため」に行動する「自己犠牲の人」であるよりも、むしろその本質は「変態」なのではないだろうか。
とにかく「みんな」と同じことをやっているのが、退屈で退屈で我慢ならないという「持って生まれた性分=変態性=天凛」を持つ者だけに、それが可能なのではないだろうか(そもそも哲学者とは、基本的に「変態」なのだと思う)。
一一したがって、そんなことを「普通の人」に求めるのは、無駄なのである。合理的に考えて、そんなことするわけがないのだ。
本書は、「勉強する」とは「どういうことか」を哲学し、語った本だと言えるだろう。だが、本書を読んでも「深い勉強」ができるようになるわけではない。
読めば自分にも「深い勉強」ができるような「気分にさせてくれる」だけで、ちょっと考えればわかることだが、この薄い本を一冊読めば、誰でも「深い勉強ができるようになる」わけなどないのである。
実際、著者の千葉雅也自身、いま人気の「哲学者」なのだが、「深い勉強」をしているはずの千葉その人が「ウケている」こと自体、本書で語られる「深い勉強」を、どこかで避けている証拠なのだ。そうでなければ「ウケる」わけがない。「資本主義リアリズム」を受け入れていなければ、今どきの「哲学オタク」の「ノリ」に合わせていられるわけなどないのである。
で、実際、本書の後半では、著者は周到に「徹底的であること」を否定している。こんな具合だ。
(4)『 第一章で、無限vs.有限という対立が、本書では重要になると述べました。
勉強は無限に広がってしまう。逆に、絞って勉強するというのは、哲学的な言い方をすると、勉強を「有限」にする、「有限化」するということです。「まずこれだけ」、そして「ここまででいい」という「有限性」を設定しなければ、勉強は成り立ちません。
勉強の有限化が必要である。
しかしこれは案外ややこしい話になる……。本章でも原理的に考えていきます。
勉強は、二つの方向できりがなくなる一一追求と連想、アイロニーとユーモアです。言い換えれば、「深追いのしすぎ」と「目移り」になる。勉強はアイロニーが基本なので、「深追いしているうちに目移りしてしまう」というのがよく起こることです。
先の(2)のケースで、何かフェミニズムの本を一冊読み、ある程度の知識をゲットできたとしましょう。でも、そこで終わりにはならない、というか、なるべきではない。そもそも勉強はアイロニーが基本なのであり、第二章で見たようにアイロニーは際限なく深まる。
何か入門書を一冊読めばわかりますが、一口にフェミニズムと言っても、複雑な論争があることがわかります。フェミニズムはぜんぜん一枚岩ではありません。
女性は女性であることで連帯すべきなのか。主婦ではダメなのか。問題は複雑です。女性に力を与えるための確実な根拠は何なのか……と根拠の深追いが始まる。そして困ったことに、アイロニーを停止せず、遥か遠くに「絶対的な根拠」=「真理」を目指して、途中のハンパな根拠付けを破壊していくことになる一一。
深追いから目移りへ。女性の労働について深追いすれば、労働という問題の巨大さに気づき、日本の雇用システムの問題に深入りし、関連する本を漁り始めたら、女性のことはどこか行ってしまう。よくあることです。
さらには、性とは何かとか、社会とは、欲望とは何かとか、テーマはデカくなって、最終的には「世界のすべての絶対的な根拠を知りたい」になってしまう。
世界の真理がついに明らかになる「最後の勉強」、そんなものはあるのか?
もしかしたら、哲学や数学はきわめて抽象的で原理的なので、それこそ「最後の勉強」なんじゃないかと思う人がいるかもしれません。が、そこでもアイロニーは止まらない。哲学や数学でも、現状、学者の世界において究極の根拠づけの合意はありません。
アイロニーに主導権をとらせたままならば、全方位にあらゆる問題にツッコミを入れ続けながら、決して到達できない究極の真理を夢見続ける、という人生になりかねないのです。
僕が言いたい事はシンプルです一一「最後の勉強」をやろうとしてはいけない。「絶対的な根拠」を求めるな、ということです。それは、究極の自分探しとしての勉強はするな、と言い換えてもいい。自分を真の姿にしてくれるベストな勉強など、ない。
深追い→目移り→深追い→目移り……というプロセスを止めて、ある程度でよしとするのが勉強の有限化です。』(P130〜132)
ここでは「勉強の有限化」が奨められる。『「まずこれだけ」、そして「ここまででいい」という「有限性」を設定しなければ、勉強は成り立ちません。』とのことだが、一一これは本当だろうか。
別に、どこまでも「無限」にやってもかまわないのではないか。どうせ、嫌でもいずれは死ぬんだし、なぜ、わざわざ「有限化」しなければならないのか。
その理由として『勉強は、二つの方向できりがなくなる一一追求と連想、アイロニーとユーモアです。言い換えれば、「深追いのしすぎ」と「目移り」になる。勉強はアイロニーが基本なので、「深追いしているうちに目移りしてしまう」というのがよく起こることです。』とのことだが、「深追い」し「目移り」して、何がいけないのだろうか。
平凡な答としては、世間様に評価してもらえるような「わかりやすい成果が得られない」ということだろう。
つまり「専門のない人=何でも屋」というのは「専門家」より、「何をやっているのかわかりにくい」分、世間から理解されにくい。要は、「世間から評価されてナンボ」という「世間のノリ」から逸脱してしまうのである。
だが、そもそも「勉強」とは、そうした「世間のノリ」の外部に出るために行うことではなかったのか。
『さらには、性とは何かとか、社会とは、欲望とは何かとか、テーマはデカくなって、最終的には「世界のすべての絶対的な根拠知りたい」になってしまう。/世界の真理がついに明らかになる「最後の勉強」、そんなものはあるのか?』一一あるのかないのかは、やってみなければわからないし、やってみてもわからないのかもしれないが、だからといって、そんな「無駄なこと」をやってはいけない、という決まりはないはずだ。
何しろ「勉強」は、「世間のノリ」の外部に出るためにやることなのだから、「無謀と思えることに挑戦してみる」という「自由さ」は、あってしかるべきではないのか。「敗れる戦いに、それでも挑む(冒険の)」権利だってあるはずだ。
なのに、どうして「無難に手堅く生きろ」という「世間のノリ」の範囲内に止まらなくてはならないのか。
『哲学や数学でも、現状、学者の世界において究極の根拠づけの合意はありません。』一一どうして『学者の世界』でも「合意」のないことを、やってはいけないのか。それは「学者の世界のノリ」に合わせておいた方が「(世間的にも、変人扱いされないから)何かと得だよ」ということなのだろうか。
『アイロニーに主導権をとらせたままならば、全方位にあらゆる問題にツッコミを入れ続けながら、決して到達できない究極の真理を夢見続ける、という人生になりかねないのです。』一一私が今やっていることが、これに近いわけだが、そんな人生がいけない、というのだろうか。
「世間的に損だ」ということなら、言われなくてもわかっているが、それでは「世間様のノリ」の内に、無難に止まることでしかないのではないか。
それに『決して到達できない究極の真理を夢見続ける』と言うけれども、それは違う。
『決して到達できない究極の真理を夢見続ける』のは、『究極の真理』を夢見ているからではなく、多くの場合「ひとまず目の前にあるものが気に入らない」からに他ならない。目の前のものを片っ端から否定していった先に『究極の真理』があるとは思っていなくても、「ひとまず目の前にあるものが気に入らない」のなら、それにツッコミを入れるのは自然なことだし、その結果、何も残らなくても、それはそれで仕方がない。その手の届く範囲のリアルな世界が、そこまでのものであった、というだけの話だろう。
ともあれ、人間が「有限な存在」である以上、最終的には、何をやっても『究極の真理』など認識できないというのは、初手からわかりきった話でしかない。
であれば、やりたいやり方でやって、何が悪いというのか。
単に、そういう「自分勝手なやり方」をされると傍迷惑だと「世間様」が許さないだけではないのか。それならそれで、殺されない程度にやるという工夫くらい、やる人は言われなくてもやるだろう。
『「最後の勉強」をやろうとしてはいけない。「絶対的な根拠」を求めるな、ということです。それは、究極の自分探しとしての勉強はするな、と言い換えてもいい。自分を真の姿にしてくれるベストな勉強など、ない。』一一絶対的な根拠になど到達できないという点は同感だが、それを承知で、そちらの方向を目指すというのは「あり」だろう。
ここでは『究極の真理』を目指すことと『究極の自分探し』が、どちらも「到達不能な目標」として否定的に並べられているけれども、どちらも「到達不能な目標」であることを承知の上で、ある意味ではロマン主義的にそれを選ぶのは、その人の勝手であって、他人がとやかく言うべきことではない。
さらに言うと、『究極の真理』探求に、世間で評判の悪い『自分探し』のレッテルを貼ることは、悪しき「印象操作」でしかないだろう。
そもそも「哲学」なんてものは、長らく『究極の真理』を求めてきたあげくに挫折した学問なのだから、その挫折を逆手にとって「わかるわけない」などと言うのも、あまり自慢のできる態度とは思えない。
(5)『 決断は、実はアイロニーを徹底した場合に起こる。
アイロニーでは、絶対的な根拠を求める。そしてそれに永遠に到達できないのでした。何かを選ぶにあたり、アイロニカルな態度を突き詰めるならば、究極の、真にベストな選択をしたいということになる。絶対的に信頼できる人を選びたいということになる。
ですが、比較にベストな解はありません。絶対的に根拠づけられた選択はありえない。
そこに、ある転機が訪れる一一。
絶対的な根拠を求め続けていて、到達できない……この無限に先延ばしされた状態を、一点に瞬間的に圧縮し、絶対的な無根拠への直面にしてしまう。
そして、「絶対的な無根拠こそが、むしろ、絶対的な根拠なのだ」という逆転が起こる。
絶対的な根拠はないのだ、だから無根拠が絶対なのだ。
だから一一ここで起きる論理の飛躍に注意してください一一、無根拠に決めることが最も根拠づけられたことなのである。次のイコールが成り立つ、絶対的な無根拠=絶対的な根拠。
実際的に言えば、これは要するに、「決めたんだから決めたんだ、決めたんだからそれに従うんだ」という形で、まあ「気合い」で、ただたんに決めるのだということです。
聞いたことがあると思うんですが、自己啓発書などで、「明日からあなたが決めさえすれば、あなたはそうゆうあなたになる」といった形で言われることです。
それはマズいのだと僕は言いたいのです。』(P136〜137)
「決断主義」が安直だ、というのは意見には、完全に同意する。しかし、『絶対的な根拠』を求める態度が「断念」としての「決断」を生み出すという理屈は、間違ってはいないけれども、そうとばかりも言えないだろう。
つまり、「私」は『究極の真理』や『絶対的な根拠』を求める「旅路の途中で死なざるを得ない存在である」という事実を認める「リアリズム」だって、当然あるからだ。
その場合には「決断」は必要はない。「決断」するまでもなく、私たち有限な人間存在は、『究極の真理』や『絶対的な根拠』の有無さえ知ることもなく死んでいくのが、「必然」だからである。
つまり、「決断主義」とは、『究極の真理』や『絶対的な根拠』の探求から「必然」的に生まれるものなのではない。そうではなく、自分は、その探求の「旅路の途中で死なざるを得ない存在である」という「わかりきった事実」を直視できない「弱さ」によって生み出されるものに過ぎない。
自分が「生きている間」に『究極の真理』や『絶対的な根拠』に到達できないという「わかりきった事実」を直視できず、ただ「生きている間」にそれに到達できないと、自分は「生きている間」に「世間様から評価されない」「愚か者だと笑われる」とか言ったことが恐ろしくてしかたのない、そんなチンケな人間が、手っ取り早く『究極の真理』や『絶対的な根拠』を手にしたと思い込みたくて、「自分は特別な存在だ」と信じ込みたくて、安易な「決断主義」に走るのである。
(6)『 こうして、アイロニーはそもそも批判的になることなのに、決断主義に転化すると無批判な生き方になってしまいます。狂信的になってしまう。他の考えを聞く耳をもたなくなる、というか、他の考えをもつ複数の他者がそもそも存在しなくなる。
だから決断主義は避けなければならない。これが本書の立場なのです。
そうならずに、アイロニーの批判性を生かしておくには、絶対的なものを求めず、そして複数の他者の存在を認めなければならない。
アイロニカルの批判は、むしろ半端な状態に留めておく必要があるのです。
そこでユーモア的な有限化へと転回することになる。第二章の流れと同様に、アイロニーを徹底せずにハンパな状態で生かしておいて、ユーモアの方へ転回するのです。』(P140)
「決断主義」の問題点が『他の考えをもつ複数の他者がそもそも存在しなくなる。』という点にあるのだとしたら、『究極の真理』や『絶対的な根拠』を追い求める立場、つまり「深追い」や「目移り」を良しとする立場も、『他の考え』として『認めなければならない。』のではないだろうか。千葉の言っていることは、寛容なのか不寛容なのか、よくわからないものになってしまっているのではないか。
『アイロニカルの批判は、むしろ半端な状態に留めておく必要があるのです。』一一とのことだが、有限な存在である人間の行う『アイロニカルな批判』なんてものは、所詮は、嫌でも『ハンパ』ものに留まってしまうのではないか。
もともと徹底できない『アイロニカルな批判』に対し、その代替案として、無難な『ユーモア』を提起しておけば、それは「ハンパな世間」の「ウケ」も良くて当然であろう。つまり、これは「ノリ」やすい意見だ。
(7)『 ある結論を仮固定しても、比較を続けよ。つまり具体的には、日々、調べ物を続けなければならない。別の可能性につながる多くの情報を検討し、蓄積し続ける。
すなわちこれは「勉強を継続すること」です。
これはエネルギーが要ることで、大変だから、環境のノリに保守的に流されたり、「エイヤッ」で決断してしまったりするのです。そうならないようにするために、そうならないというのは「比較を中断しながら続けること」であると明確化し、原理を説明しているのです。』(P141)
『ある結論を仮固定しても、比較を続けよ。つまり具体的には、日々、調べ物を続けなければならない。』『勉強を継続すること』が大切だ、という意見には賛成である。
しかし、ここで問題なのは、「私は、究極の答を持たないから、ここでの意見表明は差し控えておいて、勉強を続けます。それが知的に誠実な態度だと思います」というような、(今どきの官僚答弁的な)「無責任な現実逃避」の自己正当化だ。
有限な存在である人間の意見など、所詮はどこまで行っても『仮固定』された「暫定的意見」でしかないのは明らかだ。しかし、だからといって、その「暫定的意見」あるいは「暫定的良心」や「暫定的正義」に従って行動しないでは、人間は生きてはいけない。なぜなら、人間は「暫定的な存在」だからである。
なのに、「暫定的意見」だから「何もできません」などと言うことの方が、よほど『究極の真理』主義、あるいは『絶対的な根拠』主義であり、「お前は神様か!」と批判されて然るべき「傲慢」ということになるのではないか。
したがって、『「エイヤッ」で決断』が、理想ではあり得ないにしろ、私たちには否応なく「決断」しなければならない時があるし、事実として私たちは、いつでも「決断」してきたのだということに気づくべきであろう。
言い換えれば、「決断主義はいけないよ」みたいなことを、何の「痛み」もなく、したり顔で語れるのならば、それはその人自身が、いかに安易に決断してきたかに気づいていないことの証拠にしかならないのである。
(8)『 信頼に値する他者は、粘り強く比較を続けている人である。』(P142)
私はこのように、実践しています。
(9)『 決断主義の場合と違って、比較を行う私は個性的な中身をもっている。何かにこだわる私がいる。享楽的な私が。他方で、決断する私は、決断するだけのカラッポの私だった。比較の中断は、最終的に、享楽的なこだわりがあるからこそ起こる。
ここから次の問題に進みましょう。
こだわりというのは、要は「昔から自分はこうだった」ということです。
ならば、自分の「頑固な」部分でものごとを決めるしかない、ということなのか。
その部分は、いかんともしがたい部分なのでしょうか。
そこで、第二章で予告したように、本章では、享楽的こだわりは絶対的に固定されたものではなく、変化可能であるという考え方を示したい。
ラディカル・ラーニングでは、自分の根っこにある頑固さに勉強を通して介入する可能性を考える。自分の根っこに触れるのは難しく、その変化には限度があるにしても、可能性としては変えられる部分があることをこれから説明します。
享楽的こだわりが、比較のプロセスを途中で切断する刃である。
その刃自体が変化するという可能性を考える。』(P143〜144)
『決断主義の場合と違って、比較を行う私は個性的な中身をもっている。何かにこだわる私がいる。享楽的な私が。』一一なんて言葉に、うかうかと乗せられる、頭の軽い「哲学オタク」は少なくあるまい。だが、その軽い頭の中に『個性的な中身』や『こだわる私』なんてものは、ほとんど詰まってはいないだろう。『享楽的』というよりは、端的に「楽天的(ノーテンキ)」なのだ。
『他方で、決断する私は、決断するだけのカラッポの私だった。』一一嫌々ながらも決断せざるを得ないから決断した場合だって、山ほどあるんじゃないのか。千葉自身は、決断しないで生きてきたのとでも言うのだろうか。
この言い方では、実際には幅のある「決断」を、あまりに戯画化しすぎだろう。
『比較の中断は、最終的に、享楽的なこだわりがあるからこそ起こる。』一一つまり、偏執してしまうものがあるから、フラットな比較ができない、という意味だ。
たしかに『昔から自分はこうだった』という部分はあって、それは容易に脱ぎ捨てられるものではない。だが、千葉も言うとおり『享楽的こだわりは絶対的に固定されたものではなく、変化可能である』なんてことは、当たり前でしかない。
『その変化には限度があるにしても、可能性としては変えられる部分があること』は、その『限度』を認めるなら、別にわざわざ「ハウトゥー」的に説明してもらうまでもないことなのではないだろうか。だからこそ、このレビューでは、実践編たる本書第4章は扱わなかった。
○ ○ ○
本書の基本的な主張は「バカになろうよ」ということだった。そして、私はこの意見に大賛成であった。
ところが、本書は肝心なところで「腰砕け」になっており、結局は「世間ウケ」を意図し、「世間のノリ」に迎合している自分を正当化してもいる。
つまり「言っていることと、やっていることが、バラバラ」なのだ。
だから「言っている」ことには賛同できても、「やっている」ことの方は批判せざるを得なかった。
「世間のノリから、外れてみようよ」と言いながら、しかしその人の「身振り」は間違いなく「世間のノリ」に迎合したものでしかなかったのだ。
そして、こんなにも露骨な「矛盾」にすら気づけない読者が、本書でのんきに、ノリノリになれるのである(その実例は、Amazonカスタマーレビューを参照)。
(2022年3月15日)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
