
佐藤究 『爆発物処理班の遭遇したスピン』 : 佐藤究の 「夢野久作」性とは何か
書評:佐藤究『爆発物処理班の遭遇したスピン』(講談社)
著者の本を読むのはこれが初めてだが、なるほど「力」のある作家だというのがよくわかった。
本書は短編集で、8本の作品が収められているが、冒頭の表題作だけ少し毛色が変わっているものの、後の7本は、ハッキリとひとつの傾向を示しており、そこに著者の、基本的な「作風」を窺うことができた。

私が著者の名前を最初に知ったのは、第62回江戸川乱歩賞受賞作となったデビュー作『QJKJQ』(2016年)である。
昔から乱歩賞受賞作にはなんども裏切られてきたので、近年は乱歩賞受賞作に興味はなかったのだが、この『QJKJQ』の、いかにも怪しげな装丁に惹かれ、手にとってみると、選考委員の有栖川有栖が、帯に「これは平成の『ドグラ・マグラ』である」と書いていた。こう書かれていては、年来の『ドグラ・マグラ』ファンとしては、とうてい無視し得なかったからだ。
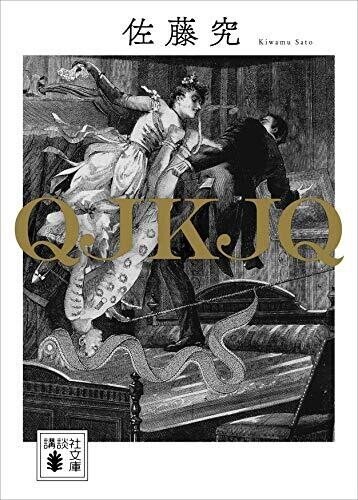
しかしそこは、乱歩賞に痛めつけられてきた者として「いやいや、選考委員の言葉ごときに迷わされてはいけない。それに有栖川有栖は、特別に夢野久作のファンだというわけでもないのだから、ここは話半分に聞いておくべきで、この作品が本当に、平成の『ドグラ・マグラ』と呼ぶに値する作品であったなら、すぐに大評判になるはずだから、もう少し様子を見てからにするべきだ」と、じつに賢明にも、自制心を働かせたのだった。
実際、この有栖川有栖の言葉は、必ずしも支持されなかったようだし、作品の評判もそこそこという感じで、結果としては、少なくともこの作品が『ドグラ・マグラ』級の作品でないことは確かであったようなので、私も結局は、読まなかった。

しかし、その後、著者は、『Ank: a mirroring ape』で第20回大藪春彦賞、第39回吉川英治文学新人賞を、『テスカトリポカ』で第34回山本周五郎賞、第165回直木賞を受賞し、特に『テスカトリポカ』の評判は抜群で、ベストセラーにもなったから、そのうちこれだけは読もうかと思っていたところ、短編集である本書『爆発物処理班の遭遇したスピン』が刊行されたため、これで味見してみることにしたのである。

○ ○ ○
【以下、作品の内容や仕掛けに触れるので、未読の方はご注意ください】
まず、冒頭の表題作「爆発物処理班の遭遇したスピン」を読み始めて最初に感じたのは、意外に普通の文体の持ち主で、少なくとも夢野久作のような特異な文体の持ち主ではない、ということだった。
無論、文体というのは、ある程度は意図的技術的に変えることが可能なのだが、しかし、私がここでいう「文体」とは、そういう形式的なものには止まらず、「体臭としての文体」というほどのものを含んでいる。つまり、表面上を変えても、そこに通底する「臭い」があるのだが、それが夢野久作とは、だいぶ違う、ということだった。
しかしながら、私はこの表題作をとても気に入ったし、よく書けた短編だと高く評価する。
私がこの短編「爆発物処理班の遭遇したスピン」で最も面白く感じたのは、「蓋を開けて内部の気圧が下がると、爆弾が炸裂するという仕掛けの施された、人の入ったままの酸素カプセル」から、どのようにして内部の人を救い出すか、という難問について、爆発物処理班が出した「酸素カプセルの内部と同じ気圧にされた部屋に、酸素カプセルごと運んで、そこで蓋を開ける」という解答(アイデア)だった。
警察の爆発物処理班を主人公とした作品なので、「本格ミステリ」ではないと思い込んで読んでいたから、このリアルかつトリッキーなアイデアに「やられた!」と嬉しい悲鳴をあげたのである。
ところが、ここまでは、まだ物語の半ばに過ぎなかった。この後の後半で、タイトルにもなっている「量子力学的起爆装置」の難問が明らかになり、物語は「本格ミステリ」とは違った方向に展開していき、やがて独特の余韻を持つ結末へと着地するのである。
だが、結末こそ「本格ミステリ」的ではなかったものの、私はこの作品が、その結末の味わいや余韻を含めて、大変に凝った、よくできた作品だと感心させられた。
だから、後続の短編にも、同じような「本格ミステリ」的な味わいを期待したのだが、これは完全に期待ハズレだった。後の7本は、基本的に方向性が違っており、むしろこちらの方が、作者本来の作風なのではないかと思えるほど、一定の方向性を示していたのである。
では、その、作者の基本的な方向性と思しき「一定の方向性」とは、どのようなものであったか?
それは、「狂人」「動物」「警察」「暴力」「怪物性」といった「共通点」に、見出せるものだと言えるだろう。
こうした特徴の中から「狂人」や「怪物性」という部分を抜き出せば、それは確かに「夢野久作」に通づる個性だと言えるだろう。実際、作者は、夢野久作の影響下にある長編『QJKJQ』でデビューしたためだろうか、『幽』誌の「夢野久作特集号」に寄せた短編「猿人マグラ」も、この7本のうちに含まれている。
だが、だからと言って、本作作者を夢野久作直系の作家だと判断したのでは、短絡の誹りを免れないだろう。なぜなら、残りの「動物」「警察」「暴力」といった要素は、必ずしも夢野久作の特徴とは重ならないからで、そのあたりに、佐藤究と夢野久作の「個性の違い」を、はっきりと見ることができるからである。

佐藤究と夢野久作の、根本的な違いとは何か?
一一それは「即物的か心理的かの違い」だと断じていいだろう。
佐藤究の場合、「動物」「警察」「暴力」といった要素が示すとおり、彼の嗜好は「即物的」であり「身体的」であって、あまり「心理・精神・内面性」といったところには拘泥しない。
夢野久作が「発狂」にこだわったのとは違って、佐藤究の場合は、「どうして狂ったのか」というところには、あまり興味がなくて、単純に「狂人」が好きなのだ。その「理解不能な存在」としての「怪物」の「(暗く強い)力」の側面に惹かれるのであって、夢野久作のように「どうして、人は狂うのか?」というような「内面性」には、特段惹かれている様子はないのである。
また、だからこそ佐藤究の場合は、「動物」や「警察」へのこだわりがある。それは「心が見えない存在」であり、その意味で、迷いもなく「暴力」を行使することのできる「怪物性」を、それらは隠し持っている。だから惹かれるのだ。
佐藤究が「動物」や「警察」に惹かれると言っても、コミュニケーションの取れるような「動物」や「警察官」には魅力を感じない。その「何を考えているのかわからない」ところ(秘められた暴力性)にこそ、怖れを伴った、言い知れぬ「魅力」を、佐藤究は感じているようなのだ。

(映画「13日の金曜日」シリーズのシリアルキラー、ジェイソン・ボーヒーズ)
だから、佐藤究が「狂人」を好むと言っても、単なる精神障害者や精神病者ではダメで、「理解不能で、何を始めるかわからない不穏な存在」としての「狂人」でなければ、それは佐藤の興味の対象ではない。
したがって、彼の興味の対象は、暴力的な「シリアルキラー」などの方に傾いており、夢野久作の「少女地獄」のような「繊細な心理的迷宮」という方向には向かわないのである。

そして、こう考えると、当然気になるのは、本集中で「異色」作と読んでいい表題短編「爆発物処理班の遭遇したスピン」の位置付けである。この作品の「異色性=例外性」を、どう理解すればいいのだろうか?
答は、本作「爆発物処理班の遭遇したスピン」は、たしかに、他の短編のような「わかりやすい狂気」が描かれておらず、むしろ「論理性」を強調している点で、著者らしくない「本格ミステリ」的な味わいを持ってはいるのだが、しかし、やはりその本質は「暴力的な狂気」ということなのではないだろうか。
つまり、本短編は、佐藤究の作品としては「異色作」ではあったけれども、決して「例外作」ではなかった、ということである。
本作前半では、「酸素カプセルの中の人物」を救助すべく、爆発物処理班の面々が奮闘するが、しかし、物語の後半では、犯人の仕掛けた「もう一つの爆弾」に絡んで、くだんの「酸素カプセル」は、人が入ったまま、米軍に召し上げられることになってしまう。事が、高度に政治的な問題となってゆき、政府が、解決を米軍に委ねるしかないという判断をしたのだ。だから、現場の警察官である爆発物処理班の面々にとっては、本件は、否応なく手の届かないものになってしまった。
米軍に召し上げられた「日本人が入ったままの、爆弾の仕掛けられた酸素カプセル」と、新たに見つかあった「アメリカ人が入ったままの、爆弾の仕掛けられた酸素カプセル」は、ワンセットでの解決を必要とするものであり、「両方が無理でも、どちらか一方を必ず助けることができる」という性質のものではなかった。
そこで米軍は、二次被害を防ぐために、そして何より「量子コンピュータを使って、今回の前例を見ない犯罪を行った、謎のテロ組織」との「今後の対決」のために、「酸素カプセルの中の2人」の命を諦めることにする。その強烈な爆弾を無効化して、研究資料とするためには、爆弾の起爆装置の電池が切れるのを、数年がかりで待つしかない、という結論に達したため、中の二人をそのままにはできないから、ガスを送り込んで安楽死させることを選んだのである。

つまり、「極めて危険な、謎のテロ組織」による、今回のような「防ぎようのない犯罪」の今後の発生を考えれば、今回の2名の犠牲も「止むを得ない」という「合理的判断」をした、ということになる。
しかしだ。何の罪もない2人が、本人も気づかぬまま、国家の判断によって抹殺され、犠牲にされて、その遺骸は、爆弾の起爆装置が電池切れになるまで、腐るにまかせて放置され、埋葬されることもないのである。
しかも、当然のことながら、本件の真相は、極秘事項として家族にも世間にも知らされることなく、世間的には「爆発物処理班の失敗による爆死」ということことで、「合理的」に処理されてしまうのだ。
つまり、こうした「公安的な正義」というものの「冷たい合理性・論理性」というものを、無表情で冷徹な「暴力」であり、一種の「狂気」として描いたのが、本作「爆発物処理班の遭遇したスピン」だと、そう言えるのではないだろうか。
この作品に描かれた「狂気」は、シリアルキラーのそれとは完全に異質で、極めて「論理的」なものであり、その「暴力性」は、怪物のそれとは違って、実に「理性的」である。
だが、だからこそ、この「論理的で理性的な狂気」つまり「人間的な狂気」というのは恐ろしいし、そうした意味では、見かけこそ、全然違っているが、この短編こそが、最も夢野久作に接近した作品なのだと、そう言えはしないだろうか。
胎児よ
胎児よ
何故躍る
母親の心がわかって
おそろしいのか
(夢野久作『ドグラ・マグラ』巻頭歌)
胎児は、「父=国家」の「心=国家理性」がわかり、それがおそろしくて、踊らずにはいられない。
だが「酸素カプセルの中の男たち」は、踊ることさえ許されなかったのである。
(2022年7月29日 ※ タイトル下の日付「7月28日」は、未完成のものを誤ってアップした際の日付です。)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
