
panpanya 『蟹に誘われて』 : 〈乗り過ごし〉の恐怖体験とその癒し
書評:panpanya『蟹に誘われて』(白泉社)
2013年8月31日刊行の『足摺り水族館』から、2021年7月30日の『魚社会』まで、現在8冊の単行本を公刊しているpanpanyaの、本書は、2014年刊行の第2著書である。
つまり、プロとしての活動期間は、現在までの10年ほどだが、その中で本書は「初期」に属する短編集だと言えるだろう。
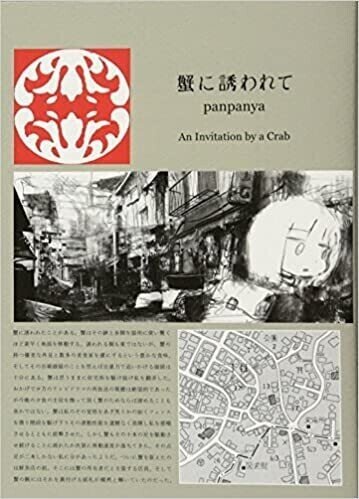
第3著書『枕魚』(2015年)のレビューでも書いたことだが、最近の作品と比べると、やはりその作風が微妙に変化してきているのが、本書でも確認できる。
(1)最近のものは「エッセイ」的な性格が強いが、本書では「オーソドックスな短編マンガ」的な作品が少なくない。
(2)語り手の「主人公」の少女が、最近の作品に比べると、どこか幼く可愛い感じがある。最近のものは(西原理恵子とまでは言わないが)どこか「おばちゃん」的な落ち着きが出てきた。
(3)主人公が迷い込む「迷宮的異界」に対して、主人公が「おびえ」を感じる作品がある(最近のものには、そういう負の感情はないに等しい)。
こんなところだろうか。一一つまり、ぶっちゃけてしまえば、作者が「大人になった」のであり、世界に対する無用な「不安や恐れ」を持たなくなったのが、作品にも反映しているのだと思う。
そして私は、この変化を肯定的に捉えている。
もちろん、本書所収の「オーソドックスな短編マンガ」的作品も面白いのだけれど、最近の「エッセイ」的な性格の強い作品の方が、この作家らしさがよりよく出ていて、個人的には面白いと思うのだ。
○ ○ ○
さて、私が、本書で注目したいくつかの作品の中から、ここではひとつだけを紹介しておこう。
それは、比較的長めの短編「方彷の呆」。
電車でウトウトしてしまい、乗り過ごしていることに気づいた主人公が、あわてて電車を飛び降りると、そこは見知らぬ駅。

反対方向の電車に乗って戻ろうとするが、真昼間であるにも関わらず、駅員は「今のが終電です」と、すげない返事。仕方なく主人公は、徒歩で帰ることにして駅を出、バス停を探すも、建物の壁に「バス停はない。」という奇妙な貼り紙があるだけ。不安になりながらも、やっとタクシーを見つけ、やれ助かったと思って近づくと、タクシーに運転手はおらず、しかもタイヤがすべてパンクしており、乗り捨てられたもののように見える。しかも、周囲には、そんなタクシーがたくさん駐められている。これは明らかにおかしい。まるで「お前はもう、うちには帰れないぞ」と言っているようではないか…。
一一ということで、この作品は「異世界に迷い込んだ主人公」の語る「迷い子奇譚」だと言えるだろう。
じつは本書は再読で、前に読んだのは、たぶん本書の刊行当時だと思うのだが、この作品がいちばんハッキリと記憶に残っていた。
というのも、私は幼い頃、似たような「乗り過ごしの恐怖体験」をしており、それがずっと忘れられないからだ。
幼い頃の私は、慢性の中耳炎を患っていて、罹っては治し罹っては治しというのを繰り返していたのだが、主治医の個人医院が電車で一駅の隣町にあったため、私は一人で電車に乗って、隣町の医院まで通っていたのである。私の町の駅は各駅停車しか止まらなかったが、隣町の駅は3路線が並列している乗換駅であり、特急や急行列車も停まった。つまり、行きは、来た電車に乗れば、隣町に着くのだが、帰りは各駅停車に乗らないと、乗り越してしまうことになる。
で、私の恐怖体験は、この「初めての乗り過ごし」であった。
慣れのせいで、各駅停車だと思って乗り込んだ帰りの電車が、特急か急行で、私が乗り間違いに気づいたのは、自分が降りるべき駅に電車が近づいたのに、電車がいつものように減速しなかったからだ。
その時「えっ?」と思っただけだったが、電車はそのまま駅を通過してしまい、私はその時になって、ハッキリと乗り間違いに気づいて焦った。次に止まる駅がどこかなど知らなかったが、とにかく次に停まった駅で反対側に乗り換えて引き返さなければならないと、そこまでは考えることができた。
しかし、車窓から電車が駅を呆気なくスルーし、さらに、これまでは車窓からは見たことのない、いつも歩いている(主観視点で見てる)自分の町を、車窓から(客観視点で)見るというのは、なんとも不安で悲しい気持ちだった。まるで、どこかへ連れ去られていく自分が、町に別れを告げているような気分になったのである。やがて、車窓外の風景は、知らない街並みに変わる。それがいつまでも続くのである。

早く次の駅に着かないかなと焦るのだが、電車はなかなか停まらず、いくつかの知らない駅を通りすぎてゆき、もう、このままどこにも止まらずに、どこか遠くの知らない場所へと連れ去られるのではないか、一一そんな不安におびやかされたのだ。
幸いというか、当然のことながら、電車はやがて、次の乗り換え駅に着いた。
私は電車を飛び降りると、戻りのホームへ行こうとしたが、まだ幼かったし、初めての駅だったから、どうしてそこへ行けばいいのかよくわからない。それで、ホームにいる優しそうな大人に「○○駅に行くには、どこから乗ればいいんですか?」と、何度も尋ねながら、やっとの思いで戻りの各駅停車の電車に乗ることができ、電車が、いつもの駅に止まって、いつもは乗り込む方のホームに降り立った時は、心の底からホッとしたのを今でも覚えている。それくらい、幼い私は、ずっと緊張していたし、おびえていたのだ。
こうした体験は、きっと軽いトラウマになっていたのであろう。大人になった私は、乗用車を運転したいとは、一度も思わなかった。
後から気づいたことだが、自転車やバイクとは違い、乗用車は、どこでもすぐに止まって、そこで引き返すということがしにくい。つまり、いちど道を間違えると、その先の交差点なり転回可能な場所までは進まないといけないことが多いのだが、こういうのが私は嫌いなのだ。自転車なら、間違ったと気づけば、すぐに逆戻りすればいいし、バイクなら間違って一方通行路に入ったところで、そこで止まって、バイクを押して戻ればいいわけだが、乗用車では、そういうわけにはいかないからである。
それでも、仕事の都合で、どうしても乗用車を運転しなければならなくなったことがあり、7、8年間、乗用車を運転したのだが、それでも「高速道路」は怖かったから、ほとんど利用しなかった。長い距離が一方通行で、逆戻りする場所がない。しかも、周囲を防音隔壁で囲まれていて、道を逸れることができないからだ。
私が、乗用車を運転するようになるずっと以前の若い頃に、SF作家・山野浩一の「メシメリ街道」という短編作品を読んでいるが、この作品の醸し出す恐ろしさは、まさにこうした「もどれない隔離感」だったと思う。

ともあれ、私にとっては、幼い頃の「乗り過ごし」体験は、このようにずっと残る、軽いトラウマになったようで、似たような話を読むと、作品の出来不出来に関係なく、決して忘れることはない。
例えば、マンガ家・模造クリスタルの長編『ビーンク&ロサ』では、主人公の一人で、うつ病気味のビーンクが、電車を乗り過ごして「もう帰れない」と落ち込むシーンがあるが、その気持ちが私にはよくわかった。
また、最近観た国産のホラー映画『きさらぎ駅』(永江二朗監督)も、電車でウトウトして、ハッと目をさますと、電車が見知らぬ景色の中を走っており、おかしいと思いながらも、次の駅である「きさらぎ」という聞いたこともない駅でおりてみると、そこは怪異現象が襲いかかる「異界」であった一一というお話であった。
つまり、私好みの「異界彷徨譚」ではあったのだが、いかんせんこの映画は、いかにも安っぽい凡作だったので、観た映画については、たいがいはレビューを書いている私も、これについては書くだけ時間の無駄だと、レビューを書かなかった。

で、こうした「電車を乗り過ごし、あわてて飛び降りた駅は、異界の入り口であった」というのは、(筒井康隆の短編に「乗越駅の刑罰」なんて作品もあるし)意外と多くの人が潜在的に抱えている恐怖のパターンのひとつなのかなとも思うのだが、panpanyaによる短編「方彷の呆」は、そうしたパターンの作品には珍しく、最後は「泣かせる話」になっており、読み返してみて、私のトラウマを癒す方向での傑作だと感心もし、再び感動したのであった。
いろいろな作品が収められている本短編集だが、個人的には、こうした理由で、特にこの「方彷の呆」を、多くの人に読んでほしいという気持ちを禁じ得ない。
(2022年9月11日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
・
