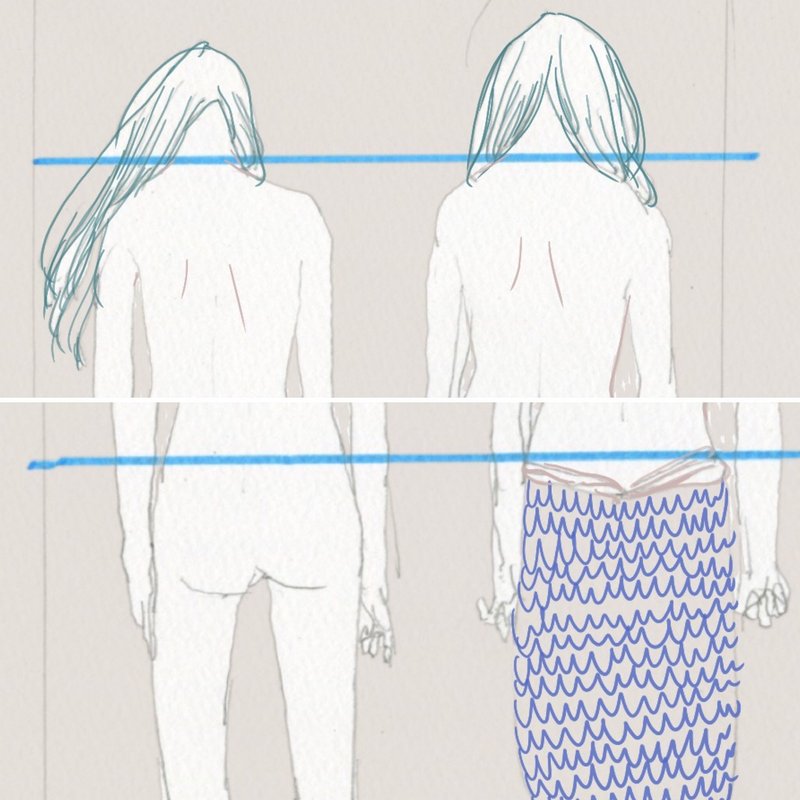#エッセイ
ビジネスモデルとしてのアートとアイデンティティの喪失、およびアートの市場原理主義的志向から見る批評の可能性について
マイケル・フィンドレーは自著『アートの価値』にて、アーティストはマーケットに意図的に参画することにより自己同一性を失いつつあり、それにより作品そのものの「意味」は喪失し、しばしば他の商品と代替可能であるという「抽象性」を持つとした。
ただしそれはアガンベン的な「なんであれかまわないもの」としての個物ではなく、そのものの個々の独立性を失ったものとしての「商品」としての作品であり、そこに存在するもの
なんかそろそろのアレなのでというお話(2019年の展覧会、良かった本など)
さて年の瀬になりましたが、なんだか色々と間に合いそうに無いので、今の時点でできることを書いておきます。今これを読まれているあなたにとって、2019年はどんな年でしたでしょうか。
私は、そうだなあ、色々なセレンディピティに出会って自分自身を取り戻せたと言うか・・めっちゃ平たいこと言ってしまった。
駆け足になりそうですけど、今年よかったものなどを振り返ろうと思います。
今年よかったなあと思った展