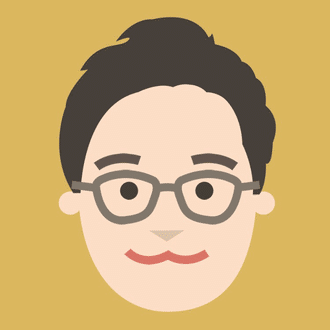自分の記事とどう向き合う? noteをヘルシーに「続ける」ための考え方
「自分で作った作品は子供みたいなもんですね」
こんな言葉を見聞きすることがあります。仕事柄、商品開発をしていると似たようなことを聞くことも多いです。マーケッターの担当者は心血注いで商品を生み出します。その過程で愛情が注がれて、そのたとえが「子供」という比喩になるのかなと思います。
また、アーティストや芸術家の話でも生み出した作品を「子供」というたとえで表現したりするのは聞いたことがあるのではないでしょうか。
そして、このnoteもそうですね。記事という作品を世に送り出すという意味ではアーティストのそれと同様の側面があります。
「この考え方、ちょっと危険かも」というのが今日のこの記事のメッセージです。なぜ記事を子供と例えるのが良くないのか。自分の記事との向き合い方を考えてみます。
自分の記事をどう捉えるか
これは特にnoteをはじめて間もない方にはぜひお伝えしたいことです。今私は1年前の自分に伝えるつもりで書いています。
結論から言うと、自分の記事を子供の様に考えるのはやめましょう。
私がnoteを書き始めたのは昨年の4月です。その頃はnoteというサービスも良く分からずに、とにかく何かをアウトプットしたいという想いがありました。そして初めて書いたnoteはえらく緊張して書いたのを覚えています。
はじめの頃に書いた記事は「公開」ボタンを押すのがとても怖かったです。まるで自分の子供がスクールバスに乗って出発するような感覚。大丈夫かな?、身なりはちゃんとしてるかな?、人様に失礼はしないかな?、など色々不安でした。
そして結果どんなことが起こるか。ビューもスキもつかない記事を量産することになります。これは当然のことですよね。著名人でもない一般人の自分が初めから注目を集まられるはずもありません。でも、「なぜ?」「どうして評価されないの?」と不安になったり、絶望したりします。その時に、「記事=自分の子供」と考えていると、精神衛生上かなりキツくなってきます。なんせ子供が無視されているということですからね。軽いイジメにあっているようなものです。これは親は悩みます…。
仮に、自分の記事が誰かにディスられたり炎上したらどうでしょうか。noteは比較的そういったことは起こりにくい創作活動のフィールドですが、全く無い事もありません。その時に「自分の子供」と考えていると、その記事に向けられた矛先を自分に結び付けて自分に向けることになります。
さらに、自分が作った記事(子供)が部分的に切り取られ加工されたりすると、自分の無力さを感じたり、「こんなnoteなんかやめてやる」と創作活動を続けるモチベーションまで下げかねません。
だからこそ「自分の記事は自分の子供ではない」と捉えておくことが大切です。
自分こそが「子供」
記事は自分の子供ではありません。私はその逆だと思ってます。つまり自分こそが「子供」であると。これは創作活動を続けていくうちに芽生えた感情です。日々生み出していく記事や創作物が下支えして今の自分があると強く思います。
つまり、記事や作品によって生み出されたのが今の自分。自分こそが「子供」なんじゃないかと思います。生み出した記事たちは少しずつ、でも確実に自分を成長させてくれています。今まで生み出してきた記事無くして今の自分はない、そう思えます。
こう考えると、記事に対しては過剰な想いを込めることもなくなります。最新にアップデートされているのは子供である自分だからです。自分が成長する中で考えや意見は変わります。過去の自分がアウトプットしたことは時代を経て合わなくなってくることもあるでしょう。それはそれで良いのです。自分が最新ならそれでよい。そう割り切ってアウトプットするととても気が楽になるのではないでしょうか。
楽しいのはいつからか?
noteは創作活動を続けるフィールドです。この「続ける」というのが結構難しいところです。
続ける上で大切な期間が「インキュベートの法則」と呼ばれる21日間です。一般的にどんな習慣も21日続けば習慣化できると言われます。つまり、大体のことは3週間頑張って毎日続けば、習慣化し、恒常性が働き逆に続けないと気持ち悪くなるということです。この仕組みをうまく活用するのがよいです。
とはいえ21日間は結構な期間です。なかなか続かずに辞めてしまうケースも多いと思います。それはとても残念なことだと心から思います。
記事を日々書いているとすごく注目される記事とそうではない記事があります。そして、その感覚は見事に自分の感覚と逆だったりします。渾身の思いで書き綴った大作だと思った記事が全然評価されなかったり、ふと思ったことを気軽に書いた記事が多くの共感を得たり、周りの評価はなかなか読めないものです。
そして、渾身の思いで書いた記事が注目されないことが続いた時に感じるのが「徒労感」です。「あれだけがんばったのになぜ・・・」と落胆にも似た気持ちに押しつぶされそうになります。ここでだいたいの人が創作をやめてしまいます。
でも、そこで是非踏ん張ってほしいです。なぜなら、面白くなってくるのはそこからだからです。これはどんなスポーツも同じです。はじめからうまくできることってハマりませんよね。「なぜできないんだろ?」からスタートして、「どうやったらうまく行くのかな」と考え始めるところが出発点です。そこからそのスポーツの奥の深さを味わっていく。初めには見えてなかった世界が少しずつ見えていく。そこが面白いのです。
「うまくいかないな…→だからやめよ」ではなく「うまくいかないな…→ここから面白くなるぞ!」なのです。その過程で自分が成長していくのだと思います。
大切なことは「工夫をする」ということ。そして「もがくプロセスを面白がる」マインドセットかなと思います。
まとめ
今回はnoteをこれから続けて書こうと思っている方向けの記事だったので、読む方を選ぶ内容だったかもしれません。でも、記事との向き合い方一つで続くものも続かなくなるので、是非伝えたかった内容を記事にしました。
300日間毎日書き続けて思うことは記事に価値があるというよりも「続ける」ことそのものに価値があるのではないかと思います。創作し「続ける」ということは、何かを学び「続ける」ということ。そしてそれは自分が変わり「続ける」ということだと思います。
noteをはじめて間もない方は、「何を書くか」よりも、「どう続けるか」を考えた方が良いです。商品開発の世界では「量が質を生む」という言葉があります。良質なアイデアは大量のボツアイデアの上に成り立っているという意味です。つまり、続けて数をこなす内におのずと質は上がっていくということですね。
そして、記事を「自分の子供だ」と情熱を注ぎ過ぎずに、自分と切り離して考えた方が良いです。過去の記事と今の自分を結び付けすぎると、その記事がアンカー(錨)のようになり、身動きがとりにくくなります。
過去に書いた記事はあくまで過去の自分が書いたものです。今の自分はもっと進化しているはずです。昨日、「風の時代とは」という記事も書きました。タンポポの種のように、できるだけ軽く、身軽に自分を捉えた方が今の時代にもマッチして良いと思います。
なるべく気軽に創作を「続ける」工夫をして、ヘルシーに自己成長を楽しめたら良いですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
【最後に(お知らせ)】
サークルを始めました。サークル未経験者でも安心して楽しめるサークルです。こちらの記事をご覧いただき、興味のある方はご参加下さい😌
いいなと思ったら応援しよう!