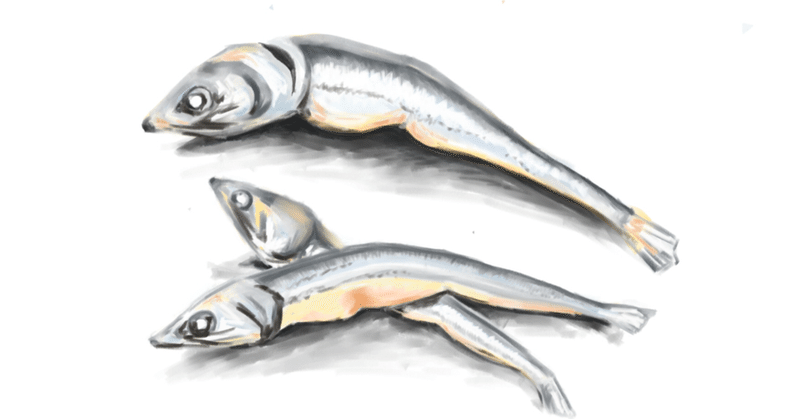#海外生活
らせん状に流れる日々。
生活サイクルを丁寧に回せば人は「成長」する、というのはどうやら本当の話らしい。しかも年齢は問わない。ただ、そのサイクルを回すにあたっては自分の感覚を信頼してやる必要がある。
2年ほど前から趣味で筋トレを継続している。ジムでの筋トレ愛好家との話題はもっぱら「負荷」についてだ。どのような種目を、何セットぐらい、どんな順番でメニューを組むのが筋肉の発達にとって最適かといった話題が大半だ。効果的な負荷の
転職して、「他人の評価」というモノサシは「納得感」に変わった。
「仕事ができない」と言われる人の中にも本当に思いやりのある方は沢山いるし、逆に「仕事のできる」人の中にも人間的には参考にしたいと思えない方も沢山いる。
仕事で結果が出ないからといって、ぼくらの人生や人間性が損なわれるべきではないし、ぼくらの人生には仕事のほかにも大切なものが沢山ある。
このような見方ができるようになったのは数年前に大企業から小さな会社へ転職してから。
大企業に入る人というのは
ぼくは、怖くて仕方ない方の道を選びました。
・「平均点の高い」「均質な」人材育成を狙った高等教育を受ける。
・出来るだけ大きな会社に入って将来を安泰に過ごす。
もう20年以上前の話だ。
こんなギチギチの狭い価値観の上に築かれたレールの上を行くこと、それが日本社会での成功体験とされていた。改めて言葉に起こしてみて、時代は大きく変わったと実感する。
かく言うぼくも、そのレールの上をひた走っていた。人よりも「早く」「効率的に」「上手