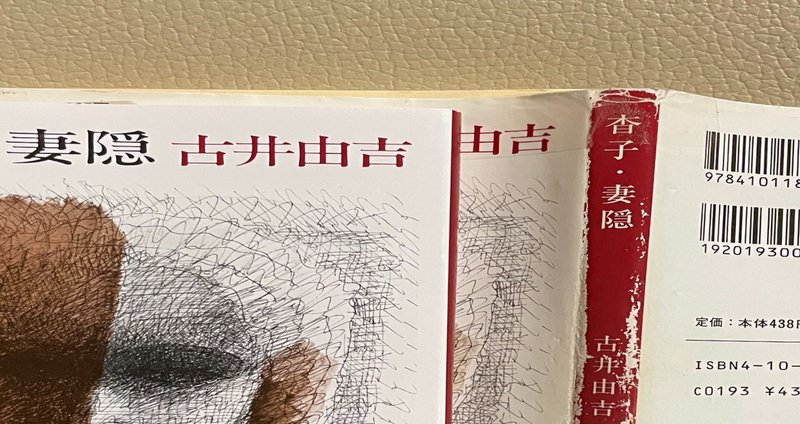2024年11月の記事一覧
型を壊す、型が壊れる
*はじめに
「ジャンルを壊す、ジャンルを崩す(言葉とイメージ・07)」の続きです。
今回は、藤枝静男と古井由吉が自分の小説をどのように壊していったか、その小説がどのように壊れていったかについて、私の考えを述べます。
ここで言う「壊す」と「壊れる」は悪い意味ではありません。詳しくは「ジャンルを壊す、ジャンルを崩す(言葉とイメージ・07)」をご覧願います。
小説は散文で書くものですが、散文
始まりと途中と終わりのあるものを、始まりと途中と終わりのないものとして読む(散文について・05)
違う連載の記事ですが、「「どこでもない空間、いつでもない時間」(「物に立たれて」を読む・08)」の続きとして書きます。
「壊れていたり崩れている文は眺めているしかない(散文について・01)」の続編でもあります。
*はじめに
みなさんは、ある種の短詩、たとえば俳句をどのように鑑賞なさっているでしょうか?
俳句であれば、五七五です。短いです。短いからこそ、できることがあるように思います
「どこでもない空間、いつでもない時間」(「物に立たれて」を読む・08)
*「転々とする、転がる、ころころ変わる(「物に立たれて」を読む・06)」
*「客「である」、客「になる」、客「を演じる」(「物に立たれて」を読む・07)」
古井由吉の『仮往生伝試文』にある「物に立たれて」という章を少しずつ読んでいきます。以下は古井由吉の作品の感想文などを集めたマガジンです。
*
引用にさいしては、古井由吉作の『仮往生伝試文』(講談社文芸文庫)を使用します。
壊れていたり崩れている文は眺めているしかない(散文について・01)
今回は「ジャンルを壊す、ジャンルを崩す(言葉とイメージ・07)」の続きです。
「散文について」という連載を始めます。私は一般論やなんらかの分野の専門用語や学術語には疎いです。そんなわけで、ここでは私にとっての散文と小説について書きます。
*最初から壊れている
文学史的なことは知りませんが、私にとって散文とは最初から壊れているものというイメージがあります。
何をどんなふうに書いてもいい形
客「である」、客「になる」、客「を演じる」(「物に立たれて」を読む・07)
*「「物に立たれて」(「物に立たれて」を読む・01)」
*「月、日(「物に立たれて」を読む・02)」
*「日、月、明(「物に立たれて」を読む・03)」
*「日記、日記体、小説(「物に立たれて」を読む・04)」
*「「失調」で始まる小説(「物に立たれて」を読む・05)」
*「転々とする、転がる、ころころ変わる(「物に立たれて」を読む・06)」
古井由吉の『仮往生伝試文』にある「物に立たれて」とい
転々とする、転がる、ころころ変わる(「物に立たれて」を読む・06)
*「「物に立たれて」(「物に立たれて」を読む・01)」
*「月、日(「物に立たれて」を読む・02)」
*「日、月、明(「物に立たれて」を読む・03)」
*「日記、日記体、小説(「物に立たれて」を読む・04)」
*「「失調」で始まる小説(「物に立たれて」を読む・05)」
古井由吉の『仮往生伝試文』にある「物に立たれて」という章を少しずつ読んでいきます。以下は古井由吉の作品の感想文などを集めたマガ