
◆読書日記.《『昭和陸海軍の失敗 彼らはなぜ国家を破滅の淵に追いやったのか』》
※本稿は某SNSに2020年10月30日に投稿したものを加筆修正のうえで掲載しています。
半藤一利、秦郁彦、平間洋一、保阪正康、黒野耐、戸髙一成、戸部良一、福田和也、の8人による対談集『昭和陸海軍の失敗 彼らはなぜ国家を破滅の淵に追いやったのか』読了。
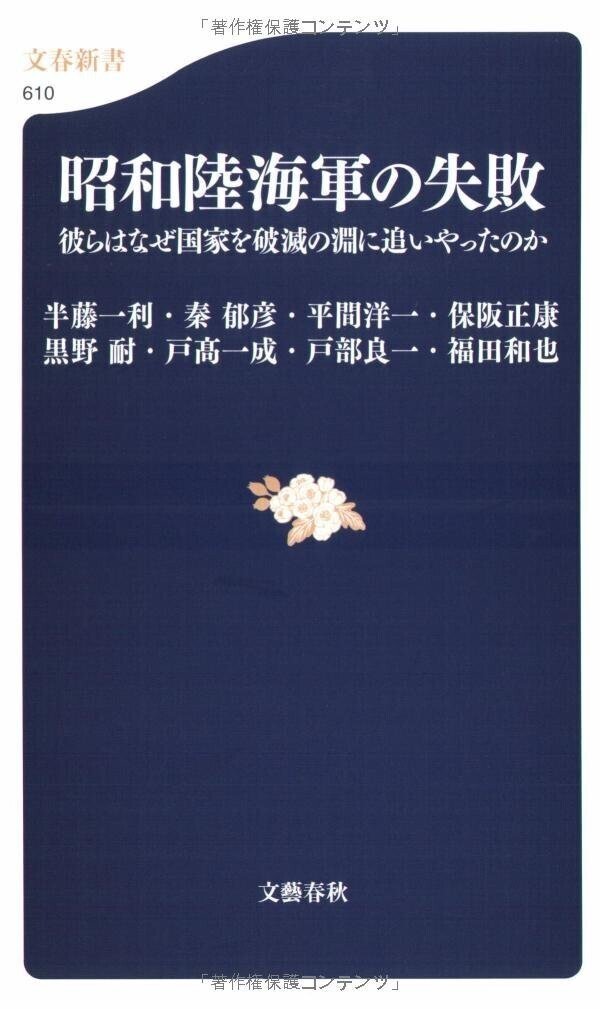
戦史研究を行う8名の識者による大日本帝国の陸海軍の問題点について「個々の人材」という視点を元に話し合う対談集。
本書は2007年に「文芸春秋」誌に掲載された2つの対談記事をまとめたもので、8人同時に対談したのではなく、まず陸軍について5名が、そして海軍について5名が集まって対談を行ったものである。
ちなみに両者の対談とも出席しているのは『日本のいちばん長い日』で有名な昭和史研究家の半藤一利である。
対談の参加者は戦史研究家、防衛大教授、日本大学講師、昭和史研究家、文芸評論家、ノンフィクション作家、に加えて元自衛隊海将、陸将補など、戦前の軍人に直接かかわっていた人物も含めた研究者らが並ぶ。
戦前の日本軍について組織的な問題点を考察する書籍は多いものの人材に焦点を当てたものは珍しい。
◆◆◆
この対談を読んでいるとどうも「鶏が先か卵が先か」の問題を思い浮かべてしまう。
作られた組織の性格が個々の人材をダメにしていくのか、それとも集まった人材がダメなので組織構造そのものをダメにしていくのか。
本書では組織ではなく人材のほうに焦点を当てていたが、結局は組織的な弱点がどうしても関わってくるのだ。
何よりも感じるのは、大日本帝国というのは全く一枚岩ではなかったという事。
日本は同一民族で宗教的な対立も人種的な対立もない国で国民がまとまり易い。まとまり易いにも関わらず、その内部では細かく派閥が分かれて足を引っ張り合い、手柄を主張し合い、既得権益を奪い合うような対立を生み出してしまう。
先日ご紹介した野島博之『謎とき日本近現代史』でも指摘されていたが、大日本帝国の組織というのは天皇の元に平等という考え方なので政府も軍隊も平等でどちらかがどちらかに対して指示監督できるような権限が与えられていない。
所謂政府によるシビリアンコントロール(文民統制)ができないような組織構造を持っていたのだ。
となると当然、軍隊は軍隊で自分の利益を追求し、自身に都合の良いような行動に出てしまうし、それを政府が抑制しようとしてもできるものではない、という状態にあった。
このような状態にあるから帝国の組織は組織ごとにやってる事がちぐはぐで全体的な視野に欠け、個々の利益を追求して長期的な視野が欠如していた。
◆◆◆
けっこう前に菊澤研宗『組織の不条理 日本軍の失敗に学ぶ』という本をご紹介したが、この本に書かれていた戦中の帝国組織の問題点について「限定合理性」の考え方から説明していたのが実に面白かったのを覚えている。
人間は完全に合理的には考えられない。だが、そうかといって完全に非合理的にも考えられない。組織の原子たる個人個人は限定的な情報や個人的な事情といった「個別の条件の中で合理的に行動する」というのが「限定合理性」の考え方だ。
これは新制度派経済学の考え方による組織論の学説なのだそうだ。
組織人として行動する個人は、全体的な視野を持てるものではない。
自分たちとは別の部署や別の組織の条件が分かっているわけではないし、他の専門分野を担当する部署の人びととも視野が当然違っていて、そのために持っている情報も違えば考え方も違ってくる。個々人はそういった限定的な視野で仕事をしているのだ。
だからこそ組織はスペシャリスト(専門職)だけでなく、全体的で長期的な視野で物事を考えられるジェネラリスト(総合職)が重要となってくる。
しかもそれは組織が大きくなればなるほど重要性が増してくる。しかし、戦前の軍隊にはどうも決定的にこのジェネラリストの養成に欠ける部分があったようなのだ。
◆◆◆
本書には陸軍大学校の問題点が幾つか指摘されている。
戦前の陸軍士官学校というのは士官の養成学校であり、この陸軍大学校というのはそれ以上の指揮官を養成するために参謀教育をする学校であった。
しかし、この陸大の問題はあくまで「参謀用教育」である戦術中心主義という伝統があったという点にある。
陸大創立当初は陸軍のジェネラリストとして大山巌や児玉源太郎などのそれ以前からの軍の大立て者らが戦略面を考えていたので、陸大出身者たちは参謀に徹していたのだが、それ以後に昭和に入って総力戦の時代に移行して以降もこの戦術中心主義的な教育方針は変わる事がなく、戦略的な視野が育まれてこなかったという。
陸大出身者は広い視野を獲得できるような教育を行ってこなかったのだ。
また、陸軍の組織としても陸大の出身者の中でも陸軍幼年学校から陸軍に関わっている人材が優遇されるという仕組みが出来ていたようだ。
例えば陸大出身の将校でも、中学校を卒業してから士官学校に入学した栗林忠道中将、今村均中将、本間雅晴中将といった将校たちは、戦後になっても評価されるような優秀な人材であったにも関わらず、「中学卒業を経てからの陸大卒業者」という条件で陸軍省や参謀本部などの軍の中枢に関わった人間はほとんどいなかった。
硫黄島防衛戦で6万のアメリカ軍を相手に2万人の兵士で一カ月弱も連合軍を足止めした事で有名な名将・栗林中将は陸大を2番で卒業した秀才だった。
陸大で優秀な成績を修め、人望も厚かった栗林中将でも中学からの士官学校入学組であったために軍の中枢には近寄れなかった。
栗林の弟から「中学から士官学校を受験したい」と相談された際、陸士では幼年学校卒業者が優遇されるからやめておけ、もっと勉強して海軍兵学校へ行けとアドバイスしているくらいである。
幼年学校から陸軍に関わり、軍の中枢を担っていく事となる人材は、その事で更に視野を狭めていく事となる。
彼らは軍人志望の人間のみで固まって交友関係を作ってしまうので、外の空気を知らずに育ってしまう事となる。
世間一般の感覚とも乖離してくるし、外交や政治や国際情勢など他分野の情報に疎くなってくる。
所謂「世間知らず」になる。
陸軍幼年学校出身者と言えば陸軍大臣を経験した畑俊六や首相経験者である東条英機などもそうだったが、彼らは東京裁判の時に九か国条約違反、パリ不戦条約違反、といった彼らに示された罪状について、それら条約の詳細について何も知らなかったという。
ちなみに、畑も東条も決して無能ではない。
畑は陸大を首席で卒業しているし、東条も陸軍では切れ者として有名だった。
終戦時に大本営の参謀を務めていた朝枝繁春中佐などは陸大の教育は「なってない」とバッサリ切っているという。
「なにしろ全てが他律主義で、上から言われたことだけをするように教育され、本来柔らかかったはずの自分の頭がどんどん固くなって、融通がきかなくなっていく、前の時代のやり方を踏襲するような思考法しか教わらなかった、というのです」との事。
こういった人材で作られた組織というのは、改革を主張する者や良識派というのはパージされたり孤立したりするようだ。陸軍としては稀有な戦略的視点を持っていた石原莞爾もそうだった。
因みに石原莞爾も幼年学校を卒業し士官学校を経て陸大に入学、そして次席卒業という秀才であったが、それでも視野の広さは同じ陸大出身の東条英機と比べるべくもなかった。
石原は陸大に行っていたとは言えども授業はほとんどサボって、外で様々な本を読んでいたと言われている。
軍事以外にも歴史や哲学や宗教なども勉強していたそうで、東条などとは価値観が違っていて当たり前だった。
それでいて試験となると直前にざっと勉強して楽々パスするような能力の持ち主だったため、そういう要領の良さなんかも、コツコツ努力型の秀才であった東条英機から毛嫌いされた理由の一つだったのかもしれない。
◆◆◆
「能力よりも人間関係」というのは、今も昔も共通して見られる日本型組織の傾向なのかもしれない。
石原莞爾ほどの能力があり、参謀時代にも満州事変を成功に導いた実績も作っているにも拘らず、軍人仲間からはけっこう嫌われていたそうで、最終的には犬猿の仲だった東条英機によってクビ(予備役)にされてしまう。
これは今の日本の組織でも変わらない事なのだろう。
「個人的にどれほど嫌いな人物でも、客観的に評価が高ければ人事評価を上げる」といった公平な評価ができる管理職などほとんど見たためしがない。
これも「限定合理性」だ。会社全体の利益を考えるのではなく、自分個人の判断を優先させてしまうのである。
また、上述のように陸軍幼年学校~陸大出身者で固められた陸軍の中枢が一枚岩となって力を発揮したかというとそうでもなく、皇道派と統制派に分かれて足の引っ張り合いをしていたりと派閥闘争も発生している。
しかも、そういった派閥で固まるから作戦で甚大な被害が出ても身内でかばいあってしまう事となる。
例えばノモンハン事件でソ連軍に大敗北を喫した服部卓二郎と辻正信のコンビは責任を取らされることもなく再び参謀本部に戻ってくる。再びガダルカナル作戦で戦死者二万五千人という甚大な被害を出した責任を取り、いったん東条英機の秘書官に転属されても、十カ月あまりでまた参謀本部に戻ってきてしまう。
つまり、陸軍の人事は全くもって合理的ではなかったのだ。
これは海軍も例外ではないだろう。
ミッドウェー海戦で大敗北を喫した際、命からがら戻ってきた南雲忠一中将は山本五十六司令長官に対してヌケヌケと「もう一回、自分達に名誉回復の機会をくれ」と訴えるし、山本も「よかろう」等と許してしまっている。
山本五十六が自らの責任と感じていたら、南雲中将に「よかろう」等と言えたものではない、と本書の対談でも批判されている。
海軍も山本五十六に責任を取らせる事はできなかった。陸軍も海軍も、仲間内では無責任体質が板についてしまっていて、責任を取らせられるのは孤立した「良識派」「改革派」くらいだったのだ。
◆◆◆
上述してきたような、良識派や改革派というのは組織の中で孤立しなかなか出世できない、合理的な人事評価ができず個人的な好き嫌いや人間関係で評価が決まってしまう、合理的な人材配置ができない、派閥の仲間は合理的に処断できない無責任体質……こういった戦前の陸海軍の組織的弱点といったものは現代の日本の組織にも当てはまる点が多々見られるのではないだろうか。
大きい組織であればあるほど、こういった弱点を見る事ができる。
事実、ぼくが以前紹介した山崎豊子の『沈まぬ太陽』から見るJALの体質や、大鹿靖明『東芝の悲劇』の東芝の組織風土、池井戸潤『空飛ぶタイヤ』に見る三菱自動車の体質などなど……日本の大企業の凋落にも似たような欠点が見られた。
という事はこれは、日本人の気風や組織風土に根付いている特徴なのかもしれない。
「歴史」を軽視するという事は、こういった昔から続いている弱点についても反省する事ができないという事だ。
「過去の歴史を反省する」という事は、歴史修正主義者が目をそらしたがるような「過去の汚点を見る事」ではない。
「同じ過ちを二度三度と繰り返して起こさないように、何が悪かったのか、どういう要素が失敗に結びつくのか、その要因を考えて次の事態に備える」ために行うのだ。それをするためには、しっかりと過去の失敗を認めて、過去の失敗事例と向き合って、分析しなければならない。
現代の日本人も、能力とは関係なく仲間という理由だけで優遇したり失敗をかばいあったりするような非合理的なネポティズムがないか?
一度組織が決定した事はどれだけ犠牲が出ても中止する事ができない「インパール作戦」的な硬直性はないのか?
好き嫌いで人事が決まってしまう非合理的な人事制度になっていないか?
こういった点を考えてみれば、戦前陸海軍の組織的な弱点を現代人が「もう過ぎ去った事」だとか「他人事」だとして看過してしまう事などできないのではないか。
「歴史」というものは、二度三度同じ失敗を繰り返さないための貴重な事例集なのである。
単なる「物語」的なものではなく、切実に自らに関わる前例と思って教訓化すべきであろう。
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
