
◆読書日記.《J・G・バラード『ハイ・ライズ』》
<2024年1月10日>
<あらすじ>
ロンドン中心部に聳え立つ、知的専門職の人々が暮らす新築の40階建の巨大住宅。1000戸2000人を擁し、マーケット、プール、ジム、レストランから、銀行、小学校までを備えたこの一個の世界は事実上、10階までの下層部、35階までの中層部、その上の最上部に階層化されていた。その全室が入居済みとなり、ある夜に起こった停電をきっかけに、建物全体を不穏な空気が支配しはじめた。3か月間にわたる異常状況を、中層部の医師、下層部のテレビ・プロデューサー、最上階の40階に住むこのマンションの設計者が交互に語る。バラード中期の傑作。
<編著者略歴>
J・G・バラード
――――――――――――――――――
英国を代表する作家。1930年、上海生まれ。「人間が探究しなければならないのは、外宇宙(アウター・スペース)ではなく内宇宙(インナー・スペース)だ」として、SFの新しい波(ニュー・ウェーヴ)運動の先頭に立った。終末世界を独自の筆致で美しく掻き出した<破滅三部作>と呼ばれる『沈んだ世界』『燃える世界』『結晶世界』や、濃縮小説(コンデンスド・ノベル)と自ら名づけた手法で書き上げた短編を発表し、その思弁性が多くの読者を魅了した。本書『ハイ・ライズ』はベン・ウィートリー監督、『太陽の帝国』はスピルバーグ監督、『クラッシュ』はクローネンバーグ監督によって映画化されている。他の著作に『時の声』『溺れた巨人』『人生の奇跡 J・G・バラード自伝』など。2009年没。
ジェイムズ・グレアム・バラード『ハイ・ライズ』読了。

1960年代、イギリスSF文壇で「ニュー・ウェーヴ」と呼ばれた新しい流れの中心人物の1人と呼ばれたバラードの中期「テクノロジー三部作」の一作。
というわけで皆さま、明けましておめでとうございます。
新年はキリリと冷えた空気の中で美しい文章の小説を読むのが、近年自分の中の習わしになっているのだが、本年はいろいろと迷った末にバラードにしたという次第。
バラードは、長編『クラッシュ』はぼくの中ではオールタイムベスト級の傑作だと思ってこの作品を読んで以降、気になる存在だったのだが、何故かその後、代表作の『結晶世界』と若干短めの長編『殺す』ぐらいしか読んでいなかった。
この人の作品は「ストーリー」をあれこれ説明する事にはあまり意味を感じない。そもそもバラード自体、そういうものを重要視している風ではないのだ。
実際、この人の作品はどれを読んでもストーリーは紆余曲折するようなものはなく、一本調子で意外な展開もどんでん返しもない。
たいていは、当初の状況が徐々に徐々にエスカレートしていくというだけの話に終わる事が多い。
そういう「筋の意外性」とは無縁の作家と思ったほうが良いだろう。バラードに、そういう所を期待してはいけない。
本作もその例外ではない。
本作の「テーマ」となり「舞台」となるのは、<あらすじ>にあるように「ロンドン中心部に聳え立つ、知的専門職の人々が暮らす新築の40階建の巨大住宅」である。
この巨大高層マンションは川岸に建っており、ロンドンはその川一本隔てて向こうに隔絶されてあり、このマンション以外に周囲にはほぼ何もない状態である。
それは文字通り「周囲から隔絶された小都市」のごとくであり、まるで陸の孤島のように、その高層マンションはその建物一個で完結した世界となっている。
そのような環境であるから、このマンションは「1000戸2000人を擁し、マーケット、プール、ジム、レストランから、銀行、小学校までを備え」ており、住人は普段の生活のほとんどをこのマンションの中で完結させているのである。
彼らは、勤め人が会社に出勤する時以外はほぼマンション内での生活がメインになっているのである。
主婦は子供を小学校まで送ったらプールやジムで運動をし、マーケットで買い物をし、レストランで昼食をとり、近所の友人宅に呼ばれてお茶などをする。 休日になると、特に高層階の住人らはホームパーティを開いて騒ぐ。
仕事に行く以外のほぼすべての生活が、この一個の巨大な建築の中に納められているというわけである。
本作が発表された1975年という時期を考えると、この集合住宅構想は「SF」と呼べるような最先端の技術だとは思えない。当時の集合住宅を多少、規模を大きくしただけのさほど珍しくない集合住宅である。
例えば、ぼくなんかは本作に出てくる高層マンションは、ル・コルビュジエのユニテ・ダビタシオンを連想させたものだ。

ル・コルビュジエのユニテ・ダビタシオンの中でも最も有名なのがマルセイユにあるものだが、これは8階建てで337戸あり、最大1600人ほどが居住可能な集合住宅であった。
この集合住宅にはレストランや商店、郵便局、保育園、体育館、プール等が併設されている。まさに本作に出てくる巨大集合住宅をコンパクトにまとめた施設といった感じである。
で、このマルセイユのユニテ・ダビタシオンが竣工されたのが1952年。
バラードが「SF作家」という肩書を持っているので勘違いしてしまうかもしれないが、本作の執筆時期の70年代から見ても、この40階建の巨大住宅は、多少巨大ではあっても「未来の建物」というほどのものではない、現実的な建物だったというわけである。
つまり、本作は70年代に書かれた「未来予想」的なお話ではなく、当時のバラードからしてみれば「現代的な問題」としての高層マンションという舞台だったと思われるのだ。
◆◆◆
本作を読み始めた当初は、バラードがどういうスタンスで書いているのか、かなり戸惑ったものである。
本書はちょっとしたマンション内のいざこざから始まる。
それは、例えば「故障しがちのエレベーターと空調、原因不明の停電、騒音、駐車スペースの奪い合い(P.26)」といった些細ないざこざで、これも割と日本の現代のマンションでもありがちないさかいである。
ぼくも以前住んでいたマンションで、管理組合の会合に出席した際はこの手の問題がけっこう頻繁に発生しているというのを管理人さんから聞かされたものである。
深夜に上からスリッパの音が聞こえてくるとか、休日に共用部で子供が騒いでいてうるさいとか、バルコニーにタバコの臭いが漂ってくるとか、マンション前の道路の路上駐車のマナーだとか、ごみ捨てのマナーだとか、共用部のどこそこにタバコの吸い殻が捨ててあっただとか、そういったものである。
つまり、本書の冒頭に出てくる住人たちの争いというのは、割と生々しいリアルな状況だったわけである。
多少、違和感を抱いたのは、この高層マンションに住む人々が、かなり頻繁にご近所づきあいを行っており、交流が非常に活発だったという事だろう。
日本のマンションでは、これほど近所の人たちと頻繁にホームパーティを開いたり、近所の人たちと交流を持って部屋に呼んだりお呼ばれしたり、等という事はないのではないだろうか(まぁぼくはご近所づきあいがニガテなほうなのでそう思ってるだけかもしれないが)。
この「ご近所との付き合いの濃さ」が、マンション内に様々な派閥を作って後にこのいざこざを大きくしていく原因になるわけである。
が、ぼくが感じたこの違和感も、日本と英国との文化の差と言ってしまえばそうかもしれず、「非現実的」と呼べるほどのものではなかった。
マンションの施設はその執筆当時でも成立しうる現実的な設定で、マンション内の住人たちの行動も説明できるおよそ現実的なものであった。
だから、ぼくは当初、この作品は「現実的な舞台でリアルに"こういう状況が起こりうる"というシミュレーション的な構想で作った思考実験的な小説」なのかな?という理解で読んでいたわけである。
だが、この物語は状況がエスカレートしていく毎に、あまりに非現実的な、ヘンテコな自体に発展していくのである。
◆◆◆
まずこの高層マンションの住人らは、19世紀末にギュスターヴ・ル・ボンが提示した、いわゆる「群集心理」のままに暴走していく事となる。

「群衆」とは近代に入って初めて現れた。中世ヨーロッパに、「群衆」はいなかったのである。
中世ヨーロッパの約9割の人間は農村に住んでいた。彼らはほとんど互いに顔も名前も知っている中で生活をしており、何かしら集団で行動する場合は、そういう顔なじみの人間らとして組織となった。
近代に入って、農村から離脱した人々が都市部に流入して来た。そんな彼らは一人一人が顔なじみで名前も知っている間柄ではなく、様々な出自の「知らない顔の人たち」が一地域に集中していた。
彼らは自分の顔と名前とその身分を周囲の人間らに知られているという環境の農村共同体から切り離され、都市部での生活に入ると、互いにどういった人物かも良く知らない多くの人々で成り立つ「群衆」となったのだ。
農村部に住む中世ヨーロッパ的人民と違って、近代的な都市の人民とは「匿名性・無名性」をその特徴としていたわけである。
「匿名的」な近代ヨーロッパの住民は、その無名性を利用して犯罪を犯すと、匿名の群衆の中に紛れてその身を隠した――探偵小説というものは、こういった都市人の無名性の中から生まれた文学だったとも言えるだろう。
このように近代ヨーロッパに成立した「群衆」というものは、「匿名性」のヴェールに包まれて特定個人としての責任感を群衆の中に溶け込ませる事が出来るので、無批判的/無責任的な感覚に囚われ、暗示にかかり易く、それは中世ヨーロッパ的な「特定個人」とは明らかに違った行動をとるようになるのである。
こういった無名性の人々の暴走というのは、その当時統治者にとっては脅威であった。新しく発生した都市部の「群衆」という人々に、統治者らは警戒心を強くしたのである。
まだパリ・コミューンの記憶の生々しい時期に、そういうスタンスで「群衆」という新しい人間の心理を分析したのがフランスの思想家ギュスターヴ・ル・ボンであったと言えるだろう。
群衆のなかへはいると諸個人はふつう氏名、地位、職業の別なく無名の一員としての気やすさを享受することができ、個人としてふるまうさいの行動の社会的制限をつよく感じないですみ、群衆への同一視によって個人的行為の責任を群衆全体に転嫁しやすいので、無批判、無責任な言動が誘発されやすい。このような傾向は感情的雰囲気の高調とともにますますつよくなる。適時に発せられる激昂、声援、アジ、スローガンなどは成員の相互作用による感情状態の強化をますます容易にし、成員の個人的抑制をとりのぞき、成員間のつよい親近感と一体感をつよめていく。こうして群衆は巨大な行動的エネルギーを発揮するにいたる。
フロイトもル・ボンの分析した群集心理について『集団心理学と自我の分析』で言及しており、この「群衆」の特徴を、無名性による責任感の欠如、伝染性、暗示されやすさ、の三点にまとめている。
で、本書における高層マンションの住人たちは、まさに上に書かれた「群集心理」そのままの暴走を繰り広げていく事となる。
ル・ボンは群集心理学をはじめて組織的に取り扱った点で有名である。かれは群衆の強大なエネルギー、衝動性、無批判性、被暗示性、単純性、道徳性の低下、知性の低下などの特徴を指摘した。
マンションの住人たちのいざこざは、次第に稚拙な嫌がらせ(知性の低下)が横行するようになり、徐々に暴力的な事件(衝動性・道徳性の低下)に発展するようになっていく。
壁には様々なスローガンやアジが書かれ、空調から異臭が放たれ、ダストシュートは詰まって機能不全になり、廊下にはゴミ袋が溢れ、部屋部屋にはバリケートが築かれて、住民は様々なグループに分かれて抗争に発展するようになる。
ここまでであったら、ぼくは、バラードはル・ボン的な群集心理をこの近代的な高層マンションの中の住民抗争に適用したのだな、と捉えたのだが、そういう「マンション内のリアルな抗争のシミュレーション」と言うには、本作に書かれている状況は明らかに不可解な事が幾つもあるのである。
大きな違和感は、マンション内に初めての死者が出てから初めて感じたものである。
◆◆◆
ある日、40階に住む宝石商が、最上階のガラスを突き破って地上の駐車場に落下して死んでしまったのである。
この時点で、駐車場にはマンションの住人が投げ落としたワインボトルや割れた卵、溶けたアイスクリームを始め、様々なゴミが散乱して明らかに異常な状態となっていた。
警察が事情聴取でマンション内に入ったら、この明らかに異常な状態を、確実に目の当たりにするだろう。
では果たして、この建物の中に吹き荒れる暴力と破壊と略奪の嵐を見て、官憲が目をつけないなどという事があるのだろうか?
――しかしその後、この異常事態がマンション外で取り上げられて何かしらの問題になったという話は一切出てこない。
このマンションの住人には、雑誌の編集者やテレビのプロデューサーやアナウンサーまで住んでいるのである。この建物の無秩序状態が外部に漏れる事がないなどという事がありうるのか?
――だが、このマンションの中で起こっている事件は、川向こうにあるロンドンには一切知られる事なく、どんどんエスカレートしていくのである。そんな事がありうるのか?
住人は夜になると、まるで原始人のように欲望の限り暴力を振るい、略奪し、そこらじゅうに糞尿をふりまき、不倫をし、犯し、バリケードを築いて通路を塞ぐ。――それなのに朝が来ると、顔をぬぐってスーツに身を包み、何食わぬ顔をしてロンドンへ出勤していくのである。
これは全く「群集心理」では説明のつかない事態である。
マンションの住人らは、この建物の中で起こっている事を、一切外には漏らさないのである。外部では普通人を装い、自宅に帰ったらまた原始人に戻って欲望の限りをつくすのである。
明らかに死人が出ており、マンション内で窃盗や暴行や住居侵入や破壊行為が繰り返されているというのに、外部から警察が来ているという描写はほとんどない。
当初の舞台がある程度リアルに基づいていたからこそ、この住人達のちぐはぐな心理には戸惑いしかなかった。
だが、この物語が後半に行くにしたがって現れるその「光景」を見た時、――ぼくは、ああ、バラードは『結晶世界』から続く「美しい滅亡の景色」に魅入られた人だったんだな、とやっと理解したのである。
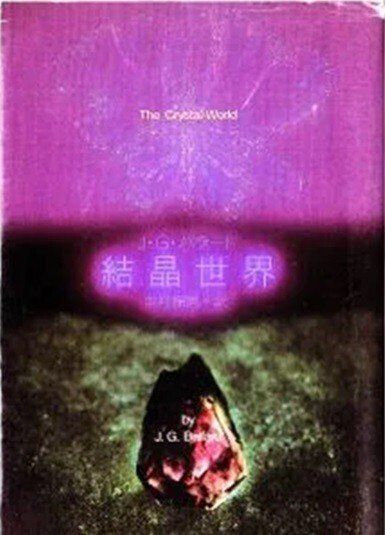
全ての舞台装置は、バラードが魅入られている「美しい滅亡の景色」を成立させるために設定されていたのだ。
ラストにまで至ると、マンション内の設備はほどんど機能しなくなっている。
空調は止まって異臭しか吐き出さなくなり、水道から水も出なくなる。ダストシュートは詰まって、ゴミ袋は廊下に溢れかえる。住民は小さなグループごとに別れ、部屋にバリケードを作って立て籠もり、夜になると他グループに襲撃を加えに出動する。人々は風呂に入る事も出来ず、糞便もそこらじゅうに出されて衛生状態が悪化する。停電は常態化し、暗闇の中でやりたい放題の暴力が荒れ狂う。ここまでくると勤め人らももう出勤しなくなり、マンション内抗争に集中する事となる。
異常なのは、このマンションの住人たちは、この事態を非常に穏やかに受け入れているのである。
それどころか、外部の余所者にさえこの欲望を解放した無秩序状態を邪魔されたくない、という意識が強く芽生えているのである。
パトカーが外周の入り口に近づいてきた。この早朝から住人が数人、きちんとスーツとレインコートを着て、ブリーフケースをさげて出勤するところだった。進入路にうちすてられた車が邪魔になって、パトカーは建物のメイン・エントランスまでくることができず、警官は車をおりて通りがかった住人に話しかけた。ふつうならだれも外部の人間に返事はしないところだが、彼らはふたりの警官のまわりにあつまった。ワイルダーは彼らがせっかくのゲームをばらしてしまうのではないかと思ったが、彼らの声はきこえなくても、なにをいっているのかは確信できた。あきらかに彼らは警官をなだめ、マンションのまわりはごみと割れびんだらけなのに、なにも異常はないと請け合っているのだ。
この描写を見て、やっとぼくはバラードが成立させたかった、このマンションの住人たちの異常な心理を理解したのだった。
この心理はほとんど、不条理――それも「カフカ的な不条理」なのである。因果関係が分からぬまま異常事態が進行し、その理由も原因も全く説明される事がない。
本作では、バラードはこの高層マンションの住人らの「異常なほど外部を排除して暴力に没頭する群集心理」の原因を、全く説得的に扱ってはいないのである。不条理なほどに。
バラードはそう言った「理由」や「原因」に、ほとんど価値を見出していない、あるいはあまり関心がないかのようなのである。
考えてみればバラードは『結晶世界』でも、世界のあらゆる物体が徐々に結晶化していく事の原因についても、あまり説得的に説明しようとはせず、それよりも徐々に破滅していく世界の描写へ集中していたのではなかったか?
また『クラッシュ』でも、交通事故と性交の結びつきに異様に固執する人物「ヴォーン」の様子は非常に詳細に描写をしていたものの、「どうしてヴォーンはそのような異常心理を持つに至ったのか?」という、SF読者であったならば最も知りたい部分についてはほとんど言及されていなかったのではなかったか?
本書も同じなのである。
住人らがマンション内で起こす様々な暴力無秩序状態が徐々にエスカレートしていく様は非常に詳細に書かれるのだが、なぜ住人らがそういった無秩序状態に魅了され、なぜ警察や外部の何者にも邪魔される事なくこの暴力と略奪と不衛生と荒廃した状況を継続されるようにしているのか――その住人らの「異常心理」の側面については、ほとんど説得的に理由を説明しようとしないのである。
これはある意味、不条理な状況を描写した「不条理小説」と言う事も可能だろう。
その結果、現れる光景とは、瓦礫とゴミと糞尿と死体に彩られ荒廃してドロドロの不衛生状態の中で原始人のような姿で、静かな気分で死んでいく登場人物らや、その環境に安息と快適さのようなものさえ感じている住人たちの姿である。
そこには、何も苦悩も懊悩も迷いもないのである。
この物語の目的は、おそらく近代テクノロジーの結晶である高層マンションという殻に封じこまれた人間たちが、限りなく醜く原始退行していき、黙示録的な荒廃の中で朽ち果てていく状況に、なぜか魅力と安寧を感じている人々の姿を描く事である。
それは「大破局を目前にしながら、それに"安寧"を感じて受け入れる人々」という残酷な景色なのだ。
それは、確かに『結晶世界』や『クラッシュ』でバラードが描き出してきた光景と同じく「思わずウットリと見入ってしまうような、美しいほど残酷な光景」であり、それこそまさしくバラードの個性なのだと感じられた。
この残酷にして圧倒的な「美」の力によって、この説明の欠落した不条理な状況を最終的に納得させようというのが、バラードの意図としてあったのではないか。
バラード的な「美しいほどの残酷な光景」「美しい滅亡の景色」というのは、ぼくにはどこか、『白痴』で坂本安吾が提示した、空襲下で燃え上がる帝都の様子を見て感じた「美」と同じようなものに思えるのである。
安吾をして「偉大な破壊、その驚くべき愛情、偉大な運命、その驚くべき愛情」と言わしめた、帝都大空襲というカタストロフの景色である。
バラードという人間は、おそらくこの「美しい滅亡の景色」に、魅入られた人間なのだ。
ぼくはまだ未読なのだが、この感覚は恐らくバラードの半自伝的小説『太陽の帝国』を読むと、理解できるのだろうと思っている。
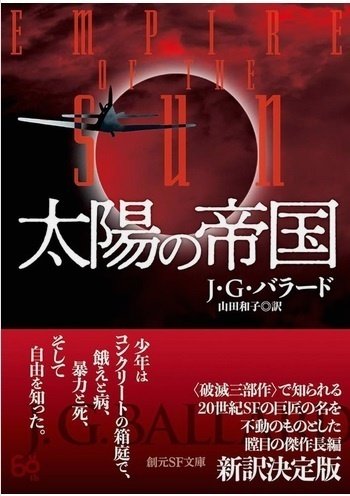
日中戦争中の上海。日英間の開戦を機に日本軍が上海のイギリス租界を制圧し、少年ジムは避難民の大混乱のなか両親とはぐれてしまう。独りぼっちになったジムは混乱する都市を彷徨う中、ほかのイギリス人とともに日本軍によって龍華捕虜収容所へ送られる。信用できる大人も庇護もないまま、飢餓、病、孤独、絶望に晒されながら、ジムは生と死の本質を学んでいく――スピルバーグによる映画化で知られる、二十世紀の歴史に名を刻むバラードの代表作を新訳決定版で贈る。
よくバラードの代表作である『結晶世界』は、バラードの少年時にいた上海の日本軍の捕虜収容所の体験が「原体験」になっていると言われ、バラードの少年時代のこの荒廃と破滅的な体験を描いている等と言われるが、これは『ハイ・ライズ』にも言える事なのではないだろうか。
特に『太陽の帝国』のあらすじに紹介されている捕虜収容所の「飢餓、病、孤独、絶望」という状況は、そのまま『ハイ・ライズ』のラストのマンションの中の荒廃した状況に当てはまる。
バラードはおそらく、少年時代に経験した「うっとりするほど美しいカタストロフィの光景」に魅入られ、PTSDを患った患者が何度も何度もトラウマをフラッシュバックという形で追体験しなければならないように、「美しい破滅」を自分の作品によって何度も何度も追体験している――そういう人だったのではないかと思うのだ。
