
ウディ・アレン監督 『カイロの紫のバラ』 : 弱者への温かな眼差し
映画評:ウディ・アレン監督『カイロの紫のバラ』(1985年・アメリカ映画)
ウディ・アレン監督は、子供の頃にテレビで見て、すっかり好きになった映画監督だ。
ただし、その後に見た、ひとつかふたつのの作品がイマイチだったので、すっかりご無沙汰してしまっていた。一一と、このパターンは、スタンリー・キューブリック監督の時と、まったく同じである。
キューブリックの場合は、『2001年宇宙の旅』で惚れ込んで、『フルメタル・ジャケット』を物足りなく感じて離れてしまったのだ。
では、アレン監督の場合は、どの作品で惚れ込んで、どの作品で離れたのかなのだが、その記憶が、もはや定かではない。
ただ、このレビューを書くために、アレン監督のWikipediaを確認したところ、好きになった作品は、ほぼ間違いなく『カメレオンマン』(1983年)ではないか、と思われた。

その理由は、私は子供の頃から、あの変幻自在のカメレオンというトカゲが大好きだったということが、まずある(同様の理由で、『仮面ライダー』のカメレオン男も、私の好きなショッカー怪人のベスト3に入った)。

またひとつの大きな理由は、この『カメレオンマン』が、「メタ・フィクション」作品だからである。そのことに、今回初めて気づいたのだ。
知識のない子供の私は、この「変わった作品」が、「メタ・フィクション」作品だとは気づきようもなかった。
だが、その後、読書家としていろんなジャンルの本を読んでいく中で、自分の好きな作品が、しばしば「作中作」(入れ子構造)形式だとか、「自己言及」的な内容のものなのだとわかり、それが「メタ・フィクション」と呼ばれる作品だということを知ったのである。
だから、今になって『カメレオンマン』の「あらすじ」を見てみると、「ああ、これ、典型的なメタ・フィクションじゃないか。子供の頃の私は、そこに惹かれたんだな」とわかったのである。

では、アレン監督から離れるきっかけとなった作品はどれなのかというと、これはもうわからない。Wikipediaでタイトルを見ただけでは、とうてい思い出せない。
ただ、ひとつ考えられるのは、たしかアレン監督は、オーソドックスな恋愛映画も撮っているはずなので(そう側聞しているので)、そういう「普通の恋愛映画」を見たんじゃないか、とは推察できるのである。
と言うのも、私はもともと恋愛映画に(も小説にも)興味の持てない人間であり、まして、主演のウディ・アレンに似合いそうな、暗い恋愛(失恋)映画では、なおさらダメそうだからだ。
ともあれ、気に入った『カメレオンマン』が、アレン監督の主演作品だったから、その後に見た作品も、きっとアレン監督の主演だったはずだ。映画に詳しくない子供や若者にとっては、まず目につくのは主演俳優だからである。
だが、そこまでが推理の限界だったのだ。
で、今回見た『カイロの紫のバラ』も、典型的な「メタ・フィクション」である。
しかし、だからこれを選んだのかと言えば、そうではない。

そもそも、どうして、ひさしぶりにウディ・アレンの映画を見たいと思ったのかという、最近読んだ蓮實重彦の本のどれかの中で、蓮實が、ハリウッドの「つまらない映画」だか「監督」の名を列挙していた中に、ウディ・アレンの名が含まれていたので、古いファンとしては、それがカチンと来たためである。
そう言えば先日、私に難癖をつけていた、映画評論もやっている「武蔵大学の教授」で「表象文化論学会の役員」もやったとかいうフェミニスト評論家の北村紗衣が、次のようなことを、ツイートしており、「やっぱり、こいつは馬鹿だな」と、そう確信させられた。
『しかし、自分が好きな映画をつまらないと言われただけでこんなに怒るの、あなた方そんなに自信が無いんですか?私は人につまらないとか嫌いとか言われたくらいで自分がその映画が好きな気持ちはゆるがないし、面白いところを言い続ければ誰かが見て楽しんでくれると信じてますが?』
(https://twitter.com/Cristoforou/status/1830180767592312916)
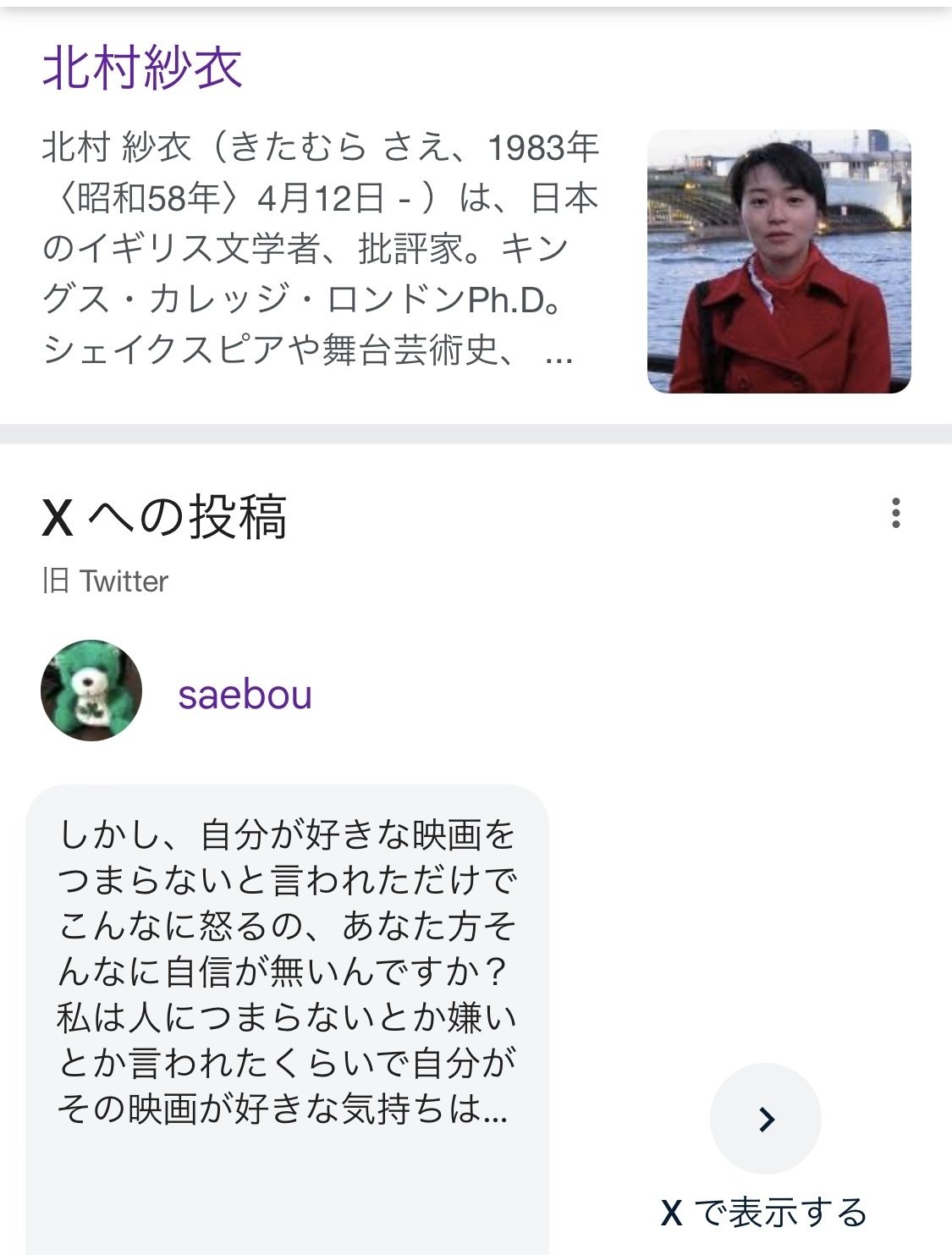
北村紗衣によるこの間抜けなツイートについては、こう書かれたご当人が、完璧に反論論破しているので、ここでは、そのリンクを張っておくだけにする。
それにしても、普通に考えて、
『自分が好きな映画をつまらないと言われただけでこんなに怒るの』って、「自信の有無」の問題じゃないことくらい、普通の頭があればわかることだろう。
それを「私は自信があるから、怒りませんよ」なんてことを言って「自慢」して見せているところが、馬鹿丸出しなのである。
まあ、北村紗衣は、ご自分に自信がおありだがら、「女みたいな男」と言われようが「武蔵大学のポンコツ教授」と言われようが「お前の爺さんデベソ」と言われようが、平気なのだろう。
ましてやその程度のことで、また「スラップ裁判」を起こすなんていう、恥晒しな真似はしないはずだ。
○ ○ ○
閑話休題。
私がひさしぶりにウディ・アレンを見たいと思ったのは、蓮實重彦がアレン監督を貶していたからなのだが、しかし、それに腹を立てた私自身、アレン監督の作品をほとんど見ていないことに思いいたりもしたので、「もう少し、他の作品を見てみよう。今なら、作品情報も多いから、作品個々の評判の良し悪しもすぐにわかるし」ということでネット検索し、この『カイロの紫のバラ』を選んだという次第である。

だが、その段階では、本作『カイロの紫のバラ』が「メタ・フィクション」だと気づいていたものの、『カメレオンマン』のことはすっかり忘れていたから、かえって「ウディ・アレンって、メタ・フィクション的な作品も撮ってるんだな。まあ、これなら無難に、私に合いそうだ」と、そう思っていたのだ。
さて、本作『カイロの紫のバラ』だが、簡単にまとめると、次のような内容の作品だ。
暴力亭主を持つ、当人もいまいちパッとしない中年女性セシリア(シシリア)。そんな彼女の慰めは、映画を見ることだけだった。
そんなある日、彼女が繰り返し見ていた新作映画『カイロの紫のバラ』のスクリーンの中から、彼女の憧れの男優が演じる登場人物のトムが、いきなり出てきて、彼女に求愛する。
一方、この大事件のために映画会社も大騒ぎで、トム役の俳優ギルまで現地入りして事態の収拾を図るのだが、その彼までがセシリアを好きになってしまい、セシリアは二人の間で板挟みになる。一一と、こういう恋愛コメディである。

私が本稿で論じたいのは、ラストの解釈なので、まずは下に、「全ストーリー」を、引用で紹介しておこう。
『舞台は1930年代、大恐慌の最中にあるアメリカ・ニュージャージー州。セシリア(ミア・ファロー)はウェイトレスをして、失業中の暴力亭主モンク(ダニー・アイエロ)との生活を支えている。惨めな生活と愛のない結婚から逃避するために通い詰めていた映画館で、セシリアは上映中の映画「カイロの紫のバラ」に夢中になる。
ある時、「カイロの紫のバラ」の登場人物であるトム(ジェフ・ダニエルズ)が上映中に第四の壁(※ ここではスクリーンのこと。作中世界と現実世界との間の「見えない壁」)を破ってセシリアに話しかけ、白黒のスクリーンからカラフルな現実の世界へ現れる。トムが抜け出した映画はストーリーが進まなくなってしまい、苦情を受けた「カイロの紫のバラ」の制作陣は事態の収拾のため、トムを演じた俳優ギル・シェパード(ジェフ・ダニエルズ)と共にニュージャージーにやってくる。
探検家で詩人のトムは「君と現実で恋がしたい」とセシリアの手を取り、二人はロマンチックな一時を過ごす。一方でトムを追うギルもまたセシリアと出会い、映画について二人で語らううちに心惹かれていき、トムとギルとセシリアは普通ではない三角関係を築く。
エンディングでは、ギルはセシリアに駆け落ちを申し込み、それを受けたセシリアはトムに映画の世界に戻るよう諭す。トムが戻った「カイロの紫のバラ」のフィルムは制作陣に回収され、二度と同じ事が起こらないよう焼却処分が決まる。セシリアはモンクに積年の鬱憤をぶつけ、荷物をまとめてギルとの待ち合わせ場所へと向かうが、ギルはセシリアを見捨て既にハリウッドに戻ってしまっていた。
恋人も仕事も家庭も失ったセシリアは、映画館の席について『トップ・ハット』のフレッド・アステアとジンジャー・ロジャースのダンスを見つめている。自分の悲惨な状況を忘れ、映画の世界に魅了されるセシリアを映し映画は幕を閉じる。』
(Wikipedia「カイロの紫のバラ」)
つまり、本作は、「映画の魅力とその限界」を描いた作品であり、その上で「映画を肯定した作品」でもあるわけなのだ。
「現実の生活」に疲れたセシリアは、いつでも「映画」の華麗な世界に、いっときの救いを見出している。
そんな彼女の想いに惹かれるように、映画の中から、憧れの男性がやってきて、彼女に求愛をする。もちろん、彼女は彼に夢中になる。



しかし、「映画の中の世界」からやってきた彼は、「現実世界」の「厳しさ」を知らない。
セシリアとレストランに入って食事をし、彼が支払いのために金を払うと、ウェイターは怪訝な顔をする。そして「お客様、ご冗談はお止しになってください。これは本物ではございませんよね。映画の小道具か何かですか?」と尋ねるのである。つまり彼は、こちらの世界では、一文なしなのである。
それで仕方なく、セシリアを連れてレストランから逃げ出し、路上駐車されていた車に乗り込んで逃げようとするのだが、エンジンがかからない。
「おかしいな」とつぶやくと、セシリアから「そりゃあ、キーが無ければ車は動かないわ」と言われて、それでもトムは「おかしいな。いつもなら動くのに」と、そんな調子なのだ。
二人がデートしているところを、セシリアの旦那のモンクに見つかってしまう。
セシリアを乱暴に連れ帰ろうとするモンクに対し、トムは「僕は、彼女を愛しているんだ。君みたいな男に、彼女を渡すつもりはない。正々堂々の勝負だ」となって、殴り合いをする。
当然、ヒーローであるトムの方が強いのだが、モンクは卑怯な手を使い、トムの隙をついての急所蹴りで、トムを倒してしまう。
セシリアは、自力でモンクを拒絶して追い返し、トムを助け起こすのだが、大太刀回りをしたはずのトムの髪は、少しも乱れていない。驚くセシリアにトムは言う。「これが普通だよ」。彼は映画の中の人物だから、そのくらいのことでは、髪は乱れないのだ。

こんな具合で、トムは良かれ悪しかれ「映画の中の人」なのだ。こちらの世界の住人にはなりきれない人(異質な存在)なのである。
だから、最後に、トムとギルの双方から「どちらを選ぶ」と迫られた時、セシリアは、ギルを選ぶことになる。
「ごめんなさい。でも貴方とは生きられないわ」と、セシリアがトムに謝罪すると、トムは肩を落とし、悄然とスクリーンの向こうへと帰っていくのである。

ギルとともにハリウッドへ行くために、いったん家へ戻って荷造りをし、その時また、モンクと喧嘩をしてまで家を出てきたのに、約束した映画館の前には、すでにギルの姿はなかった。
映画会社の関係者と共にすでにハリウッドへ帰ったと、映画館の人から知らされるのである。
トムを失い、モンクも職も失い、そして、希望の綱だったギルまで失って、すべてを失ったセシリアは、仕方なく、泣きながら、また映画館に入って映画を見るうちに、その表情には、ほのかな笑みが浮かぶのだった。

つまり、一一「映画」は、この「つらい現実」から、人を救ってくれるほどの力など持ってはいない。だから、人は、つらくても現実に生きるしかないのだが、その現実は、しばしば「約束」さえ違え裏切る過酷なものであり、人は時に、すべてを失うこともある。
だが、そんな時にも、映画は「いっときの救いと励まし」を与えてくれる。
それが、実質的には「現実逃避」だとしても、劇場が明るくなった途端に雲散霧消してしまう「はかない夢」だとしても、それでもやはり、「夢を見させてくれる」という事実に、かわりはないのだ。
したがって、ウディ・アレンがこの作品に込めたメッセージとは、そんな「か弱い映画」が「か弱い人たち」の「味方」である、ということだったのではないだろうか。
「俺には、君の力になれるほどの力なんて無いけれど、でも、力を出しなよと、そう励ますことだけはできるよ」
と、そう言いたかったのではないだろうか。
こうしたメッセージは、あの「裏なりナスビ」みたいな顔をしたウディ・アレンだからこそ、似合いもすれば、説得力も持つものではないかと、私はそう思うのである。
そしてタイトルの「カイロの紫のバラ」とは、「幻(非実在)の美しいバラ(愛)」ということであり、「映画」のことを含意していたのではないだろうか。

(2024年9月7日)
———————————————————————————————————————
【追記】本稿中の、リンク切れについて(2024年9月12日)
見てのとおりで、私な高山と批判された「北村紗衣」は、私に一度として反論することもないまま、「管理者通報」によって、私の記事、
・「北村紗衣という人:「男みたいな女」と言う場合の「女」とは、フェミニズムが言うところの「女」なのか?」
(2024年8月30日付)
を削除させました。
これが「フェミニスト批評家」を自称する、「武蔵大学教授」北村紗衣のやり方であり、現実です。
(2024年9月12日)
———————————————————————————————————————
【追記】拙稿「北村紗衣という人」削除に関する事情紹介(2024年9月14日)
一昨日ご報告しましたとおり、拙稿「北村紗衣という人」が、突然削除されましたので、そこに書かれたいたことなど、削除に至る事情などを説明した文章を書きました。
こちらも削除される恐れは大いにありますので、早目にお読みいただき、ログ、スクリーンショット、魚拓などと、それぞれに採っておいていただけると幸いです。
(2024年9月14日)
———————————————————————————————————————
○ ○ ○
● ● ●
・
・
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
