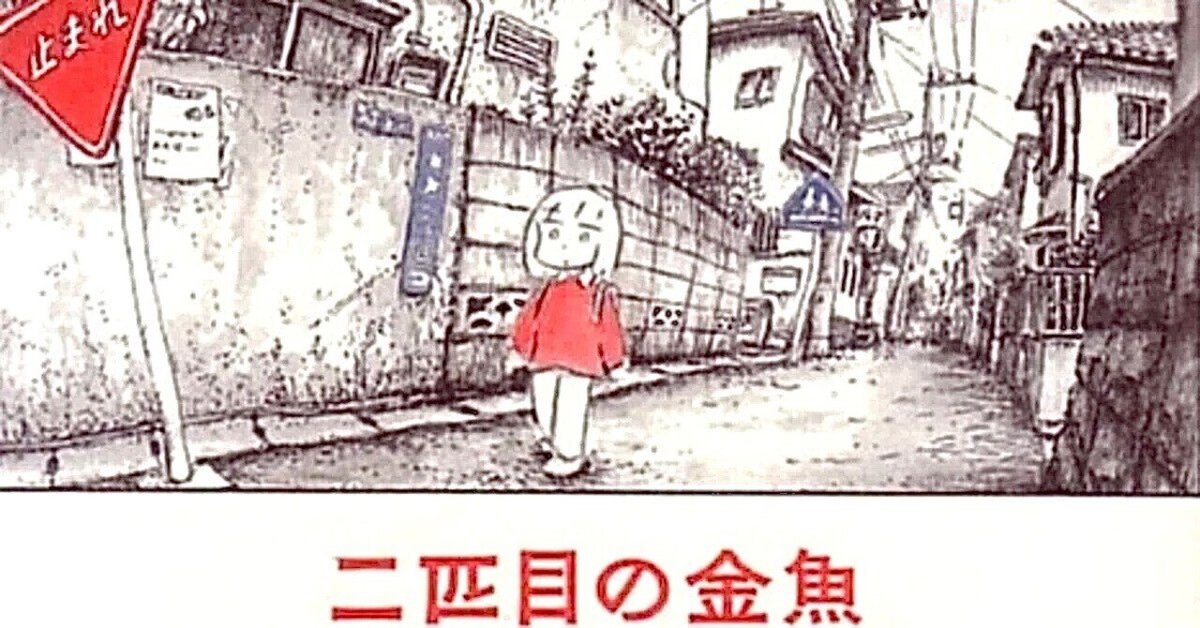
〈日常と異世界〉をつなぐもの : panpanya 『二匹目の金魚』
書評:panpanya『二匹目の金魚』(白泉社)
再読である。
友人が、panpanyaのレビューを書いていたので、また読みたくなったのだ。
しかし、同作者のどの著作を読んだのか、レビューを書いた最近のものは別にして、それ以前の本が、いまひとつハッキリしない。そこで、安価(古本)かつすぐに手に入る「たぶん読んでいないであろう」本書を取り寄せたところ、読み始めてしばらくしてから、既読であることに気づいたという次第である。
しかしながら、タイトル(と表紙)だけでは既に読んでいることを思い出せないくらいだから、再読だといっても、決して楽しめなかったわけではない。panpanyaの作品は、「ストーリー」ではなく、その独自の世界観で楽しませるタイプだから、その世界観が好きなら、何度読んでもそれなりに楽しめるのだ。それに、以前に読んだ時よりは、こちらもそれなりに教養を深めているので、新たな発見もあったのである。
panpanyaの単行本は、下の既刊8冊である(「1月と7月」は刊行社名)。
1、足摺り水族館 (2013年8月31日、1月と7月)
2、蟹に誘われて (2014年4月30日、白泉社)
3、枕魚 (2015年5月2日、白泉社)
4、動物たち (2016年12月5日、白泉社)
5、二匹目の金魚 (2018年1月31日、白泉社)
6、グヤバノ・ホリデー(2019年1月31日、白泉社)
7、おむすびの転がる町(2020年3月31日、白泉社)
8、魚社会 (2021年7月30日、白泉社)
このうち、最新の7と8については、レビューを書いているから、間違いなく読んでいる。
で、たぶん読んでいるんじゃないかなあと思うのは、2と3。
今回、「たぶん読んでいないんじゃないかなあ」と思って、誤って再読したのは、5である。
ちなみに、友人がレビューを上げてたのは、1の『足摺り水族館』だ。羨ましい。
そんなわけで、ここまできたら、ぜんぶ読もうと思う。
○ ○ ○
さて、『二匹目の金魚』だが、今回再読して発見したのは、前の2つのレビューでそれぞれ触れた、panpanyaの特徴である「異世界探訪」と「日常探求」の、一見したところ相反するように見える、2つの方向性を「つなぐ部分」である。

普通の場合、「異世界探訪」の傾向を持つ作家というのは、おおむね、この「現実世界」に倦み疲れていたり、嫌悪を抱いていたりするものだ。そのために、言葉は悪いが「現実逃避」的に「異世界」を求めるのである。
言い換えれば、「日常」を愛し、そこに尽きせぬ魅力を見出せるような作家は、普通は「異世界」を求めたりはしないものなのである。
ところが、panpanyaの場合は、この2つの方向性が、矛盾なく並立しているのである。これは、なぜだろうか。
本巻『二匹目の金魚』の収録作品は、部分的には「異世界探訪」性を持つものの、基本的には「日常探求」系である。
その中で、前者の傾向が強く出たのは「知恵」や「二匹目の金魚」であり、私は基本的には、こちらの「異世界探訪」系が好みである。一方、後者の「日常探求」系の作品としては、「通学路」や「かくれんぼの心得」といった作品が挙げられるだろう。
しかし、読まれた方はすでにお気づきだろうが、この2つの傾向は、作品として綺麗に二分できるわけではない。
例えば、私が最も好きな「知恵」は、一種の「迷子もの」で、あるきっかけによって、見慣れた風景が、見知らぬ風景(異世界・異界)に反転してしまう、というパターンの作品である。
だが、この「知恵」で描かれる「見知らぬ風景」とは、決して、非現実的な「異世界・異界」というわけではない。
この作品では、毎日行き来していた通学路を、ある理由から、リヤカーを引いて帰宅しようとしたところ、リヤカーは道路交通法でいうところの「軽車両」に当たるため、日頃の徒歩ではまったく気にしなかった「交通規制(標識標示)」の対象となってしまった。そして、法令を守ろうとすると、どうしても家にたどり着くことができず、まるで呪いにでもかけられたように、家の近くを何度もぐるぐると、さまよい歩かなければならない羽目に陥る、というそんなお話である。
つまり、これまでは、当たり前だった風景が、リヤカーを引いた途端に、主人公に「牙を剥いた」というわけだ。

だから、登場するのは「普通の町」だけれども、それが主人公にとっては、見かけは同じでも、ぜんぜん違った「敵意を持つ町」に変貌するというところで、本作は「異世界・異界」ものの魅力を発するのである(これに似た傾向の話として、『ウルトラセブン』の第47話「あなたはだぁれ?」がある。夜のうちに、団地がそっくりそのまま、うり二つの団地に入れ替わるという、宇宙人による陰謀を描いたお話)。

その一方、私が「日常探求」系の作品として挙げた「かくれんぼの心得」は、子供のオーソドックスな遊びのひとつである「かくれんぼ」を、主人公がふかく探求していく中で、素晴らしい「隠れ場所」を発見するのだが、その場所の描写が、まさに「異世界」なのだ。
昔は、家の周囲を、人の背丈よりも高い「ブロック塀」で囲った家が、たくさんあった。主人公が見つけたのは、四方をそれぞれのブロック塀(三方が個人宅のブロック塀、残りの一方は、かくれんぼをする公園を囲うブロック塀)に囲まれた、いずれの敷地でもない、言うなれば「エアポケット」的な、ごく狭い「空き地」である。
そこは、外から見ると、反対側の敷地内の見えるのだが、実はそうではない。そうではないが、外見上、そのように見えてしまうために、誰もその「ごく狭い空間」の存在に気づいておらず、隠れ場所としては最高なのだ。
で、主人公は、その四方をブロック塀で囲まれた狭い空間に身を委ねて、次のようにつぶやく。
『優れた隠れ場所というのは
こんなにも居心地が良いもの
だったんだな…
やみつきになりそう…
絶対的な安心感、優越感…
これこそかくれんぼにおける
至上の時間に違いない』(P45)
ここで、主人公が感じているのは、その「狭さ」「薄暗さ」そして「安心感」からくる、「母胎内」的な空間認識に間違いなかろう。
つまり、「かくれんぼ」という遊びが「関係性における緊張感」を利用したゲームであるとすれば、主人公が、この「狭い空き地」に見出したのは、そうした「かくれんぼが行われる日常空間」から「隔絶した世界」、「ストレスの失われた楽園」とも呼ぶべき空間であり、そうした意味で「異世界・異界」性を帯びていたのである。

このように、panpanyaの描く世界においては、「日常空間」と「異世界・異界」は、必ずしも、排除し合う関係にはない。
panpanyaにとっては、「異世界・異界」とは、どこか「隔絶した、他の世界」を意味するのではなく、「日常空間の中に隠れている世界」なのだ。だから、愛を持って「日常世界」を凝視する中で、「異世界・異界」は見えてくる。
panpanyaの描く「異世界・異界」が、親しみのあるものなのは、理の当然だったのである。
では、前述の「知恵」における「異世界・異界」が、panpanyaには珍しくも「怖ろしい異世界・異界」だったのは、なぜだろうか?
一一それは、この場合、探そうとして「見つけた」のではなく、これまで見落としていた世界の一側面(異貌)を、心の準備がないまま、「知らされてしまった」からであろう。
それは、「愛による、主体的な接近」ではなく、「思いがけない、客体的転落」であったからこそ、恐ろしかったのではないだろうか。
ともあれ、panpanyaにおける「異世界・異界」とは、このように「愛を持って、日常の中に見出すもの」であり、多くの人が見落としている「日常の豊かさ」の発見なのであろう。
せっかちな私は、そこまで根気よく「日常を凝視」することができず、どんどんと外に出ていく(新しい本を読んでいく)ことで、効率的に「異世界・異界」を発見しようとする。一一だが、どっちが効率的かは、いちがいには言えないだろう。
だがまた、どちらの方法で「異世界・異界」を見出そうとするかは、結局のところ、人の持って生まれた性分による、としか言いようのないのではないだろうか。
(2022年8月17日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
○ ○ ○
・
