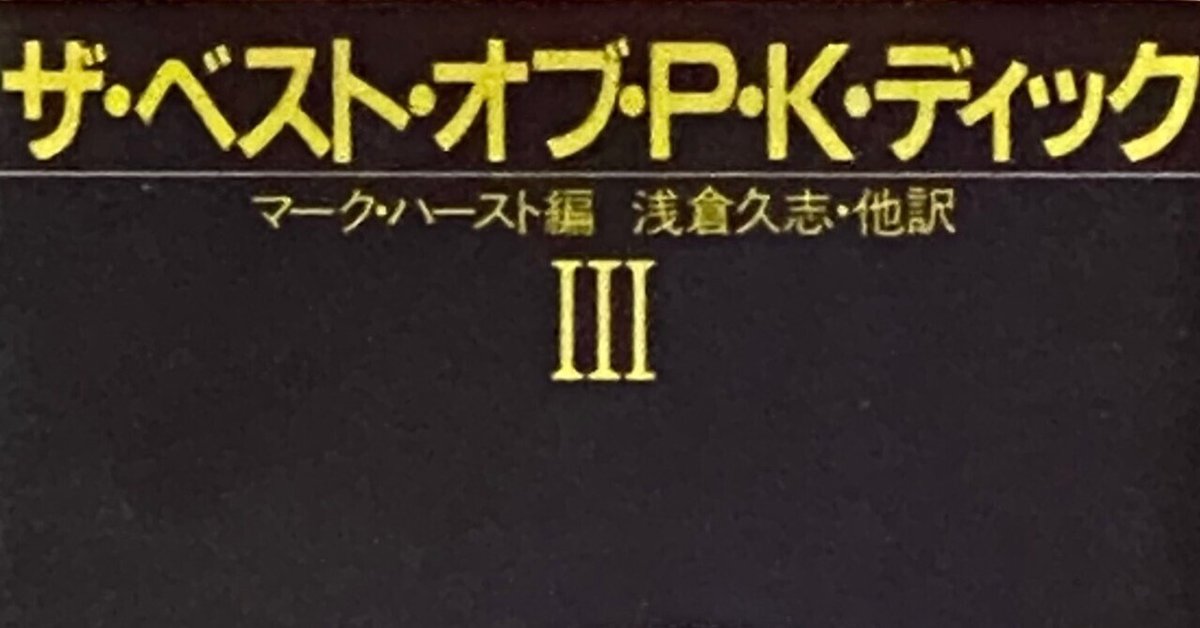
フィリップ・K・ディックの 〈信仰と懐疑〉 : マーク・ハースト編 『ザ・ベスト・オブ・P・K・ディック 〈3〉』
書評:マーク・ハースト編『ザ・ベスト・オブ・P・K・ディック〈3〉』(サンリオSF文庫)
フィリップ・K・ディックの主要なテーマとして「偽物」ということがあるのは、本シリーズのレビューの中でも書いてきたことだし、ディックファンには周知の事実に類することかもしれない。
この「偽物」テーマの根底にあるのは、ディックが「この世界は本当に、私に見えているままの、この世界なのか?」というところから発しているようだし、それは、「私」に見られ、認知される対象である「この世界」という域をも超えて、「この世界」を見ている「私」にまで及ぶ。つまり、「この世界を見ている、この私」が、そもそも「本物」なのか、という疑問。「我思うゆえに我あり」などと、本当に言えるのかという、今日的な「意識論」にまで及ぶ、そんな疑問である。
本作品集の第1巻、第2巻は、ジョン・ブラナーによって編まれたものであったが、本巻と、次の第4巻は、マーク・ハーストによって編まれている。たぶん、原著には、第2巻と第3巻の間に、時間的な隔たりがあるのだろう。

本巻に収められているのは、次の諸篇である。
・はじめに(マーク・ハースト)
・まえがき(フィリップ・K・ディック)
(1)ゴールデン・マン
(2)リターン・マッチ
(3)妖精の王
(4)ヤンシーにならえ
(5)ふとした表紙に
(6)小さな黒い箱
(7)融通のきかない機械
・作品メモ(フィリップ・K・ディック)
・現代文学としてのディック(日野啓三)
第1巻、第2巻に所収の「初期作品」に比べると、本巻所収の作品では、「見るからにSF的」という部分が後退し、そのぶん「宗教」テーマが前面に出てきており、そのせいもあって、お話自体もそうだし、「何を語らんとしているのか」という部分でも、分かりにくくなっている。つまり、いかにもディックらしい「難解さ」が増している。
幸い、本書にはディック自身による「作品メモ」が付録されているので、作品読解のヒントとして、それを参考にすることができる。
もちろん、まんま「ぜんぶ説明してくれている」というようなものではないが、作品の背景となる部分が語られていたりするので、十分に参考になる。けれども、決して、作品を読むにあたって、興醒めになるような「ネタバレ」的なものにはなっていない、ということは申し添えておこう。
さて、本巻所収の作品を通読して感じるのは、前記のとおり、「難解」の度を強めているということばかりではない。
これまでの作品では、「この世界」や「私自身」などが「本物か(偽物ではないのか)」という懐疑に付されていたわけだが、本巻の作品では、その視点が反対になって「いかに私たちが、騙されやすいか」に、問題の中心が移っているように感じられた。これは、興味深い変化ではないだろうか。
収録作品を個別簡明に論評してしておくと、
(1)「ゴールデン・マン」は、「ミュータント(新人類)」テーマの作品で、本作に登場する新人類は「黄金色に輝く、神のごとき美しい男」である。彼の特徴は「思考しない」ということであり、要は「本能だけ」で生きているのだが、その「本能」が、人類の知性を凌駕するものであり、自身を駆逐しようとする(旧)人類に対して、その本能と、持って生まれた「美しい外見」によって、まんまと生き延び、人類の生存競争に暗い影を落とす、というところで終わっている。つまり、本作では、映画『ブレードランナー』『トータル・リコール』などのように、アンドロイドやミュータントの側に立って、マイノリティーである彼らに「同情する」といったスタンスでもなければ、かと言って(旧)人類の側に立って、新人類の台頭への反撃を支持するというようなものでもない。そうではなく、「生物が進化すれば、旧来の生物は取って代わられるしかない」という事実を、客観的に「観察している」という感じの、ある種「人類の運命を、突き放して見た」作品だと言えるだろう。無論、本作でも、人類は、ミュータントの「美しさ(中身を反映しない外見)」に敗れてしまうというかたちで、「偽物」テーマが登場する。また、「神とは何か」の問題にも通ずる。

(2)「リターン・マッチ」は、人類侵略兵器としての「賭博ゲーム機」が登場し、人類が、それと知っていながら、それに「おぼれてしまう」姿が描かれる。その意味では「ゴールデン・マン」に通じる作品だが、こちらは、「偽物」が「ゲーム機」だというところに、皮肉なユーモアが強く感じられる。宇宙人が「バーチャル・リアリティーの美男美女」ゲームを作ったら、私たちは簡単に侵略されてしまうだろう。すでに、人類間ですら、それに近い現実があるのだから。

(3)「妖精の王」は、ディックには珍しいファンタジー作品であり、しかもハッピーエンドだ。当初は、バッドエンドだったそうだが、書き直しを要請されたようで、たしかに引っかかる部分はある。ただ、ファンタジーとは言っても、そこはディックであり、いつもとぜんぜん違うというわけではない。要は、現実の世界に、妖精たちが現れ、主人公である親切な爺さんに助けを求め、妖精の王の急死を受けて、彼が妖精の王に選ばれ、トロールとの戦いに勝利して、勝利王として、妖精の世界へ入っていく、といったような話である。つまり「この現実世界」と「妖精の住む世界」の相対性が描かれていて、どちらが「本物」とは言えないわけである。なお、本作は、のちに長編化されている。

(4)「ヤンシーにならえ」は、強制手段を使わず、いかにして「全体主義社会」が実現できるかを描いた作品で、本作に登場するのは、「ヤンシー」という名の「虚構のカリスマ」である。つまり、国民すべてが崇拝したくなるような人物をでっち上げて、それをあらゆるメディアに露出させ、国民を洗脳するという手法なのだが、私が面白いと思ったのは、この「カリスマ的人物」は「あらゆる面に優れた、理想的な人物」などではなく、ちょっと泥臭い部分があったり、インテリではなかったりといった「庶民が親しみを感じられる」ような性格や外見が、意図的に仕込んである、という点である。だから、あらゆることについて語る彼の見解も、決して「首尾一貫して、徹底的に論理的なもの(正論)」などではない。例えば、「戦争は絶対にいけない。しかし、祖国を守るためならば、私たちは敢然と立ち上がらなければならない。これは当然だ」といった「中途半端な意見」である。本当に大切なのは、そこにある「矛盾」を直視して思考することなのだが、「庶民」はそんな「難しいこと」には興味がなく、「ヤンシー」が語る程度の「中身はないが、もっともらしい意見」の方を支持するだろう。「スキ(イイね)」をもらうためには、深すぎてはいけない。これは「大衆操作」の本質を突いた、リアルな寓話だといえよう。

(5)「ふとした表紙に」は、不死の生物の皮革を使って本を装丁したところ、その本の内容が一部書き換えられていた、という不思議な事件を描いた作品で、その真相は、皮革になっても、その生物は生きており「生物は不死になれる」という、自分たちの事実に基づいた信念を持っていたため、その信念に反した書物の内容については、事実に即して「訂正」を加えていたという、かなりユーモラスなお話である。しかし、これも「事実は事実」なのか、それとも「間違った事実は事実にあらず」なのかといった問題を扱って、「偽物」問題に通じており、例えば「歴史修正主義」などの、アクチュアルな問題などにも通じていると言えるだろう。

(6)「小さな黒い箱」は、ある流行宗教の、教祖とつながるための共感装置である「黒い箱」をめぐる、きわめて「宗教的な作品」で、この教祖は、当局から、民衆をたぶらかす「危険人物」であり、もしかすると「異星人(侵略者)」の手先かもしれないと考えられている。その真相は、本作の中では語られないのだが、「宗教」というのは元来、その本質において、「この現実」への「侵略」なのだと言えないこともないだろう。なお、本作は、映画『ブレードランナー』の原作長編小説『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』の原型になった作品だが、『ブレードランナー』をイメージすると、「だいぶ違う」ということになるだろう。

(7)「融通のきかない機械」は、あらゆるものに擬態する「小型の暗殺メカ」を描いた作品で、本作中では「小型テレビ受像機」に化けたりするのだが、面白いのは、このメカは、暗殺を行うだけではなく、現場に「偽の証拠」を残して「偽装工作」を行う点だ。つまり、血痕や足跡といった「偽の証拠」を残して、捜査を撹乱するのである。これを「本格ミステリファン」が聞いたなら、「それって、初期クイーン問題じゃないか!」と驚くことだろう。そこまで考える必要はないのだが、これが「ディック的偽物問題」であるというのは、間違いのないところである。

以上のように、本作品集でも、ディックの「偽物」問題への興味は一貫しているが、それは以前よりも深められているように思える。
この「偽物」問題への、ディックの「アンビバレントな感情」は、(5)の「ふとした表紙に」についての「作品メモ」の、次のような言葉に、端的に示されているといっても良いだろう。
『 ここで提出されているのは、その頃のわたしの願望の一つである。つまり、聖書が事実だったら、という願いだ。明らかに、わたしは懐疑と信仰との中間点にあったらしい。それから十年あまり経ったいまも、やはりその位置にいるようだ。聖書が事実であればよいとは思うけれども、しかし一一そう、もしそうでなくとも、われわれがそれを事実にすることはできる。ただ、悲しいかな、それにはたいへんな努力が必要だろう。』
(P316〜317、ゴシック部の原文は傍点)
われわれが、その「努力」によって『事実にすること』のできる「聖書的事実」とは、いったい何を指しているのだろうか?
普通に考えれば、「神の国」の到来だということになるのだろうが、その場合、到来した「神の国」とは、どんなものを指すのであろうか?
これだけでは、まったくハッキリとしないので、ディックの他の作品を探る必要があるだろう。

○ ○ ○
※ なぜか「Amazon」には、『ザ・ベスト・オブ・P・K・ディック』の、第1巻、第2巻、第4巻のページはあるのに、当第3巻のページだけがないので、ここでは、1、2、4巻のリンクを張っておく。
(2023年4月3日)
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
