
北村紗衣の エリート・フェミニズム : シンジア・アルッザほか 『99%のためのフェミニズム宣言』
書評:シンジア・アルッザ、ティティ・バタチャーリャ、ナンシー・フレイザー『99%のためのフェミニズム宣言』(人文書院)
170ページほどの比較的薄目の本なので、正直なところ少し舐めていたのだが、濃厚かつとても素晴らしい本で、大いに啓蒙された。
本書に関して紹介しておきたいことは、大きく2点ある。
(1)北村紗衣に代表される「リーン・イン・フェミニズム」の問題。
(2)なぜ「反資本主義」のためには「フェミニズム」が必要なのかという理論的根拠。
本書は、そのタイトルからも分かるとおり「99%の」人々のための「フェミニズム宣言(マニフェスト)」であり、その「綱領(platform)」である。要は、
「私たちは、たった1%の社会的エリートのためのフェミニズムではなく、その他99%の人々のためのフェミニズムであることを、ここに宣言して、その綱領を示す」
という内容のものである。

だが、本書を冒頭から読んでいくと、「私たちの〈99%のためのフェミニズム〉とは、このようなものであらねばならず、このように行動していく」ということが、短く区切って明確に語られて行くのだが、その考え方の「根拠」となるところが、少々わかりにくい。
「こう考えて、こうやる」というのはよく分かるのだが、「どうして、そのように考えるのか」という前段の「根拠」の部分が、「フェミニズム」や「社会主義」に詳しくない者にはわかりにくいし、「旧来の(マルクスなどの)社会主義思想」しか知らない者が読むと、「社会主義」と「フェミニズム」が結びつく「必然性」がよくわからないため、単に、「左派フェミニズム」の人たちによる、主流派フェミニズムに対する批判を含んだ、行動主義フェミニズムのアピールなのだろう、くらいにしか感じられない。
ところが、そうした理解がまったく不十分だというのは、最後に収録された、40ページにおよぶ長い「あとがき」を読むことで、はっきりと理解できるような構造になっている。
この長い「あとがき」において、著者らが「こう考えて、こうやる」と主張していることの「理論的根拠」が、やっと詳しく説明されて、「そういうことだったのか!」と、盲を開かれることになるのだ。
したがって、私のおすすめとしては、まず冒頭の「マニフェスト」を含む本文部分を二、三章読み、それでおおよその雰囲気を掴んだところで「あとがき」に飛び、それを読んでから、ふたたび本文に戻って続きを読めば良いと思う。そうすれば、その主張の「理論的根拠」が頭に入っているから、本文の「こう考えて、こうやる」と主張も、素直に「納得できる主張」として読むことができるようになるからである。
そんなわけで、このレビューでは、前記のとおり、
(1)北村紗衣に代表される「リーン・イン・フェミニズム」の問題。
(2)なぜ「反資本主義」のためには「フェミニズム」が必要なのかの理論的根拠。
の2点について、この順に分けて説明したいと思う。
つまり、(1)の批判は、決して単なる北村紗衣への個人攻撃などではなく、北村紗衣に代表される「リーン・イン・フェミニズム」というものがどういうものなのかをまず知ってもらい、それがなぜ批判されなければならないものなのかという根拠としての(2)を説明する、という段取りとなっているのだ。
○ ○ ○
私は、これまでの「北村紗衣批判」関連レビューの中で、何度となく、北村紗衣のフェミニズムについて、次のように批判してきた。
「フェミニズムとは、本来、すべての被差別者や弱者に対し、同じ被差別者、弱者として、共闘の手を差し伸べるべきはずのものではないのか? にもかかわらず、北村紗衣のフェミニズムとは、男性を悪魔化して女性の被害者性をアピールし、そのことで党派的利益の拡大を目指すものでしかない。例えば「部落差別」や「在日朝鮮人差別」「沖縄米軍基地問題」といった、日本人の宿痾ともいうべき差別問題については、一言半句とも語ろうとしないのは、一体どうしたことなのか? この、いかにも不自然な点からしても、北村紗衣のフェミニズムとは、自己の利益確保のためだけの、偽善的な建前としか思えない」
私は、「部落差別」「在日朝鮮人差別」「沖縄米軍基地問題」といった「差別問題」について、長らく注目し論じてきた人間の一人として、当たり前の「疑問」を感じ、このような点を北村紗衣に問うたのである。
そして無論、「呉座勇一に対するオープンレター」問題と同様、北村紗衣は、自身に不都合な事実には「だんまり」で応じることしかしなかったのだ。
だが、本書『99%のためのフェミニズム宣言』を読んで、私の上のような批判が、北村紗衣やその仲間である東大教授のフェミニスト・清水晶子などの「弱点」を正しく突くものであったことを教えられた。
具体的どういうことなのかは、本書の冒頭の、以下の部分を読んでいただければ、たちまち理解できるだろう。
『 マニフェスト
分岐点
二〇一八年春、フェイスブック社の最高執行責任者(COO)であるシェリル・サンドバーグは世界に向けてこう発言した。「すべての国と企業のうち半数が女性によって運営され、すべての家庭のうち半数が男性によって切り盛りされれば、状況はずっとよくなるでしょう」。そして「その目標を達成するまで、私たちは決して満足してはいけないのです」。企業フェミニズムの主唱者として、サンドバーグはそのときすでに女性経営者らが役員会の「内側に入りこむ(リーン・イン)」よう促すことで名声(かつ財力)を得ていた。アメリカの財務長官ラリー・サマーズ一一ウォール街の規制を緩和した男性一一の元首席補佐官であった彼女は、ビジネス界の荒波をくぐり抜けて勝ち取る成功こそがジェンダーの平等へとつづく王道なのだ、とすこしの懸念もなく力説した。
同じ年の春、闘争的なフェミニスト・ストライキがスペインを機能不全に追いこんだ。五〇〇万人を超える参加者に支えられ、二四時間にわたるストライキを組織したウエルガ・フェッニスタ(フェミニスト・ストライキ)の主導者たちが呼びかけたのは、「性差別的抑圧、搾取、暴力から解放された社会の実現」であり、「私たちに従順であること、服従すること、沈黙することを要求する家父長制と資本主義の協力体制に抵抗し、闘いを挑む」ことだった。マドリードとバルセロナの上に太陽が沈んだとき、フェミニスト・ストライキの参加者たちは世界にこう表明したのである一一「この三月八日、我々は断固として、すべての生産活動、また再生産活動を停止させる」。そして今後、「同じ労働に従事する男性よりも劣る労働条件や賃金を決して認めない」と。
これら二つの声は、フェミニストの運動においてまったく逆の方向を示している。他方、サンドバーグや彼女と同階級に属する人々は、フェミニズムを資本主義の侍女であるとみなして(※ それを肯定して)いる。彼(女)らが望むのは、職場での搾取と社会全体における抑圧を司る仕事が、支配階級の男女によって等しく分担される世界である。これは支配の機会均等という特筆すべき展望であり、つまりは普通の人々に対し、フェミニズムの名の下にこう求めるのだ一一あなたがたの労働組合を破壊し、あなたがたの親を殺すようドローンに命じ、あなたがたの子どもたちを国境沿いの檻のなかに閉じこめるのが、男性ではなく女性であることをありがたく思いなさい(※ それをするのが女性であるならば、それは悪ではないのだ)。こうしたサンドバーグのリベラル・フェミニズムとはまったく対照的に、ウエルガ・フェミニスタの主導者たちは「資本主義に終焉をもたらす」ことを主張している。つまり、上司(ボス)というものを生み出し、国境を設け、それらを警備するためにドローンを生産する(※ 資本主義)システムの終焉である。
フェミニズムのこの二つのヴィジョンを前にして、私たちは一つの分岐点に立っていることがわかる。そして、私たちの選択は人類全体に誰も予想のできなかったような結果をもたらすことになる。一方の道は、人間の暮らしが存続可能なのかわからないほど悲惨なものになってしまう焼け焦げた地球へとつづいている。もう一方の道は、人間が見うるかぎりもっとも崇高な夢のなかで語られてきたような世界へと向かっていく。すなわち、富と天然資源がすべての人によって共有された世界、平等と自由がもはや渇望の対象ではなく、前提となった公正な世界へと。』
(P9〜12、傍点はゴシックに変えた。※ は、引用者註または補足説明)
ここに示されているのは、「フェミニズム」と言っても色々あって、「資本主義の侍女でしかない、リーン・イン・フェミニズム」もあれば、それが依存する「不公正な世界の原理たる資本主義」に抵抗し、これを打倒しようとしている「99%のためのフェミニズム」もある、ということだ。
「リーン・イン・フェミニズム」とは、女性が「1%のエリート」の中で半数以上を占めることを目標としており、残りの「99%の人々(である男女)」のことを、本音では気になどしていない。
だから、こうした「リーン・イン・フェミニズム」は、現在の「格差社会」を生み出している「資本主義」を否定してはおらず、ただ、自分が「男性同様に、上位1%に入る」ことしか目指していない「エリート主義フェミニズム」なのだ。
またそのために、資本主義社会では原理的に「1%には入れない」ことが自明である「99%の女性たち」を、フェミニズムの名の下に煽動して、自身の「立身出世」のために利用するだけなのである。「私がこうなれたように、あなたたちもこうなれるのだ。だから、私を応援して」と、そう言って欺くのである。
「資本主義」というのは、他人が生産した価値を「搾取」するところに成立する社会体制なのだから、みんなが「1%の搾取する側」になれるわけではない。
「被搾取対象」が大多数を占めないかぎり、「1%のエリート(選民)」の存在はあり得ないのだ。
だから、「エリート(選民)」になりたいと望んでいる男女は、今の「資本主義」体制を否定したりはしない。あくまでも、その体制の中での「1%」を目指すのであり、その「1%」になって、「99%からの搾取」を喜んで肯定しているのが、「リーン・イン・フェミニズム」なのだ。
したがって、地方新聞社社主の娘として東京大学に入り、イギリスに留学して博士号を取得し、日本に帰ってから勤めた武蔵大学では、40歳にならず「テニュア(終身雇用補償)教授」になった北村紗衣は、どこからどう見ても、日本における「リーン・イン・フェミニスト」の代表選手である。
また、そんな北村紗衣が起こした、山内雁琳に対する「名誉毀損民事賠償」のスラップ裁判では、北村紗衣は8人もの弁護士による弁護団を組んで、弁護士一人を雇うのが精一杯だった、一介の大学講師でしかなかった山内雁琳側を責め立てた。
そして、これに抵抗するための裁判費用をカンパに求めようとした山内を「裁判で金儲けをしようとしている」と非難して、その職を奪ったばかりか、名誉毀損裁判の常識的賠償額とは一桁違う200数十万円をむしり取ったのが、金持ちエリートの北村紗衣である。
要は「資本の力」を活用して「立身出世」し、「札束の力」で論敵を葬ってきたと呼んでいいのが、フェミニスト北村紗衣の「リーン・イン・フェミニズム」なのである。
したがって、本書が主唱する「99%のためのフェミニズム」とは、そうした「リーン・イン・フェミニズム」が自明のものとして寄生している「資本主義」体制を打倒することを目指すものだ、という意味である。
言い換えれば、「資本主義」体制の下では、どんなにうまくやっても「経済格差は広がる一方」でしかなく、しかも「資本主義」は、「富の独占」のために「地球資源の独占」を進める結果、この地球環境を、決定的に損滅しようとさえしている。
だからこそ、私たち「99%に属する男女」は、それがどんなに困難なことであろうと、私たち自身の尊厳と、私たちの子供や子孫の尊厳ある生を守るために、「資本主義」体制を打倒しなければならない、一一というのが、本書の主張なのだ。
では、「99%のためのフェミニズム」が実現を目指す「社会体制」とは、どのようなものなのかといえば、それは「平等な社会主義体制」であり、要は「みんなが平等に生活を保証される社会」の実現である。
無論それは、決して容易なことではないのだけれど、しかし、それを少しでも実現していかなければ、「99%に属する男女」は、今後ますます「1%のエリート」のための食い物にされ、何のために生きているのかもわからない、「搾取されっぱなしの人生」を送った末に、その奴隷的生涯を終えなければならない、ということになってしまう。
そして、さらにその先には、地球環境の決定的な破壊による、人類の滅亡なのだ。
だから、そうした「みんなが平等に生活を保証される社会」の実現が簡単ではないことくらいはわかっているし、過去には同種の理想を掲げながら、それが真逆の「過酷な独裁体制」に転化した挙句に破綻したという歴史があることも重々承知している。
それでも、私たちは、だからと言って「資本主義しかない」と、そう思い込まされ、諦めさせられてはならないのだ。
理想を目指しつつ、その中で常に議論と反省を繰り返しながら進んでいくのが、目指されるべき「新たな社会主義運動」であり、その中核となるのが「99%のためのフェミニズム」なのである。
『2 リベラル・フェミニズムは崩壊した
一一私たちは前に進まなければならない
主流メディアでは、フェミニズムという言葉自体がリベラル・フェミニズムを意味するのだとして(※ すべてのフェミニズムが)同一視されつづけている。しかしリベラル・フエミニズムは、解決策を提示することはおろか、それ自体が(※ 資本主義による格差)問題の一部なのである。グローバル・ノース(※ 豊かな北半球の国々)における経営者層に集中するそれは、「体制の一員になる(leaning-in)」ことと「ガラスの天井を打ち破る(cracking the glass ceiling)」ことを重要視する。特権を持つごく少数の女性たちが企業と軍隊(※ 大学など)の出世階段を上っていけるようになるという、そのことばかりに尽力した結果、リベラル・フェミニズムは市場中心の平等観を提唱することになった。その平等観は、現在世の中に蔓延する「多様性」に対する企業の熱意と完璧に符合する。「差別」を糾弾し、「選択の自由」を掲げているとはいえ、リベラル・フェミニズムは大多数の女性たちから自由とエンパワメントを奪う社会経済的なしがらみに取り組むことを頑として避けている。それがほんとうに求めているのは、平等ではなく能力主義(メリトクラシー)なのだ。社会における序列をなくすために働きかけるのではなく、序列を「多様化」し、「勇気を与えてくれるような(エンパワリング)」「才能ある」女性たちがトップへと駆け上がることを目指すのである。女性全体を単純に「過小評価されている」集団とみなすことによって、リベラル・フェミニズムの提唱者たちは少数の特権的な人々が同じ階級の男性たちと同等の地位や給料を確実に得られるようにしようとする。もちろんその恩恵を受けられるのは、すでに社会的、文化的、経済的に相当なアドバンテージを有する(※ 恵まれた)者たちである。その他の者はみな、地下室から出られないままなのだ。
ふくれあがっていく不平等とすっかり親和しながら、リベラル・フェミニズムは抑圧をアウトソースする(※ 弱者に外注して押しつける)。経営者層の女性たちはそれによってまさしく体制の一員となる(lean in)一一薄給の移民女性にケアの提供と家事を外注し、彼女たちに寄りかかれる(lean on)ように自ら膳立てすることによって。リベラル・フェミニズムは階級や人種に対して無関心を貫き、我々の(※ 女性は尊重されるべきという)信念をエリート主義や個人主義につなげてしまう。またフェミニズムを「孤立無援」の運動に仕立てあげることで、私たちと多数を脅かす方策とを結びつけ、その方策に対抗する闘いから私たち(※ 99%のために闘うフェミニスト)を切り離してしまう。端的に言って、リベラル・フェミニズムはフェミニズムの名をおとしめたのだ。
リベラル・フェミニズムの精神は企業的思考に集約されるだけでなく、新自由主義の文化における「逸脱的」な流れにも表れているだろう。個人の上昇という概念とリベラル・フェミニズムの親和性は、ソーシャルメディアで名を挙げたセレブリティたちの世界にも同様に充満しており、そのことがまた、フェミニズムと女性個人の社会的上昇とを混同させる。そうした世界では、「フェミニズム」は流行りのハッシュタグやセルフ・プロモーション(※ 自家宣伝)の手段となるリスクを負い、多数を解放するよりも少数を引き上げるために展開される。
概して言えば、リベラル・フェミニズムは新自由主義にとっての完璧なアリバイを提供したということになる。退行的な方策を解放のオーラで包み隠し、世界中の資本を支える勢力が自らを「進歩的」だとして演出することを可能にしたのだ。ヨーロッパにおけるイスラム嫌悪を擁護しながらアメリカの国際金融と提携するこのフェミニズムは、女性権力者の手中にある。「リーン・イン」を説く企業の指導者たち、構造調整やグローバル・サウスにおけるマイクロクレジットを推し進める(※ ことで、グローバル・サウスの奴隷化を図る)女性官僚、ウォール街でスピーチするごとに六桁の謝礼を巻き上げるパンツスーツ姿の「女性政治家」の手中に。
リーン・イン・フェミニズムに対する私たちの返答は、キック・バック・フェミニズムである。(※ガラスの天井を破るために)飛び散った破片の片づけを圧倒的多数の人々に押しつけてまで、ガラスの天井を打ち破ろうとすることに興味はない。役員室を占拠する女性CEOたちを賞賛することはおろか、私たちはCEOと役員室(※ に象徴される特権階級)自体を撤廃したいのである。』(P27〜31)
ドナルド・トランプに象徴されるような「保守派」の「男女差別的伝統主義」に対して、「リベラル・フェミニズム」は「男女が平等に活躍できる社会を目指すフェミニズム」を語っているかのように見える。
まるで「保守派とは真逆」な、「差別からの解放」を謳っているかのように見えるが、そうではない。
一一どちらも、「資本主義体制」つまり「1%のエリートと、その搾取対象たる99%のその他」によってのみ継続可能な「資本主義」体制を前提として肯定している点では、まったく同じなのだ。
両者は、「資本主義体制護持」のための補完勢力でしかなく、「保守派」というのは「リベラル・フェミニズム」の「引き立て役」でしかない。
男女平等を求める女性は、男女差別を伝統として認める「保守派」を敵視し、同じく「保守派」を敵視しているかのような「リベラル・フェミニズム」を味方だと思って、支持するだろう。「リベラル・フェミニズム」を支持していれば、男女の平等な社会が近づくように思っているだろう。一一だが、そうではない。
「リベラル・フェミニズム」とは「リーン・イン・フェミニスト」による「綺麗事のおためごかし」でしかなく、「平等な社会」を目指すものではあり得ない。
「リーン・イン・フェミニズム」たる「リベラル・フェミニズム」が目指すもの、その本音とは「1%のエリートと、その搾取対象たる99%のその他」によって構成される「資本主義体制」の護持なのだ。
エリートの仲間入りを目指し、それを果たした「リーン・イン・フェミニスト」たる「リベラル・フェミニスト」たちが、どうしてわざわざ「無能な大衆連中」と「同列化」されることになる「みんなが平等に生活を保証される社会」など望むだろうか。そうなれば、当然その分、自分たち(エリート)の生活水準は下がるのだから、そんなことを目指すはずがないのである。豪邸を捨ててアパート暮らしする気など、もとより彼(女)らには無いのである。
では、そうした「リベラル・フェミニズム」の「敵」と見なされている「保守派」とは、どういう存在なのかといえば、それは「リベラル・フェミニズム」に対する「敵役=悪役」を担う、言うなれば「引き立て役」なのだ。
世の中の流れは、基本的に「男女平等」「ジェンダー平等」に向かっている。しかしそれは、「すべての男女」や「すべてのジェンダー」が「平等に幸福になる」社会を目指すものではなく、「1%のエリート男女」によって搾取される対象として「平等」な「男女」であり「ジェンダー」に至るものでしかない。
どんな範疇に入ろうと、それが「搾取対象」であるのならば「なんら問題がない」。「平等だと認めてさえやれば、搾取対象のままであっても満足できるような愚かな大衆」には、形式上の「平等」を夢見させておき、「われわれ1%のエリートは、彼らから搾取する実を取ろう」というのである。
そして、その際に「悪役」になってくれるのが、わかりやすく反時代的な「保守派」である。

「保守派」が、わかりやすく「貧しい人たち」の支持を取り込んで、一定の力を持ったとしても、それで「資本主義体制」が転覆されるわけではない。
だから「リーン・イン・フェミニスト」も「エリート」のままだし、憎まれ役の「保守派」がいるからこそ、「リベラル・フェミニズム」は「あんな、反時代的な差別主義者(保守派)に騙されてはいけない。私たちは皆、平等であるべきだ!」などと「正義の味方」を気取ることもできるのである。
そうした意味で、「リベラル・フェミニズム」と「保守派」は、「資本主義体制護持のための補完勢力」なのである(日本で言えば、公明党と自民党みたいなものか)。
だから、上の(2つ目の)引用文の中で、
『概して言えば、リベラル・フェミニズムは新自由主義にとっての完璧なアリバイを提供したということになる。退行的な方策を解放のオーラで包み隠し、世界中の資本を支える勢力が自らを「進歩的」だとして演出することを可能にしたのだ。』
ということになるのである。
また、だからこそ、日本における「リーン・イン・フェミニスト」の代表格たる、「武蔵大学の教授」でフェミニストを自称する北村紗衣は、「部落差別」「在日朝鮮人差別」「沖縄米軍基地問題」になど、興味はないのだ。
なぜなら、それらは「資本主義体制」において必然的に生み出された「搾取対象」であり、そうしたものがすべて無くなってしまうことなど、「リーン・イン・フェミニスト」である北村紗衣は、毛ほども願ってはいないからである。
だから、私たち「99%の男女」は、「資本主義体制」に組み込まれた、その「御用思想」でしかない「リベラル・フェミニズム」に騙されてはならない。
「リーン・イン・フェミニスト」たちは、本当の意味での「平等」など求めていないし、「みんな(100%)のための平等」など、まったく望んではおらず、むしろ、それを妨害するために、「偽物の理想」としての「リベラル・フェミニズム」を振り撒いて、「資本主義の侍女」としての役目に邁進しているのである。
一一以上が、(1)の〈北村紗衣に代表される「リーン・イン・フェミニズム」の問題。〉についての説明だ。
○ ○ ○
では次に、(2)の問題たる〈なぜ「反資本主義」のためには「フェミニズム」が必要なのかの理論的根拠。〉についての説明をしよう。
経済学に詳しくはないので、大雑把で不正確な説明しかできないかもしれないが、そこはご容赦願いたい。
さて、カール・マルクスに始まる「反資本主義」としての「社会主義」経済論というのは、「労働における搾取」理論(剰余価値論)を中心に展開されてきた。
労働者がその労働によって産む「価値」の中から、少なからぬ「余剰(剰余)価値」を資本家が搾取する。そしてさらに、その「余剰価値」を新たな価値を生むための資産とすることで、「資本主義」経済を、発展的に回してきたのである。
言い換えれば、「資本主義」経済が、発展的に成長するためには、より多くの「搾取」が必要だということであり、言うなれば、資本家(経済エリート)は、労働者大衆から、可能なかぎり搾り取ってこそ、資本主義は目覚ましい発展を遂げることが可能だということである。だからこそ、労働者は「生かさず殺さず」なのだ。
つまり、搾り取りすぎて殺してしまっては、金儲けのための「労働力」が失われてしまうから、そこまでは、したくても出来ない。しかし、より効率的に搾り取る社会体制を構築できるならば、労働者に「余裕」を与える必要はなく、いかにギリギリまで搾り取るかが問題となるのだ。
例えば、労働力を国内だけで調達しているかぎりは、その労働力に対して支払われるべき対価は、一定のところで限界に達してしまう。しかし、外国から安い労働力を調達できるようになれば、それに合わせて、国内の労働力への対価支払い水準を下げることができて、その分が「儲け」になる。国内労働者は、これまで以上にその身を削ってでも頑張らないわけにはいかなくなるのである。
で、これは「外国から労働力を調達する」という譬え話だが、日本を含む多くの国では、現実には「生産ラインを外国に移して、安い労働力を確保することで、生産コストを下げる」ということになった。そうなって久しいのだが、これが「グローバル経済」の基本的な構図だ。
しかし、人間を含む「地球資源」は、基本的に「閉鎖系」であるから、「誰かが儲ければ、誰かが損をしている」ということになる。
もちろん、「太陽光線(エネルギー)」のように、外部から一方的に持ち込まれる「資源」もあるけれども、それも「消費」すれば「ゴミ」となって、地球という閉鎖系の中に溜まっていくだけだ。つまり、もともと地球にある資源は掘り尽くされてゴミに変わり、外からくる資源もゴミになる。
ここで問題となるのは、地球環境の「回復力」で、その範囲内での「消費」なのであれば、地球環境の「恒常性」は保てるわけなのだが、「資本主義」における加速度的な「拡大再生産」とその「過剰消費」においては、その「消費」を、地球の「恒常性」の範囲内にとどめておくことはできない。
したがって自ずと、不可逆的な「環境破壊」へ、そして「資本主義」が必然的にもたらす「人類の破滅」へと、まっしぐらに進んでいるというのが、今の私たちの世界なのである。
そして、そうしたことと「フェミニズム」がどう関係してくるのかというと、要は「女性差別」というものもまた「資本主義的な搾取」の重要な一形態であり、そうでありながら、マルクスの経済学では、「女性が無償で担わされた家庭内の(ケアの)問題=社会的再生産の問題」が、ほとんど意識・考慮されていなかった、ということなのである。
『社会的再生産とはなにか
私たちの「マニフェスト」は今日の危機のあらゆる側面に対処しようとするものである。しかしそのなかでも、ジェンダーの非対称性と構造的につながっている社会的再生産の側面に特別の関心を寄せている。よって、もうすこし踏みこんだ質問をさせてほしい一一社会的再生産とは、厳密には何なのだろう?
「ルオ」の例について考えてみよう。ルオ(姓以外非公表)は台湾人の母親で、二〇一七年に息子に対して訴訟を起こした。その内容は、彼の養育に費やした時間と費用に対して賠償金を払うことを求めるものだった。ルオは二人の息子をシングルマザーとして育てあげ、その双方を歯学部に入学させた。それに対する返礼として、彼女は息子たちに自分の老後の面倒を見てほしいと考えていた。息子のうち一人がその期待を裏切ったとき、彼女は彼を訴えたのだった。台湾の最高裁判所は、その息子にアメリカドルで九六万七千ドル〔日本円で約一億四百万円〕支払うよう求めるという前例のない判決を下した。その名目は、彼の「養育費」としてだった。
ルオの例は、資本主義の支配下にある生活の三つの基本的な特徴を示している。ここでまず明らかにされたのは、資本主義が無視したがる、あるいは隠そうとする人間の普遍的事実である。それはつまり、人間を産み、世話し、生かすことには莫大な時間と費用が必要であるということだ。二つ目に示されたのは、人間をこの世に生み出し、その生命を維持する仕事は、我々の社会ではいまだに女性たちによってなされているという事実だ。もう一つルオの例が明らかにしたことは、自然な成り行きに任せていては、資本主義社会は前述の仕事に依存しつつもそれに対して何の価値も認めないということである。
また、ルオの事例は私たちに四つ目の気づきを与えてくれる。それはこの「マニフェスト」とも深く関係している。すなわち、資本主義社会は二つの必要条件一一綿密に編みあわされ、かつ対立してもいる一一によって成り立っているということだ。その必要条件とは、利潤の形成という特徴的なプロセスを通して資本主義それ自体を存続させようとすることと、人間の形成というプロセスを通して人間たち自身が自らを生かそうとすることである。「社会的再生産」は、後者に属している。一丸となった社会的存在としての人間、つまり食べたり眠ったりするだけでなく、子どもを育てたり家族の世話をしたり、共同体を維持したりしながら、未来への希望を抱いている人間たちを生かす行為は、社会的再生産に含まれる。
人間を育むこのような行為は、すべての社会においてなんらかのかたちで表出する。しかし資本主義社会には、これらの行為が従属すべきもう一人の主人がいる一一それは資本である。資本は、社会的再生産労働が「労働力」を生み出し、補塡するかぎりにおいて存続できる。最小のコストでその「特殊な商品」を十分な量確保したいがために、資本は社会的再生産の仕事を女性や共同体、国家に押しつけつつ、利益を最大化するのに一番特化したかたちに落としこもうとしている。マルクス主義フェミニズムや社会主義フェミニズムを含むさまざまなフェミニズム理論、また社会的再生産論は、資本主義社会における利潤の形成と人間の形成のあいだにある性質の矛盾を分析してきた。また、前者の実現のために後者を手段として利用する資本の本質的な傾向を明らかにしてきた。
マルクスの『資本論』を読めば、搾取とは何であるかがわかる。それはつまり、生産という過程のなかで資本が賃金労働者を不当に扱うことである。搾取の場において、労働者たちは本来ならば生活費を十分にまかなえる程度の賃金を支払われるはずだが、実際彼(女)らが生産している量はそれよりもずっと多いのだ。言いかえれば、私たちは自らの生活や家族を支え、属する社会のインフラを維持するのに必要な時間を超えて、より長く労働することを「上司」たちから求められている。彼(女)らは、私たちが上げた余剰を事業主や株主の利益に割り当てる。
社会的再生産論者たちはこのような状況を拒絶するというよりは、その不完全さを指摘してきた。マルクス主義者や社会主義フェミニストと同じく、私たちはしつこく疑問を投げかけつづける。仕事に来る前に、彼女は何をしなければならなかったのか? 誰が彼女の夕食を作り、ベッドを軽え、くたびれる毎日、それでも仕事に戻れるよう、彼女の苦悩を和らげてやるのか? こうした人を育む仕事はほかの誰かがやってくれるのか、それとも彼女自身が一一自らのためだけではなく、家族の誰かのためにも一一それをしてきたのか?
これらの疑問が明らかにするのは、資本主義が包み隠そうとしてきた一つの事実である。すなわち、利潤の形成のための賃金労働は、人間の形成に関わる(ほとんどの場合は)無償の労働なしには存在しえないという事実だ。したがって、資本主義による賃金労働の制度は、余剰価値以上の何かを隠していることになる。そのなかには、制度の成立条件でもある一一つまり消えない痣のようなものだ一一社会的再生産という労働が含まれている。とは言っても、人と利潤の両方の「生産」にとって不可な社会的過程や制度は、分類上区別されたとしても、たがいに補完しあっていることには違いない。
さらに言えば、それら二つを区別すること自体が資本主義社会の産物だと言えるだろう。これまでも話してきたように、人間を育む仕事はいつだって存在し、つねに女性と結びつけて考えられてきた。しかし、過去の社会では「経済的生産」と社会的再生産がここまで明確に区別されることはなかった。資本主義が到来してはじめて、社会的存在のこれらの側面は二つに引き裂かれたのである。生産は工場や炭鉱、オフィスなど、現金給与によって対価を支払われ、「経済」に関係があるとされている空間へ移動していった。再生産は「家庭」へ、つまり女性的・感傷的であると規定された空間へと追いやられていった。「家庭」において、再生産労働は「仕事」ではなく「ケア」だとして定義され、金銭ではなく「愛」のためになされる行為となった。すくなくとも、私たちはそう教えられてきた。実際のところ、資本主義社会が社会的再生産を完全に個人の家庭に委ねたことは一度もない。そうではなく、社会的再生産の一部をつねに地域に、つまり小規模な共同社会に、また公的制度に、市民社会に割り当ててきたのである。そして、一部の再生産労働を長いあいだ商品化しつづけてきたし今日ほど大々的に行われた時代は一度もなかったにせよ。
それでもなお、利潤の形成と人間の形成の分断は、資本主義社会の核となる根深い摩擦をあぶり出している。利益を増やそうと資本がシステマチックに奔走する一方で、労働者階級の人々は社会的存在としてまっとうな、有意義な暮らしを送るべく努力しているのだ。これらは根本的に共存しえない目標だろう。なぜなら、資本の利益の分け前は、社会生活における私たちの取り分を犠牲にしなければ増えることはないからである。家庭生活を豊かにする社会慣習や、家庭外での暮らしを支えてくれる社会福祉は、つねに利益に食いこむ恐れがある。ゆえに、それらのコストを抑える財政的措置や、そうした労働を弱体化させる思想的策略が、資本主義というシステム全体に特有のものとなっている。
利潤の形成が人間の形成の重要性を上回ること、もしもそれだけが資本主義の物語であるとするなら、資本主義というシステムは正式に勝利を宜言することができるだろう。しかし資本主義の歴史とは、まっとうかつ意義のある生活を求める人々の闘いによって形作られてきた歴史でもある。賃金闘争がしばしば「パンとバター(生活の問題)」をめぐる闘いとして語られてきたことは偶然ではないのだ。ただ、そのような生活の問題を、これまで多くの労働運動がそうしてきたように、職場における要求のみに限定してしまうことは間違っていると言わざるを得ない。資本は、単なる生活の手段として賃金を定める。そうやって制度化された社会における賃金と生活の不安定な関係、その嵐のような様相を、これまでの運動は見過ごしてきた。労働者たちは賃金のために闘っているのではない。そうではなく、彼(女)らはパンとバターを得るために、賃金をめぐって聞うのだ。生活の手段を求めることは決定因子であり、結果ではない。よって、食物や住居、水、医療、教育などをめぐる闘いはつねに賃金闘争のかたちをとって一一つまり、職場においてより高い賃金を求めるというかたちで一一表れるわけではない。たとえば、思い出してみてほしい。近代におけるもっとも大きな二つの革命、すなわちフランス革命とロシア革命は、女性たちによるパン暴動から始まったということを。
社会的再生産をめぐる闘争が真に求めるのは、人間の形成を利潤の形成よりも優先する社会構造である。決してパンだけを求めているのではない。このような理由から、99%のためのフェミニズムはパンとバラのための闘争を具体化し、推し進めていくのである。』(P123〜132)
どうだろうか? 多少は難しいかもしれないが、私のそれまでの説明で、おおよその雰囲気くらいは掴めたのではないだろうか。
要は、これまでの「資本主義論」では、「家庭」を中心とした社会的な「再生産」を、「資本主義経済」の問題(そのもの)だとは考えておらず、そこまで含めて「賃金」を支払うべき対象だとは考えられていなかった、ということなのだ。
どこまで意識されていたかは別にして、「資本家」たちは、それは「労働とその対価」という問題とは完全に無関係な「私生活の問題=感情生活の問題」だと考えることによって、そこでの女たちの労働を「搾取」してきたのであり、私たちはそれに、まんまと騙されて(あるいは、乗せられて)きたのである。
今この「不平等」な「格差社会」を考える上で、私たちが重視しなければならないのは、これまで「家庭の問題」として、主として女性たちが「無償で担わされてきた労働」に対して、正当な対価としての賃金を、「資本家」たちに支払わせることなのだ。
だからこそ、その意味で「フェミニズム」は、「格差を生む資本主義」に対抗するための、中心思想のひとつとして重視されなければならない。それは、これまで見逃されてきた「資本主義の欺瞞」を暴いて、平等な社会を実現するための思想なのである。
しかし、そうした「平等な社会」が実現すれば、当然、資本主義経済社会におけるそれのような「急激な進歩発展」は見込めない。
だが、そんなものは所詮「1%のエリート」のためのもの(過剰な贅沢)でしかない。私たちはこれまで、その「おこぼれ」を、過大に「ありがたがらされてきた」だけなのだ(しかも、その過剰な贅沢によって、地球環境は毀損されている)。
本当は、もっともっと「平等に」豊かになる権利が、私たち労働者にはある。少なくとも「すべての人が平等に生活を保証される社会」を享受する権利を持っているのである。
だから、私たちは「本来、女性がケアワーク(=社会的再生産)の対価として得られるべき対価」を、平等に「分配」しなければならない。当然、男性が働いて得る対価も含めて、それらが平等に「再分配」される「非資本主義」的な社会体制を実現しなければならない。
それがなされないかぎり、女性ばかりではなく、「99%の人々(男女)」の誰もが、真の意味での「社会的平等」を享受することはできないのである。
この「99%のためのフェミニズム」とは、「すべての人の平等」を実現するための足がかりとして、決して無視し得ない思想的要諦なのである。
○ ○ ○
ところで、私は以前、黒澤明監督の映画『天国と地獄』のレビューで、以下のように論じた。
『本作についての私の評価は、「刑事もの」「誘拐もの」の「エンタメ作品」としては十分に楽しませてもらったものの、黒澤が込めようとしていた「天国と地獄」のテーマは、(※ 営利目的の誘拐犯である)竹内銀次郎の造形が曖昧であったために、今ひとつ成功していなかったのではないかと思う。
ただ、本作に描かれる、人間にとっての「天国と地獄」とは、「社会的・経済的な地位に、比例即応するものではない」という、いかにも黒澤らしい「庶民の側に寄り添ったヒューマニズム」であったことは確かだろう。
しかしながら、その「弱者」であったはずの竹内銀次郎が、「子供という弱者」を狙った犯罪を犯した段階で、彼の「正義」は、すでに破綻していたと言えるだろう。
つまり、「被差別者」であるならば、「何をしても許される」というわけではない、ということだ。
だからこそ彼は、相応に断罪されねばならず、同情を惹くことも叶わなかった。
まただからこそ、「哀れみなどいらない」と、そう強がるしかなかったのではないか。
そしてこれは、「社会的弱者」としての「少数民族」「貧乏人」「女性」などなどについても、基本的には同じことであろう。
彼ら彼女らが、その「社会背景」や「権力関係」において犯罪を犯す場合、そこには「考慮されるべき点(情状)」が多々あるにしても、それだけで、その行為が「すべて免責されるわけではない」ということである。』
こう論じた上で、北村紗衣による次の書評を引用した。
『『書評『男はクズと言ったら性差別になるのか』アリアン・シャフヴィシ著
「不平等を考える良い手引き」
2024年9月28日 2:00
差別の問題を考える時にまず頭に置かなければならないのは、社会における権力関係で一般的に優位な立場にあるのはどちらか、ということだ。たとえば女性より男性のほうが、少数民族よりも多数派の民族のほうが、同性愛者よりも異性愛者のほうが優位な立場にあることが多い。これを頭に入れずに差別を考えると、混乱したり、おかしな結論が出たり、場合によっては差別の存在そのものを否定してしまったりするようなことにつながり(以下略)』
(「日本経済新聞」掲載の、北村紗衣の書評より)』
そして、この書評について、次のように論じた。
『つまり、この書評の例のように、「男性が女性をクズ呼ばわりする」のは、その「社会的な権力関係」における「男性の優位性」にあぐらをかいてのものだから「問答無用に許されない」が、「女性が男性をクズ呼ばわりする」場合は、その背景にある「権力関係」に注目して、それが「社会的弱者」としての「止むに止まれぬ行為」だったのではないか、といった「配慮」が是非とも必要だ。一一というような考え方は、書評子の指摘を待つまでもなく、もはや「常識」に類する話ではあろう。
だが、問題は、考慮されるべき「権力関係」とは、なにも「男性社会だから」といったこと「ひとつだけではない」という現実である。
例えば、「男女(性別)」に限らず「年齢」「職業」「経済状況(貧富)」「知名度」「社会的な肩書き(階級)」等々も、すべて考慮の対象としなければならない「権力関係」なのである。
したがって、彼や彼女の犯した「罪」について考慮されるべき「背景」として、当然「権力関係」の問題があるにせよ、考慮されるべきそれは、決して「単純・単相的もの」ではなく「複雑・多層的なもの」だ、ということをも、決して忘れてはならない。
それはちょうど、本作『天国と地獄』の犯人である竹内銀次郎が、「貧乏人という弱者」ではあったけれども、その一方で「子供の対する大人という強者」であったがゆえに、その犯行は、完全に「免責されうるものではなかった」というのと同じことである。
本作『天国と地獄』が、どこかすっきりしない作品になってしまった原因は、そんなリアルにおける「多層性」を、「天国と地獄」という「両極二層性」の図式に還元してしまったことによるものだったのではなかったか。
「現実」とは、そう単純に「図式化」できるものではない、ということである。』
つまり、この段階では、私自身、女性差別の問題を「資本主義」の問題として捉えるということが出来ていなかったものの、この社会の問題を「男女差別」の問題に一元化する発想には、当たり前に異を唱えていた。
私たちが考えるべき差別は、単なる男女差別の問題でも、経済的貧富の問題でもないと。
問題の根底には、「他者からより多く搾取することで富を築き、そのことで必然的な貧富を産む資本主義システム」というものの問題があった、ということである。
このシステムを打倒しないかぎり、私たちはただ「幸せになりたいだけ」で努力しても、「どこかの誰かからの搾取」をしないではいられないのである。
その意味でも、私たちは「すべての人の幸福」のために、公平な「再分配」のなされる社会を目指さなくてはならないのだ。
たとえ、それがどんなに困難なことであろうとも、むざむざ、誰かの餌食にはならず、誰をも餌食にしないために。
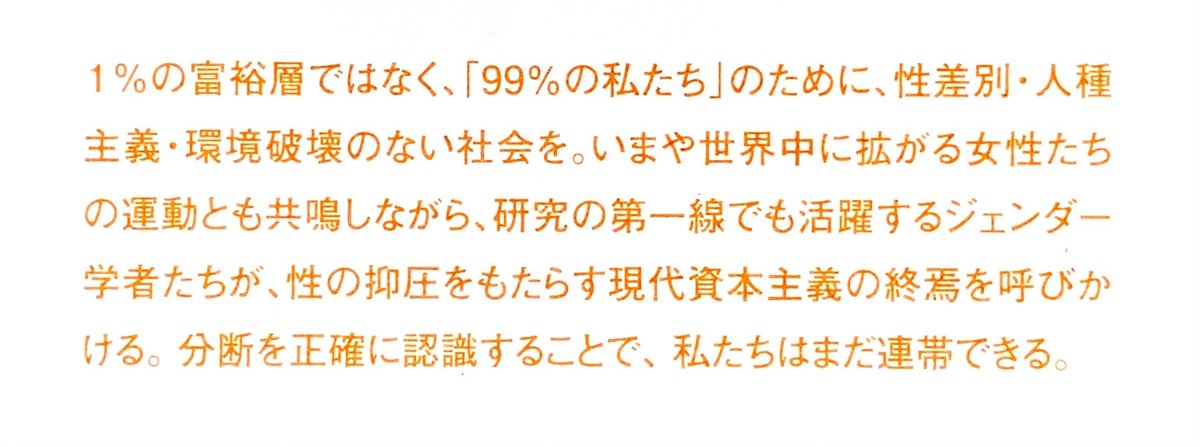
(2025年1月15日)
○ ○ ○
○ ○ ○
(※ 北村紗衣は、Twitterの過去ログを削除するだけではなく、それを収めた「Togetter」もすべて削除させている。上の「まとめのまとめ」にも90本以上が収録されていたが、すべて「削除」された。そして、そんな北村紗衣が「Wikipedia」の管理に関わって入ることも周知の事実であり、北村紗衣の関わった「オープンレター」のWikipediaは、関係者名が一切書かれていないというと異様なものとなっている。無論、北村紗衣が「手をを加えた」Wikipediaの項目は、多数にのぼるだろう。)
● ● ●
・
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
○ ○ ○
