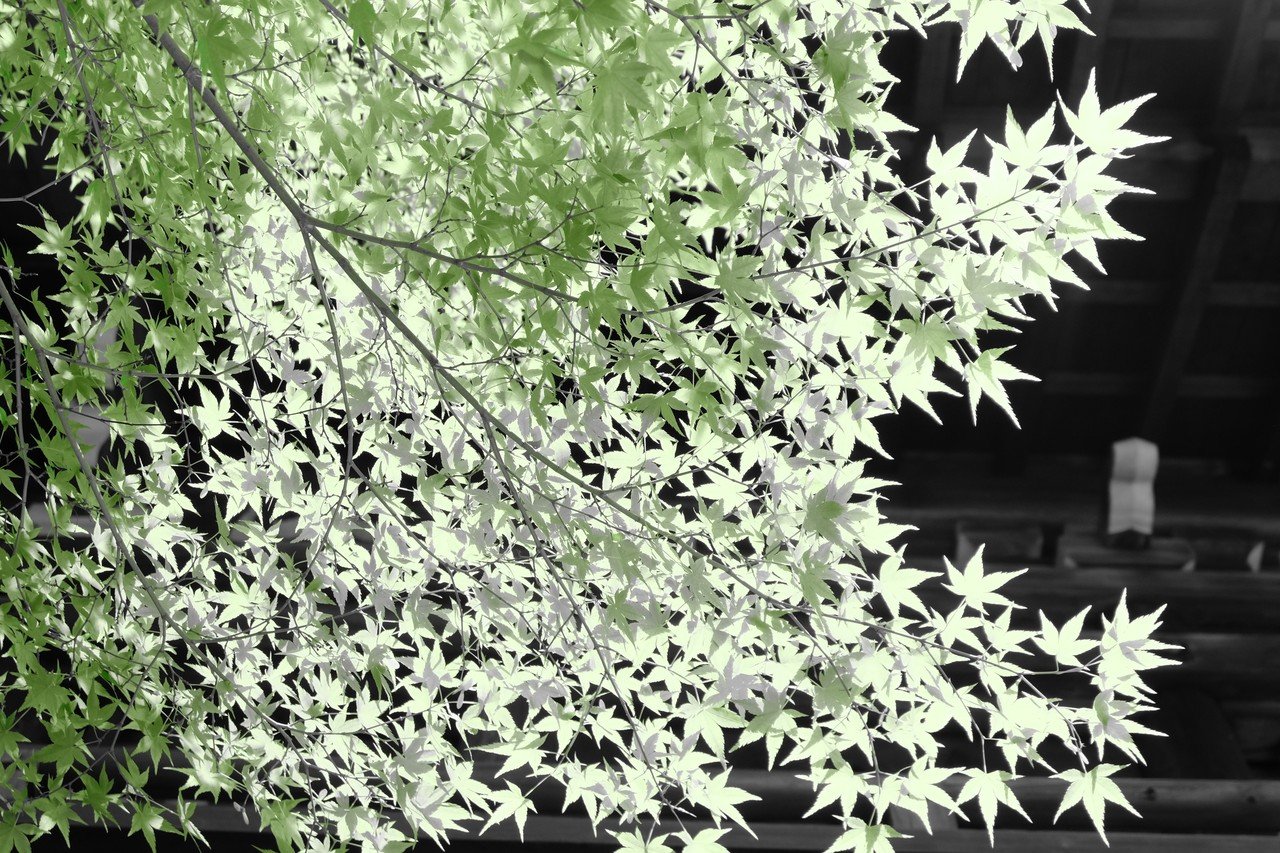2020年6月の記事一覧
過日の茶室に飾られていたお軸は『渓聲』であった。或る晩に坐っていると、水のせせらぎが釈迦の聲に聴こえたという有名な蘇東坡の句になる。眼と同様、私たちの耳には外界の聲がほとんどはいっていない。おそらく森羅万象が今朝もささやきかけてきているものの、一度も耳を傾けられたことはないのだ。

靈は霊に堕してから、祝詞箱を意味する「口」を三つも失い、文字通り靈力を失った。人が守護靈に依存するようになった分岐点である。肉がある奇蹟を忘れ、目に映らぬ虚へと逃げた。本来は人が靈を護るべき存在であるのに。このような心意氣を灯せば、日々、靈は肉端会議をしにやたらと人に集まるのだ。