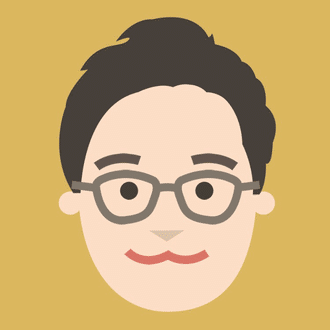改めて考えるSTEAM人材の本質とは? 中心に人間性が求められる時代
「STEAM人材って、本質はそこにあったのか・・。」
ここ2-3年でよく耳にするようになったSTEAMという言葉。アメリカのシリコンバレーを中心に優れた人材に求められる要素として、またこれから育成されていく未来の人材開発としても注目されています。
STEAMとは、科学(Science)技術(Technology)工学(Engineering)アート(Arts)数学(Mathematics)の5つの頭文字を取った造語。STEAM人材とは未来を担う新しい人材像、STEAM教育はそのような人材を育成するための教育のことを言います。
元々は科学、技術、工学、数学のSTEMというバリバリ理数系の4要素で構成された概念が2000年代初めに登場し、そこにアートが加わり最近STEAMとして注目されるようになりました。
このSTEAMの5つの要素を持つとはどういう意味なのか、アートが加わることは何を意味しているのか、改めて「今求められる人」について考えます。
STEAM人材
SETAM人材とは、先のご紹介の通り科学(Science)技術(Technology)工学(Engineering)アート(Arts)数学(Mathematics)の5つの分野に長け、最先端テクノロジーやサイエンス、エンジニアリングのスキルを持ちながら、芸術やデザインでも才能を発揮し、失敗を恐れずに積極的にチャレンジし続ける人たちのことです。
彼らの頭に常に言葉があります。それは「Why」。答えのない問題に「なぜ?」という問いを投げかけ、個人の知を他の人の知と結びつけながら学習し問題解決していきます。
もともとはSTEMという理数系の4要素だったものに、追加された要素が「A=アート」。このアートは、音楽、芸術、演劇や映画といったものに加えて、文学や哲学といった教養としてのリベラルアーツも含まれています。
それまでのSTEMにA=アートを加えることで人間の生活がより豊かになることがわかり、ビジネスの分野でもアートやデザインの役割がこれからますます大きくなると言われています。先日アートシンキングという言葉も取り上げました。お時間があればご参考ください。
STEAM人材について詳しく書かれた書籍「世界を変えるSTEAM人材 シリコンバレー『デザイン思考』の核心」はこれから求められる人材、そして誰もが持つべきマインドセットについて非常に分かりやすく書かれています。この本が出版されたのはコロナの前ですが、この本で書かれていることはコロナショックによって、ますます重要性が高まっていると感じます。必読の一冊と言えます。
この本には、これからの変化の多い時代を生き抜く我々が持つべきマインドセットとスキルセットについて詳しく解説されています。未来を牽引するSTEAM人材に求められる3つのマインドセットがこちらです。
1.型にはまらない自由な発想(think out of the box)
2.「ひとまずやってみる」精神(give it a try)
3.失敗して、前進する(fail forward)
特にこのコロナ禍においては、これまでの常識では測れない事が増え、今まで不可能と思えた事柄に対しても積極果敢にチャレンジし、スピードを持ってアイデアを作り上げる力が求められるようになりました。
上記の3つのマインドセットは正に今、我々が求められるマインドセットと言えます。世の中をhappyにするためのイノベーションを起こすには「とりあえずやってみて、失敗して、前進する」というマインドセットが重要となります。
私の周りにもシリコンバレーで学んできたメンバーがいますが、現地では失敗を「誇り」だと考えます。より多く失敗した人間は「人財」として認められより価値の高い仕事に就けます。失敗は新しい価値創造へのチャレンジの証。その経験はプライスレスです。積極的に失敗し、経験し、学び、前進する。このスタンスが前提としてあります。
STEAMの「A」が持つ意味
前述の通り、STEMの理数系要素にアートのAが加わったことは何を意味しているのでしょうか。まずSTEAMは5つの要素の頭文字でありますが、単にこの5つの「科目」を重点的に学ぶことを指しているわけではありません。
大切なのは「融合」によるシナジーです。多分野の要素を有機的に結合させて新しい問題に対して答えを探していく思考と行動力を身に着けていくことが大切です。
そして、STEMからSTEAMへという流れの背景にある考え方として先に紹介した書籍には「人間を重視する」という思想・行動原理があり、つまりはヒューマニズムが根底に流れていると解説しています。
STEMにアートを組み合わせること自体は手段にすぎません。その目的は「人間を幸福にする」というヒト視点が加わっているところが重要な変化点です。STEAM人材が大切にしている考え方として次のような思いが共通しています。
・人類のために役に立ちたい
・人間の生活をよくしたい
こうした熱い想いの上に、人間とは何かという答えのない問いかけを続ける姿勢があります。テクノロジーを駆使してヒト視点で問題解決をしていく、その根底には「人の幸せ」があるということです。
過去の経済成長期の日本はいかに企業の売上利益を上げるのかという、利己的な視点が蔓延していた時代がありました。しかし、今はそうした視点では立ち行かない時代です。透明性が当然として求められ、社会課題を解決するために活動する企業に生活者は熱い視線を送ります。こうした時代には、人々の生活をどうすれば豊かにできるのかという、熱いパッションとアクションが求められます。それをスピーディに具現化していく人材のことをSTEAM人材と言っているのだと思います。
まとめ
今回ご紹介したSTEAM人材に求められるスキルは、もともとはシリコンバレーの人材やイノベーションに関係のある仕事に就く人に求められるものでした。しかし、コロナ禍の今、こうしたスキルは一部の限定的な人に求められるものではなく、答えのない問題に取り組む多くの人に求められるスキルと言えます。
今回ご紹介した書籍には「イノベーションに求められるスキルやマインドは後天的に身に着けることができる」とあります。これはとても勇気づけられます。イノベーションは誰でも起こせるということです。
しかしそこには重要なポイントがあります。例えば、ある問題に取り組んで正解した後にかける言葉として「君は頭が良いね」と「君はよく頑張ったね」と2つの言葉をかけるとします。前者は「固定型マインドセット fixed mindset」と言って、問題が解けなかったり失敗したりすると自分には能力がないと思い込んでしまいチャレンジしなくなります。後者は正解したかどうかよりもそのプロセスに目を向けることができ努力に意識がいきます。これを「成長型マインドセット growth mindset」と言い、リスクをとって果敢にチャレンジしていくことができます。
イノベーションは失敗を経験と学びに変えながら前に進んだ先にあるもの。そう考えると「成長型マインドセット growth mindset」を持つ必要があり、人材育成上は結果よりもプロセスを重視することが求められます。
こうした要点を抑えながら、好奇心をもって、失敗を恐れず、新しいイノベーションにチャレンジできる自分でありたいし、そうした組織で働きたいと改めて思います。そして子育ての視点としても学びが多かったです。
今回の記事はご紹介した本の片鱗をピックアップしたにすぎないので、伝えたいことが他にたくさんあります。新しい価値創造にチャレンジする人も、変化の見えない今の時代に組織で働く人も、そして未来を担う子供達を育てる親御さんにも参考になろうかと思います。未来の羅針盤にもなりえる一冊ですので、是非ご一読されるとよいのではないでしょうか。
「人間を重視する」という行動原理を中心に置きながら、利他の精神で豊かに生きていきたいですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
いいなと思ったら応援しよう!