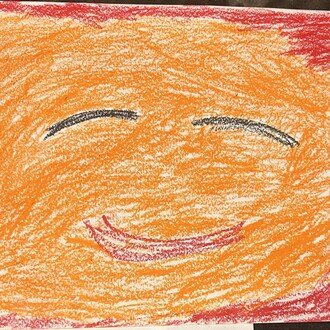【拡散希望・みんなで考えたい】学校って本当に行く必要があるの?今こそ声を届けるチャンス。
「入学当初は50分間座っていられず15分づつ色々なプログラムを切り替えているみたいですが、1年生が終わる頃には座っていられるようになるって言っていました。集中できているとは別なんですけどね」
とある日。
次男の通う保育園で「就学前懇談会」が開かれた。
就学まで残すところ2ヵ月となり、就学に向けて保育園や家庭で取り組んでいる事、不安な事を皆で話そう…という会だった。
その中で、保育園の先生から近隣小学校の先生から聞いた「最近の子供の傾向、小学校入学後の様子」という話が伝えられて、そのな中で出てきた言葉。
「1年生が終わる頃には座っていられるようになる」
え、そこ?
座る事が目的なの?
私はこの一言が無性に気になってしまった。
少子化の今、数十名を一箇所に集めて「座っていられるようにする」事が、本当に必要なのだろうか?
この記事を書くキッカケ
芦屋市の高島市長が、次の「学習指導要領」の方向性の検討に関わる事になったそうだ。
この記事の中で、私が最もドキっとしたのはこの部分だった。
私は、そろそろ真剣に、学校って本当に必要か、考えなければならないと思っています。もしかすると基礎学力をつけるだけなら、家でAIと学んだほうが効率的かもしれません。
でも私は、学校は必要だと思います。なぜなら、学校が「学び合いの場」だからです。学校はこどもたちにとって、最も身近な社会です。だからこそ、学校を、民主主義を学ぶ場にしたい。
学校って本当に必要か?
高島市長の記事の通り、「基礎学力」をつける事が目的なら別の方法が沢山あるし、一斉授業の難しさを何度も感じてきた。
日本人は「長く続ける事」を美学とする部分があり、この「学校スタイル」を変える事には物凄く抵抗を感じる人が多いと思う。
だけど、不登校が毎年増え続けて、産業構造も大きく変わろうとしている今、本当に100年以上続くこのスタイルを継続するべきなのか?
勇気を持って、ゼロベースで必要性を問い直してみたい。
「学び」とは何なのか?
保育園の懇談会でも、「就学を前に取り組んでいる事」として学習面に関しても様々な意見交換が行われた。
でも。
そもそも論として。
たった6歳の子供が皆一律にできるようになるって凄くハードルが高い気がする。
4月生まれと3月生まれでは、生きてきた時間が1年も違う。
40歳の1年なんて、つい昨日の事みたいだけど(笑)
6歳の1年は物凄く密度が濃くて、大きく成長する1年だ。
その1年の開きがあり、興味・関心・生活リズムが違う子供が一律に学ぶ。
1年生に限った事ではなく、学校での学びは学習指導要領に合わせなければいけない。
1年生は足し算・引き算
2年生は九九
3年生は割り算
と言う様に、既に分かっていても、足し算が分からないままでも、どんどん「学校の授業」は先へ進んでいく。
「人生100年時代」なんて言われて、子供が義務教育を終える15歳から100歳まで85年もある。
それなのに、義務教育の9年間をこんなに慌ただしく「足並みを揃えて」学必要が本当にあるのだろうか?
主体性とは何なのか?
高島市長は、記事の中でこんな事を書かれていた。
中でも、大切なテーマが「主体性の回復」です。学力は高い、でもウェルビーイングや学びへの意欲は低い。この課題の解決には、主体性をどう取り戻すかが重要だと考えます。
工藤先生の講演でも頻繁に出てくる「主体性」という言葉。
改めて調べてみたら、こんな風に定義されていた。
・主体性:何をすべきかを自ら決定し、責任やリスクを理解したうえで周囲に影響を与える
・自主性:目的が明かになっている枠の中で、何が必要かを自ら判断して行動する
無理じゃない?
小学校へ行けば、北海道から沖縄まで。
6学年全体で10人にも満たない小学校でも、1学年が150人超いる学校でも、みんな一律に「1学期は〇〇」ってやる事を決められている。
就学前に「1年生になった時に困らないように」と、先取学習が始まる。
小学校1年生から中学3年生まで、きっちりとカリキュラムが組まれていて、息つく暇もないほど「学び」という名の「ノルマ」が降りてくる。
更には、放課後の過ごし方すらも「自由な意思決定」が許されない子供が増えている。
学校でも家でも、「あぁしろ、こうしろ」と指示されて日々を過ごしている子供に「主体性」を求める。
これって無理じゃない?
誰かを責めているワケでもなく、何かを批判したいワケでもなく。
自戒も込めて、笑ってしまう。
「これは無理ゲーだよ」って。
大人も自信がない
教育現場を見ても、社会を見ても、政治を見ても。
何だかモヤっとした気持ちになる。
それは、やっぱり「正解のない時代」が来てしまったからではないか。
昔のように、人口が増え続けていた時代は競争があった。
同世代の中で、より良い学校へ行き、より良い就職先を見つける事が勝ち組へのルートだった。
だけど、2010年代に入ってから徐々に「殆どの仕事はAIに代替される」等と言われるようになり、何を学ぶべきか?すら分からなくなってきた。
大人自身も、自分が続けてきた仕事が10年後20年後も存在するのか?世の中に必要な仕事なのか?が分からない。
子供に対しては、本当に身につけなければいけない力は何なのか?が全く見えない。
ここ数年は特に「自分軸」という言葉に代表されるように「自分の幸せを追求せよ」という風潮も高まってきている。
でも、かつて子供だった私達も「自分の幸せ」と言われても分からない人が多いのではないだろうか?
学校の成績、進学先、就職先で常に「他人からの評価」を受けてきた。
結婚するしない、子供を産む産まない、そんな人生の意志決定すら「他人からの評価」を全く気にしないという人は少ない。
だからこそ強い言葉で訴えかけてくる「中学受験は絶対にした方が良い」みたいな声にすがりたくなる。
誰かが「これはいいよ」と薦めてくれたものに、乗ってしまった方が楽。
行先を示してくれる存在がほしくなる。
大人自身が「主体性」を意識せずに生きてきた。
その中で今、子供には「主体性」を求めている。
子供の不登校が増え続けているのは、こんな社会に対する「NO」なのではないか。
高島市長の記事に掲載されている、文部科学省の諮問内容は大変読みづらいものだった。
たった6ページと言うものの、文字がぎっちり並び、次々とキーワードが出てきて、要点が掴みづらいと感じた。
だけど、これはチャンスだ。
文部科学省と言う、一体どこに存在しているのか?も分からない組織。
声が届きそうもない組織。
小学校時代は半世紀前みたいな人ばっかりで構成されているイメージの組織。
その組織の意志決定の場に、子供の頃から携帯が身近にあった高島市長が参加している。
私達にとってとても身近なnoteという場所で、高島市長に声を届ける事ができる。
これは生かさない手はないのではないか?
子供が不登校で困っているとか。
教育現場に言いたい事があるとか。
強く要望したい事があるとか。
子育て中の人、教育現場に関わる人、若手の育成に苦慮している管理職の人。
10年後、20年後の社会で活躍する人を育てる教育現場に対して、思いを巡らせて意見をする事は、確実に社会を変える一歩になる。
是非、高島市長のnoteへのコメント。
こどもが自ら意見を届けられる「こども家庭庁」のアンケートフォームへの回答を通して、思いを届けてもらいたいと思う。
ここまで熱く語ったものの。
私は教育現場に一切関係のない、単なる二児の母である事を改めて申し伝えておきたいと思う(笑)
<あとがき>
そもそも私自身が、「座っている事」がとても苦手な子供でした。
授業中は常に「今、急にウロウロ歩きだしたらどうなるかな?」とか、「今日家に帰ってから何して遊ぼうかな?」とか、聞いてるフリをしながらも全く違う事を考えて授業中を過ごしていました。
家庭教師が家に来るようになってからも、目の前で話す先生の言葉にウンウンと相槌を打ちながらも全く違う事を考えていました(笑)
つまりは、「スタイル」なんてどうでも良いのです。
集団だからとか、個別だから…という事ではなく、本人が興味があるか?必要性を感じているか?なワケです。
それを「全国一斉で一律に学び方決めようぜ」って言う事が、そもそも無理じゃない?って思うんですよね。。。
**「昨日読んだ本」コーナー**
オンライン読書教育「ヨンデミー!」に、毎日「感想提出」をしている子供達が昨日読んだ本を紹介するコーナー
〈長男〉
<次男>
今日も有難うございました。
いいなと思ったら応援しよう!