
この現実を 〈直視〉せよ : 「第5回本格ミステリ大賞」の、出来レース性について
(※ 再録時註:予想が当たっても、こんな見え見えな「出来レース」では、自慢にもならない。だが、こうした裏事情が、のちの「容疑者X論争=本格論争」への伏流となり、笠井潔一派が「信任投票に破れた」と言って、本格ミステリ作家クラブを割って出ることにもつながっていくのである)
すでに公式発表のあったとおり、「第5回本格ミステリ大賞」(本格ミステリ作家クラブ主催)の結果は、私が予言したとおり、
小説部門 : 法月綸太郎『生首に聞いてみろ』
評論・研究部門: 天城一『天城一の密室犯罪学教程』
ということになった。
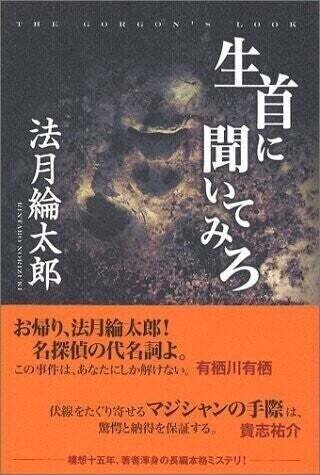
しかし私に、この「予言」を自慢するつもりなど毛頭ない。
こうした予測・予言は、現在の日本の本格ミステリ業界の内幕、なかんずく「探偵小説研究会」や「本格ミステリ作家クラブ」などの「内幕」を知っておれば、誰にでも容易に可能なことだったからである。
逆にいえば、この結果は、「本格ミステリ大賞」の主催者である「本格ミステリ作家クラブ」の会員たちならば、当然予測しえはずだし、また予測しながらも、あえて「カマトト」ぶって知らん顔をし、口を噤んでいた内容だ、とも言えるのである。
そんなわけなので、同クラブ員のなかには、こうした「意向」を形成する、笠井潔と「新本格第一世代」を中心とした「本格ミステリ作家クラブ」の主流派に、内心反発を覚えている者も、当然いるだろう。そうした者の票が、例えば今回の「小説部門」でならば、時点に泣いた芦辺拓の『紅楼夢の殺人』に(妥当に)流れたのかもしれない。
つまり、『紅楼夢の殺人』票は、「妥当な作品に、妥当に投じられた」というに止まらず、「主流派への反発」表現、言い換えれば「主流派の思惑どおりにはならない票の流れであった」という側面があったのかも知れないのだ。

そしてその意味では、「本格ミステリ作家クラブ」は、決して「教祖を頂点にいただく、一枚岩の本格ミステリ教団」というわけではなく、内部的には、いろいろな思惑の錯綜し渦巻いている集団なのである。
けれどもまた、主流派は主流派であり、「数」において他派閥を圧しているので、「多数決」になればやはり強いのだ。
そして、さらに言えば、「本格ミステリ作家クラブ」内においては、主流派であろうと少数派であろうと、彼らは「本格ミステリを顕彰する」という目的においては「利益を共にしている(確信犯的共同正犯である)」ため、外部に向かって「内部的な不公平問題」を語ることは、決してない。
なにしろ、小説的には優れていても、「本格味」に薄い作品ならば、ハードボイルドも冒険小説でも警察小説でもすべて排除し、いわゆる「本格ミステリ」という「身内」限定で「賞」を与えてくれるような「都合の良い組織」など、他には無いなのだから、少々気に入らないことがあっても、だから「ぶち壊す」というわけにはいかないのである。
そんなわけで、私に批判されている「本格ミステリ作家クラブ」の主流派にすれば、「アレクセイ(※ 私、年間読書人)さんによれば、まるで本格ミステリ大賞の受賞作は、笠井さん(笠井潔)の意志で決定し、それを探偵小説研究会の人たちが投票で実現化しているというふうに聞こえますが、実際には、探偵小説研究会の人でも笠井さんや法月さんの作品に投票しなかった人はいるんですから、探偵小説研究会や本格ミステリ作家クラブを、カルト的な集団であるかのように言うのは、被害妄想的な陰謀説としか言えないですよ」ということにしたいのだろうが、私が言っているのは、そういう「極論」ではなく、世間のどこにでも見られる「俗物組織」論に過ぎないのである。
で、私が、笠井潔を特にきびしく批判するのは、まず第一に笠井潔が「批評家」を騙る「党派理論家」でしかない、ということへの批判があるのと、その延長戦上に、笠井潔が実質的リーダーである「探偵小説研究会」所属の評論家の面々が、評論家であるにもかかわらず、こういう現実を黙認し、あまつさえ加担しさえしているという事実があるからだ。
つまり、リーダーが「エセ批評家」ならば、その子分も「エセ批評家」だということで、私の批判は、主として、リーダーである笠井潔に向かざるを得ないということなのである。
○ ○ ○
さて、では次に「今後の本格ミステリ大賞」についての見通しだが、実力的にみれば、次に長編賞受賞すべき作家は、芦辺拓であろう。
芦辺は、一定水準以上の作品をコンスタントに発表しているし、今回の『紅楼夢の殺人』のように(ジャンルを「本格ミステリ」に限定すれば)年間「ベスト3」級の作品も、決して稀ではない。
しかし、以前にも書いたとおり、芦辺の場合は、デビュー当初、「新本格主流派」である「京大ミス研」出身作家(綾辻行人・法月綸太郎・我孫子武丸・麻耶雄嵩)らに対し、あらわな対抗意識(反エリート意識)を示していたことから、現在でも主流派からは、すこし外れたところに位置せざるを得なくなっていて、彼への評価は、もっぱら作品至上主義的なものに止まらざるを得ない状況が続いている。
逆に、その党派性ゆえに受賞の可能性が高いのは、当然、綾辻行人・我孫子武丸・麻耶雄嵩・小野不由美の「京大ミス研」出身作家と、彼らと近い位置にあり、かつ「本格ミステリ作家クラブ」設立に際して、同クラブの会長に就任した現会長有栖川有栖、それから有栖川有栖と同じ「鮎川哲也と13の謎」叢書の出身者で、同じく「本格ミステリ作家クラブ」設立時の主要メンバーの一人である北村薫、また「京大ミス研」出身ではないものの、その流れを汲む実力派作家として好意的な評価を受けている殊能将之なども、有力候補と呼べよう。
これらの中で、極端な寡作である綾辻行人は、今回畢生の大作『暗黒館の殺人』で受賞を逸した結果、おのずと当面の受賞の可能性は低くなった。

一方、長らく「本格ミステリ」の長篇を刊行していない北村薫の場合は、今回の法月綸太郎や綾辻行人と同様「この機会に受賞させないと、次はいつになるかわからない」という「授賞」する側の心理的な要因もあり、それなりの本格長篇さえ刊行すれば「下駄を履かせて」もらえる可能性も十分にある。
それは、有栖川有栖も同様で、『マレー鉄道の謎』で日本推理作家協会賞を受賞したとは言え、この作品が「本格ミステリ大賞」の候補止まりだったというのは、この作品が有栖川有栖を代表させるほどの作品ではなく、日本推理作家協会賞の「授賞」は、所詮「出し遅れの証文」に近いものだったということなのだ。
言い換えれば、有栖川有栖もまた、近年、これといった「本格ミステリ」の長篇を発表していないため、それなりの作品を書けば、北村薫と同様というか、今回の法月綸太郎と同様と言うべきか、優遇措置をうける可能性は大いにある、ということになる。
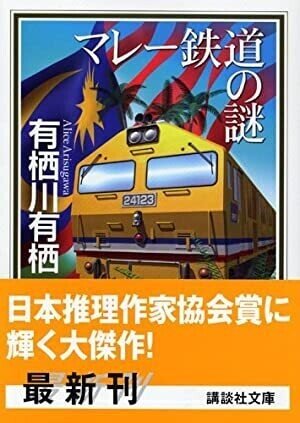
しかし、次回第6回で注目すべきは、なんと言っても、我孫子武丸ひさびさの長篇ミステリ『彌勒の手』 (文藝春秋・2005年4月1日刊行)であろう。同書の「内容紹介」によると、

『妻を殺され汚職の疑いまでかけられた刑事。失踪した妻を捜して宗教団体に接触する高校教師。錯綜する事件、やがて驚愕の真相が!愛する妻を殺され、汚職の疑いまでかけられて追いつめられたベテラン刑事、蛯原。妻が失踪し、途方に暮れる高校教師、辻。否応なく事件の渦中に巻き込まれていく二人は、やがてある新興宗教団体の関与を疑い、ともに捜査を開始するのだが……。』
『新本格の雄が実に13年ぶり(!)に書き下ろしたミステリ長篇は、綿密な警察取材を踏まえた本格捜査小説です。待ち受けるのは唖然呆然、驚天動地の大破局! ミステリの神が微笑む瞬間を、あなたもぜひ味わってください。』
ということで、ここで問題となる文言は
(1) 新本格の雄が実に13年ぶり(!)に書き下ろしたミステリ長篇
(2) 本格捜査小説
(3) 唖然呆然、驚天動地の大破局!
ということになろう。
つまり、(1)は、前述のとおり「この機会に受賞させないと、次はいつになるかわからない」という、「授賞」への心理的な誘因の存在を示している。
しかし、問題は(2)で、『本格捜査小説』という呼称は、はたして本作が「警察捜査のリアリズムで読ませる」ことを主眼とした「警察小説」であることを意味し、「本格ミステリ」であることを否定するものなのか、それとも単に警察が前面に描かれる小説だという「形式的説明」でしかなく、内容的に「本格ミステリ」であることを否定するものではないのか、そこが問題となる。なぜなら、その如何によって、本作が「本格ミステリ大賞」の候補となりうるか否かが決まってしまうからである。
しかしまた、(3)は本作が「本格ミステリ的」な「仕掛け」や「どんでん返し」のある作品だということを暗示しているとも取れるので、本作が「本格ミステリ」と認知される可能性は、十分に高いだろう。
もちろん『唖然呆然、驚天動地の大破局!』などといった表現は、いかにも「眉唾な修辞」だとも言えるから、実際にどうかはわからず、読んでみれば「どこが(唖然呆然、驚天動地の大破局)?」と言いたくなる作品である怖れも十二分にある。
その場合は、本作が「本格ミステリ」と評価されることはないわけだが、ひとまずこの「惹句」を信用するならば、本作は「優れた本格ミステリ」であらねばならず、そうであったならば、本作が「第6回本格ミステリ大賞」の有力候補となるのは、「党派力学的」に見ても間違いない、と言えるのだ。
ただし、私も、多くの「本格ミステリ」マニアも、我孫子武丸を「本格ミステリ作家」として(法月綸太郎ほどに)は高く評価してはいないので、この『彌勒の手』が受賞作になるとまでは、さすがに断言できず、「候補作になる可能性が高い」と言うに止まらざるを得ない。とうてい、今回のような、受賞「予言」など出来ないのである(笑)。
(※ 再録時註2:ちなみに「第6回本格ミステリ大賞」は、東野圭吾の直木賞受賞作『容疑者Xの献身』となった。我孫子の『弥勒の手』は、候補作にもならなかったのだ。きっと「本格ミステリ」としては弱かったのだろう。この時の候補作は、柄刀一『ゴーレムの檻 三月宇佐見のお茶の会』、石持浅海『扉は閉ざされたまま』、道尾秀介『向日葵の咲かない夏』、島田荘司『摩天楼の怪人』で、島田作品以外は、気鋭による文句なしの評判作であった。なお、北村薫は『ニッポン硬貨の謎 エラリー・クイーン最後の事件』で「評論・研究部門」を受賞し、笠井潔の『探偵小説と二〇世紀精神 ミネルヴァの梟は黄昏に飛びたつか?』は候補作に止まり、同部門の受賞を逸している。つまり、2006年は、笠井潔にとってはケチの付き始めの年であり、私のとっては積年の「呪い」が効果を発揮し始めた、実にめでたい年であった)


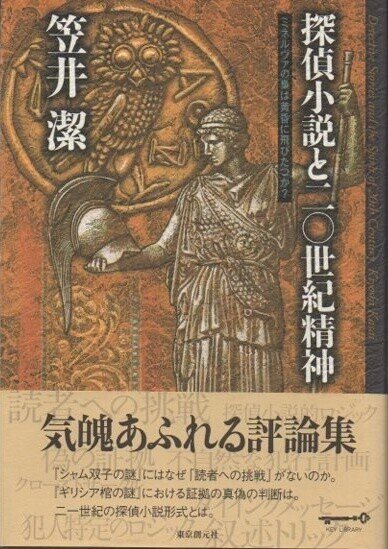

○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
