
ウディ・アレン監督 『カメレオンマン』 : 現実と虚構の狭間の人生
映画評:ウディ・アレン監督『カメレオンマン』(1983年・アメリカ映画)
数十年ぶりに見た『カメレオンマン』は、思っていた以上に面白くかった。多くの人にオススメしたい、これは見ておくべき、個性派の傑作だ。
形式的に言えば、本作は「フェイクドキュメンタリー(モキュメンタリー)」の恋愛コメディ映画である。
しかし、アレンの主演・監督作品の多くが「恋愛コメディ」だから、本作の特徴は「フェイクドキュメンタリー」の部分にあると言っても良いだろう。

では、どういう作品なのかというと、1920年代後半に登場して30年代半ばまでのアメリカを騒がした「ゼリグ」という名の男の物語。そのゼリグをウディ・アレンが演じており、ゼリグが「実在の人物」であったかのように、「ドキュメンタリー」タッチで撮られている作品なのだ。

(わかる人にはわかるように)わかりやすく言うと、NHKのドキュメンタリー番組『映像の世紀』のような作りで、かの時代のアメリカを象徴する人物として「ゼリグの半生をとらえた作品」として、本作は作られている。
これも、喩えて言うなら、第二次世界大戦の終結を知らないまま、アメリカ領グアム、あるいはフィリピン・ルバング島に隠れ住み、戦後30年近くを経て日本に帰国し、一躍「時の人」となった横井庄一や小野田寛郎といった人たちが、戦前戦中戦後にまたがる「昭和」という時代を象徴した人物であったように、ゼリグもまた、1920年代後半から30年代半ば頃のアメリカを象徴する「実在の人物」として、本作では描かれているのである。
ゼリグは「カメレオンマン」の異名を持つことからもわかるとおり、周囲の人間に合わせて、その姿形(顔つき、体型、肌の色など)を変えるだけではなく、言語や職業まで、無意識かつ、ほとんど瞬時に、それらしく「似せてしまう」という特殊能力の持ち主である。
当然、そんな能力など現実にはありえないものなのだから、本作の鑑賞者が大人であれば、これはハッキリと「フィクション」だとわかる作品にはなっている。
しかし、そんな「馬鹿馬鹿しいまでにあり得ない設定」を、リアリティを追求したかたちで、実在の人物として描いてみせたところに、本作の「コメディ」としての妙味もあるのだ。






本作の「ストーリー」は、次のとおりである。
『1920年代と1930年代を舞台にしたこの映画は、自分の行動や態度を周囲の人々のそれに合わせて変える能力を持つ、これといった特徴の無い男、レナード・ゼリグ(ウディ・アレン)が主人公である。彼を最初に目撃したのはあるパーティーでのF・スコット・フィッツジェラルドで、彼は、ゼリグが上品なボストン訛りで裕福な客たちと話し、彼らの共和党支持に同調していたかと思えば、使用人たちと厨房にいる間は粗野な口調になり、民主党支持者のようであったと語る。彼はすぐに「人間カメレオン」として国際的に有名になる。
目撃者への取材シーンの1つで、インタビューされる心理学者のブルーノ・ベッテルハイムは次のようにコメントする。
「ゼリグが精神病者なのか、それとも単に極度の神経症なのかという問題は、彼を診た医師たちの間で際限なく議論された。私が感じたのは、彼の感情は、いわゆる『よく適応した普通の人』と実際のところ、それほど変わらない、但し、その適応が極度に、過剰に行われているのではないかということである。私自身、彼は正に究極の順応者であると考えられると思った。」
精神科医のユードラ・フレッチャー博士 (ミア・ファロー) は、この奇妙な障害で入院したゼリグを助けたいと考える。彼女は催眠術を使った結果、ゼリグが余りにも強く(※ 周囲からの)承認を求めるため、周囲の人々に合わせて身体(※ などの特徴)を変えてしまうということを発見する。 フレッチャー博士は最終的にゼリグの同化への衝動を治すが、逆方向の効果が過剰に出てしまい、短期間、彼は他人の意見に余りにも不寛容となり、その日の天気が良いか否かについてさえ口論してしまう(※ ことにさえなった)。
フレッチャー博士は、(※ ゼリグの内心での、自分への思い知ることで、やがて)自分がゼリグに恋をしていることに気づく。この(※ ゼリグ)事案がメディアで(※ 煽情的に)報道されたため、ゼリグもフレッチャーも当時の大衆文化の一部となる。しかし、その名声が彼らの不仲の(※ と言うよりは、二人を引き裂く)主因となってしまう。(※ 二人の婚約が報じられると)多くの女性が、自分は彼と結婚し妊娠させられたと主張し、大きなスキャンダルとなった。ゼリグを英雄にしたのと同じ(※ 大衆)社会が彼を破滅させる(※ だが、フレッチャー博士は、一貫してゼリグを愛し続けた)。
ゼリグの病気が再発し、再度、回りに適応しようとするが、彼は姿を消してしまう。フレッチャー博士は、第二次世界大戦勃発前のドイツで(※ 人気の高まっていた)ナチスに協力していた(※ 正しくは、入り込んでいた)彼を(※ ニュース映画の中に)発見する。ゼリグは(※ ドイツまで彼を迎えに来たフレッチャー博士と共に、ナチスの追っ手から逃れるべく、その)模倣する能力を再度使い、フレッチャーの飛行機操縦技術を模倣し、上下逆さまになりながらも(※ 複葉機で)大西洋を渡って帰国する。彼らは最終的にアメリカに戻り、そこで英雄として認められ、結婚して幸せな生活を送る。』
(Wikipedia「カメレオンマン」。※ は、年間読書人による補足)



本作を見始めて、最初に驚いたのは、冒頭に近い部分で、「ゼリグ」を実在した人物として論評する「識者の(インタビュー)コメント」映像の部分に、いきなりスーザン・ソンタグが登場したことだ。

昔、初めて『カメレオンマン』を見た当時の私は、たぶんソンタグのことを知らなかったから、映画の中の彼女を見ても、それを俳優のお芝居だとしか思わなかったはずだ。だからこそ、記憶にも無かったのであろう。
だが、今回は、ソンタグの著書をすでに読んでいたからこそ「おっ」と思ったし、ソンタグの後に続く「ゼリグを語る識者」の少なからぬ者が実在し、その本名で、自分の役を演じているということにも気づけたのだ。
ちょっと調べてみると、ソンタグの他に、批評家のアービング・ハウや、作家のソール・べロー、心理学者のブルーノ・ベッテルハイムが、実在の人物だと確認できた。
この3人で、私の聞いたことのある名前はソール・べローだけだった。



それにしても、面白いのは、これらの実在の著名人が、ゼリグを「実在の人物」として論評的に語る際、その態度がじつに自然だったことである。きっと、彼らはインタビュー慣れ、カメラ慣れしているから、演技にさほどの困難を感じなかったのであろう。
また、それに加えて、ゼリグやフレッチャー博士の「関係者」として登場する、明らかに虚構の人物たちまでもが、「後年になってインタビューを受けた」という体裁で登場し、その「記憶」を証言するのだが、こちらの演技もまた、いかにもリアル。そのため、前述の「実在の著名人のインタビュー」映像と、ほとんど区別がつかない。
著名か無名か、ゼリグと直接関係があったのか否かで、その人物が「虚構の人物(俳優が演じた人物)」か否かがわかるだけで、「実在の著名人」についての予備知識がなかったなら、両者の区別がまったくつかないほどのリアリティだったのである。






また、本編の見どころである、昔のフィルムにウディ・アレンを合成して作られた「擬似ドキュメンタリー」映像の部分も、いま見てもとてもよく出来ており、合成による違和感は、ほとんどない。
ただ、私たちは、それがアレンだと知っているから、合成だとわかるだけなのだ。
例えば、オーソン・ウェルズの名作『市民ケーン』の、ケーンのモデルとなった実在の新聞王ハーストが、『市民ケーン』でも描かれたその豪壮な居城に、著名人を多数招いてパーティを開いた際のニュースフィルムが、現実に残っている。そこには、当時の人気俳優やスポーツ選手などの著名人が大勢登場し、その中には、若きチャールズ・チャップリンなどもいるのだが、そうした中に、アレンのゼリグもごく自然に入り込んでいるのだ。



物語の後半では、ドイツに逃亡していた(ユダヤ人の)ゼリグが、ドイツ人になりすましてナチス党に入り、ヒトラーが演説する演壇の後方の幹部席に座っていたりもする。
ここなどは、映像的にちょっと不自然な感じもないではなかったが、こうした「擬似ドキュメンタリーフィルム」の部分は、単なる合成だけではなく、新たに撮影したモノクロフィルムに古色加工を施し、それを本物のドキュメンタリーフィルムとモンタージュする(組み合わせる)ことで、うまく「一連の映像」のように見せてもいるのだ。

とにかく、アレンが写っている以上「現実にはあり得ない映像」だとわかっていながら、それがじつにリアルに出来ているというところが面白く、また今となっては、この映像が「ディープフェイク」のような、完全な作り物ではないところに、味があったのではないかとも思われる。
ぜんぶ作り物なのではなく、本物の中に偽物の紛れ込んでいるところに、曰く言いがたい味があったのだ。
さて、お話の方はというと、ウディ・アレンの作品らしく、例によって「臆病な男の恋物語」ということになる。
「変身能力」を持つ不思議な男ゼリグに、心理学者として興味を持ったフレッチャー博士 は、彼の「心の傷」を癒すことで社会に適応させようとする、というのが本作の大筋なのだが、これがまた、とても私の好みだった。




ゼリグは、複雑な家庭環境に育ったせいで、自分に自信が持てず、自然な人間関係の築けない男であった。
そんな彼が、決定的な精神的危機の晒された際に、強く「周囲に同化することで、身を守ろうとして」、その「変身能力」を身につけた(発症した)のではないかと、フレッチャー博士は考えた。だから、ゼリグに「安心と自己承認(自信)」を与えてやれば、自分が自分のままでいて良いと思えるようになり、自ずと奇妙な変身能力も消えるだろうと、そう考えたのである。



で、そんなフレッチャー博士の、ゼリグに対する診察・研究・治療シーンが面白い。
静かな環境を求めて、田舎の屋敷で行われたその治療において、フレッチャー博士が、精神科医として、ゼリグから聞き取りをしようとすると、ゼリグは反射的に身を守ろうとして、精神科医に擬態してしまう。
自分は精神科医であって患者などではなく、精神科医のフレッチャー博士と、同じ医師として対等に話しているのだという態度をとり、それをフレッチャー博士がいくら否定しようと、彼は頑として自分は精神科医だと言い張るのである。

そこで博士は作戦を変更し、今度は自分が「じつは患者」であり、精神科医のゼリグに「相談に乗ってほしい」と持ちかけるのだ。
するとゼリグは、勝手が狂って「僕は他の患者で忙しい」などと話を逸らそうとする。
しかし博士は「私は、難しい環境で育ったせいで、自分に自信が持てません。それでつい無理して自分を周囲に合わせてしまうようになったんです。どうすれば、こんな自分を変えられるでしょうか?」と、ゼリグの態度を逆手に取ると、ゼリグはすっかり混乱してしまい、ついに精神科医のフリを止めてしまう。そして、それまでは「私は精神科医だから」と断っていた催眠治療も受け入れるようになって、自身の素直な気持ち(内面)を語り出すようになるのである。
この、ゼリグと博士の「心理の裏のかき合い」という駆け引きが、とても私好みで面白かったのだが、しかしそれだけではなく、博士がゼリグに催眠術をかけて「何でもいいから、思っていることを正直に話してごらんなさい。例えば、私のことをどう思っている?」と尋ねたところ、ゼリグが次のように語り出す部分などは、秀逸なシナリオとして大笑いできた。
「博士はとにかく料理が下手だ。特にあのパンケーキはひどい。彼女の見ていない隙に捨てるのに苦労させられる。僕はこの田舎家の生活が我慢ならない。虫も大嫌いだし、雑草が生い茂っているのも嫌だ。都会に帰りたい」

などと言って、博士を面食らわせるのだが、しかし、それに続けて、
「でも、彼女は優しくしてくれるから、彼女との生活は楽しい。ずっと一緒に暮らしたい。彼女と寝たい」
などとも言い出して、博士を驚かせる。
この後、博士の方も徐々に、その気持ちをゼリグへと傾けてゆく。

そして、婚約もし結婚式も間近となるのだが、「カメレオンマン」としてすっかり有名人になった彼の、博士との婚約記事が出た途端、彼が博士たちに見出される以前の「多重人格」時代に、彼と結婚していた、子供まで作ったと主張する女性が次々と現れる。
ゼリグ自身も、その時の記憶がないためにそれを否定することができず、彼は「重婚」「器物損壊」などの罪に問われ、多額の賠償金を求められて、そうしたいくつもの裁判に追われつつ、世間からも激しい非難を浴びるようになる。
そしてついに、彼は「変身病」を再発させた後、博士を残して失踪してしまうのだ。

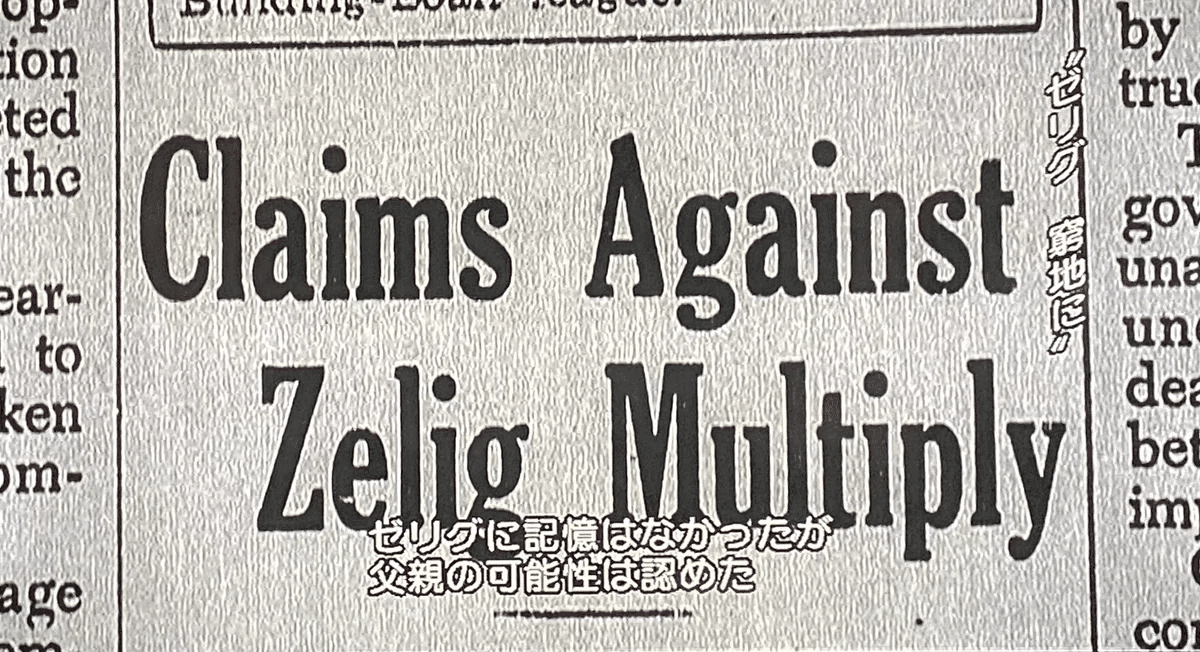



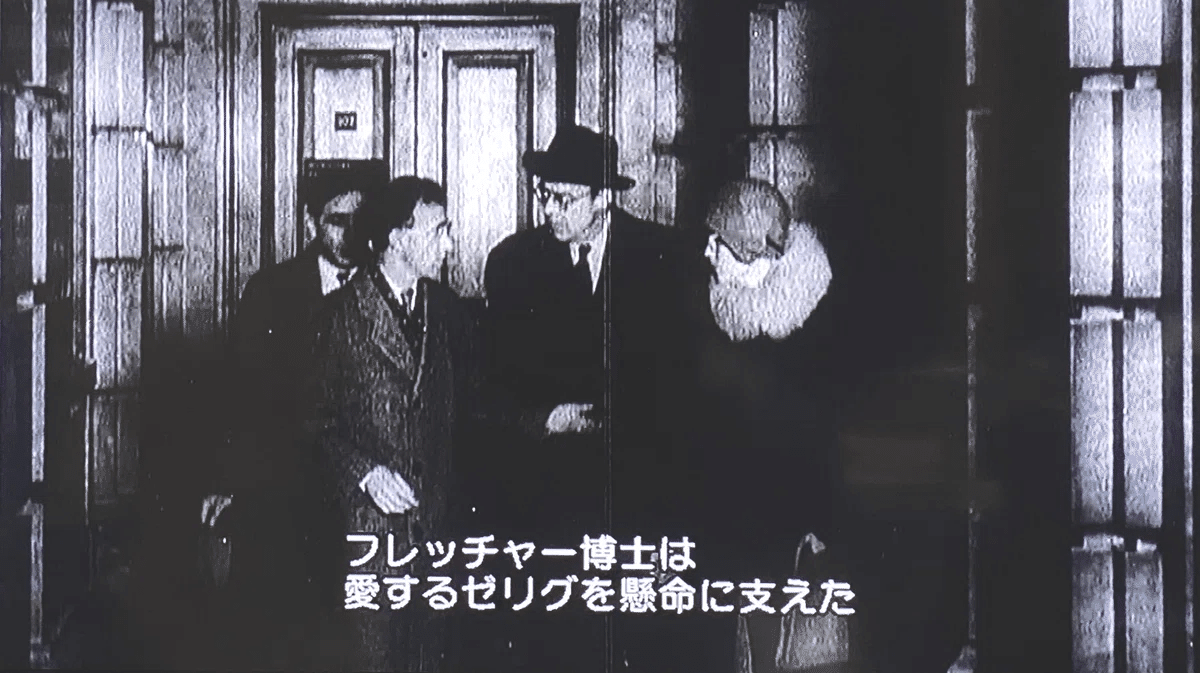
で、この後、ナチス党の躍進を伝えるニュース映画の中にゼリグを発見した博士が、ドイツへと向かい、一一という展開になるのだが、そこはもう良いだろう。
この映画の、面白いディテールとしては、ゼリグが「時の人」として世間からの注目の的になり、彼をテーマにしたレコードが何種類も作られたり、各種グッズが作られたりといったことを伝えるニュース映像などもあって、これがとても良くできている。





しかし、そうした「フェイク」の極めつけは、作中に何度か登場する「ゼリグの伝記映画」のワンシーンであろう。映画化されたら、きっとこんなふうに誇張の入った「感動物語」にされるんだろうなと、そう思わせる、じつに「リアルなもの(作中作)」になっており、またその伝記映画について、歳をとった「現在の(お婆さんの)フレッチャー博士」がインタビューに答えて「現実は、そんなものではありませんでした」などともっともらしく語る映像も、これまたリアルで、じつに笑えたのである。






一番下は、往時の状況を語る元ナチス親衛隊幹部。ヒトラーは、ジョークを言おうとしたところをゼリグらに邪魔をされカンカンになった。そのため二人を捕まえようとした、と証言)
このように、本作は「フェイクドキュメンタリー」としてとても良くできており、だからこそ何度も「笑える」作品なのだが、しかし、本作の魅力は、それに(そうしたコメディ性に)止まるものではない。
私が、本作に感じた魅力とは「(大衆)社会に翻弄された男」の「悲しみ」が、ウディ・アレンという俳優の特異な存在感において、見事に表現されている点なのだ。
あの「うらなりのナスビ」みたいな見かけがなければ、この「悲しみ」や「哀れさ」は、なかなか表現できないのではないかと思うし、その存在感においてこそ、本作は「笑える作品」であるばかりではなく、「感動させられる」作品ともなっているのである。






○ ○ ○
しかし、ただひとつ残念なことは、現実のウディ・アレンが、この映画でフレッチャー博士役を演じたミア・ファローと結ばれながら、この映画のように「ハッピーエンド」とはならず、むしろ、ゼリグがドイツへの逃亡を企てる前のような、スキャンダルに塗れてしまったという現実である。
もちろん、作品と作者の実生活は区別して評価すべきだし、アレンのスキャンダルは、どこまでが真実で、どこまでが責められるべき事実なのか、その正確なところは、他人の私にはわからない。
ただ、彼のファンとしては、やはりそうした生々しい現実は、どうにも残念だと思わずにはいられなかったのである。
『家族
舞台『Play It Again, Sam』で共演し、のちに映画でも共演したダイアン・キートンと交際していたが、長く続かず破綻。
その後、フランク・シナトラとアンドレ・プレヴィンの元妻のミア・ファローと交際するようになったが、彼女の養子のスン・イー(当時21歳)との肉体関係が発覚しファローと訴訟になった。肉体関係が始まったのは、スン・イーの高校時代。ウディ・アレンは当時彼女のヌード写真を個人的に撮影しており、それをファローが発見している。その事実が明らかになった当時ウディ・アレンは、ファローに度重なる謝罪をした。後にウディとスン・イーはその後結婚し、女の子二人を養子に取っている。
元交際相手のキートンとは『マンハッタン殺人ミステリー』(1993年)で共演しているが、これは本来ファローの役として話を書いたところを、私生活のごたごたの関係でキートンに代わってもらった、とアレンは語っている。
性的虐待の疑惑
養女ディランへの性的虐待を告発されたのは1992年だった。ディランによれば、当時7歳の1992年8月4日に「ウディに屋根裏部屋に誘われ、腹ばいになっておもちゃで遊ぶように言われ、近くに腰を下ろしたウディに指で陰部を触られた」と主張している。
これに対してウディは「親権訴訟で有利になるためにファロー側がでっち上げたもの」として、虐待行為を一貫して否定している。1994年の親権裁判では、虐待疑惑についての証拠が決定的でないとの判断が下され、コネティカット州警察の捜査でも訴追に至ることはなかった。
事件の余波
ハーヴェイ・ワインスタインのセクハラ暴露をきっかけに起きた「#MeToo」運動でハリウッドから干されていたウディ・アレンが、沈黙を破って自伝の出版を発表すると、実の息子であるローナン・ファローが反発。ローナンは、ハーベイ・ワインスタインのセクハラを暴く『New Yorker』の記事を執筆し、ピュリツァー賞を受賞した「#MeToo」のリーダー的存在であり、「#MeToo」が盛り上がる中、世間はローナンの側に立った。2017年12月1日に劇場公開された『女と男の観覧車』は、それだけが理由かどうかは不明ながら、アメリカで興行的に失敗した。
次に控えていた映画『レイニーデイ・イン・ニューヨーク』に出演したグリフィン・ニューマンは本作に出演したことを後悔し、今後一切アレンと仕事をしないとの声明を発表し、本作のギャラ全額を寄付した。2018年1月、レベッカ・ホールも本作への出演の後悔と今後一切のアレンとの仕事を拒否する声明を発表し、本作のギャラ全額を寄付した。同月、ティモシー・シャラメはアレンへの批判は避けたものの、本作への出演で報酬を得ることを望まない意向を発表し、本作のギャラ全額を寄付。のちにセレーナ・ゴメスは、本作での出演料を100万ドルほど上回る額を寄付した。2018年3月、エル・ファニングも本作への出演を後悔する声明を発表し、出演料は具体的に明らかにはなっていないが、寄付をしたことを明らかにした。
アマゾン・スタジオは批判を受けて本作のアメリカでの上映を無期限延期を決定し、アレンとの4本の映画製作の契約をキャンセルした。アレンはこれを不服として、2018年2月に同スタジオを契約不履行で訴え、6800万ドルの訴訟で和解。映画はアメリカ以外では劇場公開された。』
(Wikipedia「ウディ・アレン」)

(2025年2月18日)
○ ○ ○
● ● ●
・
・
・
○ ○ ○
・
・
○ ○ ○
・
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○
