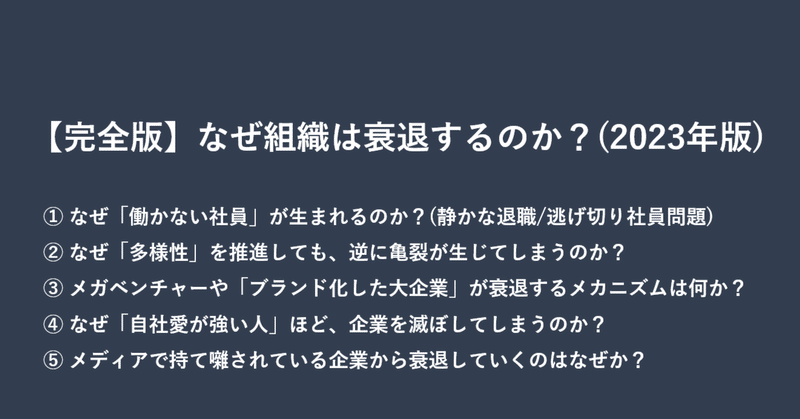記事一覧
「キャリア論の変遷」と「答えはあなたの内側にある」の欺瞞性について
近年、「市場価値を上げるためには、こういう経験をするべき」などの論調を聞くことがありますが、いつの間にか「人生価値が市場価値に侵食される現象」や「自分の市場価値を最大化させるために、会社を使う」というキャリアテイカー的な側面が強くなりすぎていないだろうか?という違和感があり、本稿で思考をまとめました。
「お金がない不幸」も当然あるが、「市場価値という仮想概念に翻弄される不幸」もあるのではないだろ
係員と係長の最大の違いは○○のマネジメント
昨年、2021年の春に係長になった私が、係長としての日々の学びを備忘録兼成長(?)の記録として書き残しています。
前回は、係長になったからといって誰も手取り足取り係長の務め方を教えてくれるわけではないということについて書きました。
今回は「係長と係員との違い」について考えてみたいと思います。
課長や係長になりたくないという職員が一定程度いるそうです。近年増えているとの説もありますが、私自身は
「カラフルな公務を目指して」から見える地方自治体の政策と地方公務員の仕事③離職者のリアルな声から
国家公務員の働き方について若手職員がまとめた提言「カラフルな公務をめざして」には、これまで紹介してきた注目すべき提言に加えて、職員のリアルな声がそのまま掲載されている。特に「離職者から託された思い」は、志半ばで離職せざるを得なかった方から、今なお官僚であったことに誇りと愛着を持っていること、公務がもっと良くなればという思いを持って過ごしていることが伝わってくる。今回は、の中から地方公務員との違い
もっとみるSCI-Japanウェビナー「今なぜ『政策起業家』が注目されるのか」 登壇報告
2022年2月17日、一般社団法人スマートシティ・インスティテュート(SCI)が主催したウェビナー「今なぜ『政策起業家』が注目されるのか」に、PEPプログラム・ディレクターの 向山淳が登壇しましたのでご報告します。
本ウェビナーはSCIの南雲武彦氏(SCI専務理事/三菱UFJリサーチ&コンサルティング専務執行役員)をホストとして、毎週スマートシティに関わる様々なテーマについて対談形式で配信されて
『国家公務員のパフォーマンスを最大化し、国益を最大化する聖域なき提言』全文公開
改革派若手官僚コミュニティ「プロジェクトK(新しい霞ヶ関を創る若手の会)」は、霞ヶ関改革の優先課題を洗い出した提言として『国家公務員のパフォーマンスを最大化し、国益を最大化する聖域なき提言』を取りまとめました。この記事ではその内容を全文公開したいと思います。
Ⅰ 本提言の問題意識と方向性
1.機能不全に陥りつつある官僚機構
「理不尽な激務化」と「政策ブレーン機能の劣化」
国家公務員
【イベントレポート】第1回「意外と変われる霞が関大賞」を開催!発表内容と審査結果を一挙にご紹介
2022年5月29日、プロジェクトKは『第1回・意外と変われる霞が関大賞』ピッチイベントをリアルとオンラインのハイブリッドで開催し、河野太郎賞、小室淑恵賞、千正康裕賞、そしてグランプリを贈りました。またオブザーバーとして人事院総裁の川本裕子氏もご臨席いただいた中、ノウハウ共有とともに活発な議論がなされました。本記事では栄えある各賞を受賞したチームのみなさんとそのピッチ内容をご紹介します。受賞チーム
もっとみる「洞察」とは、突然新しい方法で問題と向き合う能力である
一般のビジネスパーソンにもデータを活用する力が求められます。なぜならば、現場力とデータは不可分だからです。例えば、マーケティング施策を考える場合、消費者行動の洞察とデータからの考察という、2つの思考が融合することで、新たな仮説が生まれます。
社会人大学院に2年間通って、データサイエンスをビジネスに活用するために必要な能力は、統計学に関する知識でもRやPythonなどの言語でもなく、事象に対する「
ド短期で売上高めるにはエクストリームユーザーの行動パクるのが1番説
「コロナ禍」で売上を増やすには?
「コロナ禍」という異常事態に突入してから3年目、制限に次ぐ制限でガタガタだった日本経済も少しずつ復調の兆しを見せています。
一方で「K字回復」と表現されるように、復調の傾向は業界・業種で状況が全く異なるようです。「コロナ禍」で大幅に市場が縮小した産業もあれば、むしろ大きく成長した会社もあります。
例えば、日本フードサービス協会によると21年の外食産業の市場規模
一気通貫に定性分析と定量分析を行った結果を約8000字で完全解説します
過去に困り事があったとしても、それが解決されてしまうと、その困り事があったこと自体の記憶を上書きして忘れてしまうことがあるという。
「不便や不安にはさまざまなヒントが隠されている。現状に至ったプロセスを解きほぐすように質問をしていくと、新しいものが見えてくることもある。生きてきた歴史が長いので、その時々の社会の変化によって気持ちも変わり続けている」(梅津氏)
ハルメクの特集企画や商品開発の原動力と
幻冬舎の箕輪さんはなぜ炎上したのかをマーケティングの失敗事例として読み解く
文春砲を立て続けに2発喰らった幻冬舎の箕輪さんは、1ヶ月経たずしてテレビ活動の自粛、ニューズピックスブック編集長の退任を発表しました。
2020年の年初に「箕輪さんがメディアから退場する」と言っても、誰も信じなかったはずです。「何言ってんの?」「嫉妬してんの?」と馬鹿にされたかもしれません。
出版業界は「ざまあみろ」「好敵手がいなくなって寂しい」の反響に分かれているでしょう。少なくとも「何も思