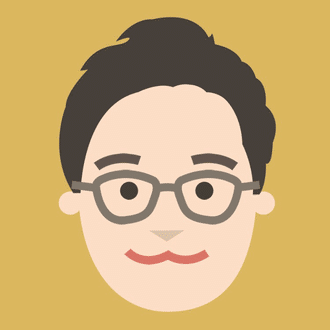「期待しない」から始める組織作りとは? フォロワーの「自立」から柔軟なチームを創る工夫
「なるほど、『期待』から距離を置くことが大切ということか」
組織作りについてある書籍に出会い、なるほどと思えるヒントを得ました。組織づくりについては、先日フォロワーシップについて整理しました。
この中で「大きなうねりを生み出すためにはフォロワーシップが重要である」ということをまとめました。そこからさらに組織におけるリーダーシップとフォロワーシップについて調べている中で、参考になる書籍と出会いました。
その本には人間関係の中で必ず生まれる「期待」について意外なヒントが記されていました。
あらためて、組織づくりにおけるメンバーの「自立」の重要性について考えてみます。
フォロワーシップと自立
今回ヒントになったのは中竹竜二さんの著書「リーダーシップからフォロワーシップへ カリスマリーダー不要の組織づくりとは」です。中竹さんは日本ラグビーフットボール協会コーチングディレクターで、指導者未経験のまま早稲田大学ラグビー蹴球部の監督に就任し全国大学選手権2連覇を達成している名監督です。「日本一オーラのない監督」とも言われ、独自のリーダーシップ論(フォロワーシップ論)をお持ちの方です。
退任後も、U20(20歳以下)日本代表監督としてワールドラグビーチャンピオンシップでトップ10入りし、企業のリーダー育成など多方面で活躍をされています。組織に属するあらゆる人におすすめしたい、生産性高く生きて行くヒントがたくさん詰まった一冊です。
この本で、中竹さんは「誰もがカリスマ的なリーダーである必要はない。リーダーシップの形は1つではなく、強い組織をつくるリーダーには誰でもなれる。そのために必要なのはフォロワーシップのアプローチだ」と主張しています。
フォロワーシップについては中竹さんはこう定義しています。
【フォロワーシップ】
組織を構成する一人ひとりが自ら考え、行動し、成長しながら組織に貢献するための機会を提供し、環境を整える努力をすること
ポイントはこの「一人ひとりが自ら考え、行動し、成長する」という点。組織論ではリーダーの方針に沿ってメンバーが行動することが正しいと考えがちです。しかし、真のフォロワーシップは「メンバーが自分で考えて行動する」ことで生まれると説きます。
特に今の世の中はコロナの影響で社会や経済が激変し、その変化のスピードは正に劇的なスピードです。この目まぐるしく変わる環境変化において、カリスマ的なリーダーシップだけでは太刀打ちできない組織がほとんどではないでしょうか。だからこそ、この今の環境においては「自ら考えるメンバー」で構成された組織が求められるようになっていると言えます。
期待に応えない
この書籍の中で特に意外な気付きを得たのは「期待に応えない」という言葉です。人は誰しも、自分に期待をかけられるのは嬉しいものです。その期待に応えようと頑張ります。それが叶えられると頑張った自分も嬉しいし、期待した側の人間とも良好な関係を築けるイメージがあります。これはある種の本能ともいえるものでしょう。人間が社会的な生き物である時点で、本能に備わった感覚ではないかと思います。
誰しも、他人から良い評価を得たいし褒められたいものです。この欲求があるがゆえに、期待には積極的に反応してしまいます。相手の期待を過度に受け止めすぎて、時に本当はできないと分かっていることであっても、誠意を見せようと自分の力以上に頑張ってしまったという経験は誰しもあるのではないでしょうか。
一方で、組織のリーダーはメンバーからの期待に反応することで、メンバーから一時的な信頼を得たりします。しかし、その期待はいつの間にかどんどん膨らんでいきます。大きく膨らんでしまった期待には、自分の努力では、相手を満足させるのが難しくなるという現象が起きてしまいがちです。しかもその期待はメンバー一人ひとり異なる期待を持っています。それら全部の期待に応え続けるのは非常に難しいことです。
リーダーが、目の前の一瞬の感謝のためにメンバーからの期待に応えてしまうと、結局、長い目で見た時にメンバーを裏切ってしまうケースがあるということです。だからこそ、中竹さんははじめから「期待には応えない方が良い」と説きます。
自分で無理だと分かっていること、または、自分のスタイルには添わないものに対しては、最初から「期待に応えない」ことが大切だといいます。それは、結局は長い目で見て期待を裏切らないためなのです。
さらに、期待にそもそも応えない態度をある一定期間貫けば、最初はメンバーから雑音が聞こえるものの、そのうち彼らはそもそも期待しなくなり、諦めるといいます。諦めて、メンバーもリーダーに過度な期待をしない。それこそがメンバーの自立のスタートラインとも言えます。
他人に期待しない
中竹さんは「他人の期待に応えないだけでなく、基本的に他人に期待しないことにしている」と言います。その理由は、他人に過度な期待をすると、がっかりしたり、怒りを覚えたりするからだそうです。
中竹さんは「日本一オーラのない監督」と言われる通り、普段からオーラを放っていないということもあり、人からよく馬鹿にされたり、文句を言われたり、生意気な態度を取られることがあるそうです。普通なら監督がそんな扱いを受けると怒り狂うのではと思いますが、中竹さんはそもそも「皆は私のことなんか、どうせ見下しているんだろうな」と理解しているそうで、彼らの態度が至極当然に見えてくると言います。
「人はそれほど私のことを深く理解していないし、また、私が尽くした分だけの誠意を相手が感じてくれるとは毛頭思っていない。」とのこと。我々はコミュニケーションの誤解の連続の中で生きており、ときに相手から期待を超えた喜びをもらったり、ときに裏切られたような態度を受けながら日々を過ごしています。
要するに、人に期待しないというのは、結局は、私自身にも期待しすぎないということだと思います。そもそも誰もが完璧な人間ではないので、常に「所詮、私なんか」というスタンスでいた方が健全であるというのです。これは自分を卑下しているわけでも悲観しているわけでもなく、自分の能力や器を冷静に見ているということだと思います。
周りからすれば、リーダーとしてのプライドがない、という見方をされたりもしますが、逆に、中竹さんにとっては無駄なプライドはなるべく持たない方が良いと考えています。このスタイルを貫くことができれば、感情をコントロールすることができ、人からどんな態度を取られてもイライラすることはないと言います。
人が人に対して残念に思うのは期待値を下回った時に起こる感情なのかなと思います。そう考えると、そもそも期待しないことで、こうした感情を回避できるのかもしれません。これはこれでタフなメンタリティが必要なので、簡単なことではないのかなとも思います。
メンバーのスタイル確立(自立)を重視
中竹さんはリーダーがスタイル(ぶれない軸)を持つことはもちろん、メンバーにも、自分なりのスタイルを持つことを奨励しています。そのためには格好悪くても嫌われても、どんな相手にもブレないパフォーマンス、どんな状況でも変わらないパフォーマンスができるメンバーを高く評価するといいます。
スタイルを重視した指導方針は、聞こえは良いですが、それは時にリーダーの意向にメンバーが合わせないことを容認する方針でもあります。メンバーの自立を求めるため、実は、組織の中に不満が高まりやすい手法とも言えます。
一般的なスポーツにおける選手選考の評価基準は「試合でのパフォーマンスの良し悪し」が全てだという認識が強いですが、中竹さんはそうしたスキルによるパフォーマンスよりもスタイル(ぶれない軸を持っているか)の重要性を説いて、自分らしくチームに貢献できる一貫性のあるパフォーマンスを発揮しているかを基準としているそうです。
こうしたコミュニケーションをしっかりと行うことで、メンバーは何を求められているのかを理解し、自立した行動をとるようになります。一人ひとりがチームのために自分は何をすべきなのかを考え、太い価値観を軸に行動していく。結果、それはチーム全体のパフォーマンスを押し上げて行くのだと思います。
まとめ
組織は複数人のメンバーで構成され、ある目指すべきビジョンに向けて生産性高く行動することが求められます。その時に、人は人に期待しがちです。しかし、他人の期待に応えて動き続けてしまうと、「期待への対応」が行動原理となってしまい、やがてそのチームは破綻してしまいます。
思うに「期待に応える」というのは、行動の軸が他人にあるということです。「誰かに期待されているからやる」という行動は、自分のステアリングを他人に委ねているように思います。
そうではなく、誰に言われたからではなく、自分が正しいと思うからやる、という風に、行動原理の軸足を自分の中に持つことが大切です。
「期待に応えない」「他人に期待しない」こう聞くと、非常に冷酷で、冷たい人間の言葉のように感じますが、実はその裏には「自立」を目指す熱い考え方が下支えしています。リーダーからの指示待ち人間ではなく、どんな状況でも自分で考えて自分で行動できる人材。こうした自立したメンバーが有機的につながることで、変化に臨機応変に対応できる組織が創られるのではないかと思います。
この考え方はアドラー心理学の「承認欲求は捨てよ」という教えにも通じる考え方のように思います。
人に対しては「過度に期待せず、自立を促す」
そして自分には「過度に期待に応えず、自ら考え行動する」
こうした思考と行動で、変化に対応できる自分でありたいですし、そうした組織の一端を担いたいと思います。
改めて、「期待」と決別する勇気を持ってみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
いいなと思ったら応援しよう!