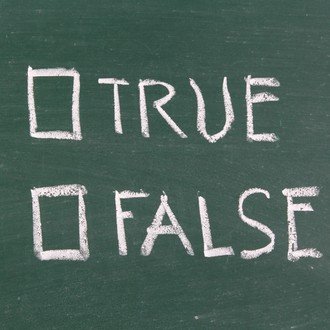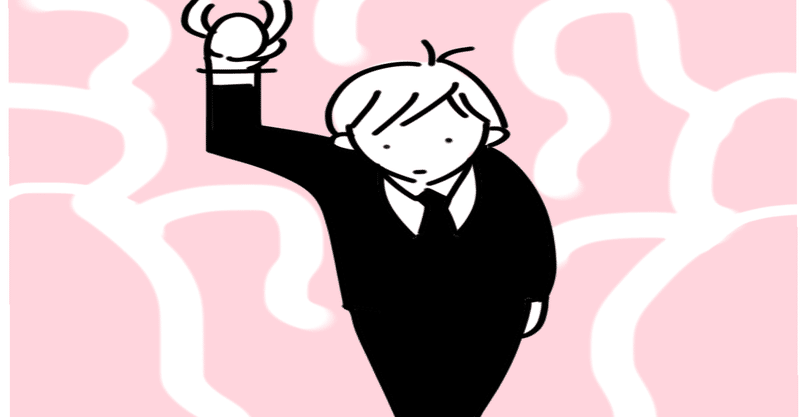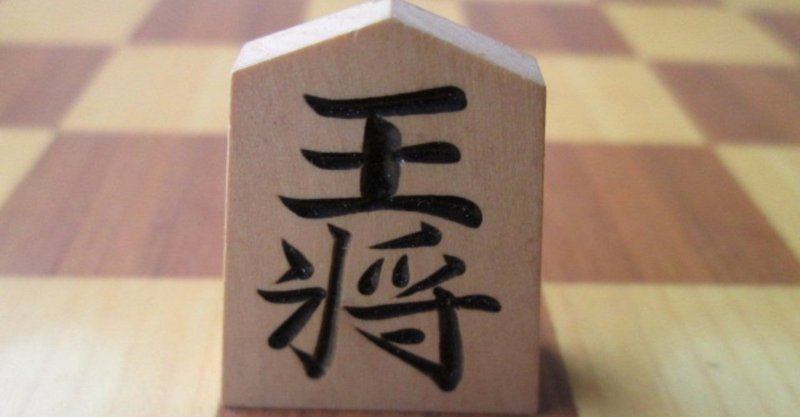#日本経済新聞
技能実習生がもう限界の件
▼コロナ禍で苦しむのは、女性、こども、そして外国人である。
2021年3月22日付日本経済新聞に、外国人の苦しみについてよくわかる記事が載っていた。適宜改行と太字。
〈技能実習生 もう限界/仕事失い帰国できず、コロナで二重苦/「生活苦で犯罪」防ぐ支援を〉
〈新型コロナウイルスの影響で、苦境に陥る外国人技能実習生が後を絶たない。雇用情勢の悪化などで働き先を失い、帰国しようにも渡航制限でかなわな
コロナ禍で苦しみの限界を超えてしまった件 2020年の自殺者数確定値
▼2020年の自殺者数の確定値が報道された。すでに2月に速報値が報道されており、ほぼ同じ内容だが、ここでメモしておく。
▼まず、2021年3月16日付の読売夕刊1面トップから。
〈女性の自殺15・4%増/7026人、コロナ影響か/20年確定値〉
〈厚生労働省と警察庁は16日、2020年の自殺者数が確定値で前年より4・5%(912人)増の2万1081人だったと発表した。女性は同15・4%(93
コロナ禍で大学の「書く」授業がとても捗(はかど)った件 金原瑞人氏の経験に学ぶ
▼2020年は、大学での授業がコロナウイルスの影響で完全にストップして、次第にオンライン授業が増えていったわけだが、そのなかで起きた面白い現象について。翻訳家の金原瑞人氏が2020年10月18日付の日本経済新聞に書いた「書ける若者たち」という文章から。
金原氏は毎年、法政大学で「創作表現論」という授業をしている。適宜改行と太字。
〈普段の対面授業では、日本で最初の本格的な英和辞典「英和対訳袖珍
アメリカと中国との関係は「新冷戦」ではなく「ハイブリッド戦争」である件
▼アメリカと中国との関係について、「新しい冷戦だ」という表現を使う人がいるが、そうではないとする論者も多い。筆者は後者に賛成するが、その論のなかでも、わかりやすい説明が2020年10月22日付の日本経済新聞に載っていた。
▼カーネギー財団モスクワセンター所長のドミトリー・トレーニン氏。適宜改行と太字。
〈いまの米中対立を「新冷戦」と称する向きがある。しかし、世界史の中で、冷戦は1度しか起きてい