
ポール・バーホーベン監督 『スターシップ・トゥルーパーズ』 : バーホーベン節炸裂の「アメリカ」嘲笑映画
映画評:ポール・バーホーベン監督『スターシップ・トゥルーパーズ』(1998年・アメリカ映画)
ロバート・A・ハインラインのSF小説『宇宙の戦士』の映画化作品。私は、ロードショー当時に観ており、これが2度目の鑑賞である。
最初に観た当時から、私はこの作品がとても気に入って、いつかもう一度観たいと思っていたのだが、それが四半世紀後の今になって、やっと実現した。だが、昔と変わらず十分に楽しめる作品であった。
映画の中に登場するコンピュータ・デバイスの表示画面などのデザインが、いささか古くさくなったことをのぞけば、CGを含む特撮シーンも特に違和感のない出来だったのだ。
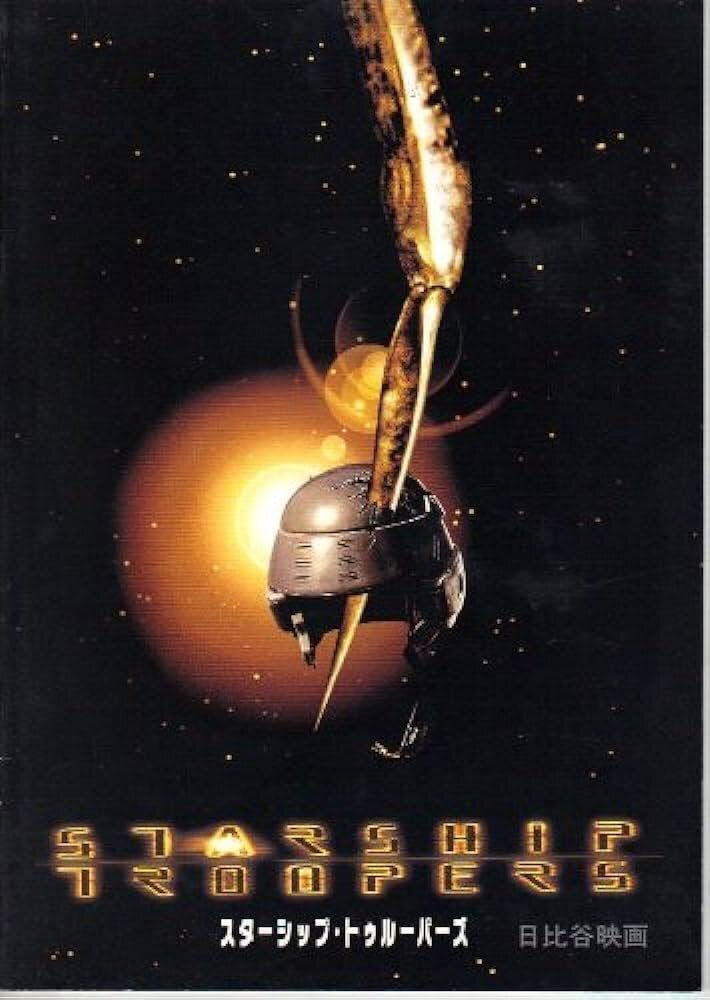
だが、この作品の「売り」は、なんといってもバーホーベン監督独特の「皮肉な批評性」だ。つまり「嘲笑」。
大真面目に「批判」するのではなく、それを徹底的にからかう、憎たらしいまでの攻撃性が、この監督の「批評性」の特徴だと言えるだろう。そして、本作で、そんなバーホーベンの槍玉に上がったのが、「戦争・愛国バカ」とでも言うべき「右翼的な鷹派性」である。
本作については、以前、2012年に制作されたリメイク版『トータル・リコール』のレビューの中で、そこそこ触れているので、まずはそれを紹介した後、今回の再鑑賞で気づいた点を付け加えたいと思う。
私は本作『スターシップ・トゥルーパーズ』を観る以前に原作の方を読んでいる。そちらの評価については、上のレビューで次のように書いた。
『原作小説『宇宙の戦士』は、私が期待したような「戦争アクションSF」ではなく、SF版『フルメタル・ジャケット』(スタンリー・キューブリック監督・1987年)といった感じの、地味な「宇宙兵養成学校物語」だった。
ひ弱な現代っ子である若者たちが、過酷な訓練を経て「愛国的な戦士」へとたくましく成長していく姿を肯定的に描いた、愛国主義的な作品であったため、私には、まったく楽しめなかったのである。』

私は、今も昔も「リベラル」だから、「右翼」的なものは大嫌いだった。だが、バーホーベンによる映画版については、次のような点に期待して観に行ったのだった。
『加藤直之が描いたようなカッコイイ「パワードスーツ」が登場することに期待して、バーホーベン版の『宇宙の戦士』たる『スターシップ・トゥルーパーズ』を観に行ったのだが、残念ながらこの映画では、「重装備の兵隊」は出てきても、加藤直之が描いたような、ロボットめいた「パワードスーツ」は登場しなかった。』
上のような点では、映画『スターシップ・トゥルーパーズ』は「期待外れ」だったのだが、しかし、期待したものとは違った点で、この映画は、私を大喜びさせてくれた。
『しかしである、この映画は、予期しなかったところで、私を大喜びさせてくれた。それは、この映画では、バーホーベン監督の「皮肉な批評性」が、ハッキリと表れていた点であった。
そして、それはたぶん、次のようなバーホーベンの「出自」に由来するものだったのであろう。
『幼少期を第二次世界大戦下のオランダのハーグで過ごした。その中で、自分たちオランダ人の味方であるはずの連合軍がナチスの軍事基地があるハーグを空爆し、死体が道端に転がっているという日常を過ごしている。』
(Wikipedia「ポール・バーホーベン」)
要は、バーホーベンは「〝世界の警察〟的なアメリカの、星条旗よ永遠なれ的な、単細胞な愛国心」が大嫌いだったから、このSFアクション映画では、それを徹底的におちょくっていたのである。
もちろん、鈍感な観客ではそれと気づかない「捻った描写」による「皮肉」ではあったのだが、「よくもまあ、ここまで原作を嘲笑うような映画を撮ったものだ」と、私は大笑いし、大喜びしたのだった。』
と、このようなわけで、私はこの映画を「SFアクションもの」としてではなく、その「皮肉な批評性」において高く評価し、バーホーベンという人を強く意識するようになったのである。
なお、本作のストーリーは、原作とは違って、『地味な「宇宙兵養成学校物語」』に終わるのではなく、それが最初の4分の1程度で、あとは「バグス」と呼ばれる敵宇宙生物との戦いが描かれ、その中で「愛国(愛星)戦士」として成長していく主人公の姿が描かれていく。

詳しい、ストーリーについては「Wikipedia(スターシップ・トゥルーパーズ)」の方で最後まで丁寧に紹介されているので、そちらをご参照願いたい。ストーリーを知ったからといって、それでつまらなくなるような「わかりやすい」作品ではないので、「ネタバレ」については、心配無用である。
○ ○ ○
さて、今回、本作を再鑑賞する以前に、私はハインラインの別の代表作『異星の客』を読んでいる。最近のことだ。
なぜこの『異星の客』を読んだのかというと、この作品が「右派」思想的なものとは、およそ真逆の作品だという評判を聞いたからだ。そんなことがあり得るのだろうかと、気になったのである。
私が『宇宙の戦士』を読んだかぎりでは、ハインラインは本気で「愛国戦士への成長ドラマ」を肯定的に描いているという感じしかなく、それを「装って書いた」という感じは、まったくなかった。
では、問題の『異性の客』の方が、逆に「リベラルを装って書いた」作品なのだろうか?
そのような疑念を持って、『異性の客』を読んだのだが、この作品での「リベラル」さも、とうてい「演技」だとは思えないものだった。
ただし、『異星の客』を読んでひとつ言えることは、ハインラインは「複雑な人=屈折を抱えた人」であって、簡単に「右派」だとか「リベラル」だとか決めつけることはできない、ということであった。その意味で「面白い」人だというのがわかったのである。

したがって、できれば『宇宙の戦士』を再読して、そのあたりを「今の私の目」で確認すれば良いのだけれど、ただ、『宇宙の戦士』は、いま読んでも私には「楽しくない」作品だろうという印象が拭えないし、それなりに分厚い長編作品なので、この「課題」については、ハインラインの他の作品をいくつか読み、それで読もうと思えるようになれば、その時には読むこととし、当面は判断保留のまま残しておくことにした。
よって、本作『スターシップ・トゥルーパーズ』において、バーホーベン監督が、ハインラインの原作小説をどう評価していたのかは、定かではない。
かつての私のように、この原作を「右翼・愛国小説」としてバカにしていたのか、あるいは、私より深く読み込んで、ハインラインの意図をそうしたものではなかったと理解した上で、「右翼・愛国」的なものを嘲笑する映画を作ったのか、そのあたりは見定めがたい。だが、少なくともバーホーベンが、ハインラインの意図に関わりなく、「右翼・愛国」的なものを嘲笑する映画として本作を撮った、というのは間違いのないところだとは断じてもいいだろう。

では、どのようなところから、本作が〈「右翼・愛国」的なものを嘲笑する映画〉だとわかるのかというと、それはもう「冒頭」からして明らかである。
この映画の冒頭は「軍事国家」となったアメリカ(あるいは、アメリカ主導の地球連邦)政府の流す「兵隊募集のプロパガンダ番組」から始まるのだが、これがまあ露骨にこの種のプロパガンダ番組の「わざとらしさ」をからかうようなものであり、その「わざとらしさ」を殊更に誇張して描いているから、この映画の監督が、そうしたものを嫌い、馬鹿にしているというのは、比較的簡単に見て取ることが出来る。
だが、このあと本編ドラマに入ると、このような「極端なわざとらしさ」は影を潜め、ある意味では「よくまとまったSF戦争映画」になっている。
つまり、こんな具合だ。一一「世間知らずのお坊ちゃん」(主人公)が「好きな彼女が宇宙船パイロット志望」で軍を希望したので、彼も親の反対を押し切って兵隊養成学校に入り、そこでの厳しい訓練の中で成長していく。ところが、その訓練の最中、仲間を死なせるという事故を起こしてしまい、いったんは兵隊学校からの自主退学を決意するものの、そのタイミングで、故郷の街が「バグス」の遠隔兵器により壊滅し、主人公は両親を失うことで、地球を守る軍人になろうと、決意を新たにする。
そして、幾多の戦場経験をかさねる中で、尊敬できる上官や気のいい仲間との絆を育て、その一方、好きな彼女との別れと再会などのラブロマンスや、仲間の死などを経験して、主人公は優れた戦士として成長し、最後は「バグス」の「頭脳」ともいうべき個体の捕獲作戦に成功することで、この戦争の未来は明るいだろうということを暗示して、物語は幕を閉じるのである。



そんなわけで、この映画は、うかうか観ていると、当たり前の「娯楽戦争SF映画」として楽しめるような作品になっている。「リアル」な「反戦映画」とは違って、基本的には「味方はいいヤツ」ばかりだし、「敵は醜い虫」である。物語の展開も、いささかご都合主義にすぎる部分はあるものの、娯楽映画とは大抵そういうものだから、特に気になるほどのものではない。
そのため、この映画は、単純な「SF戦争映画」として楽しむこともできるし、その上で、少し深読みをすれば、「右翼・愛国」主義の「ノータリン」性をおちょくった映画として楽しむことができるという、一粒で二度美味しい「二重構造」を持っているのである。
少し物を考える人なら、この作品の「二重構造」は容易に見抜けるし、またそのように作られているのだから、この作品を、単なる「SF戦争映画」だと評価するような映画評論家は、まずいないだろう。むしろ、そういう人を見つけることの方が難しいのではないかと思う。
だから、ここまで指摘した程度のことなら「馬鹿でも書ける」のだが、今回の再鑑賞で、気づいたことが、ひとつあった。これは、ほとんど指摘されていないことだろうから、その点について書いておこう。

実は、この映画の最後もまた「兵隊募集のプロパガンダ番組」で終わる。
その中で、本作「本編」の主人公やその仲間の活躍なども簡単に紹介されて「君も、彼らのような誇り高い戦士にならないか」みたいなナレーションが入るのだ。
前回観た時は、最初と最後を「兵隊募集のプロパガンダ番組」でまとめて、「形式を整えたのかな」くらいの感じで流したのだが、今回は、この「サンドイッチ形式」を見て、もしかすると、主人公の活躍する「本編」部分は「政府の作ったプロパガンダ映画」という「(隠し)設定」なのかもしれないぞ、ということに気がついた。
つまり、「本編部分」が「SF戦争映画」として当たり前に楽しめるものになっているのは、バーホーベンが本作を、自身の「批評性」とは別のところで、普通の観客にも楽しめる「娯楽映画」とするために、妥協して描いたものだった、のではないのではないか、ということである。

バーホーベンが撮った、「兵隊募集のプロパガンダ番組」である「外枠」の部分は、明らかに「右翼・愛国」主義的なものを、嘲笑し批判するものだった。しかし、それと同じようには見えない「本編」部分さえも、「バーホーベンが撮ったもの」というよりは、「軍国政府が作った戦意高揚映画を、バーホーベンが批評的に再現したもの」と理解できるのではないかということ気づいたのだ。そして、もしそうだとすれば、この映画では、バーホーベンは、いっさい「妥協」などしなかった、ということになるのである。
このような「額物語=メタフィクション」の形式を、そうと察せられにくいかたちで採用し、自身の信念と作家性を貫いたバーホーベンに、私はいたく感心し、この「反骨の映画作家」に惚れ直すことになったのである。
○ ○ ○
ところで、今回私が観たDVDでは、オリジナルの映画にはあったのかなかったのか、今では記憶していないのだが、たぶん無かったであろう「日本語テロップ」が、タイトルの後の冒頭部に掲げられている。次のような文言のものだ。
『1959年 著者ロバート・ハインラインは、軍事政権に支配された未来社会を想定し、SF小説「スターシップ・トゥルーパーズ」を大胆に書き上げた。』
これがあると、ハインラインは、SF小説「スターシップ・トゥルーパーズ」(邦題で『宇宙の戦士』)を、「軍事政権」的なものに対し批判的に書いた、という印象を与えるだろう。
そして、その意味で、これがあると、この映画版も、決して「右翼・愛国」的なものを肯定しているわけではないし、「戦争讃美」をしている作品ではないことも「わかりやすい」とは思う。一一だが、こんなものは、最初からあったのだろうか?


私は今回、日本語吹き替え版でこのでDVDを観たので、この冒頭の「日本語テロップ」も、もしかすると英語オリジナル版では「英語表記」で登場するのかと思い、英語版に切り替えて、再度この部分を確認したのだが、やはり同じ「日本語テロップ」が登場した。
ということは、このテロップは、本来、無かったものを、後から日本で「何らかの配慮なより付け加えた」ものなのではないだろうか?
だとすれば、それは、バーホーベンが本作に込めた「皮肉な意図」を「わかりやすくするため」のお節介だった、ということなのかもしれない。
だが、バーホーベンが本作で批判的にからかっているのは、単に「右翼・愛国」的な思想だけではなく、「アメリカ文化の痴呆性」ということも含まれていると、私は本作「本編」の「通俗エンタメ」的な作りに見ている。したがって、このお節介な「日本語テロップ」も、ある意味では、観客に対して「過剰に優しい」、アメリカ的な「通俗エンタメ」性に竿を差すものでしかないのではないかと思うのだ。
つまり、バーホーベンならば、このような「解説テロップ」を冒頭に置かなくても、当たり前の人間なら、監督の意図したことくらい理解できるはずだし、理解できなくてはならない、とさえ考えていたのではないかと思うのだ。
だとすれば、この「日本語テロップ」自体が、バーホーベンの意図を汲んだというよりは、意図を汲みそこなって、かえってバーホーベンの嘲笑を買う代物になってしまっているのではないだろうか。
このあたりも、DVDを観ただけでは、その真相は不明だが、私のバーホーベン理解からすれば、この冒頭の「日本語テロップ」は余計なものであったばかりではなく、むしろ恥ずかしいものということになるのだが、さて、諸兄のご意見は、いかがであろう?
(2023年11月27日)
○ ○ ○
○ ○ ○
・
・
