
『また失敗するかも』ぐるぐる思考を止める4つのステップ-セルフディスタンシング
朝、目が覚めるとまず「今日も失敗したらどうしよう…」という不安が頭をよぎる。
出社しても「またミスをして上司に怒られるかも…」とぐるぐる考えが止まらない。
夜になれば「明日も同じことの繰り返しなのかな」と落ち込んで、気づけば眠れない。
都内で一人暮らしをする事務職の「えみさん(32歳)」(仮名)は、不安障害や適応障害の傾向があり、職場の環境変化が続く中で日々の仕事に追われています。彼女は真面目で責任感が強い反面、ちょっとしたミスでも「自分はダメだ」「どうせまた失敗する」と考えてしまいがち。実際に大きな問題が起きたわけではないのに、失敗に対する強い恐怖感だけが脳内をぐるぐる回って、常に疲れを感じているそうです。
もし、あなたも似たような経験をしているなら、今回の記事が少しでも参考になるかもしれません。なぜ同じ不安が頭の中を堂々巡りしてしまうのか? どうすれば“ぐるぐる思考”から抜け出し、健全なセルフトークを育めるのか? ひもといていきましょう。
【第1章:なぜ“ぐるぐる思考”は止まらないのか】
えみさんのように「また失敗するかも」という思いが何度も頭に浮かぶ状態は、反すう思考とも呼ばれます。私たちは不安や恐怖を感じると「危険を回避しなければ」という脳の本能的な働きで、同じ心配を繰り返す傾向があります。
脳の安全装置が誤作動している
危険をいち早く察知し対処することは、生き延びるために重要な本能です。しかし、現代社会のストレス源は、必ずしも命に直結するものばかりではありません。それでも脳は「失敗=危険」として過度に反応し、ぐるぐる思考を加速させるのです。思考は現実ではないのに、現実のように感じてしまう
私たちの脳は“想像”と“現実”を完全には区別できません。頭の中で繰り返される失敗イメージを、あたかも本当に起こった事実であるかのように受け止めてしまうのです。
このようにして始まったぐるぐる思考は、次第に自己否定を強め、さらに不安を増大させてしまいます。しかし、そこから抜け出す方法として効果的だと言われるのが、「セルフディスタンシング」というテクニックです。
【第2章:“セルフディスタンシング”とは何か?】
“セルフディスタンシング”を簡単に言うと、「自分の思考や感情を客観的に捉える」という方法です。具体的には、不安や恐怖でいっぱいの“自分”と少し距離を置き、「別の視点」からその感情を眺めてみるイメージといえます。
セルフディスタンシングは「登山の途中で一度高台に登るようなもの」
登山に例えてみましょう。ゴールへ直行しようと急いでいるときは、足元しか見えていません。すると岩につまずいたり道に迷ったりして、目の前の不安ばかり大きく感じますよね。
でも途中で高台に登ってみると、山全体の地形やルートが見渡せます。
「あの急な道は避けられるかも」
「もう少しで頂上が見えてきた」
「あの先で休憩できる場所がある」
このように、大きな視点で物事を捉えると、不安や恐怖に圧倒されるだけではなく、他の選択肢や現状を知ることができます。これが“セルフディスタンシング”の本質なのです。
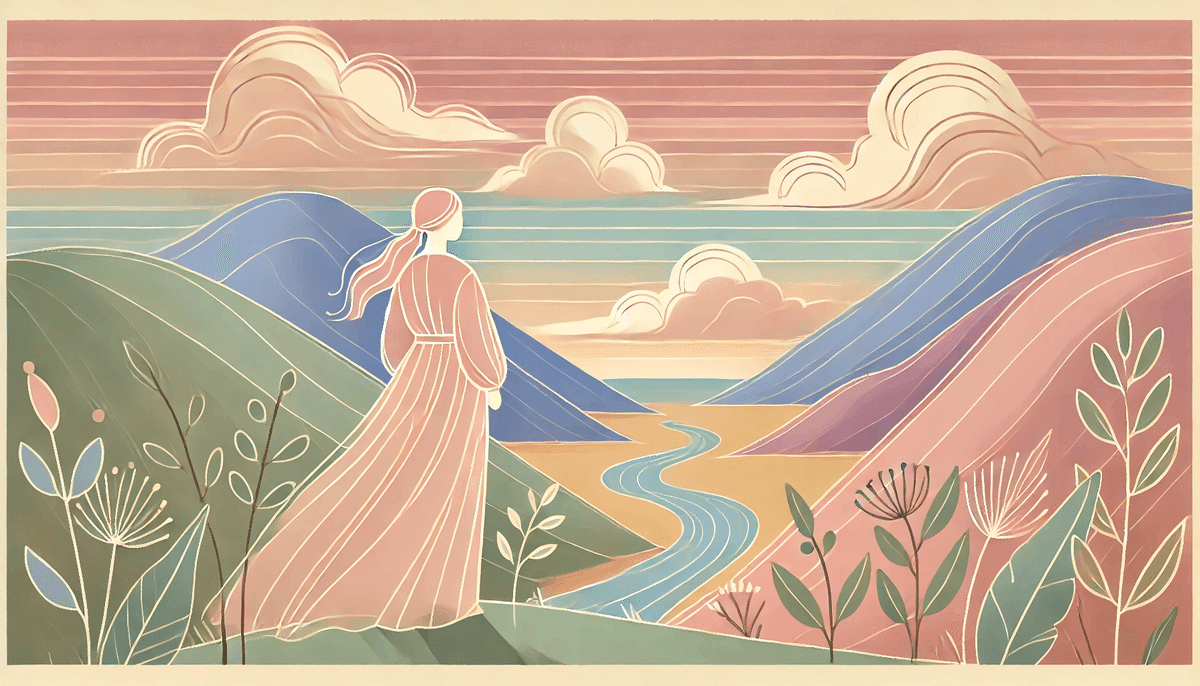
【第3章:ぐるぐる思考から抜け出すセルフディスタンシングの具体的ステップ】
ステップ1:思考を書き留める
まずは、自分が考えていることをノートやスマホのメモに“そのまま”書き出します。
「失敗するのが怖い」
「上司にまた怒られるかもしれない」
「周りから見放されるのではないか」
書き出すことで、頭の中だけで感じていた不安を客観視しやすくなり、「今、自分はこういう思考をしているんだな」と気づく手がかりが得られます。
ステップ2:思考を“人ごと”として眺める
次に、書き出した思考を「もし友達が同じことを言っていたら?」という視点で読んでみてください。誰か大切な人が同じ悩みを打ち明けてきたら、あなたはどんな言葉をかけますか?
「大丈夫だよ」「そんなに自分を責めなくていいよ」と思うかもしれません。自分の不安に対しても、同じように寄り添ってあげることが大切です。
また、こんなテクニックがあります。
今、映画館にあなたがいるとしましょう。あなたが映画館で、あなた自身の状況を眺めているようなイメージです。もがき苦しんでいる自分を映画館で眺めていると、自分ごとではあるのに、客観的にものごとを見れるはずです
ステップ3:現実か想像かを仕分ける
思考の中に「絶対」「いつも」「誰も」といった極端な言葉が混ざっていないか確認します。多くの場合、それらは根拠のない思い込みや拡大解釈であることが多いはずです。
「絶対に失敗する」の根拠は?
「誰も助けてくれない」と決めつけていない?
もし明確な証拠がないと感じたら、それは“想像”に過ぎない可能性があります。「思考は現実ではない」という認識を強めましょう。
ステップ4:言葉をほんの少し言い換えてみる
いきなりポジティブになる必要はありません。たとえば、「絶対にダメになる」を「そんなに大きな問題にはならないかもしれない」に変えるだけでも、心の負担は軽くなります。
【第4章:健全なセルフトークにつなげるために】
ぐるぐる思考を止めるには、脳の“危険探知モード”を少しずつ“落ち着きモード”へ切り替えることが必要です。セルフディスタンシングはその一つの手段ですが、さらに以下の工夫を組み合わせることで効果が高まります。
深呼吸やストレッチで身体をほぐす
身体が緊張していると、不安が高まりやすくなります。定期的に休憩を挟み、軽いストレッチや深呼吸を取り入れましょう。ポジティブな言葉の“種”を用意する
「どんな未来があるか、まだわからない」など、完全ポジティブではなくても、少し前向きになれるフレーズをストックしておくと不安時に役立ちます。周囲の協力も検討する
カウンセラーや信頼できる友人、家族に話を聞いてもらうことで、より客観的な視点を得ることができます。
【おわりに:あなたのペースで大丈夫。今日も一歩踏み出そう】
えみさんが感じている「失敗への恐怖」は、決して特別なものではありません。むしろ、誰しも少なからず抱える“人間の自然な反応”と言えます。だからといって、そのまま放置しておくと苦しい思いは積み重なるばかり。ぐるぐる思考から抜け出すためには、まず「思考は現実ではない」と自覚し、セルフディスタンシングを活用して客観的に自分を見つめることが重要です。
それは、登山の途中で高台に上がるように、いま立ち止まって景色を見渡す行為かもしれません。急ぎすぎず、自分のペースで大丈夫。途中で休憩しても、遠回りしてもいいのです。自分を追い詰めるセルフトークではなく、「まだ結論は出ていない」「今やっていることはどうとでもなる」といった少しだけ優しい言葉を、自分にかけてみませんか?
どうか「また失敗するかも」という不安に負けず、自分の力を信じて、ほんの少しだけ前に進んでみましょう。あなたには、あなたの素敵なペースがきっとあります。焦らず、自分を見守ってあげる気持ちで、ぜひ日々を過ごしてみてくださいね。
もし共感したり、なるほど!と思ったらスキやフォローをよろしくお願いします('ω')
