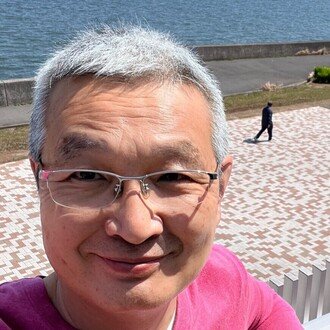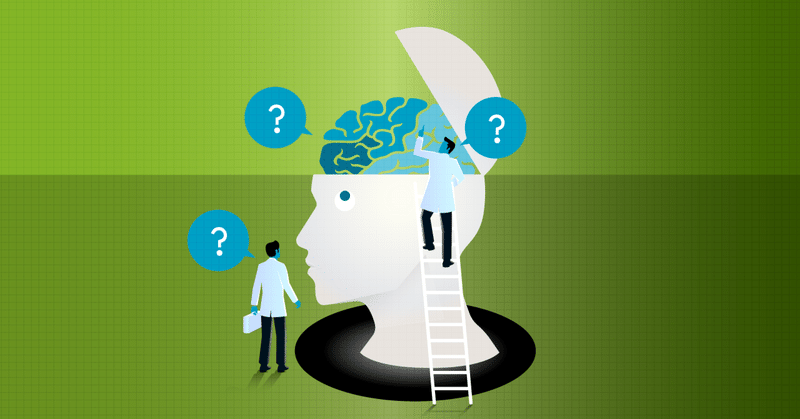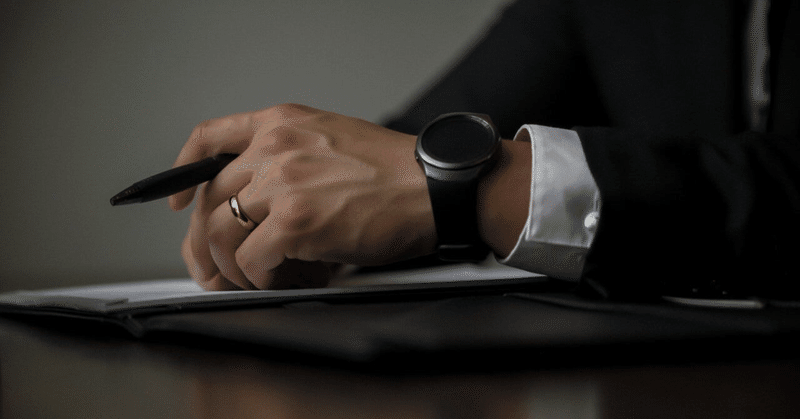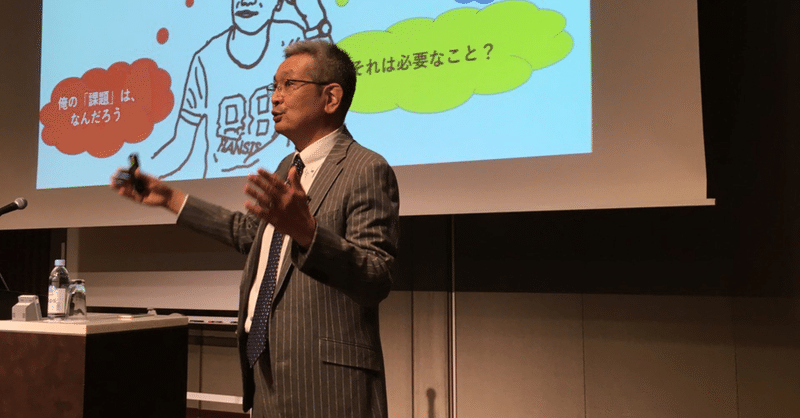
- 運営しているクリエイター
#仕事の心がけ
「成果マネジメント」の終焉。次は「学習マネジメント」が始まる。_これ知らないリーダーは必ず失敗します。
最近、もてはやされているマネジメントスタイルは、
リーダーと社員が学習と実践を通して「質の高い情報」を共有し、協働で成果を上げることです。
それなにのワンマンな経営者が大きな成果を上げると、以下のような論調でメディアが注目します。
抜群の指導力
強烈かつ俊足な意思決定力
成果主義の厳しいマネジメント
この場合の成果とは業績を意味します。
いったい、どちらのマネジメントが成功するのでしょうか
「直感」で判断する人が成功しない理由_脳科学でマネジメントを見ると面白いことが分かります。
直感で、人にレッテルを貼ったり、物事を判断してしまうことがよくあります。
「あの人の考え方では、とても仕事ができると思えない。」
「このマーケットは将来性がないので、やめておこう」
「今は、この案件に手を出すべきではないと思う」
最近ではリモートで一度も会ったこともないのに、親しく話す人、そうでない人もいます。
人は、いちどレッテルを貼ってしまうと、それを張り替えることはまずありません。
「ツラい目標」を「ワクワク目標」にする方法_心理的安全術
人が活動するときは、必ず何がしかの目標を立てます。
経営企画部門は、理念、コアコンピュタンスに沿った中長期・年度目標。
営業は、販売目標、利益目標。
開発部門は、新製品の開発計画。
生産部門は、生産目標、品質目標、コスト目標。
間接部門は、間接費の低減目標。
などです。
しかし、私達が「目標」という言葉を聞くと、なんだか重苦しく感じます。
何故でしょうか。
それは日々数字に追われ
②/⑥「デキる人、頭の良い人」の定義は、『人間偏差値が高い人』です。_心理的安全を創れる人の話。
前回の記事で、これから求められる「デキる人、頭の良い人」は、好奇心とコミュニケーション力を持ち、以下の6つの要素を満たす人とお話しました。
今日は、好奇心とコミュニケーション力の醸成法についてお話します。
まずはロジラテ思考のファーストステップ Whatから分析してお話します。
1.What_インナーコミュニケーション(社内)の実態
これまで訪問した企業で、インナーコミュニケーションについて
①/⑥「デキる人、頭の良い人」の定義は、『人間偏差値が高い人』です。_学力偏差値の終焉の話。
仕事柄、たくさんの経営者やマネージャーにお会いしますが、皆さんの共通する悩みはこの3つです。
・コミュニケーションが活発な組織にしたい。
・社員が能動的に動き、成果を上げることに喜びを感じる組織にしたい。
・イノベーションを上げられる組織を創りたい。
私が入社した80年代は、こんな悩みをもった経営者やマネージャーはいませんでした。
彼らが望む社員とは、昔流の言い方で「猛烈社員」です。
例えば