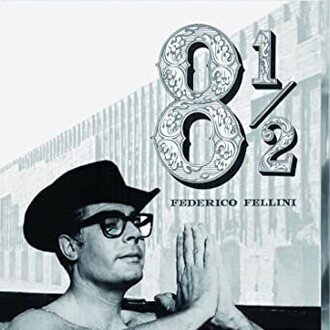記事一覧
シン・短歌レッスン188
2000年代──「かけがえのない私」と失われた二十年
大野道夫『つぶやく現代の短歌史(1985-2021) 「口語化」する短歌の言葉と心を読みとく』から。
斎藤斎藤
口語短歌と諧謔性。歌名からしてそんな感じだが、ときどき読む批評とかは鋭いところを突いている。前衛短歌が継承されているとしたら彼の短歌かもしれない。
県道というのがポイントか。地方性はどことなく都会にならない僻みみたいもの。「
シン・短歌レッスン187
1990年代──「わがままな私」とバブル経済の崩壊
大野道夫『つぶやく現代の短歌史(1985-2021) 「口語化」する短歌の言葉と心を読みとく』から。
穂村弘
短歌で一番親しみを感じるのは穂村弘か。
不完全な言葉「ゆひら」で了解できる男女の間。今読むとそれは内輪なんだが、『シンジケート』という歌集がアンチ俵万智の世界を吹っ飛ばす破壊力を持った言葉のように感じた。
言葉は排泄物か?そ
シン・短歌レッスン186
NHK短歌
安田登は能楽師だけれども和歌より漢詩好きのようで面白かった。あと安田登の独自な解釈は俵万智の現実的解釈よりも深いけど、そこまで読むかみたいな。
この歌は「飛び石」で下を向きながら不安な仕草から別れ話をしに行くつもりだったのに、「抱きとめられに」であなたに抱かれるという逆の展開になりそして三月(別れの季節)に向かっていくと歌だという。最初徐々に歩いているのだが、あなたが見えたとたん
シン・短歌レッスン185
1930年代以前生まれの歌人
大野道夫『つぶやく現代の短歌史(1985-2021) 「口語化」する短歌の言葉と心を読みとく』から。短歌史は篠弘を読んだのがけっこう面白かった。
それで短歌史は「前衛短歌」(60・70年代)ぐらいまでしか語られず俵万智世代(80年代)以降を見ていこうという本なのだが、こういう本を読みたかった。俵万智以後なんかそれまでの短歌の文法とは違っていると感じるのだが、そ
シン・短歌レッスン184
NHK短歌
詩になる瞬間。一言の言葉で日常世界を詩的に変える言葉の発見。その意味でのキーポイントとしての「鍵」なのか?
竹中優子だけどよくわからん短歌だ。なんで扇風機の羽が繁殖期と結びつくんだ。「ごとき」は直喩で、呼びかけの「よ」か?「ひかり」はよく使われる詩的言語だと思うが、生物的比喩で非生物を語るということだった。扇風機の羽の意味がよくわからない。天使の羽に見えたとか?無機物なものに生命
シン・短歌レッスン183
歌集『『老人ホームで死ぬほどモテたい』上坂あゆ美
『昭和遠近短歌でたどる戦後の昭和』島田修三
原爆
火の見櫓
これだけでは大空襲とはわからんな。夕焼の情景かと思ってしまう。
物売り
ノスタルジー短歌だった。
「三種の神器」
戦後の三種の神器とは、昭和30年代初期に普及した白黒テレビ、電気洗濯機、電気冷蔵庫です。その次が車、クーラー、カラーテレビとなっていく高度成長期。今はなん
沼津発ガールズムービーのような短歌
『老人ホームで死ぬほどモテたい』上坂あゆ美
タイトルから中年過ぎの歌人かと思っていたら30代の若手歌人だった。『うたわない女はいない』働く三十六歌仙で気になったから借りたのだがそのときの短歌も「いつもありがとう青汁 健やかな自傷行為をしてからねむる」というわかりやすい歌だと思う。
穂村弘や東直子から影響を受けたと思わせるセンスは、その選者の元で投稿していたのだという。沼津という地方都市が16号
シン・短歌レッスン182
NHK短歌
「おはよう」は声に出すけど「おやすみ」は静かに言うというその差をどう表現するか?なんか今日の枡野浩一の短歌いいじゃないか?
一日の中で何かを諦めた時に眠るという。今日は「シン・短歌レッスン」を上げるまで眠れない。
改悪コーナ
改悪例は言葉ではなく絵になるが上の歌は言葉でしか表現できない。フレーズがだれでも真似したくなるような言葉にする。
四月から選者が変わるんだ。
荻
シン・短歌レッスン181
NHK短歌
ゲストが町田康で期待してしま。そう言えば歌集だしたんだよな。
町田康がグラサンしたヤクザで大森静佳を恐喝しているような構図でやりにくそうだった。尾崎世界観は一応先輩作家でもありミュージシャンだから一目置いているようだ。いつもはじわじわやドキッはもっと出るのだがあまり出なかったな。大森静佳が三席上げた歌はまったく町田康好みじゃなかったようだ。
「自在自由」という言い方が仏教っ
シン・短歌レッスン180
NHK短歌
日記は若い時からよく書いていたが、若いときは忘却するために日記を書いていたような。今は健忘録になっているが、若いときはこんなに詳しく書いてなかったと思った。日付のない日記や観念だけの日記とか具体的な行動は現在の方が書き残している。まあどうでもいいような日記ではあるが、俳句や短歌と一緒か?今日の一首。
一条天皇の辞世の歌なのだが、行成と道長の日記では下の句が違うという。実際に臨