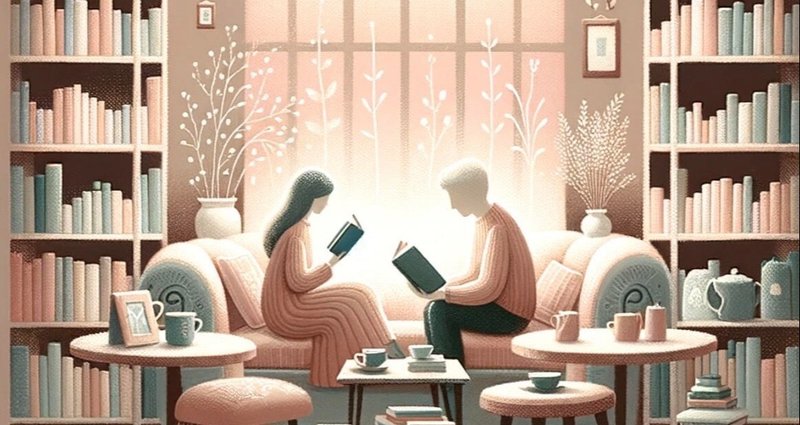記事一覧
「異次元緩和の罪と罰」 山本謙三著 講談社現代新書
この本を読んでいて思い出したのですが、1960年、当時の池田勇人総理大臣は、「所得倍増」をスローガンとしました。これは分かりやすく、実際その後10年で倍増以上の成果を出しました。
それに比べ、異次元緩和「物価前年比2%増」・・これは分かりにくい。そもそも一般大衆は、物価の上昇を恐れるものです。政府と日銀がこの目標を掲げたとき、僕は、なんでこんな文言にしたんだろう?と思いました。「所得前年比◯%増
「ドイツ人のすごい働き方」 西村栄基 著 すばる舎
日本は、ドイツにGDPで抜かれました。人口が日本の2/3ぐらいなのに・・・です。
この本は、ドイツの働き方がなぜ効率が良く、生産性が高いのかについて書かれています。
ドイツ人は残業しません。
朝早くに働き始め、夕方には颯爽と仕事を終える
終業間際には一斉にデスクを片付け始め、17時にはオフィスから人が消える
デスクの上は毎日、新品のように整理整頓されている
年間約30日間の有給休暇をフル取
「スタグフレーション」 加谷珪一 著 祥伝社新書
「スタグフレーション」 加谷珪一 著 祥伝社新書
2年前に書かれた本ですが、ここで指摘されていることが本当に起こり始めているように感じます。
日本は、先進国の中で、最も不景気下でのインフレ、つまり「スタグフレーション」が起こりやすいと著者は言います。
このところの物価上昇とどうも景気がいいとは感じられない状況は、もはやスタグフレーションに片足突っ込んだ状態なのではないかと思ってしまいます。
「データでわかる2030年雇用の未来」 夫馬賢治 著 日経プレミアシリーズ
このまま何もしないと、地球温暖化は止まらず、先進国の少子高齢化が進み、食糧は不足する・・・。生成AIの発展により、仕事を奪われる人が増え、格差は拡大するでしょう。
著者は、そうならないために、産業革命が起こるだろうとのことです。産業革命は、ウェディングケーキ・モデルを考慮しなければならないと言います。
ウェディングケーキ・モデルとは、
「世の中の状況を、「経済層」「社会層」「環境層」の3つに分
「世界の終わり」の地政学 下 ピーター・ゼイハン 著 集英社
著者によれば、アメリカが国際秩序の維持に積極的でなくなり、世界から撤退していくと言います。
その理由は、著者の主張に従えば、以下のようにまとめられます。
エネルギー自給の達成:シェール革命により、アメリカはエネルギー自給が可能になり、中東などのエネルギー供給地域への依存が大幅に減少。そのため、これまでのように海外の安定を守る必要性が薄れている。
内面に向かう国内世論:アメリカ国内の世論も、海
「世界の終わり」の地政学 上 ピーター・ゼイハン 著 集英社
原題は、「The End of the World is Just The beginning」です。物騒ですねぇ。
今回は、その上巻についてです。
上巻の目次は、
第1部 一つの時代の終わり(始まりは、いかにして始まったのか?;偶然の超大国アメリカ;流れをがらりと変えたもの ほか)
第2部 輸送(長い道のり;制約からの解放―輸送を工業化する;アメリカナイズされた交易 ほか)
第3部 金融(通貨―
「デジタル生存競争」 ダグラス・ラシュコフ 著 ボイジャー
著者の考えによれば、少数の富裕層やデジタルエリートたちは、世界の富のほとんどを所有しています。彼のマインドセットは、指数関数的な成長を信じ、壁にぶつかったらそれを乗り越える技術が生まれると信じているように見えます。
AIがいろいろな問題を解決してくれるかもしれません。でも、AIには莫大な電力が必要なのです。
しかし、例えば、「電力の大部分を再生可能エネルギーによって賄うためには、風力発電や太陽