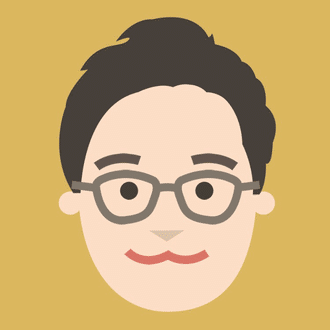右脳と左脳どうバランスすべきか? アートシンキングから考える脳の使い方とは
「デザインがうまくなるコツの半分は数学的思考なの!?」
ちょっと意外な情報に触れました。アートシンキングという考え方を取り上げた本の中で見つけた一言。なかなか気づきの多い一冊でした。
デザインやアートという言葉から、右脳左脳の話など、自分の頭をどう使えばより自分の能力を発揮できるのかについて、発見がありました。
この本の魅力をご紹介します。
アートシンキングとは
今回、出会ったのはこちらの書籍。増村 岳史さんの著書「ビジネスの限界はアートで超えろ!」です。
ロジカルシンキング、クリティカルシンキング、ラテラルシンキング、デザインシンキングという言葉は見聞きしていましたが、アートシンキングというのは初めて耳にしました。
「絵が描けることは、0から1を生み出せることにつながる」
絵を描くことで、新たな知覚と気づきが手に入る。眠っている自分の才能が目覚め、開花する、とこの本は説きます。
アートアンドロジックを主催する著者の増村岳史さんはビジネススキルを向上させる講座なども開いているそうです。その講座はデッサンを書くことで、右脳と左脳のバランスを生かし、思考能力を高める講座だそうです。「新しいものを発想していく力」「物事を俯瞰して捉える力」「調和のとれた思考力」などが身に着くとのこと。
この本で、デッサンが上手くなるコツとして「数学的な物事の見方」があると言います。「絵を描く」となると、大概の人は感性を司る右脳が重要だと考えます。私もそう思います。しかし、右脳も大切だが、論理を司る左脳と統合した能力が必要なのだと著者は説きます。
対象をしっかりと観察し、頭の中のイメージを手先の鉛筆のタッチに変換する作業は、言い換えれば情報を分解して、体で翻訳して表現するということでもあります。「論理を身体で習得していく」ということなのかも知れません。スポーツの反復練習に近いのかもしれません。どうすれば自分の体がイメージ通りに動くのかを分解して、トライ&エラーを繰り返す。この経験によりスキルが上達します。
デッサンや絵を描くのもこれと同じであると言います。野球でいう素振り。やればやるだけ基礎が身に付き、上達します。デッサンもそうであると言えます。鉛筆を動かした経験の蓄積が、結果的にデッサン力を向上させます。
デッサンがうまくなるコツの半分は、数学的、論理的にものごとを考えられるか。そして残りが、その人が本来持っている感性の力を引き出すことにあります。絵を描くことは、感性や感覚をつかさどる右脳と、論理をつかさどる左脳を統合した、調和のとれた能力が求められるということ。
クリエイティビティとは
クリエイティビティと聞くとどんなイメージを持つでしょうか。「センス」「豊かな感性」などを連想してしまいます。「自分にはセンスなどない」とあきらめてしまう人もいるかもしれません。
アートの歴史では、印象派は「対象物を感じたままに描く」スタイルでした。そこに対しピカソは「複数の対象物を多面的に描く」ことでキュビズムを生み出しました。つまりクリエイティビティとは「組み合わせ」であるとこの本は説きます。
クリエイティビティ=既存のあるものに別のものと組み合わせることで新しいものを生み出すこと
そう考えると、何もアートの世界だけの話ではありません。クリエイティビティは我々の日常の生活の中にたくさん隠れています。冷蔵庫のあまりもので料理を作るのもクリエイティビティです。モノを観察して組み合わせることで誰でも発揮できる機会はあります。
昨今はアートブームとも言える状況です。今アメリカではMBAよりもMFA(美術学修士)を持っている方が人材として人気とのこと。ビッグデータとロジックによる戦略だけでは、消費者の未充足ニーズに応えられる驚きのある商品は生み出せません。企業はデザインやアート性、さらにはストーリーを組み立てられる人材を求めていると言えます。
そういう意味では、右脳と左脳をバランスよく使える人材、その要素としてクリエイティビティという能力は多くのビジネスパーソンに求められてるスキルとも言えます。
まとめ
今の時代は「これでいいんじゃないですか時代」と言われます。大概の欲求がある程度満たされ、「これでいいんじゃね?」と多くの欲求が満たされています。モノがあふれる世の中で、それでも魅力的な商品やサービスを生み出せるかは、ロジカルな思考だけでは不十分です。そこにはデザインシンキングや、アートシンキングが鍵を握っていると言えます。
右脳と左脳を統合し、バランスよく思考できる人材が今後より高く評価される世の中になっていきます。その時に重要なのは「観察する力」。観て、気付き、物事を分解する頭の使い方が重要になってくると思われます。
全体を直感的に大掴みする感性や、課題を独自の視点で発見し、クリエイティビティを発揮して解決する力が求められてきます。
今回の書籍に出会い、個人的には「絵を描く」は感性だけでなく、実は論理的な視点も重要というのは、右脳と左脳をバランスよく使うという意味で、新しい気づきでした。
アートやデザインに関わるかどうかに関係なく、アートシンキングを日々の仕事や生活に取り入れて、組み合わせによる新価値創造をしていけると良いですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
いいなと思ったら応援しよう!