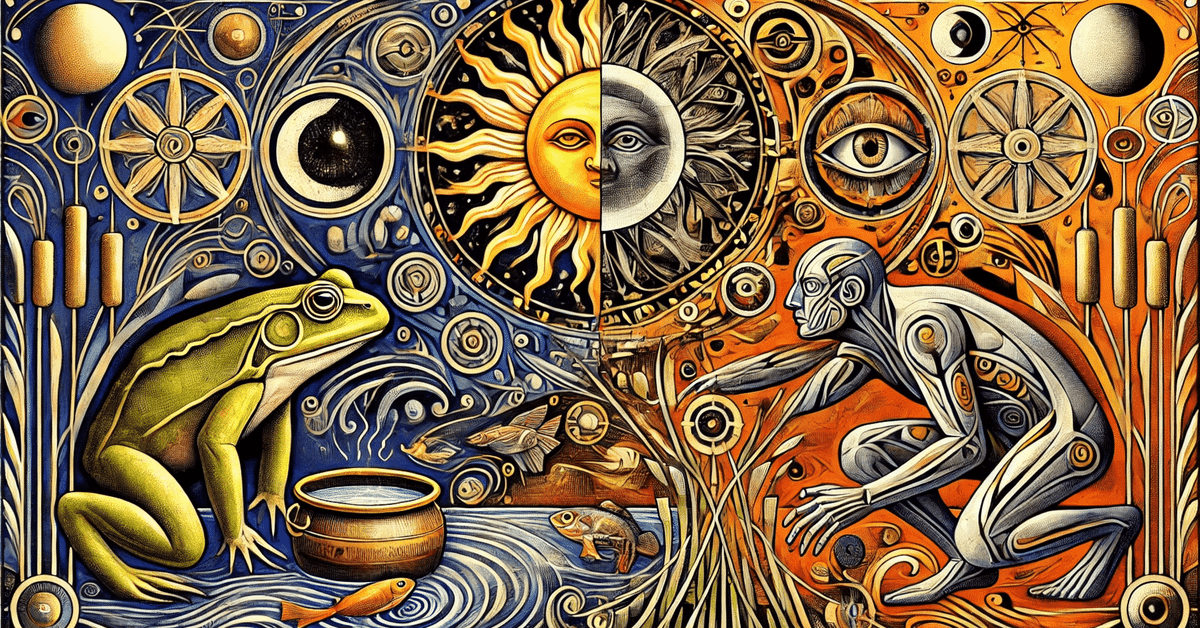
分離と結合のマンダラは2/3/6/4/8極に伸び縮みする -レヴィ=ストロースの『神話論理』を深層意味論で読む(77_『神話論理3 食卓作法の起源』-28,M430b天体の妻たち)
クロード・レヴィ=ストロース氏の『神話論理』を”創造的”に濫読する試みの第77回目です。『神話論理3 食卓作法の起源』の第五部「オオカミのようにがつがつと」を読みます。
これまでの記事は下記からまとめて読むことができます。
これまでの記事を読まなくても、今回だけでもお楽しみ(?)いただけます。
はじめに
レヴィ=ストロース氏の「神話の論理」を、空海が『吽字義』に記しているような二重の四項関係(八項関係)のマンダラ状のものとして、いや、マンダラ状のパターンを波紋のように浮かび上がらせる脈動たちが共鳴する”コト”と見立てて読んでみる。
神話は、語りの終わりで、図1におけるΔ1〜4を分けつつ、過度に分離しすぎない、安定した曼荼羅状のパターンを描き出すことを目指す。

そのためにまずβ二項が第一象限と第三象限の方へながーく伸びたり、β二項が第二象限と第四象限の方へながーく伸びたり、 中央の一点に集まったり、という具合に振幅を描く動きが語られる。
お餅、陶土、パイ生地を捏ねる感じで、四つの項たちのうち二つが、第一の軸上で過度に結合したかと思えば、同時にその軸と直交する第二の軸上で過度に分離する。この”分離を引き起こす軸”と”結合を引き起こす軸”は、高速で入れ替わっていく。
そこから転じて、βたちを四方に引っ張り出し、 β四項が付かず離れず等距離に分離された(正方形を描く)ところで、この引っ張り出す動きと中央へ戻ろうとする力とをバランスさせる。
ここで拡大と収縮の速度は限りなく減速する。そうしてこのβ項同士の「あいだ」に、四つの領域あるいは対象、「それではないものと区別された、それではないものーではないもの」(Δ)たちが持続的に輪郭を保つように明滅する余地が開く。
*
ここに私たちにとって意味のある世界、 「Δ1はΔ2である」ということが言える、予め諸Δ項たちが分離され終わって、個物として整然と並べられた言語的に安定的に分別できる「世界」が生成される。何らかの経験な世界は、その世界の要素の起源について語る神話はこのような論理になっている。
私たちの経験的な世界の表層の直下では、βの振動数を調整し、今ここの束の間の「四」の正方形から脱線させることで、別様の四項関係として世界を生成し直す動きも決して止まることなく動き続けている。

というわけで前回、前々回に続き「天体の諍い」シリーズの神話である。
レヴィ=ストロース氏は神話の分析を通じて、私たちが理解したり伝達したりすることが容易にできる日常の表層の言葉の直下で、”Aでもなく非-Aでもない”両義的媒介項たちが分離したり結合したりまた分離したり結合したりと脈動しつづけており、そこから表層の分節システムの”元型”となる分離と結合の定常的なパターンが、対立関係の対立関係の対立関係としての八項関係を描きながら現れては消える様を語る。

というわけで『神話論理3 食卓作法の起源』から「M430bヒダッツア 天体の妻たち(二)」を見てみよう。
天にある小屋に、ひとりの女とそのふたりの息子である太陽と月が住んでいた。太陽と月は交代で大地を照らしていた。
ある日、太陽は兄弟に、どこの国の娘たちがもっとも美しいだろうとたずねた。
月は答えて「グロヴァントル(=ヒダッツア)の国の娘たちが一番だ。彼女たちは地上の小屋のなかに住んでいて、化粧をして太陽の熱から肌を守っている。しばしば水浴びをし、身体の手入れをよくする。グロヴァントルの娘たちがもっとも美しい」と言う。
太陽は「そんなことはない。彼女たちは昼間、わたしを見て、しかめっ面をし、顔を背ける。それで、片側がかげになってしまう。カエル娘たちは瞬きもせずわたしを見るし、顔をしかめることもない。カエルたちが一番きれいだ」と言い返す。月と太陽 はそれぞれの種族から女をひとり連れてきて、その美しさを比べてみることにした。
*
月は、ある夫婦とその三人の娘たちが住む場所へ出かけていった。
上のふたりはすでに結婚しており、下の娘は未婚だった。
末娘は美しくしかも清純であった。
ある日、姉たちがヤマアラシを欲しがり、姉ふたりに命じられた末娘はヤマアラシに続いて木に登り、姿を消す。
* *
月の母親は息子の選択を誇らしく思う。
入り口に放置されたカエルはゲロゲロ鳴き、不平を言う。
カエルは鍋の後ろに隠れる。
月は噛み方比べを催すことにした。
「氷の固まりを砕くような音を立てて臓物を噛むことのできる女を置いておこう、勢いよく噛むことができず、よだれをたらす女には帰ってもらおう」
というルールとした。
月は兄弟の気分をそこねるつもりはなかった。
競技は、自分たちと仲良く暮らすことなどけっしてできないだろうと思われカエルを追い払う格好の口実となると考えたのである。
母親が臓物を煮ると、女たちはそれぞれ自分の分を選んだ。
インディアンの娘は薄い方、カエルは厚い方である。
女たちは石のナイフで肉を切り、噛みはじめた。
インディアンの娘はカリカリいい音をたてた。
カエルがボリボリ音をたてる音も聞こえた。
月が鍋をどけると、太陽の妻が炭を噛んでいるのが見えた。
カエルはよだれをたらし、身体を汚していた。月は彼女を火の中に投げ入れたが、カエルは彼の額に飛びついた。カエルを振りはらおうとの努力もむなしく、カエルはそこに落ちついてしまった。
「おまえとおまえの兄弟はわたしをいらないと言う。けれどもわたしはここにいよう。おまえがわたしを傷つけることなどはできないし、わたしはけっして死なない」
とカエルは言った。
グロヴァントル族は月の隈を「月のカエル」と名づけている。
緑色のカエルではなく、太陽が妻とした大きな 砂漠のヒキガエルのことである。この種のカエルを「おばあさん」と呼び、太陽は「おじいさん」と呼ばれる。これらのヒキガエルは聖なるもので、子供たちにそれを敬い、祈りを捧げるようにと教えるのである。
神話では祖母と孫の話、太陽の息子の話がつづく。

三位一体からはじまる
まず冒頭、今日では星であるはずの太陽と月が、まだ人間のように「小屋」に住んでいる。一つ屋根の下に、三人の星人間、母と二人の息子(兄弟)が集まって住んでいる。男/女、老/若、兄/弟、親/子などなど、経験的で感覚的な二項対立の両極を一点に集めたようになっているわけである。しかも彼らは天体でもなく人間でもない、つまり経験的な分別に対して両義的な位置に立っている。
両義的な項が、ぎゅっとまとまって一つになっている。
ところで、この神話がおもしろいのは、この星=人間たちが「三」であるという点だ。
母と息子二人の三人である。
母
|
息子1(兄)/息子2(弟)
これはどうしたことか。
両義的媒介項は四つそろってこそ、収まりよく調和すると、他の神話では思考されているというのに。
この疑問を抱きつつ、先まで見てみよう。

人間とカエルの非同非異
この太陽と月の兄弟も、結婚相手を巡って対立する。
真逆の結婚相手を求めるのである。
今回の太陽はカエルと、月は人間と、結婚しようとする。
別の神話では太陽が人間と、月がカエルと結婚するバージョンもある。対立関係が対立関係をなして四項を分けつつつなぐことが重要であり、この対立関係を対立させる「向き」(つまり太陽と月の対立の太陽の側に来るのが、人間とカエルの対立のどちらなのかということ)はクルクルと回転して構わない。これが野生の思考の神話論理がダイナミックなところである。
太陽←/→月
|| ||
カエル / 人間
|| ||
太陽を見る時に目を見開く / 太陽を見る時に目を細める
ここでカエルと人間の対立軸上に、冒頭で一緒に一つ屋根の下にまとまって結合(密着)していた「太陽」と「月」を引き離す・引き剥がす・分離するのである。
*
感覚による対立、本質による対立
ところで、どうして人間とカエルが対立するのかといえば、それは太陽を見つめる時に目を細めるか/目を開いたままにするか、という点で人間とカエルが「逆」だからである。
目の開/閉。
なんと細かい、と思いたくなるが、これぞ神話である。
どれほど細かい差異でも見逃さない。
カエルと人間は、「口の中に食べ物を入れて、もぐもぐと食べる」という点ではよく似ている。どちらも鳥のようについばむのでもなく、魚のようにパクリと飲み込むわけでもなく、口に物を入れて転がす。この点で人間とカエルは”同じ”なのである。あるいはまた「二つの目で見上げるようにして太陽を見る(見ているようにみえる)」という点でも人間とカエルは「同じ」である(もちろん人間は、口にいれて転がさずに、よく噛まずに食べ物を丸呑みすることもできる。カレーが飲み物であるという場合などはそうである。そこで神話はあえて、噛むときに音が響くほど硬い、コリコリとした料理を食べさせるのである。)
そして同じでありながら、しかし同じ食べると行っても歯で噛んで音をたてる/たてない、という点では真逆に異なっているし、太陽を見るときに目を閉じる/閉じない、という点でも真逆に異なっている。
同じようでいて同じではなく、違うようでいて違うとも言い切れない。これがカエルと人間の対立関係、異なるが同じ、同じだが異なる関係である。
人間とカエルの対立関係が、なにかカエルの本質(カエル性)なるものと人間の本質(人間性)なるもの、二つの本質の対立としては考えられていないことが重要である。この神話は徹底して、感覚的区別(瞼が閉じているか開いているか、食べ物を噛む音がするかしないか)において人間とカエルの差異を感知し、また「口でパクりと食べる」「二つの目で空を見上げる」といった経験的な行動パターンの類似性においてカエルと人間が”ちょっと似ている”と感じるのである。
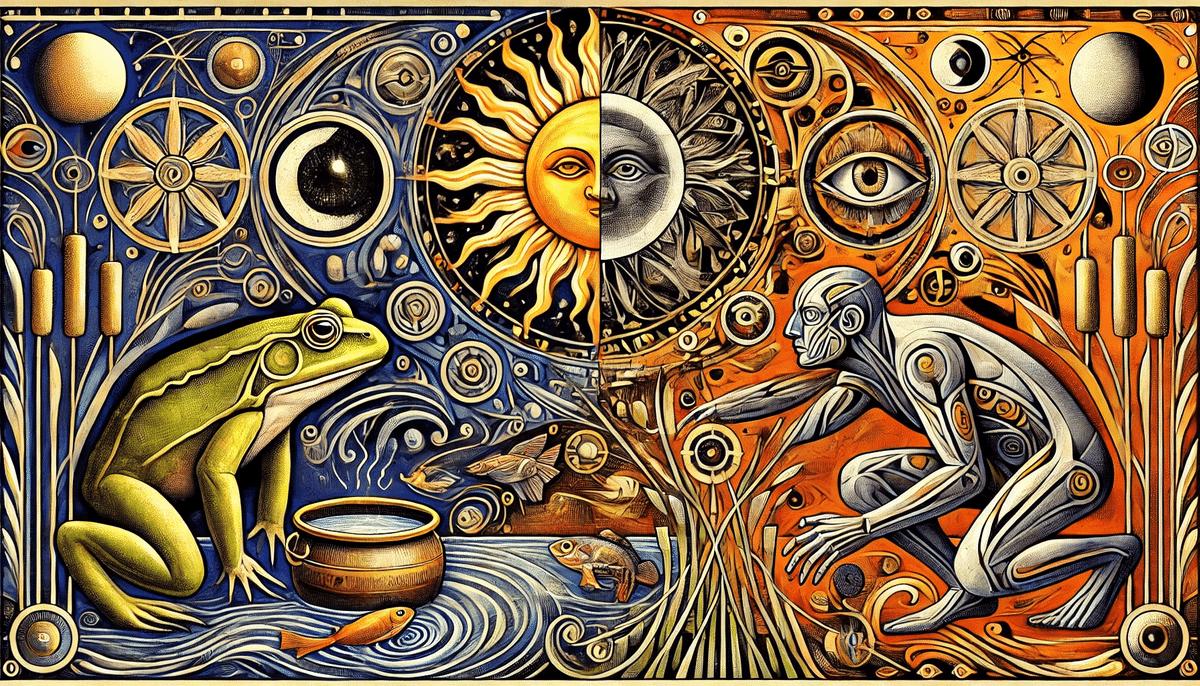
*
感覚的対立軸が変われば、対立しなくなる
ということはつまり「目の開閉」や「食べる時の音の有無」とは別の二項対立に照らし合わせると(例えば空を飛ぶ/飛ばない、とか、年に一度大群で川を遡上する/しない、とか)、カエルと人間はうまく対立しないことになる。
神話における対立はあくまでもそのつど焦点化された経験的で感覚的な差異、区別によるものであり、何らかの”本質”による対立ではない。あるいは対立する/しないの対立もまた、対立させれた対立するし対立させなければ対立しない、というどちらでもあってどちらでもない不可得モードにあることこそが神話の思考のおもしろいところなのである。
差異性と同一性との差異性と同一性
分離と結合との分離と結合
そういうことが不可得と不可得が重なり合うところで振れるのである。

* *
三人の娘と、六項関係
そうしてカエルと、人間の娘が天界の太陽と月の実家へと誘われる。
ここで面白いのは、地上から天井の昇ることになる人間の娘も「三」であるという点である。天上では太陽と月とその母親の「三」がおり、地上には人間の娘が「三」いる。
上の三と、下の三。
あわせて六である。
のちに見るようにこの六項関係は八項関係と同じことである。
曼荼羅は高速で振動しているので、同じことが見る者の視覚の振動数に応じて、六と観察されたり、八と観察されたり、その見える数が変わるのである。
ちなみにこの三人の娘も三姉妹という点では「同じ」であるが、ヤマアラシの針を無闇に(?)欲しがる少々節操のない(?)二人の姉に比べて、末娘は命じられて仕方なくヤマアラシの居る木に昇るという点で、このヤマアラシ狩りにあまり積極的ではない(控えめ)。また姉娘二人は既婚であるのに対し、末娘が未婚であるという点も二者択一で対立している。
この神話では、一場面一場面、ワンカットごとに、それぞれ異なる対立関係とその中間の両義的媒介項からなる三項関係が全面に出てくる。
食卓マナー合戦
そしてここから、定番の食卓作法対決である。
この世界では、「硬いモツ煮込みを良い音を立てながら歯で噛むこと」がベストな食卓作法とされている。
氷の固まりを砕くような音を立てて臓物を噛むことが
できる / できない
↓ ↓
天界にとどまる / 天界から追われる
このシンプルなルールで勝負が行われ、カエルが敗退する。
この勝負、おもしろいことに少し不公平になっている。つまり平等、公平な勝負ではなく、初めから差異が開いたところで勝負が始まっている。レヴィ=ストロース氏は次の点に注目する。
「[…]インフォーマントの記憶の中に二重の対立が残っているということに注目しよう。胃の毛むくじゃらな部分は薄く、厚い部分はなめらかなのである。したがって神話においても、厚いと薄いの対立はもうひとつの毛むくじゃらとなめらかの対立を隠しているかもしれないのである。」
人間の娘は薄い/厚いの対立でいえば「薄い」肉をとり、また口で噛む前に「石のナイフ」を使って食べやすいサイズに切っている。同じ臓物料理を食べているのに、食べやすい/食べにくい、という対立軸上ではカエルの条件と真逆に異なる。
厚い / 薄い
毛むくじゃら / なめらか
食べにくい / 食べやすい
”同じ”ひとつの臓物料理について、実に細かな対立が連なって重なり合っている。

不死が不死なら人間は
この勝負に敗退したカエルは、天上界から追われるはずが、開き直って義理の兄弟である月の「額」にへばりつき、離れなくなる。
結合から分離へと傾向が切り替わったかと思うと、すかさず翻って過度に結合する。そしてそのカエルとの結合の結果、月は、天界の小屋での母と兄弟との結合から分離されて、昼に対立する夜の天体として独立する。こちらで結合するとあちらで分離し、あちらで分離するとこちらで結合する。
このような分離と結合の間の振れ幅を描く動きから、私たちが今日よく知る、日々空に見ている、あの隈のある月の存在が始まったのである。
そしてこの月と一体化したカエルは「不死」である。
ちなみにカエルが月に張り付くポジションも、神話によって、背中/腹、頭/頭から下、といった細かい対立のあちらになったりこちらになったりする。
そして、このカエルが不死になるがゆえに、カエルと対立していた人間は、不死ではなくなることになる。これが人間の起源である。

八項関係を六項関係に圧縮する
さて、レヴィ=ストロース氏は、この神話三姉妹、「三つ組」に注目する。
神話にはしばしば、同じような人が三人セットになった「三つ組」が登場する。
三つ組が二つ組み合わさると、6が出てくる。
例えば、ある老婆には三人の息子と三人の娘が居た…といったところから始まる神話がある。この場合、まず、男/女、が対立し、この男と女、それぞれの極がそれぞれ三つに分かれる。まず二つに分かれ、次にそれぞれが三つに分かれても、この2×3=6は同じ親から生まれた兄弟姉妹ということで”異なるが同じ”、非同非異の者たちである。
男:3 (長男、次男、三男)
||
老婆
||
女:3 (長女、次女、三女)
ここで男女それぞれの三人セットのうち、一番上と一番下は、極、まさに”極まった”あり方をしているのに対して、真ん中の息子と真ん中の娘は、二極の間を動き回る。
長男:昼
/||ーー次男:周期的に現れては消える”太陽”
三男:夜
長女:明けの明星(東)
/||ーー次女:北極星の回りをまわる星
三女:宵の明星(西)
次男と次女は、それぞれ、昼/夜、東/西の両極の「中間」を振幅を描きながら周期的に動く。これについてレヴィ=ストロース氏は「子供の数は、男のペアと女のペアそれぞれの項のあいだに、第三の項が入り込んで、昼の天頂(正午の太陽)あるいは夜の天頂(北極星のお供)を占める」と書く(p.334)。
この三つ組は図1でいえば、二つのΔに、その二つに対してその中間の位置を占めるβを加えた3である。ここで六人の男女の子どもたちは、下記のような関係を描いているのである。
Δ1 <β> Δ2
||
老婆
||
Δ3 <β> Δ4
つまり六項関係は、八項関係のうち、表層に全面化した四つのΔ項と、そのΔ項の並行関係にある二項対立関係における中間項二つを数えたものである。また、語られなかった残りのβ二つを一身に体現したような項(今回の場合は「老婆」)が、マンダラ状の円環配置の中央に配される。

二つの二項対立それぞれの両極に対する中間項を強調することは他の神話でも行われる。
「高と低の中間の世界の鳥であるキツツキが、すでに天と地の交点であると定義しておいたマキバドリに変わるのである[…]」
この中間項は振動しており、したがって対立関係の対立関係の対立関係を崩さない限りでいろいろなものに変容することもできる。対立関係を調和させて4極の分離と結合を付かず離れずに安定させることができるならβは三つでも良い。三兄弟の次男とその年老いた母、三姉妹の次女(男兄弟に対しては実母であり、嫁に対しては義母であるという)といった関係でもよい。この場合の”年老いた母”は、一身で高振動状態に励起され、二重化されたββになっている。
八項関係全体を三項関係に圧縮する
さて、太陽と月の結婚相手をめぐる諍いの神話を、最小構成で三項関係に圧縮した神話がある。M457 「アレクナ 天体の諍い」を見てみよう。
かつてウェイとカペイという名をもつ太陽と月は無二の親友であった。
この頃の月はまだ隈がなく、汚れのない美しい顔立ちをしていた。
*
月は太陽の娘たちのひとりに恋をして、夜ごと彼女のもとに通った。
これがウェイ、太陽には気にくわなかった。
太陽は娘に経血で愛人である月の顔を汚させた。
**
これ以来、太陽と月は敵対し、月は太陽を避けるようになった。
顔も汚れたのである。
この神話は太陽と月、そして太陽の娘であり月の愛人である者の三者だけが登場する。他の神話が対立関係の対立関係の対立関係を、2×2×2=8の八項関係を幾重にも組みつつ描いていたのに比べると、ずいぶんとシンプルになっている。
レヴィ=ストロース氏はこの神話が「三」者の関係を強調していることに注目し「三という数がアメリカ・インディアンの宗教表現に現れることはまれ」であると書いている(p.333)。もちろんここで、太陽の娘にして月の愛人である者の内部から外部へと分離した「経血」に注目すれば、この娘と経血が一即二二即一の関係にもつれつつ分離と結合の両極の間で振動している二つの両義的媒介項ということになるからして、この神話も「四」で動いていると読めるのであるが、ここはレヴィ=ストロース氏が書かれていることをじっくり読んでみよう。
「この神話は短いながらも、いくつかの点で興味深い。月の隈の起源についてこの物語が提起する解釈は、本巻の出発点であったM354と北アメリカのさまざまな神話との中間に位置している。M354ではカエルの隠喩である女 が夫の背中を排泄物でよごす。北アメリカの神話では月の隈の中に、換喩としてのカエルのイメージが見えるのである。顔、胸、背中に身体全体で張りつく場合もあれば、月の顕現である人物の身体の一部に張りつく場合もある。したがって、これらのすべての形に共通する意味場を次頁上のように定義することができる。
月の隈
全身 ┸ 体の一部
血┸排泄物
前部┸後部
それぞれの神話、あるいは神話群はこの領域をそれぞれのやり方で切り取るのみである。半身、排泄物、後部、全身、血、前部または後部(天体の諍いの北アメリカの神話群)、体の一部、血、前部(M457)のように。じ っさい、と北アメリカの群との違いは、アレクナの神話では、体の一部である経血が月の隈を生じさせるのだが、北アメリカでは、M428ではっきり語られているように、全身が経血を意味している。」
隈がある月、つまり現世のあの月の起源を語る上で、神話はこの隈がある月を八項関係をなす対立関係の対立関係の対立関係の一極として区切り出そうとする。
そのために、まず「未だ隈のない月」と「月にへばりつく隈のもと」とが元々遠く分離して隔たっているところからはじめて、この二つが接近し、反発しつつもついには過度に結合して離れなくなる、という動きを語るのである。
ここで神話の論理は「未だ隈のない月」をそれ自体として端的に存在する独立する項とはみなさず、「非-未だ隈のない月」(上の神話でいえば「太陽」)と区別される限りでの「非-非-未だ隈のない月」 として出現させる。
同じように「月にへばりつく隈のもと」についても、それ自体を端的に存在する独立した何かとはみなさずに、「非-月にへばりつく隈のもと」(冒頭の神話でいえば、カエルと対立する人間の娘)と区別される限りでの「非-非-月にへばりつく隈のもと」として出現させる。
これだけでもすでに四項が出てくる。
「未だ隈のない月」 /「非-未だ隈のない月」
| |
「月にへばりつく隈のもと」/「非-月にへばりつく隈のもと」
この四項はいずれも「あちらで分離すればこちらで結合し、こちらで結合すればあちらで分離する」といった具合に、くっついたり離れたり、伸びたり縮んだりしている。これは両義的媒介項であり、冒頭の図1の図式ではβと表記したものである。

ここで今見ている太陽と月と太陽の娘の三者だけからなる神話では、「非-月にへばりつく隈のもと」と「月にへばりつく隈のもと」である「太陽の娘」とその経血が、もともと結合=一体化していたところから、シンプルに分離される。
冒頭の神話では、「月にへばりつく隈のもと」を区切り出すために、月がわざわざヤマアラシに変身して、人間の三姉妹の末娘を天上界に連れてきて、その娘との対決を強いる形で、人間の娘”ではないもの”としてのカエルを、「月にへばりつく隈のもと」であるカエルを、ようやく生産したのであるが、それに対して二つめのシンプル版の神話では、「月にへばりつく隈のもと」はもっと自然に容易に「非-月にへばりつく隈のもと」と一体化しているところから分離できている。
レヴィ=ストロース氏が上の引用中で書いているように、「月にへばりつく隈のもと」と「非-月にへばりつく隈のもと」との分離を、経験的感覚的に対立する二者に重ねて考えるか、一者の「全体/部分」に重ねて考えるか、あるいは一者の「部分」を選んだ場合に「他ではない、どの部分」を選ぶのか(血/排泄物)といったところで、いくつもの対立関係が引き合いに出されつつ、その結合からの分離、分離からの別のところでの結合が試されることになる。

三位一体ではβ二項が区別不可能なほど一になっている
さて、八項関係(四項関係)ではなく、三項関係が全面に出る神話の場合、そこでは二つの両義的媒介項が経験的に完全に一体化(一方が他方の中に入っている)している。
マンダン族を最初に観察したひとりであるヴィート公マクシミリアンは、老婆には六人の子供がいたと書いている。男三人、女三人である。長男は凪(第一の創造物)、次男は太陽、末息子は夜である。長女は夜明けの星、次女は北極星の回りをまわる「縞模様のカボチャ」と呼ばれる星、三女は宵の星である[…]夜明けの星は東に、 宵の星は西に対応する。兄弟の太陽と同じく、三姉妹は恐るべき力をもっている。四人ともだが、とくに太陽とその姉妹の中間の地位を占める「高いところの女」は人喰いであり[…]わざわいを引きおこす
長男 凪(第一の創造物) / 次男 <太陽> / 末息子 夜
長女 夜明けの星 / 次女 <北極星を回る星> / 三女 宵の星
この二つの三項関係のうち、特に中間の「次男 <太陽>」と「次女 <北極星を回る星>」が「人喰い」、つまり分離しているところを過度に結合し、対立関係の組み替えを引き起こす力を持つものとされる、という。つまりこの「次男 <太陽>」と「次女 <北極星を回る星>」は高速で振動しており、二重にブレて見えるようであり、つまり一でありながら二の、一つでありながら二つの両義的媒介項なのである。
両義的媒介項は「項」といっても、それ自体で単独に孤立して止まっている個物ではなく、「内部にありながら外部に出てくる」とか「他を自在に喰ってしまう」とか、一と二、二と一の間で振動し続ける動きなのである。
これを粒子として観察するか、波として観察するかは、それこそ観察する側が用いる分別(神話の場合であれば、感覚と言葉)しだいである。

関連記事
*
いいなと思ったら応援しよう!

